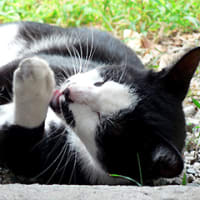2001年の6月小型機による世界一周飛行の折、給油のためデンマーク領・グリーンランド島の南部にあるナルサルスクの空港に降りて1泊した。 ホテルのバーカウンターに座り、北極の氷をオンザロックにしてパチパチはじける音を聞きながら、老バーテンの話に耳をかたむける。 そもそもここの空港は第2次世界大戦中、アメリカ本土からヨーロッパの連合国に,物資や兵員を運ぶための重要な中継基地として長い滑走路が造られた。 大量の物資や兵器を積んだ輸送機や爆撃機が、本土から大西洋をダイレクトに横断するには距離が長すぎるし、途中の天候不良や機体のトラブルを考えると、緊急着陸の可能な北極航空路が必要だったのだ。
航路はアメリカの各地を出発してカナダ、グリーンランド、アイスランド経由イギリス行きで、途中地点に位置するナルサルスクに、各種施設を完備した空港が設置された。 しかしここは地形的に離着陸が難しいうえに、天候の変わりやすいパイロット泣かせの空港で、周辺に広がる厚い氷の下には、当時空港に降りられず雪原に不時着した「ボーイングB-17爆撃機」の巨大な機体が多く埋もれているという話を聞いた。 また戦場からの帰り便には、米兵の遺体がいったんここで降ろされ、修復を施してからアメリカ本土に送り返されていたという。
第2次大戦中の大型爆撃機といえばB-17とB-24。 共に生産数や性能などに大きな違いはないものの、親近度はB-17が圧倒的に高く、多くの著書や映画を通して今なおそのフアンは多い。 1943年からドイツ本土へ出撃するようになったB-17の編隊は、当時護衛戦闘機の航続距離が充分でなかったため、ドイツ迎撃戦闘機の餌食となり、出撃ごとに10%を超える損害を出していた。 そこで考案されたのが「密集隊形」で、編隊機どうしができるだけその間隔を縮め、濃密な防護砲火の弾幕を張り、ドイツ戦闘機隊の攻撃から身を守る戦法で、逆に敵機を撃墜することも多かった。 しかし後継機となるB-29のように与圧装置や空調設備も無く、皮の航空服をまとい酸素マスクをした乗員が寒さの中何とか動けたのは、電熱服を着込んでいたから。
それでもB-17に対する乗員の評価がずば抜けて高かったのは、その優秀な防弾装備で生還率が高かったから。 機体主要部にはことごとく防弾が施され、その頑丈な造りは少々の被弾にはビクともしなかった。 また豊富な防御火器を備え、後期型のG型では実に13丁の「12・7mmブローニングM2重機関銃」を装備しており、ドイツ軍機からも恐れられた。 これらの重装備に加え、さらに2~4トンの爆弾を半径3000kmまで運び、最大時速500kmの驚異的性能を支えたのが、1200馬力×4基のターボチャージャー付エンジン。 空気密度の薄い高空でもレシプロエンジンの高出力を確保できたため、これの開発が遅れたドイツや日本の戦闘機は、高空から進入するB-17の迎撃には非常に苦戦した。
第2次大戦中、イギリスに駐留し、ドイツに対し危険な白昼爆撃の任務を繰り返すアメリカ第8空軍では、25回の出撃を達成した搭乗員を、本国へ帰国させることになっていた。 裏返せば、B-17に随伴できる護衛戦闘機が無かった1943年頃までの無事帰還が、いかにに難しかったかを物語る。 そんな中で唯一24回の出撃まで残ったB-17が実在した。 最後の飛行が無事終われば10人のクルーは英雄として故郷に帰れる。 果たして結果は・・・・この実話を映画化したのが1944年公開のアメリカ映画「メンフィス・ビル」。 この映画を観て感じるのは、B-17と搭乗員との運命を共有する一体感。 同じレシプロ機でもB-29になると何故かもうそれが感じられない。 レシプロ機らしさを残す爆撃機は、B-17が最後だったのかもしれない。
航路はアメリカの各地を出発してカナダ、グリーンランド、アイスランド経由イギリス行きで、途中地点に位置するナルサルスクに、各種施設を完備した空港が設置された。 しかしここは地形的に離着陸が難しいうえに、天候の変わりやすいパイロット泣かせの空港で、周辺に広がる厚い氷の下には、当時空港に降りられず雪原に不時着した「ボーイングB-17爆撃機」の巨大な機体が多く埋もれているという話を聞いた。 また戦場からの帰り便には、米兵の遺体がいったんここで降ろされ、修復を施してからアメリカ本土に送り返されていたという。
第2次大戦中の大型爆撃機といえばB-17とB-24。 共に生産数や性能などに大きな違いはないものの、親近度はB-17が圧倒的に高く、多くの著書や映画を通して今なおそのフアンは多い。 1943年からドイツ本土へ出撃するようになったB-17の編隊は、当時護衛戦闘機の航続距離が充分でなかったため、ドイツ迎撃戦闘機の餌食となり、出撃ごとに10%を超える損害を出していた。 そこで考案されたのが「密集隊形」で、編隊機どうしができるだけその間隔を縮め、濃密な防護砲火の弾幕を張り、ドイツ戦闘機隊の攻撃から身を守る戦法で、逆に敵機を撃墜することも多かった。 しかし後継機となるB-29のように与圧装置や空調設備も無く、皮の航空服をまとい酸素マスクをした乗員が寒さの中何とか動けたのは、電熱服を着込んでいたから。
それでもB-17に対する乗員の評価がずば抜けて高かったのは、その優秀な防弾装備で生還率が高かったから。 機体主要部にはことごとく防弾が施され、その頑丈な造りは少々の被弾にはビクともしなかった。 また豊富な防御火器を備え、後期型のG型では実に13丁の「12・7mmブローニングM2重機関銃」を装備しており、ドイツ軍機からも恐れられた。 これらの重装備に加え、さらに2~4トンの爆弾を半径3000kmまで運び、最大時速500kmの驚異的性能を支えたのが、1200馬力×4基のターボチャージャー付エンジン。 空気密度の薄い高空でもレシプロエンジンの高出力を確保できたため、これの開発が遅れたドイツや日本の戦闘機は、高空から進入するB-17の迎撃には非常に苦戦した。
第2次大戦中、イギリスに駐留し、ドイツに対し危険な白昼爆撃の任務を繰り返すアメリカ第8空軍では、25回の出撃を達成した搭乗員を、本国へ帰国させることになっていた。 裏返せば、B-17に随伴できる護衛戦闘機が無かった1943年頃までの無事帰還が、いかにに難しかったかを物語る。 そんな中で唯一24回の出撃まで残ったB-17が実在した。 最後の飛行が無事終われば10人のクルーは英雄として故郷に帰れる。 果たして結果は・・・・この実話を映画化したのが1944年公開のアメリカ映画「メンフィス・ビル」。 この映画を観て感じるのは、B-17と搭乗員との運命を共有する一体感。 同じレシプロ機でもB-29になると何故かもうそれが感じられない。 レシプロ機らしさを残す爆撃機は、B-17が最後だったのかもしれない。