トイレットペーパーを奪い合いって?
在庫は十分にあるのでは?
今のところ、新潟では普通に売ってますよ。
これから、なくなるのかなあ。。。
マスクは全くありませんね。
新潟も感染者が増えてますがマスクを売ってないこともありますが
つけている人は少ない~~~
そーすから
「コロナより怖いのは人間」と言わせた客たち
2020年3月、新型コロナウィルスの感染拡大とともに事実とデマが錯綜し、ドラッグストアなどの陳列棚からは、マスクやトイレットペーパーといった一部の日用品があっという間に姿を消した。
ドラッグストアの店員たちは、商品を手に入れられず殺気立った消費者に、ひたすら頭を下げ続ける。それでも客たちは、“本当は、在庫を隠しているのだろう”、“店員が着けるマスクがあるなら客に売れ”と食い下がる。収束の気配すら見えない新型コロナも不安だが、こうした理不尽なクレームに対応しなければならない従業員の心の状態も心配だ。
実際、“謝ってばかりで疲れた”、“コロナよりも怖いのは人間だった”と、Twitterで吐露した女性定員の悲痛な叫びが注目を集めた。これはまさに高度な感情コントロールが求められる「感情労働」*1
の、根深い問題を露見したものといえる。 本稿では、こうしたオイルショックならぬ「コロナショック」を通して、現代の「カスタマー・ハラスメント(カスハラ)」事情を中心に、消費者の逸脱的な行動を心理学の視点から概説したい。
〔PHOTO〕iStock
「買い占めの心理」
最初に用語を整理しておくが、「カスハラ」とは、和製英語「カスタマー・ハラスメント」の略称で、簡単にいうと“消費者からの過剰なクレームや嫌がらせ”を指す。よって、悪質クレームとほぼ同義といっても支障はないだろう。
筆者は、こうしたクレーム研究を専門とする一方で、モノの異常なまでのため込み(専門用語では「ホーディング」(hoarding))やモノへの依存といった逸脱的消費者行動も研究している。今回のコロナショックにみるカスハラ騒動の分析には、モノへの執着や依存に関する知見も役立ちそうだ。
まずは買い占めが起きた心理的な原因、すなわち「買い占めの心理」を紐解いてみよう。このところ、毎朝のようにテレビでは、商品を手に入れるために長い列を作る客たちの姿が映し出される。こうした事態を、“本当に令和2年の映像か”、“昭和95年か何かの間違いではないのか”と揶揄する言葉も飛び交っている。なぜ、消費者たちは一斉にトイレットペーパーを買いに走ったのか。
以前、筆者は20~60代の男女453名に、歯ブラシや石鹸などの日用品のストック数について調査を行ったことがある。その際、トイレットペーパーにおいては、日常的にため込み志向の強い人はそうでない人に比べ、平均して約3個多くストックしていることが見いだされた(ため込み群:11.6個、非ため込み群:8.7個)。
こうしたため込み志向の強さは、なくなることへの不安が根底にあることが認められている(池内,2014)。今回の買い占め行為の一端は、日常的にため込み志向の強い人が、空っぽの陳列棚の様子がテレビで映し出されることでますます不安になり、店頭に駆け込んだことで生じたといえよう。
彼らにとっては、仮に自宅に10個トイレットペーパーが残っていても、“あと10個しかない”のである。特に不安や強迫傾向の強い人は、トイレットペーパーを“使うこと”ではなく、“買うこと”自体が目的になるといった、強迫的購買(買い物依存)に近い心理が働いているといえる。そうなると、いくらメディアで“冷静な行動を”と言われても、聞き入れる余裕や理性など働くわけがない。
在庫は十分にあるのでは?
今のところ、新潟では普通に売ってますよ。
これから、なくなるのかなあ。。。
マスクは全くありませんね。
新潟も感染者が増えてますがマスクを売ってないこともありますが
つけている人は少ない~~~
そーすから
「コロナより怖いのは人間」と言わせた客たち
2020年3月、新型コロナウィルスの感染拡大とともに事実とデマが錯綜し、ドラッグストアなどの陳列棚からは、マスクやトイレットペーパーといった一部の日用品があっという間に姿を消した。
ドラッグストアの店員たちは、商品を手に入れられず殺気立った消費者に、ひたすら頭を下げ続ける。それでも客たちは、“本当は、在庫を隠しているのだろう”、“店員が着けるマスクがあるなら客に売れ”と食い下がる。収束の気配すら見えない新型コロナも不安だが、こうした理不尽なクレームに対応しなければならない従業員の心の状態も心配だ。
実際、“謝ってばかりで疲れた”、“コロナよりも怖いのは人間だった”と、Twitterで吐露した女性定員の悲痛な叫びが注目を集めた。これはまさに高度な感情コントロールが求められる「感情労働」*1
の、根深い問題を露見したものといえる。 本稿では、こうしたオイルショックならぬ「コロナショック」を通して、現代の「カスタマー・ハラスメント(カスハラ)」事情を中心に、消費者の逸脱的な行動を心理学の視点から概説したい。
〔PHOTO〕iStock
「買い占めの心理」
最初に用語を整理しておくが、「カスハラ」とは、和製英語「カスタマー・ハラスメント」の略称で、簡単にいうと“消費者からの過剰なクレームや嫌がらせ”を指す。よって、悪質クレームとほぼ同義といっても支障はないだろう。
筆者は、こうしたクレーム研究を専門とする一方で、モノの異常なまでのため込み(専門用語では「ホーディング」(hoarding))やモノへの依存といった逸脱的消費者行動も研究している。今回のコロナショックにみるカスハラ騒動の分析には、モノへの執着や依存に関する知見も役立ちそうだ。
まずは買い占めが起きた心理的な原因、すなわち「買い占めの心理」を紐解いてみよう。このところ、毎朝のようにテレビでは、商品を手に入れるために長い列を作る客たちの姿が映し出される。こうした事態を、“本当に令和2年の映像か”、“昭和95年か何かの間違いではないのか”と揶揄する言葉も飛び交っている。なぜ、消費者たちは一斉にトイレットペーパーを買いに走ったのか。
以前、筆者は20~60代の男女453名に、歯ブラシや石鹸などの日用品のストック数について調査を行ったことがある。その際、トイレットペーパーにおいては、日常的にため込み志向の強い人はそうでない人に比べ、平均して約3個多くストックしていることが見いだされた(ため込み群:11.6個、非ため込み群:8.7個)。
こうしたため込み志向の強さは、なくなることへの不安が根底にあることが認められている(池内,2014)。今回の買い占め行為の一端は、日常的にため込み志向の強い人が、空っぽの陳列棚の様子がテレビで映し出されることでますます不安になり、店頭に駆け込んだことで生じたといえよう。
彼らにとっては、仮に自宅に10個トイレットペーパーが残っていても、“あと10個しかない”のである。特に不安や強迫傾向の強い人は、トイレットペーパーを“使うこと”ではなく、“買うこと”自体が目的になるといった、強迫的購買(買い物依存)に近い心理が働いているといえる。そうなると、いくらメディアで“冷静な行動を”と言われても、聞き入れる余裕や理性など働くわけがない。










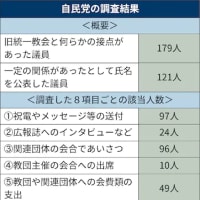


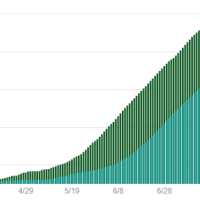





※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます