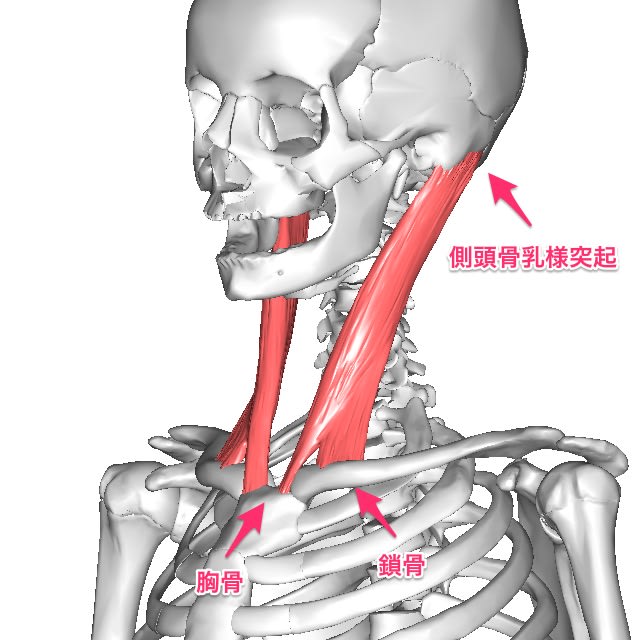正直に言うと困っています。。。
この腹筋の知識が無いスタッフが多い事に。。。
しかし、これを読んでいるあなたはそんな事はありませんよね?
どうも(^_^)
雪が降りだしてやっと冬らしくなってきました。
雪が少なくなってきたのはやはり温暖化現象でしょうか、、、
人間のせいとはいえ困ったものです。
しかし今日の我が家は、嫁さんの機嫌が悪く、、、とても寒いです(´・ω・`)
我が家にだけは温暖化が起こって欲しい。。。
そう思う男です。。。
さて、今回は腹筋について勉強して行きたいと思います。
前にも書いたかもしれませんが、、、
腹筋とは、、、
腹横筋、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋の事を言います。
一言で、腹筋と言ってもこれだけあるんですね。
一応作用だけ書いておきます。。。
腹直筋

体幹の屈曲、骨盤を後方回旋させる。
外腹斜筋

両側性では体幹の屈曲
一側性では、体幹の回旋、側屈
内腹斜筋

両側性では体幹の伸展
一側性では、体幹の側屈
腹横筋

腹部を引き締め平らにする、内臓を圧迫する
こんな所です( `ー´)ノ
そして、この腹筋、、、
ローカル筋、グローバル筋に分類する事も出来ます。

ローカル筋とは、椎骨に直接付着しているもので、通称コアマッスルと言われたりもします。
腹横筋がこれにあたり、多裂筋や大腰筋もこれにあたります。
グローバル筋とは、胸郭と骨盤を連結する筋で、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋がこれにあたります。

この腹筋群の働きは、体幹のスタビリティを保つためにも大変重要です。
ローカル筋、グローバル筋の相互作用が重要で、特にローカル筋は直接椎骨に作用し、各椎体間のスタビリティを得るためにも重要です。
ローカル筋の正しい働きは、体幹の安定性に必要不可欠です。
その為、このローカル筋を鍛える為のコアトレーニングが近年注目を集めているのです。
そして、体幹の腰椎部にはこのコアのスタビリティが多くもとめられます。
それは、腰椎部が構造上不安定だからです。
逆に、胸郭、股関節部は、構造上安定しているため、モビリティが求められることが多いです。
ついでに、言うと。。。
この胸郭。体幹の回旋はほとんどが胸椎で行われており、この胸椎のROM制限が腰椎で代償され、腰痛、肩関節障害へ発展していくケースがけっこう多いと思われます。
胸椎のモビリティが腰痛、肩関節障害の改善のキーポイントになってくることも、おうおうにしてあり得るのです。
話しが、胸郭の方へ行ってしまいましたが、、、
外腹斜筋、内腹斜筋のことに触れていきたいと思います。
この二つの筋は、体幹の回旋、側屈の主導筋であり、特に回旋時には連動して働くのです。
例えば、、、
右外腹斜筋と左内腹斜筋が同時に働くと、、、
体幹の左回旋が起こります。
右外腹斜筋と右内腹斜筋が同時に働くと、、、
体幹の右側屈が起こります。
回旋の連動は、アナトミートレインで言う所の、
SPL(スパイラルライン)で説明できますね(;^ω^)

今回はここまでにします。
読んで頂いた勉強熱心な先生。
有難うございます(*´ω`*)
また次回。
おわり
この腹筋の知識が無いスタッフが多い事に。。。
しかし、これを読んでいるあなたはそんな事はありませんよね?
どうも(^_^)
雪が降りだしてやっと冬らしくなってきました。
雪が少なくなってきたのはやはり温暖化現象でしょうか、、、
人間のせいとはいえ困ったものです。
しかし今日の我が家は、嫁さんの機嫌が悪く、、、とても寒いです(´・ω・`)
我が家にだけは温暖化が起こって欲しい。。。
そう思う男です。。。
さて、今回は腹筋について勉強して行きたいと思います。
前にも書いたかもしれませんが、、、
腹筋とは、、、
腹横筋、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋の事を言います。
一言で、腹筋と言ってもこれだけあるんですね。
一応作用だけ書いておきます。。。
腹直筋

体幹の屈曲、骨盤を後方回旋させる。
外腹斜筋

両側性では体幹の屈曲
一側性では、体幹の回旋、側屈
内腹斜筋

両側性では体幹の伸展
一側性では、体幹の側屈
腹横筋

腹部を引き締め平らにする、内臓を圧迫する
こんな所です( `ー´)ノ
そして、この腹筋、、、
ローカル筋、グローバル筋に分類する事も出来ます。

ローカル筋とは、椎骨に直接付着しているもので、通称コアマッスルと言われたりもします。
腹横筋がこれにあたり、多裂筋や大腰筋もこれにあたります。
グローバル筋とは、胸郭と骨盤を連結する筋で、腹直筋、外腹斜筋、内腹斜筋がこれにあたります。

この腹筋群の働きは、体幹のスタビリティを保つためにも大変重要です。
ローカル筋、グローバル筋の相互作用が重要で、特にローカル筋は直接椎骨に作用し、各椎体間のスタビリティを得るためにも重要です。
ローカル筋の正しい働きは、体幹の安定性に必要不可欠です。
その為、このローカル筋を鍛える為のコアトレーニングが近年注目を集めているのです。
そして、体幹の腰椎部にはこのコアのスタビリティが多くもとめられます。
それは、腰椎部が構造上不安定だからです。
逆に、胸郭、股関節部は、構造上安定しているため、モビリティが求められることが多いです。
ついでに、言うと。。。
この胸郭。体幹の回旋はほとんどが胸椎で行われており、この胸椎のROM制限が腰椎で代償され、腰痛、肩関節障害へ発展していくケースがけっこう多いと思われます。
胸椎のモビリティが腰痛、肩関節障害の改善のキーポイントになってくることも、おうおうにしてあり得るのです。
話しが、胸郭の方へ行ってしまいましたが、、、
外腹斜筋、内腹斜筋のことに触れていきたいと思います。
この二つの筋は、体幹の回旋、側屈の主導筋であり、特に回旋時には連動して働くのです。
例えば、、、
右外腹斜筋と左内腹斜筋が同時に働くと、、、
体幹の左回旋が起こります。
右外腹斜筋と右内腹斜筋が同時に働くと、、、
体幹の右側屈が起こります。
回旋の連動は、アナトミートレインで言う所の、
SPL(スパイラルライン)で説明できますね(;^ω^)

今回はここまでにします。
読んで頂いた勉強熱心な先生。
有難うございます(*´ω`*)
また次回。
おわり