昨日、福井県若狭町にある福井県年縞博物館へ行ってきました。
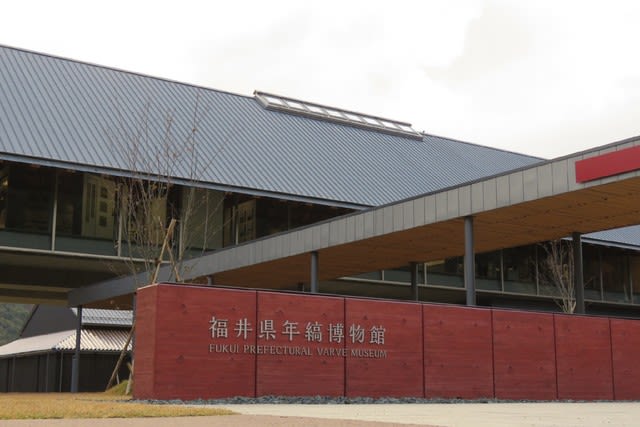
9月15日にオープンしたばかりの、世界一の年稿を展示する博物館で、何と7万年分を記録しています
年稿とは、「長い年月の間に湖沼などに堆積した層が描く特徴的な縞模様の湖底堆積物」のことです。
地層のように、1年に1層帯状に形成されます。
その縞模様は季節によって違うものが堆積することで、明るい層と暗い層が交互に堆積することできるものです。

この図の上が年稿で、下がその説明です。
水月湖の年縞は、7万年分残っており、世界一なのです。

それが、一列で展示してあるのです。

古代の骨などの出土品は、放射性炭素(炭素14)の量で年代が測定できますが、多少ばらつきが出ます。
水月湖の年縞は、7万年分の放射性炭素(炭素14)の量がわかるために、年代特定の物差しになるのです。
例えば、人骨が見つかった場合、35,678年前の骨というように、一桁までわかるそうです。
しかも、中に含まれる花粉の種類によって、気候もわかるのです。
「水月湖の年稿」はとにかく優れもの。
博物館には行って最初に見る説明動画で、小学生でも理解できます。
お近くに寄ったら、ぜひ訪問してみてください。
公式サイト http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/
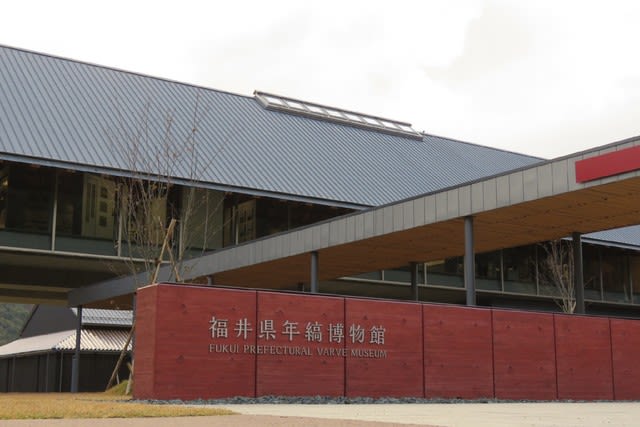
9月15日にオープンしたばかりの、世界一の年稿を展示する博物館で、何と7万年分を記録しています
年稿とは、「長い年月の間に湖沼などに堆積した層が描く特徴的な縞模様の湖底堆積物」のことです。
地層のように、1年に1層帯状に形成されます。
その縞模様は季節によって違うものが堆積することで、明るい層と暗い層が交互に堆積することできるものです。

この図の上が年稿で、下がその説明です。
水月湖の年縞は、7万年分残っており、世界一なのです。

それが、一列で展示してあるのです。

古代の骨などの出土品は、放射性炭素(炭素14)の量で年代が測定できますが、多少ばらつきが出ます。
水月湖の年縞は、7万年分の放射性炭素(炭素14)の量がわかるために、年代特定の物差しになるのです。
例えば、人骨が見つかった場合、35,678年前の骨というように、一桁までわかるそうです。
しかも、中に含まれる花粉の種類によって、気候もわかるのです。
「水月湖の年稿」はとにかく優れもの。
博物館には行って最初に見る説明動画で、小学生でも理解できます。
お近くに寄ったら、ぜひ訪問してみてください。
公式サイト http://varve-museum.pref.fukui.lg.jp/









