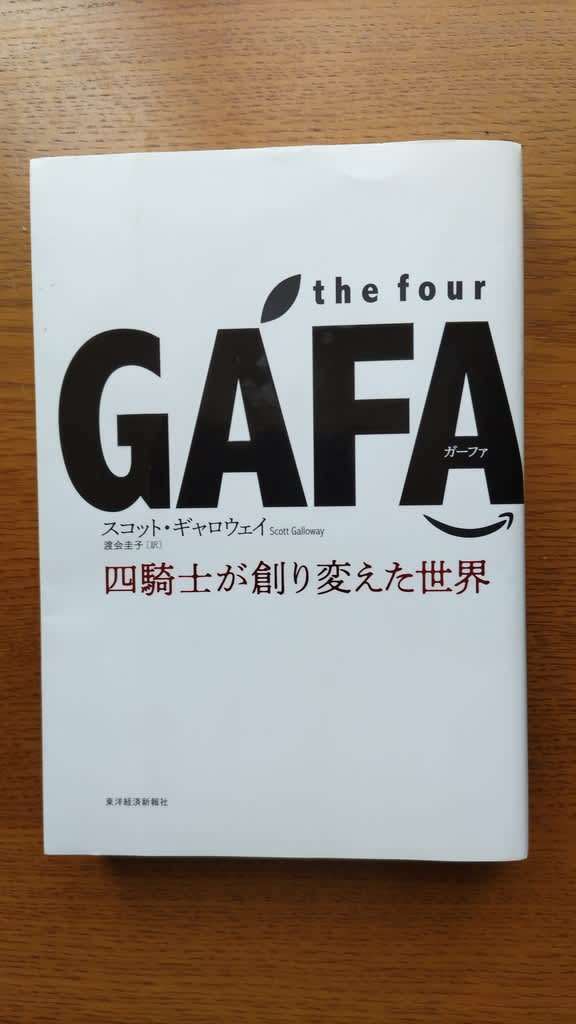手元に未読の新書がたくさんあるので、できるだけ読破しようとあがいている。
かなり前に買った本だと思うが、シュンペーターという経済学者に興味があり、購入した。
著者の伊東光晴氏には「ケインズ」の著書もあり、そちらも確保してはある。
伊東氏はかつてはテレビなどにも出ていて、経済の解説や国の審議委員などで活躍していたので知っていた。
ところで、シュンペーターであるがケインズと並ぶ20世紀を代表する経済学者といわれていたが、いまいち知名度は低かったように思う。
それでも彼の書いた「理論経済学の本質と主要内容」は25歳の時に書かれ、その4年後には「経済発展の理論」を書いているので、天才的な経済学者であったようだ。
彼に影響を与えたのは、フランスの経済学者ワルラスと哲学者ベルクソンのようだ。
シュンペーターはオーストリア=ハンガリー帝国に生まれ、オーストリア、ドイツなどで活動し、その後アメリカにわたっているようだ。
シュンペーターの経済学は、経済にとって大切なことは技術革新であり、新製品による新市場の創設であり、ケインズの有効需要創出策とは違って、供給サイドを革新するものであった。
しかし、現実の経済学は80年代のアメリカの数理経済学が誤った方向性への導きにより、グローバル経済と金融万能、格差の拡大につながったのではないかと私は思う。
シュンペーター氏の経済学に関する著作は、もっと顧みられるべき価値があるのではないかと考えた次第である。