条例のおける原理と原則の違いについて調べている。
YAHOOの辞典で検索すると、
■げん‐り【原理】
1 事物・事象が依拠する根本法則。基本法則。「てこの―」「民主主義の―」
2 哲学で、他のものを規定するが、それ自身は他に依存しない根本的、根源的なもの。
■げん‐そく【原則】
多くの場合に共通に適用される基本的なきまり・法則。「―を立てる」「―から外れる」「―として部外者の立ち入りを禁止する」
よく分からない。
また他のサイトに、
「原理は主として存在や認識に、原則は主として人間の活動に関係する。」とあった。
法律で原理と原則について規定しているのは、
生活保護法のみである。
(両方の言葉が使われているのは他にもあるが、試験科目としてなどである)
第1条から第4条の、
目的・無差別平等・最低生活・保護の補足性が、
基本原理とされ、
第7条から第11条の、
申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位が、
原則とされている。
おおまかに把握すると、
原理は、「理念、目的とするところ」といった感じで、
原則が、「やり方」といった感じだろうか。
(厳密に区別できないが)
また、第5条に、
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
とあり、
原理の方は解釈・運用指針となっていることがわかる。
「原理」の代わりに「理念」を使っている場合もあるだろう。
例えば、「循環型社会形成推進基本法」
・・・環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、・・・
バシッとした結論は出ないが、
原理はより「目的」に近く、
原則はより「手段」に近い、
ということだろうか。
YAHOOの辞典で検索すると、
■げん‐り【原理】
1 事物・事象が依拠する根本法則。基本法則。「てこの―」「民主主義の―」
2 哲学で、他のものを規定するが、それ自身は他に依存しない根本的、根源的なもの。
■げん‐そく【原則】
多くの場合に共通に適用される基本的なきまり・法則。「―を立てる」「―から外れる」「―として部外者の立ち入りを禁止する」
よく分からない。
また他のサイトに、
「原理は主として存在や認識に、原則は主として人間の活動に関係する。」とあった。
法律で原理と原則について規定しているのは、
生活保護法のみである。
(両方の言葉が使われているのは他にもあるが、試験科目としてなどである)
第1条から第4条の、
目的・無差別平等・最低生活・保護の補足性が、
基本原理とされ、
第7条から第11条の、
申請保護・基準及び程度・必要即応・世帯単位が、
原則とされている。
おおまかに把握すると、
原理は、「理念、目的とするところ」といった感じで、
原則が、「やり方」といった感じだろうか。
(厳密に区別できないが)
また、第5条に、
(この法律の解釈及び運用)
第五条 前四条に規定するところは、この法律の基本原理であつて、この法律の解釈及び運用は、すべてこの原理に基いてされなければならない。
とあり、
原理の方は解釈・運用指針となっていることがわかる。
「原理」の代わりに「理念」を使っている場合もあるだろう。
例えば、「循環型社会形成推進基本法」
・・・環境基本法(平成五年法律第九十一号)の基本理念にのっとり、循環型社会の形成について、基本原則を定め、・・・
バシッとした結論は出ないが、
原理はより「目的」に近く、
原則はより「手段」に近い、
ということだろうか。










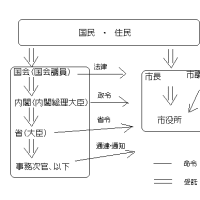


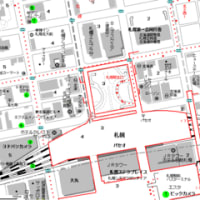
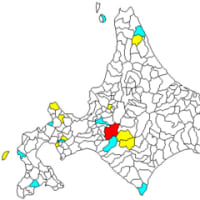
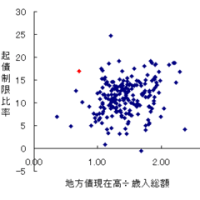
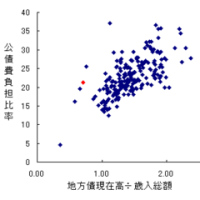
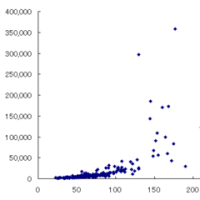
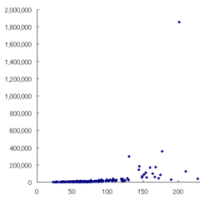

原理も、原則も、同じ。
原ということばは、
『本来は、こうだったらいいなあ・・・』
という、
形而上的世界における、
極めて幸せな前提に基づく言葉。
形而上下では、
『運用』という言葉が、
その潤滑油となって、
ある程度物事をうまく進める。
形而上的思考と、形而上下における行動が、
同じ働きをするのであれば、
誰も苦労はしないよな。
たまたま、
歯車がうまくかみ合って、
うまくいくこともあるけれど、
そんなことは
ルーキーに、
全盛期の長島から3連続三振を取れ、
ってオーダーしているのと同じこと。
不可能ではないけれど、
可能性は極めて、低い。
うちの会社にしがみついている必要はないよ。
うちの会社は、もうすぐ沈没するから。