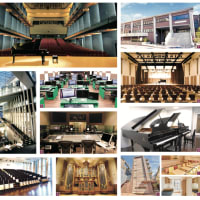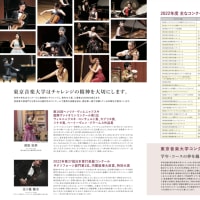伊福部昭 愛用ピアノの歴史 執筆:藤田崇文
(東京音楽大学主催 伊福部昭作品資料及び愛用ピアノ寄贈感謝状贈呈式 2022.1.15 プログラムより)
伊福部昭が生涯愛用したピアノは、昭和16年頃(1941年頃)に妻・アイ(舞踊家・勇崎愛子)の父・勇崎恒次郎により贈られた。恒次郎は伊福部を物心両面応援した理解者のひとりである。
ピアノが贈られるまでの逸話が残されている。
大家族である伊福部家は、「山鼻の家」と家族間で呼びあっていた家(札幌藻岩山の近く)に居住しており、ピアノは昭和10年(1935年)、長兄・宗夫と結婚することとなったナミの嫁入り道具であった。その後、宗夫は病から休職し、静かな場所での静養が必要となったためにピアノは売却されてしまう。しかし、伊福部の妻・アイはそれを知らなかった。ある日、アイが舞踊研究所から帰宅すると、ピアノが無くなっていた。伊福部の父・利三に訊ねると、ピアノは売ったという。事情は察したアイだったが、ピアノがなければ伊福部が作曲できない。そのため、アイは父・勇崎恒次郎にピアノを買い戻してもらうように懇願した。こうしてピアノは山鼻の家に無事戻り、伊福部のピアノとなった。伊福部の父・利三は、ピアノを弾く時間を毎晩1時間のみと時間制限を設けた。
ピアノは戦時下の空襲から戦火を免れたが、林務官であった伊福部は、圧縮木材のレントゲン撮影を繰り返すうちに放射能を浴びてしまったことから身体を壊し、終戦後、1年ほど休職する。身体が癒えた伊福部は、戦後に向かうにあたって音楽家になることを決意した。
伊福部は家族とともに故郷の北海道を後に上京を試みるが、戦後の混乱から政府は、東京への移住希望者は定職が確定し基準額の税金を納入している者に限定しており、伊福部は条件が満たされなく東京に転入できなかった。仕方なく、一旦、栃木県日光の山奥へ住むことにした。ピアノは札幌の山鼻の家から手作りの木枠で梱包して日光の住まいへ移設することにしたが、戦後の混乱期ゆえに連合国軍に接収されるのを案じ、木枠の前後に”PROFESSOR”と黒ペンキで大きく書くなどの工夫を施した。そうして無事に日光へ届けられた。その後、伊福部の転居に伴ってピアノも日光から世田谷の等々力へ、さらに奥澤から尾山台へと移っていった。
ピアノが贈られるまでの逸話が残されている。
大家族である伊福部家は、「山鼻の家」と家族間で呼びあっていた家(札幌藻岩山の近く)に居住しており、ピアノは昭和10年(1935年)、長兄・宗夫と結婚することとなったナミの嫁入り道具であった。その後、宗夫は病から休職し、静かな場所での静養が必要となったためにピアノは売却されてしまう。しかし、伊福部の妻・アイはそれを知らなかった。ある日、アイが舞踊研究所から帰宅すると、ピアノが無くなっていた。伊福部の父・利三に訊ねると、ピアノは売ったという。事情は察したアイだったが、ピアノがなければ伊福部が作曲できない。そのため、アイは父・勇崎恒次郎にピアノを買い戻してもらうように懇願した。こうしてピアノは山鼻の家に無事戻り、伊福部のピアノとなった。伊福部の父・利三は、ピアノを弾く時間を毎晩1時間のみと時間制限を設けた。
ピアノは戦時下の空襲から戦火を免れたが、林務官であった伊福部は、圧縮木材のレントゲン撮影を繰り返すうちに放射能を浴びてしまったことから身体を壊し、終戦後、1年ほど休職する。身体が癒えた伊福部は、戦後に向かうにあたって音楽家になることを決意した。
伊福部は家族とともに故郷の北海道を後に上京を試みるが、戦後の混乱から政府は、東京への移住希望者は定職が確定し基準額の税金を納入している者に限定しており、伊福部は条件が満たされなく東京に転入できなかった。仕方なく、一旦、栃木県日光の山奥へ住むことにした。ピアノは札幌の山鼻の家から手作りの木枠で梱包して日光の住まいへ移設することにしたが、戦後の混乱期ゆえに連合国軍に接収されるのを案じ、木枠の前後に”PROFESSOR”と黒ペンキで大きく書くなどの工夫を施した。そうして無事に日光へ届けられた。その後、伊福部の転居に伴ってピアノも日光から世田谷の等々力へ、さらに奥澤から尾山台へと移っていった。
勇崎恒次郎から贈られたピアノは、伊福部が91歳の生涯を閉じるまで大切に扱われ、民族主義に徹した力強い楽曲の数々を生み出していった。象牙鍵盤が凹み、剥がれるほど弾きこなされた。己の作曲活動を生涯見つめ続けたピアノについて伊福部は生前、こう語っていた。『このピアノは単なるピアノではない。私の身体の一部だ』。
ピアノは製造から100年の歳月を経たことから、さらに永続的に使用できるよう、修復(全弦交換・センターピン交換・象牙剥がれの再接着等)が施され、学長をつとめた東京音楽大学に寄贈された。

ピアノは製造から100年の歳月を経たことから、さらに永続的に使用できるよう、修復(全弦交換・センターピン交換・象牙剥がれの再接着等)が施され、学長をつとめた東京音楽大学に寄贈された。

(東京・尾山台自宅にて、撮影年不明)
■ 伊福部 昭 (作曲家 1914年5月31日北海道―2006年2月8日東京 / 91歳)
東京音楽大学名誉教授
東京音楽大学第5代学⻑(1976年3月〜1987年3月)
東京音楽大学⺠族音楽研究所名誉所⻑(初代所⻑)

(伊福部 昭 1977年撮影)
[Piano Data]
●ピアノメーカー:M.F.RACHALS(ラッハルス)
●生産国と地域:ドイツ・ハンブルグ
●製造年:1920年〜1924年
●製造番号:36161
●鍵盤数:85鍵 A0~A7 [象牙・黒檀]
●ピアノ寄贈者・修復寄付者:伊福部極(伊福部昭長男)
●ピアノ修復責任者:向井一秀 (Bechstein Japan)

(東京・尾山台にて)

(東京音楽大学にて 2022年1月15日)
---------











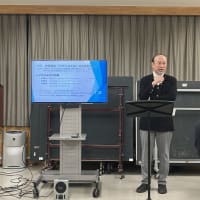
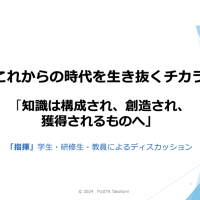
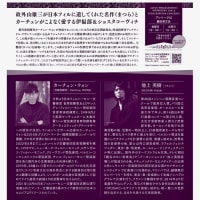

![NHK番組とのコラボ [あおきいろ]【ツバメ】オーケストラ バージョン](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/07/c3/945b7c66b9d4b6c211b95b6951013816.png)