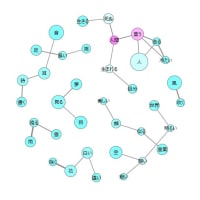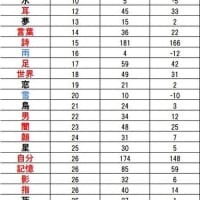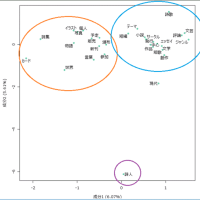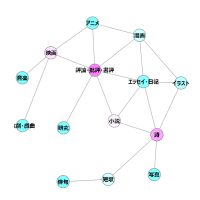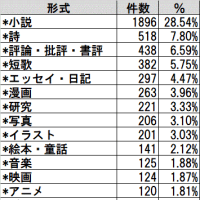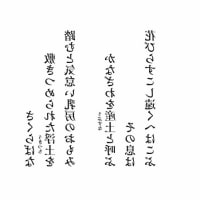本ウェブサイト「詩客」は詩歌梁山泊が運営しているが、詩歌梁山泊といえば、毎年恒例の詩歌トライアスロンである。すでに5回目の公開選考会が今年2019年3月21日に開かれている。過去5回の受賞者は、中家菜津子、横山黒鍵、亜久津歩、戸田響子、山川創。全員が自由詩や短歌において活躍中である。
詩歌トライアスロンを構想した人物であり、詩歌梁山泊・代表である森川雅美は「現在、複数の詩型の表現を試みる書き手も少なくありませんが、多くは1つの詩型に限っての表現をしています。しかし、これからの詩歌の可能性を考えるには、複数の詩型を考えることもひとつの道でしょう」と述べているが、「複数の詩型を考える」ために設けられた詩歌トライアスロンの特徴は、日本にある複数の詩型から名前通り3つ(自由詩・短歌・俳句)を選び、応募者に次の2つのうちいずれかの形式で応募する事を第1回目からの規定としている。1つは、1人による3つ全ての詩型の作品であり(三詩型ないものは無効)、1つは三詩型の二つ以上の要素を含んだ作品である。前者は、自由詩1篇・短歌3首・俳句3句をセットとし、後者は、自由詩に俳句や短歌を織り込む、自由詩に準ずる前書(詞書)と短詩型を組合せる、短詩型を連ねて自由詩を構成するなどの手法で詩型を融合させた作品とする(後者は、1つの詩型がオリジナルであれば、他の詩型は既存作品の引用でも構わない)。これら2つの形式で募集する事になったのは、森川の構想を受けて、詩歌梁山泊の会議で評者が後者を発案した上、前者と両方で募集する事を提案したからである。その責任もあって(?)、第1回目の司会は評者が引き受けた。
結果、前述した気鋭の受賞者5名を輩出する事ができたし、過去の候補作の作者たちの名前には現在精力的に活動している詩人、歌人、俳人たちが多く見受けられる。しかし、反省がなくもない。まず、過去の受賞作全部が後者のタイプなのだ。そればかりか、第1回の野村喜和夫奨励作品、第2回の石川美南推薦作、第3回の準入賞作、第4回の次点作、第5回の次点作も全部が後者のタイプなのだ。自由詩・短歌・俳句が独立している前者のタイプが相対的に不利な立場に置かれているのは間違いない。
前者のタイプが相対的に不利である理由として考えられるのは、前者のタイプだと、自由詩・短歌・俳句のうち、最低でも2つは優れていなくては、選者の過半数が支持する事にならない。つまり、選者が支持するためには、応募者は専門詩人、専門歌人、専門俳人のうち2つ以上に相当する必要があるが、そのような人物は日本広しといえども殆どいない。しかも、残り1つの詩型も一定レベルは必要であり、そうでないと深刻な瑕疵とされてしまう。しかも、内容もばらばらだと、選者の印象に残りづらい。内容的に統一感を出すと、今度は融合させて後者にしたくなる。
無論、公開選考会を聴けばわかるが、後者のタイプでも三詩型の能力は問われる。自由詩と融合している短歌や俳句の質が悪いと評価が落ちる。しかし、それだけでは致命傷にならない。なぜなら、融合されている時点で短歌や俳句は機能を失って自由詩のパーツとなり、融合作品全体が新たな自由詩になっているからである。つまり、短歌や俳句に少々まずいものがあっても、自由詩の数行以内の瑕疵として扱われる事になり、前者のタイプのように評価の3分の1や3分の2がいきなり消えてしまう事はない。逆に、融合される自由詩そのものの出来、いや、新たな自由詩となった融合型作品の出来が悪いと致命傷になる。しかし、裏を返せば、自由詩が良ければ高い評価につながりやすいわけである。よって、過去の受賞者に詩人が多いのは不思議ではないだろう。
さて、評者にとって興味深いのは、「融合されている時点で短歌や俳句は機能を失って自由詩のパーツとな」る事である。当然であるが、短い定型詩である短歌や俳句は短くない詩の部分となった時点で存在理由を失う。連歌・連句の百韻や歌仙といった定型詩にしても、構成している長短句のペアは短歌ではないし、発句は(独立した)俳句ではない。況して、自由詩に俳句や短歌を挿入する形で融合させた場合、それらは五七調や七五調の定型っぽい韻律を持った、何となく俳句や短歌を思わせる部分になるだけである。証拠として、今年2月に出た、彦坂美喜子の詩集『子実体日記 だれのすみかでもない』(思潮社)を挙げたい。これは意欲的な実験作で、「イリプスIInd」、「驟雨」、「Rose of Fukuyama」に彦坂が発表した短歌作品が再構成されて複数の自由詩となり、収められているのだ。倉橋健一による栞文によれば、雑誌発表時点では「短歌と銘打っていなければ、たいていの人が詩として読んでしまうだろう」が「一首ずつの歌として読むことで、短歌であることを了解」される作品であって、行分けや字空けによって詩に近い見え方をしていた複数の短歌であった。しかし、それらに著者の手がさらに入って、まるで「子実体」の域までに短歌という菌糸が複雑に組み合わさって複数の詩となり、詩集になったのだ。それを知って、収められた自由詩を読むと、五七調や七五調の定型っぽい韻律を持った、何となく短歌を思わせる部分が多いのが判る。まさに融合であろう……いや、正しく言えば、これは自由詩への統合であろう。定型をばらして自由にできるが、自由から定型になる事はまず有り得ない。エントロピーの法則である。
もし、森川が提唱した「複数の詩型を考える」という目的を果たすならば、詩歌トライアスロンは後者のタイプを廃止するべきだ。なぜなら、後者のタイプだと短歌と俳句について上述の知見以上得られるとは思えないからだ。逆に、魅力的な作品を求めつづけるならば、逆に、不利である前者のタイプを廃止するべきだ。
そう、詩歌トライアスロンという企画、延いては詩型の融合や越境といったものは、本質的に矛盾を抱えている。ロマンチックな矛盾である。しかも、自由詩以外の詩型が複数現存していて、いまだにそれぞれの作者が多数いる国は日本しかない事を思えば、そもそも、詩型の融合や越境といったものは、(他の言語文化圏でも自由詩とソネット、自由詩と時調、自由詩と唐詩等といった組合せは考えられるが、詩型の長さや人口から言って)たぶん日本でしか大々的に実施できないし、日本でこそ一番意義深いと思う。そういう意味では、詩型を越境できても国を越境できない。「複数の詩型を考える」事は詩歌を拓く事に直結するし、それは世界的にも意味あるはずだが、なぜかそれを充分にしやすいのは日本国内だけなのだ。これはバロックな矛盾である。
詩歌トライアスロンを構想した人物であり、詩歌梁山泊・代表である森川雅美は「現在、複数の詩型の表現を試みる書き手も少なくありませんが、多くは1つの詩型に限っての表現をしています。しかし、これからの詩歌の可能性を考えるには、複数の詩型を考えることもひとつの道でしょう」と述べているが、「複数の詩型を考える」ために設けられた詩歌トライアスロンの特徴は、日本にある複数の詩型から名前通り3つ(自由詩・短歌・俳句)を選び、応募者に次の2つのうちいずれかの形式で応募する事を第1回目からの規定としている。1つは、1人による3つ全ての詩型の作品であり(三詩型ないものは無効)、1つは三詩型の二つ以上の要素を含んだ作品である。前者は、自由詩1篇・短歌3首・俳句3句をセットとし、後者は、自由詩に俳句や短歌を織り込む、自由詩に準ずる前書(詞書)と短詩型を組合せる、短詩型を連ねて自由詩を構成するなどの手法で詩型を融合させた作品とする(後者は、1つの詩型がオリジナルであれば、他の詩型は既存作品の引用でも構わない)。これら2つの形式で募集する事になったのは、森川の構想を受けて、詩歌梁山泊の会議で評者が後者を発案した上、前者と両方で募集する事を提案したからである。その責任もあって(?)、第1回目の司会は評者が引き受けた。
結果、前述した気鋭の受賞者5名を輩出する事ができたし、過去の候補作の作者たちの名前には現在精力的に活動している詩人、歌人、俳人たちが多く見受けられる。しかし、反省がなくもない。まず、過去の受賞作全部が後者のタイプなのだ。そればかりか、第1回の野村喜和夫奨励作品、第2回の石川美南推薦作、第3回の準入賞作、第4回の次点作、第5回の次点作も全部が後者のタイプなのだ。自由詩・短歌・俳句が独立している前者のタイプが相対的に不利な立場に置かれているのは間違いない。
前者のタイプが相対的に不利である理由として考えられるのは、前者のタイプだと、自由詩・短歌・俳句のうち、最低でも2つは優れていなくては、選者の過半数が支持する事にならない。つまり、選者が支持するためには、応募者は専門詩人、専門歌人、専門俳人のうち2つ以上に相当する必要があるが、そのような人物は日本広しといえども殆どいない。しかも、残り1つの詩型も一定レベルは必要であり、そうでないと深刻な瑕疵とされてしまう。しかも、内容もばらばらだと、選者の印象に残りづらい。内容的に統一感を出すと、今度は融合させて後者にしたくなる。
無論、公開選考会を聴けばわかるが、後者のタイプでも三詩型の能力は問われる。自由詩と融合している短歌や俳句の質が悪いと評価が落ちる。しかし、それだけでは致命傷にならない。なぜなら、融合されている時点で短歌や俳句は機能を失って自由詩のパーツとなり、融合作品全体が新たな自由詩になっているからである。つまり、短歌や俳句に少々まずいものがあっても、自由詩の数行以内の瑕疵として扱われる事になり、前者のタイプのように評価の3分の1や3分の2がいきなり消えてしまう事はない。逆に、融合される自由詩そのものの出来、いや、新たな自由詩となった融合型作品の出来が悪いと致命傷になる。しかし、裏を返せば、自由詩が良ければ高い評価につながりやすいわけである。よって、過去の受賞者に詩人が多いのは不思議ではないだろう。
さて、評者にとって興味深いのは、「融合されている時点で短歌や俳句は機能を失って自由詩のパーツとな」る事である。当然であるが、短い定型詩である短歌や俳句は短くない詩の部分となった時点で存在理由を失う。連歌・連句の百韻や歌仙といった定型詩にしても、構成している長短句のペアは短歌ではないし、発句は(独立した)俳句ではない。況して、自由詩に俳句や短歌を挿入する形で融合させた場合、それらは五七調や七五調の定型っぽい韻律を持った、何となく俳句や短歌を思わせる部分になるだけである。証拠として、今年2月に出た、彦坂美喜子の詩集『子実体日記 だれのすみかでもない』(思潮社)を挙げたい。これは意欲的な実験作で、「イリプスIInd」、「驟雨」、「Rose of Fukuyama」に彦坂が発表した短歌作品が再構成されて複数の自由詩となり、収められているのだ。倉橋健一による栞文によれば、雑誌発表時点では「短歌と銘打っていなければ、たいていの人が詩として読んでしまうだろう」が「一首ずつの歌として読むことで、短歌であることを了解」される作品であって、行分けや字空けによって詩に近い見え方をしていた複数の短歌であった。しかし、それらに著者の手がさらに入って、まるで「子実体」の域までに短歌という菌糸が複雑に組み合わさって複数の詩となり、詩集になったのだ。それを知って、収められた自由詩を読むと、五七調や七五調の定型っぽい韻律を持った、何となく短歌を思わせる部分が多いのが判る。まさに融合であろう……いや、正しく言えば、これは自由詩への統合であろう。定型をばらして自由にできるが、自由から定型になる事はまず有り得ない。エントロピーの法則である。
もし、森川が提唱した「複数の詩型を考える」という目的を果たすならば、詩歌トライアスロンは後者のタイプを廃止するべきだ。なぜなら、後者のタイプだと短歌と俳句について上述の知見以上得られるとは思えないからだ。逆に、魅力的な作品を求めつづけるならば、逆に、不利である前者のタイプを廃止するべきだ。
そう、詩歌トライアスロンという企画、延いては詩型の融合や越境といったものは、本質的に矛盾を抱えている。ロマンチックな矛盾である。しかも、自由詩以外の詩型が複数現存していて、いまだにそれぞれの作者が多数いる国は日本しかない事を思えば、そもそも、詩型の融合や越境といったものは、(他の言語文化圏でも自由詩とソネット、自由詩と時調、自由詩と唐詩等といった組合せは考えられるが、詩型の長さや人口から言って)たぶん日本でしか大々的に実施できないし、日本でこそ一番意義深いと思う。そういう意味では、詩型を越境できても国を越境できない。「複数の詩型を考える」事は詩歌を拓く事に直結するし、それは世界的にも意味あるはずだが、なぜかそれを充分にしやすいのは日本国内だけなのだ。これはバロックな矛盾である。