第146回で高塚謙太郎氏がすでに評している小笠原鳥類『夢と幻想と出鱈目の生物学評論集』(archaeopteryx, 2015年 発行者は榎本櫻湖氏)なのだが、このリレー時評をしばし離脱する前に是非、私からも書かせていただきたい。鳥類詩は、現代詩手帖など詩壇の論評でしばしば取り上げられるものの、新しさや独自性への言及止まりに思う。今回は、なにが独自であるのかをひもとくために①動物という思想の根幹、②読み解かれ辛さの理由、③詩史での位置付けについて、考察した。
「動物」を愛してやまないことを公言している鳥類の作である。「評論集」と謳っているものの、もちろん「生物学評論集」の体は取らず、かといって取り上げた書籍を評論するにあらず、元の書物の本筋から逸脱して幻想的な鳥類世界を開陳させている。冒頭の一編を除いてすべてに本歌取りさながら、生き物の登場する書物から、書かれているよりさらに過剰に生き物を取り出してみせるという手品帽のような不思議な様相を呈している。喚起されたこの生き物達は、生き生きとしているかどうか不明で、時にまるで幻獣のような余計な尾ひれがついており、むしろ生き物というより博物誌に陳列された標本のような場合もあったり、もうすでに生きていない干物だったり、見間違えで楽器だったり、あるいは実体さえ失って音楽そのものだったり、自在な存在形態を擁している。動かない=植物、一方で動くもの=動物という定義を、広義の動物へと汎用し、生命存在とは何か、を問いつめる「生物学」が、根底にあるように思う。じつに清々しいまでの哲学論考である。
冒頭の詩は本歌取りはしておらず、付記によると百人による鳥類の形容を著者自ら想定したもの、つまり、他者をかたった自己紹介とでも意訳できるか。「おお、ペンギンが、南極と宇宙と湖を移動する——私についての百人の証言——」は100までの通し番号が振ってあり、構成が比較的、わかりやすい。
(1)「ペンギンが、水中を動くので、人」
(2)「動物の肉を料理するでしょう、この二種類の動物がいますが、どちらでしょう選ぶクイズであってください答える。クイズのテレビの画面には絵、並んでいて、椅子が並んでいた、人は並んで、人の前のいた、人の後ろの板には色があった飾りがあった、飾りは電気で光っていました。それで、クイズで答える人の前には板があって、板には動物の名前が書かれていたので、板の後ろには水槽があったのですよ。水槽には泳いでいます、この、人、水槽で泳いで、見ている」(クラリネットの人)
(実際は自己の分身にすぎないが)百人も集めたからには、音楽好きの鳥類としては、オーケストラができるとして、オーケストラ仕様としたのだろう。第二詩集が『テレビ』(思潮社、2006年)である鳥類詩にはテレビや水槽が頻繁に出てくるがテレビ番組の内容への感慨や、水槽という展示方法で展示される生き物たちについての一般的理解の範疇での言及は常に皆無である。枠組みとしてのテレビ、枠組みとしての水槽が語られる。ガラス越しであり、テレビに至ってはイリュージョンであるこれらの装置を、見たまま形容することから始まり、時にそれに終始する。ガラス越し以上に近づかない、イリュージョンの目的である知識だとか楽しさだとかの放送内容を鵜呑みにせず(できず)、どこでこのイリュージョンが成立するかに拘泥する。一般的には電波に載せて、制作者がお届けしたい内容を受け取るのが視聴者である筈だが、鳥類という視聴者は「動物が好きなんです」と言って動物番組にチャンネルを合わせたまま、届けてくれる装置への言及(メタ言及)から一歩奥へは踏み込まずに、ただ遠巻きに眺め続ける。対象の上空を旋回しつづける海鳥のようだ。
鳥類自身は幼少時から極度の乱視、と直接聞いたことがあるが、この視点は遠視かなあ、しかしメタ言及としては執拗に細部に執着する点で近視的かなあ、その距離感のむちゃくちゃさが乱視であると言えるのかなあと判断に迷う。いきなり私事で恐縮だが、かくいう私は左右の視力が極度に異なる(これは自慢になる(?)が岩成達也氏作中人物「フレベヴリィ」と一緒である。これまた所蔵が実家にて記憶が曖昧だが『ヒツポポウタムスの唄』だったか『フレベヴリィのいる街』だったかに出てくる。)ため立体視は得意でなく、日頃は単眼視しており、対象の大小や陰影で距離を測っている(ようだ、どうやら医学的には)。これは読書には非常に適していると思う。というのも、書かれた文字に対しては距離感など必要がないからだ。その文字から文章、意味と表現とが渾然一体となった文章のありようを読書体験にて現前させる奥行きは、(つまり空想上の奥行きは)直喩としての「対象の大小・陰影」を距離に換算して成立するものだと思う。これは通常立体視している日常とは、連続しない三次元である。直喩としての陰影とはなんのことですか、という質問には谷崎潤一郎の礼賛する「陰翳」が一番近いと答える。鳥類の独特の乱視的な記述方法は、大小はあるがこの陰翳を持たず、影を引かない。平面的な構成によって、空想の奥行きは奪われる。鳥類詩が、一読では理解しづらい点は、唐突に動物が出てくることではなく、メタ言及へのこだわりではなく、この陰翳の欠如なのではないかと思う。では一読して処理すべき情報量が、空想の二次元といった単純さを持つかと言えば、そうならないように音楽=時間軸という次元を追加してくるのが鳥類の詩の特異な、ほかで見たことのない技法であると提案したい。
(16)「それから、階段の上からはピアノが、十九世紀の音楽を演奏するのが聞こえてくるのでしょう。その音楽に調和する体操があって、紫色の内蔵を使って、展示した」(博物館の人)
平面(フラット)であること自体は20世紀最後半から21世紀のアートの場の定石であるが、“x軸 + y軸 + 詩の中に響く音楽という時間軸”という平面に時間芸術を組み込んだ方法が意識されているという私の論は、この書き手が、詩集の字面だけでは想像しがたいことに、音読に愛着を感じている点からも補強できるのではないかと思う。朗読会での鳥類は、極めて抑揚のない平面的でありながら異常にスピーディで、奇妙に独自の、20世紀朗読シーンのいずれにも該当しないようなパフォーマンスを炸裂させる。
ここまで、鳥類詩について、①動物へのこだわり=生命存在とは何か、の追求②日本文芸の基本を敢えて覆す「陰翳の欠如」による読み辛さ、について言及した。第3に、詩史上の位置づけについて言及したい。
小笠原鳥類作品は、一見変化球に見えるが、(歴程新鋭賞受賞詩人に対して言うまでもないことだが)現代詩の正統な後継者である。正統な後継たるゆえんは、外枠で迂回していつまでも内容に入り込めないタチ、すなわち、メタ言及にあると言える。メタ言及の始点は現代詩の王道に遡及できる。
(36)「(前略)私は絵の具が並んでいる箱を見て、この箱、絵のように食べられるわ、私はクレヨンを食べるのですと言ったら、するとタラを食べる人は、タラであるならどのような色にも塗れるし、タラにはいろいろな料理があります、それからタラを並べて、タラ、タラと言った、タラと言ったのだよ、すると宇宙からタラが来たのです」(タラ)
このタラ、のくだりでは、入澤康夫の「僕」がかかえていた「にしん」を想起せずにはいられない。入澤康夫の第一詩集『倖せ それとも不倖せ』の「夜」(『現代詩文庫』に収載)は、言葉という意味伝達を必然に背負う道具を用いながら、意味を脱構築させる荒技が可能であることを高らかに宣言した現代詩の、その豊穣の時代の黎明を告げる一編としてしばしば引用・評論されることの多い金字塔である。その最後の連で「所で僕がかかえていたのは/新聞紙につつんだ干物のにしんだつた/干物のにしんだつた にしんだつた」とあって、にしんのリフレインは、この詩全体の思想や意味の成立を不可能にさせる単語であると解釈されることが多い。それまで叙情の道具として背景に存在していた詩語は、この時から意味を骨抜きにされ、道具としての役割は保持したまま、どのようにでも在ればよい、これが言語という枠組みである、といきなり舞台装置が露わとなることとなった。以降、詩語は叙情から解放され、空洞となり、その骨組み(メタ)が様々の形態を取りながらも、いずれもがらんどうでインスタレーションされ続けている。「にしん」は、読者と、後世には読者となる書いた日以外の後の著者自身にとって、そこにこうして書かれてある必然性を保有しえない。で、あるならば、にしんでなくて、タラでもいいじゃないか、ということでタラがここで出現するのではないかと私は思うのだがいかがだろうか、鳥類氏。題名からして「鱈」を呼び込んだのは、入澤康夫作品へのオマージュと考える。文学史的出自、正統性をここに宣言したと捉える。
一方で乱暴さというか好き嫌いの激しさも見せる。書かなくてもよい付記で、「稲垣足穂の『ヰタ・マキニカリス』を読んでいない」と余計なことを書いている。現在30歳代後半の読書家にとって、10代の半ばから終わりに立て続けに河出書房から出ていた文庫シリーズで、タルホ、一応読んだはず。我々世代はあのシリーズで、シブサワ・タルホにしびれたはずで、(池袋リブロを経営してくれていた辻井喬氏の思惑に踊らされていただけかもしれないと今は思うが)当時のその読者層は現在、現代詩読者層と被っていると思われるのだが、いかがだろうか。これは丸善にレモンを置いてくるようなささやかだが確実な暴挙だと思う。
追記。…いや、待てよ。いま気づいたが、孫引きという無作法で、読んでいない本を本歌取りしている構造になっている!余計なことではなく、これは敢えて仕組まれた明記であった!書籍や書籍形態を引用するという形から、中身を放り出して、いきなり引用を形骸化している。どこまで空洞化させるつもりだ。
鳥類の想定する読者層はどこなのだろうか。サイエンスファンは博物学的羅列に十分楽しめると思うが文法・詩法が凝りすぎているのでたぶん大勢のサイエンスファンからは意味不明だろう。近似サイエンス・オカルト好きを鳥類自身は公言しているが、あの世界に必須である「飛躍」、その結果としての「わかりやすさ」とはほど遠い。正確な記述を心がけ、かえってわかりづらく共感しづらくさせ、記載が本当かどうか永遠に反証可能性を堅持するように書かれているあたり、むしろサイエンスと親和性がある。(よって2014年のプルリポテント細胞騒動のような爆発的人気は出ないだろう。)世界動物園水族館協会とも、ましてや海生ほ乳類保全に忙しい集団とも違う。現代詩読者層の中央とも読書遍歴を異にする知識体系が、現代詩をまったく別の出口へ向かわせる、そんな壮大な冒険をたどっているようで、わくわくする。
「動物」を愛してやまないことを公言している鳥類の作である。「評論集」と謳っているものの、もちろん「生物学評論集」の体は取らず、かといって取り上げた書籍を評論するにあらず、元の書物の本筋から逸脱して幻想的な鳥類世界を開陳させている。冒頭の一編を除いてすべてに本歌取りさながら、生き物の登場する書物から、書かれているよりさらに過剰に生き物を取り出してみせるという手品帽のような不思議な様相を呈している。喚起されたこの生き物達は、生き生きとしているかどうか不明で、時にまるで幻獣のような余計な尾ひれがついており、むしろ生き物というより博物誌に陳列された標本のような場合もあったり、もうすでに生きていない干物だったり、見間違えで楽器だったり、あるいは実体さえ失って音楽そのものだったり、自在な存在形態を擁している。動かない=植物、一方で動くもの=動物という定義を、広義の動物へと汎用し、生命存在とは何か、を問いつめる「生物学」が、根底にあるように思う。じつに清々しいまでの哲学論考である。
冒頭の詩は本歌取りはしておらず、付記によると百人による鳥類の形容を著者自ら想定したもの、つまり、他者をかたった自己紹介とでも意訳できるか。「おお、ペンギンが、南極と宇宙と湖を移動する——私についての百人の証言——」は100までの通し番号が振ってあり、構成が比較的、わかりやすい。
(1)「ペンギンが、水中を動くので、人」
(2)「動物の肉を料理するでしょう、この二種類の動物がいますが、どちらでしょう選ぶクイズであってください答える。クイズのテレビの画面には絵、並んでいて、椅子が並んでいた、人は並んで、人の前のいた、人の後ろの板には色があった飾りがあった、飾りは電気で光っていました。それで、クイズで答える人の前には板があって、板には動物の名前が書かれていたので、板の後ろには水槽があったのですよ。水槽には泳いでいます、この、人、水槽で泳いで、見ている」(クラリネットの人)
(実際は自己の分身にすぎないが)百人も集めたからには、音楽好きの鳥類としては、オーケストラができるとして、オーケストラ仕様としたのだろう。第二詩集が『テレビ』(思潮社、2006年)である鳥類詩にはテレビや水槽が頻繁に出てくるがテレビ番組の内容への感慨や、水槽という展示方法で展示される生き物たちについての一般的理解の範疇での言及は常に皆無である。枠組みとしてのテレビ、枠組みとしての水槽が語られる。ガラス越しであり、テレビに至ってはイリュージョンであるこれらの装置を、見たまま形容することから始まり、時にそれに終始する。ガラス越し以上に近づかない、イリュージョンの目的である知識だとか楽しさだとかの放送内容を鵜呑みにせず(できず)、どこでこのイリュージョンが成立するかに拘泥する。一般的には電波に載せて、制作者がお届けしたい内容を受け取るのが視聴者である筈だが、鳥類という視聴者は「動物が好きなんです」と言って動物番組にチャンネルを合わせたまま、届けてくれる装置への言及(メタ言及)から一歩奥へは踏み込まずに、ただ遠巻きに眺め続ける。対象の上空を旋回しつづける海鳥のようだ。
鳥類自身は幼少時から極度の乱視、と直接聞いたことがあるが、この視点は遠視かなあ、しかしメタ言及としては執拗に細部に執着する点で近視的かなあ、その距離感のむちゃくちゃさが乱視であると言えるのかなあと判断に迷う。いきなり私事で恐縮だが、かくいう私は左右の視力が極度に異なる(これは自慢になる(?)が岩成達也氏作中人物「フレベヴリィ」と一緒である。これまた所蔵が実家にて記憶が曖昧だが『ヒツポポウタムスの唄』だったか『フレベヴリィのいる街』だったかに出てくる。)ため立体視は得意でなく、日頃は単眼視しており、対象の大小や陰影で距離を測っている(ようだ、どうやら医学的には)。これは読書には非常に適していると思う。というのも、書かれた文字に対しては距離感など必要がないからだ。その文字から文章、意味と表現とが渾然一体となった文章のありようを読書体験にて現前させる奥行きは、(つまり空想上の奥行きは)直喩としての「対象の大小・陰影」を距離に換算して成立するものだと思う。これは通常立体視している日常とは、連続しない三次元である。直喩としての陰影とはなんのことですか、という質問には谷崎潤一郎の礼賛する「陰翳」が一番近いと答える。鳥類の独特の乱視的な記述方法は、大小はあるがこの陰翳を持たず、影を引かない。平面的な構成によって、空想の奥行きは奪われる。鳥類詩が、一読では理解しづらい点は、唐突に動物が出てくることではなく、メタ言及へのこだわりではなく、この陰翳の欠如なのではないかと思う。では一読して処理すべき情報量が、空想の二次元といった単純さを持つかと言えば、そうならないように音楽=時間軸という次元を追加してくるのが鳥類の詩の特異な、ほかで見たことのない技法であると提案したい。
(16)「それから、階段の上からはピアノが、十九世紀の音楽を演奏するのが聞こえてくるのでしょう。その音楽に調和する体操があって、紫色の内蔵を使って、展示した」(博物館の人)
平面(フラット)であること自体は20世紀最後半から21世紀のアートの場の定石であるが、“x軸 + y軸 + 詩の中に響く音楽という時間軸”という平面に時間芸術を組み込んだ方法が意識されているという私の論は、この書き手が、詩集の字面だけでは想像しがたいことに、音読に愛着を感じている点からも補強できるのではないかと思う。朗読会での鳥類は、極めて抑揚のない平面的でありながら異常にスピーディで、奇妙に独自の、20世紀朗読シーンのいずれにも該当しないようなパフォーマンスを炸裂させる。
ここまで、鳥類詩について、①動物へのこだわり=生命存在とは何か、の追求②日本文芸の基本を敢えて覆す「陰翳の欠如」による読み辛さ、について言及した。第3に、詩史上の位置づけについて言及したい。
小笠原鳥類作品は、一見変化球に見えるが、(歴程新鋭賞受賞詩人に対して言うまでもないことだが)現代詩の正統な後継者である。正統な後継たるゆえんは、外枠で迂回していつまでも内容に入り込めないタチ、すなわち、メタ言及にあると言える。メタ言及の始点は現代詩の王道に遡及できる。
(36)「(前略)私は絵の具が並んでいる箱を見て、この箱、絵のように食べられるわ、私はクレヨンを食べるのですと言ったら、するとタラを食べる人は、タラであるならどのような色にも塗れるし、タラにはいろいろな料理があります、それからタラを並べて、タラ、タラと言った、タラと言ったのだよ、すると宇宙からタラが来たのです」(タラ)
このタラ、のくだりでは、入澤康夫の「僕」がかかえていた「にしん」を想起せずにはいられない。入澤康夫の第一詩集『倖せ それとも不倖せ』の「夜」(『現代詩文庫』に収載)は、言葉という意味伝達を必然に背負う道具を用いながら、意味を脱構築させる荒技が可能であることを高らかに宣言した現代詩の、その豊穣の時代の黎明を告げる一編としてしばしば引用・評論されることの多い金字塔である。その最後の連で「所で僕がかかえていたのは/新聞紙につつんだ干物のにしんだつた/干物のにしんだつた にしんだつた」とあって、にしんのリフレインは、この詩全体の思想や意味の成立を不可能にさせる単語であると解釈されることが多い。それまで叙情の道具として背景に存在していた詩語は、この時から意味を骨抜きにされ、道具としての役割は保持したまま、どのようにでも在ればよい、これが言語という枠組みである、といきなり舞台装置が露わとなることとなった。以降、詩語は叙情から解放され、空洞となり、その骨組み(メタ)が様々の形態を取りながらも、いずれもがらんどうでインスタレーションされ続けている。「にしん」は、読者と、後世には読者となる書いた日以外の後の著者自身にとって、そこにこうして書かれてある必然性を保有しえない。で、あるならば、にしんでなくて、タラでもいいじゃないか、ということでタラがここで出現するのではないかと私は思うのだがいかがだろうか、鳥類氏。題名からして「鱈」を呼び込んだのは、入澤康夫作品へのオマージュと考える。文学史的出自、正統性をここに宣言したと捉える。
一方で乱暴さというか好き嫌いの激しさも見せる。書かなくてもよい付記で、「稲垣足穂の『ヰタ・マキニカリス』を読んでいない」と余計なことを書いている。現在30歳代後半の読書家にとって、10代の半ばから終わりに立て続けに河出書房から出ていた文庫シリーズで、タルホ、一応読んだはず。我々世代はあのシリーズで、シブサワ・タルホにしびれたはずで、(池袋リブロを経営してくれていた辻井喬氏の思惑に踊らされていただけかもしれないと今は思うが)当時のその読者層は現在、現代詩読者層と被っていると思われるのだが、いかがだろうか。これは丸善にレモンを置いてくるようなささやかだが確実な暴挙だと思う。
追記。…いや、待てよ。いま気づいたが、孫引きという無作法で、読んでいない本を本歌取りしている構造になっている!余計なことではなく、これは敢えて仕組まれた明記であった!書籍や書籍形態を引用するという形から、中身を放り出して、いきなり引用を形骸化している。どこまで空洞化させるつもりだ。
鳥類の想定する読者層はどこなのだろうか。サイエンスファンは博物学的羅列に十分楽しめると思うが文法・詩法が凝りすぎているのでたぶん大勢のサイエンスファンからは意味不明だろう。近似サイエンス・オカルト好きを鳥類自身は公言しているが、あの世界に必須である「飛躍」、その結果としての「わかりやすさ」とはほど遠い。正確な記述を心がけ、かえってわかりづらく共感しづらくさせ、記載が本当かどうか永遠に反証可能性を堅持するように書かれているあたり、むしろサイエンスと親和性がある。(よって2014年のプルリポテント細胞騒動のような爆発的人気は出ないだろう。)世界動物園水族館協会とも、ましてや海生ほ乳類保全に忙しい集団とも違う。現代詩読者層の中央とも読書遍歴を異にする知識体系が、現代詩をまったく別の出口へ向かわせる、そんな壮大な冒険をたどっているようで、わくわくする。











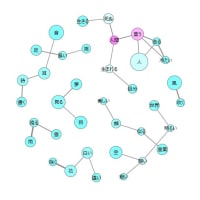


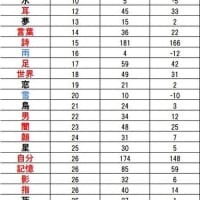
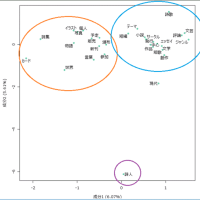
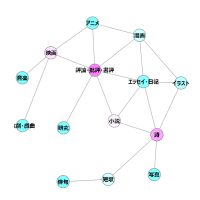
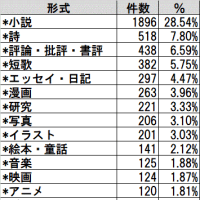
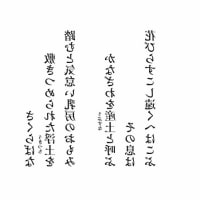
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます