Wikipediaが好きで、気がつくとあのハイパーリンクの海を遊泳しながら眠りに落ちている。外に出られないときは特にそう。そんなんだから、きのうも朝起きて、なんなんだこの「皇嗣」ってページは、誰がひらいたんだ、おれか、と頭を掻いていちにちが始まった。
外に出られないから——あるいは、出ても書店に行く足が向きにくいからか、ここ最近はもっぱらWikipediaに溺れているか、あとはときどき手に届く範囲の本を取って、ぼうっとしている。ぼうっとしているときに眺める本の、たとえば参考文献、あるいは好きなウィトゲンシュタインの一文一節なんかは、まるっきり古き良きハイパーリンクのようで、たぶんウィトゲンシュタインもいまのWikipediaは好きなんじゃなかろうか、やっぱりWikipediaってすごい、と勝手に思う。
何の話だ。
ある一続きのテクストを読んでいるときに、突如として現れるハイパーリンクは、つまりは別のテクストとのジャンクションで、気が向けばいつどのタイミングで乗り換えても良いし、帰ってこないのだって私たちの勝手である。線から線へ、テクストの縦糸と横糸の流れをつねに乗り換えて、今日もどこかのページをひらいたまま朝を迎える。
*
手に届く範囲の詩の本をひらけば、このハイパーリンクに非常に類似しているように思える手法に出会う。引用、と一般に呼ばれているものがそれである。
忽ち列車がすぎ
空の切り傷があって、まるで、
ウラン爆弾の速度
「高雲少量視程十五—二十粁南風二米程度」
彼の母校の校歌に出てくる似島
〽︎安芸の小富士にあかねさし 〽︎若き健児の血は湧きて
男子はコーラスで歯をきれいに揃えて歌う
(……中略……)
*作品中に広島の私立修道高等学校校歌を引用した部分があります。
史実に取材したと思われる詩の行のあいまに現れる校歌は、ほかの行と調和しつつもどこかその引用らしさ——たとえば、その引用箇所は「〽︎」という記号により明示的に示されている——により、ほかの行と異なる位相にいるように思える。なんといえばよいか、すーっと進んできた行が、一瞬車線を変更して、すぐさま戻ってくるような感覚というか。
あるいは、次のような形はどうか。
性交なんかしなくてもよかった。
誰かとふたりで裸になってみたいだけだった。
抱きあって一緒に眠ってみたいだけだった。
だけどそれはとても難しいことだった。
誰とすればいいのかわからないことだった。
ひょっとこは美男ではなかった。
おかめは美女ではなかった。
それでもふたりは対になって踊った。
あけっぴろげな踊りを踊る神様の子孫をまねて。
(……中略……)
*鶴見俊輔著『アメノウズメ伝 神話からのびてくる道』(平凡社)からの引用・参照箇所があります。
この詩を読んで、その最終行に出会うまでに、引用の箇所に気がつくことは一般的な事象だろうか? 「ひょっとこ」と「おかめ」についての踊りに「何かそのような伝承があるのだろう」という予想こそすれ、既存の書籍からの引用であるとは思いにくいのではないか? 個人的な知見の幅も影響していそうで、私がつまるところ無学なだけではあるのかもしれないが——この例の場合であれば引用ということには気がつきにくく、それゆえ詩の行と引用の行の境は曖昧に思える。望月作品のようにあくまで引用箇所を認識しやすいように提示するのを明示的な引用と呼ぶなら、最終的な種明かしを待たない限り引用であることを示さない大崎作品のような作品は暗示的な引用と読んで良いかもしれない。
「銀河鉄道? 池袋から出るの? 私、見たことないよ」
「いや、池袋は発着権が高すぎて買えなかったのだ。椎名町のお祭りのときにどさくさに紛れてホームの目立たないところにわしが乗り場を勝手にこしらえたのだ」
椎名町駅のホームにある銀河鉄道の乗り場は普段は誰にも見えない
「これでいいのだ!」
バカボンのパパが知恵ある言葉を囁くとベニヤ板でできた適当なつくりの乗り場が現れた
(……中略……)
*その後、松本零士先生は順調に回復し、無事に大泉学園に帰られたということを知った。しかし、それがバカボンのパパのおかげだったのかどうかはよくわからない。
![]()
こうなってくると、よくわからない。
ここでは、人口に膾炙している赤塚不二夫『天才バカボン』のフレーズをはじめ、松本零士による人気作品『銀河鉄道999』のモチーフなど、名作漫画由来のキーワードが繰り返し登場する。引用的ではあるが、最後に引用の文献が「*」で記載されるのかと思いきや、そうした通例も破られて、そのまま後日譚が続けられ、引用ということはあくまでも宙ぶらりんのまま詩は終わる。引用という扱いをせず、名称や何かのキーフレーズを置いてみただけで、そこに別のテクストへの入り口が発生するという現象は興味深い。
明示的に、暗示的に、あるいはそれらとは異なってキーワード的に、作品に引用を取り入れるということは、つまり常に読者を他のテクストという別車線へと導き込むような行為である。それは非常にハイパーリンクに似ているが、一方でその引き込む強制力は、おそらく文章に現れる引用の形の方が強くなる。文字情報を読み取るという線形な認知の在り方もあって、読者は飛ぶかどうかを選択可能なハイパーリンクに比べたら、直接そこに書き記されている引用の脇道に飛び込むことから逃れられないのである。
目に飛び込んでくる詩の行は、常にその場その場で評価されていると言える。そのさなか、引用は常に唐突であり、常にその一瞬前の引用ではない行とは別の空間を作り出す。ハイパーリンクという比較的若い技術——と言ってももうかなり手垢がついた——と見比べてみると、作品における引用という手法の不思議さが際立つようにも思えてくる。
*
引用、引用と何度も言ってはいるが、そもそも引用とは何か?
( 名 ) スル
①古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。 「古典の例を-する」
②ポスト━モダンの芸術や建築で作品の中に過去の様式や他人の作品を部分的に組み入れる手法。
上記の辞書的な定義と照らし合わせるなら、詩歌における引用とは、概ね②の意味が大きいだろう。つまりは、説明のためというよりも、ある過去の作品を引いてくることで自身の作品の強度を増そうという意図の方が大きいわけである。
このとき、どうしてもこれらの引用は、著作権との兼ね合いを考えなくてはならない。著作権が継続されている作品を、著作者の許諾なく自由に引用として利用できるような場合は、一般に以下のように定められている。
引用(第32条)
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
上記における「公正な慣行に合致」「正当な範囲内」とは、過去の判例などから、以下のような条件を満たすことを指すとされることが多い。
・明瞭に区別されていること
・主従関係があること
・引用の必要性があること
・量・範囲が必要な範囲内であること
・引用方法が適切であること
・慣例に則るものであること
こうした条件を眺めて心配に思うのは、果たして作品中への別のテクストの取り込みは、引用ないしその他の技法として適法と捉えられうるものなのかどうかということである。
引用の条件を上から見ていくと、これらはいずれもある引用の実施が、その引用元に対する何某かの効果を生み出すことによってこそ、引用であるとして捉えられている。たとえば、評論である記事の一部を引いて、その記事をほかのテクストとも付き合わせて論じる。あるいは、自由詩評で詩を引きながら、その詩や関連する事項を論じる。これらはつまり、ある引用をする目的がその引用元の何かに対して評価や批評による見え方の変化といった効果をもたらす、ということによってその引用性が担保されている。
それに対して、詩歌などの作品になんらかの形で別のテクストを引き込むというのはどうか? これは、先に引いた①の意味での引用であるとはいえないだろう。というのも、ある作品——論のように説明的な文章ではない、詩歌などの作品——がある引用を行うのは、その引用元に対する効果というよりも、その作品自体に対する引用元からの効果を期待するもののように思えるからだ。先に述べたとおり、この場合には②の意味合いでの引用と捉えられることになる。
先ほどまで引いた各詩作品(望月作品・大崎作品・野崎作品)を改めて見たとき、これらは完全にその自身への効果だけを狙った引用をしているわけではなく、その引用元への効果という逆照射もある程度効果として持っているように思う。しかし、あくまでも論としてではなく、詩として作品があるために、より意識されるのはやはり自身を補強する効果としての側面なのである。
そのように考えるなら、これらのような使用方法はどのくらい許容されているものなのだろう?
[質問] 立体作品の表面に、フォトコラージュをプリントしました。 コラージュ素材は、自分で撮影したものではなく、出版物等から収集したものですが、問題 ないでしょうか?
[解説] 条件が必要です。 素材の写真著作物の著作権が消滅していれば、原則としてその利用許諾の必要はありません。著作権が有効である場合で、その写真を複製、展示等する場合には、許諾が必要です。まずは、出版社に問い合わせてみましょう。出版社の同意が得られても、この質問の場合は素材の写真が変形されており、著作者が持つ著作者人格権にかかわるので、著作者に改変利用の許諾を受ける必要があります。他人の肖像写真を利用する場合には、写真に撮影されている本人の肖像権に配慮しておくことも重要です。この質問の場合での利用は、本人の肖像が変形されているためにその利用の態様によっては、本人が名誉を害すると感情的になることも懸念されるからです。
他人が著作権を有する写真(元写真)を無断で用いて自分の作品を制作することは、写真(元写真)の著作権の侵害行為となる。パロディ等のフォトコラージュは、他人が著作権を有する写真(元写真)に改変(コラージュ)を加えるときに著作権侵害が発生する。特に、著作者に許諾を得ずに行ったパロディの制作(元写真の改変)は、著作権(著作者人格権、翻案権等)の侵害となる(上記事例参照)。
(……中略……)
翻案については「江差追分事件」(最判平成13年6月28日)において、翻案と判断するための基準が示されている[注25]。この基準に従って他人の写真著作物を利用したパロディ制作について検討すると、まず①他人の写真著作物と似た写真を撮影する行為は他人の写真著作物への「依拠」であり、②パロディはその性質上、元写真の「表現上の本質的な特徴を直接感得する」ものであるから、パロディは翻案権侵害となる。フォトコラージュに元写真の本質的特徴が感得できないときは、著作権侵害等を免れることができるが、それではパロディの意味が喪失する。また、一定の要件[注13]を満たすことで、引用として許容される可能性はあるが、判例上支持されていない。
ここでは主としてフォトコラージュ、写真におけるパロディについての指摘であるが、これらの問題は、こうした画像に限った話とはいえまい。
実態として他者の著作物の改変を含むような、コラージュと見受けられる詩作品や表現については、完全に禁忌とまでは言えないものの、場合によっては著作権違反を侵すリスクがある。批評のための引用という形は認められている一方で、作品それ自体を作るあるいは強化する目的での引用・コラージュ・パロディと言った手法は、場合によっては他者の著作物を侵しているものと捉えられる場合があるわけである。
表現と法の二者の間で、いかに適切なふるまいを自身で選び取れるか。引用を自作品に取り入れる時、作者としてその法制度上の難しさに直面せざるを得ないことを、私たちは認識していなくてはならない。
*
ハイパーリンクを行き来する生活のさなかで、次から次へと異なる他者のテクストを飛び回っていると、いつのまにかそれぞれのテクストが溶けあって、一体のものに思えてくる瞬間がある。
詩歌に現れる引用も、現れ方としては唐突・異質ながら、実態はその異質さを自作品に取り込んで一体の美的感覚を創出しようという試みのひとつであって、それは行き着くところまでいけば一体の融合物になるのかもしれない。
唐突・異質を取り込もうと欲する交差のさなか、作る側としても、読む側としても、私たちは自身の作品に対する見方や寄り添い方が果たして適切なものであるのか、試され続けているのである。
【註】
[1]「現代詩手帖」2020年2月号(思潮社) pp. 14-17
[2]前掲書[1] pp. 25-27
[3]前掲書[1] pp. 74-76
[4]https://kotobank.jp/word/%E5%BC%95%E7%94%A8-11444
[5]https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
[6]https://ec-houmu.com/right/chosakuken_quotation.html
[7]https://www.t-kougei.ac.jp/static/file/qa201405.pdf
[8]「日本感性工学会論文誌」Vol. 12 No. 1 (Special Issue) pp. 123-133 (2013)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjske/12/1/12_123/_pdf)
*上記註のうち、Webサイトについてはいずれも2020年4月15日閲覧。
外に出られないから——あるいは、出ても書店に行く足が向きにくいからか、ここ最近はもっぱらWikipediaに溺れているか、あとはときどき手に届く範囲の本を取って、ぼうっとしている。ぼうっとしているときに眺める本の、たとえば参考文献、あるいは好きなウィトゲンシュタインの一文一節なんかは、まるっきり古き良きハイパーリンクのようで、たぶんウィトゲンシュタインもいまのWikipediaは好きなんじゃなかろうか、やっぱりWikipediaってすごい、と勝手に思う。
何の話だ。
ある一続きのテクストを読んでいるときに、突如として現れるハイパーリンクは、つまりは別のテクストとのジャンクションで、気が向けばいつどのタイミングで乗り換えても良いし、帰ってこないのだって私たちの勝手である。線から線へ、テクストの縦糸と横糸の流れをつねに乗り換えて、今日もどこかのページをひらいたまま朝を迎える。
*
手に届く範囲の詩の本をひらけば、このハイパーリンクに非常に類似しているように思える手法に出会う。引用、と一般に呼ばれているものがそれである。
忽ち列車がすぎ
空の切り傷があって、まるで、
ウラン爆弾の速度
「高雲少量視程十五—二十粁南風二米程度」
彼の母校の校歌に出てくる似島
〽︎安芸の小富士にあかねさし 〽︎若き健児の血は湧きて
男子はコーラスで歯をきれいに揃えて歌う
(……中略……)
*作品中に広島の私立修道高等学校校歌を引用した部分があります。
(望月遊馬「写真より」[1])
史実に取材したと思われる詩の行のあいまに現れる校歌は、ほかの行と調和しつつもどこかその引用らしさ——たとえば、その引用箇所は「〽︎」という記号により明示的に示されている——により、ほかの行と異なる位相にいるように思える。なんといえばよいか、すーっと進んできた行が、一瞬車線を変更して、すぐさま戻ってくるような感覚というか。
あるいは、次のような形はどうか。
性交なんかしなくてもよかった。
誰かとふたりで裸になってみたいだけだった。
抱きあって一緒に眠ってみたいだけだった。
だけどそれはとても難しいことだった。
誰とすればいいのかわからないことだった。
ひょっとこは美男ではなかった。
おかめは美女ではなかった。
それでもふたりは対になって踊った。
あけっぴろげな踊りを踊る神様の子孫をまねて。
(……中略……)
*鶴見俊輔著『アメノウズメ伝 神話からのびてくる道』(平凡社)からの引用・参照箇所があります。
(大崎清夏「ふたりは対になって踊った」[2])
この詩を読んで、その最終行に出会うまでに、引用の箇所に気がつくことは一般的な事象だろうか? 「ひょっとこ」と「おかめ」についての踊りに「何かそのような伝承があるのだろう」という予想こそすれ、既存の書籍からの引用であるとは思いにくいのではないか? 個人的な知見の幅も影響していそうで、私がつまるところ無学なだけではあるのかもしれないが——この例の場合であれば引用ということには気がつきにくく、それゆえ詩の行と引用の行の境は曖昧に思える。望月作品のようにあくまで引用箇所を認識しやすいように提示するのを明示的な引用と呼ぶなら、最終的な種明かしを待たない限り引用であることを示さない大崎作品のような作品は暗示的な引用と読んで良いかもしれない。
「銀河鉄道? 池袋から出るの? 私、見たことないよ」
「いや、池袋は発着権が高すぎて買えなかったのだ。椎名町のお祭りのときにどさくさに紛れてホームの目立たないところにわしが乗り場を勝手にこしらえたのだ」
椎名町駅のホームにある銀河鉄道の乗り場は普段は誰にも見えない
「これでいいのだ!」
バカボンのパパが知恵ある言葉を囁くとベニヤ板でできた適当なつくりの乗り場が現れた
(……中略……)
*その後、松本零士先生は順調に回復し、無事に大泉学園に帰られたということを知った。しかし、それがバカボンのパパのおかげだったのかどうかはよくわからない。
(野崎有以「銀河鉄道999 椎名町発 大泉学園行き」[3])
こうなってくると、よくわからない。
ここでは、人口に膾炙している赤塚不二夫『天才バカボン』のフレーズをはじめ、松本零士による人気作品『銀河鉄道999』のモチーフなど、名作漫画由来のキーワードが繰り返し登場する。引用的ではあるが、最後に引用の文献が「*」で記載されるのかと思いきや、そうした通例も破られて、そのまま後日譚が続けられ、引用ということはあくまでも宙ぶらりんのまま詩は終わる。引用という扱いをせず、名称や何かのキーフレーズを置いてみただけで、そこに別のテクストへの入り口が発生するという現象は興味深い。
明示的に、暗示的に、あるいはそれらとは異なってキーワード的に、作品に引用を取り入れるということは、つまり常に読者を他のテクストという別車線へと導き込むような行為である。それは非常にハイパーリンクに似ているが、一方でその引き込む強制力は、おそらく文章に現れる引用の形の方が強くなる。文字情報を読み取るという線形な認知の在り方もあって、読者は飛ぶかどうかを選択可能なハイパーリンクに比べたら、直接そこに書き記されている引用の脇道に飛び込むことから逃れられないのである。
目に飛び込んでくる詩の行は、常にその場その場で評価されていると言える。そのさなか、引用は常に唐突であり、常にその一瞬前の引用ではない行とは別の空間を作り出す。ハイパーリンクという比較的若い技術——と言ってももうかなり手垢がついた——と見比べてみると、作品における引用という手法の不思議さが際立つようにも思えてくる。
*
引用、引用と何度も言ってはいるが、そもそも引用とは何か?
( 名 ) スル
①古人の言や他人の文章、また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。 「古典の例を-する」
②ポスト━モダンの芸術や建築で作品の中に過去の様式や他人の作品を部分的に組み入れる手法。
(「大辞林」第三版[4])
上記の辞書的な定義と照らし合わせるなら、詩歌における引用とは、概ね②の意味が大きいだろう。つまりは、説明のためというよりも、ある過去の作品を引いてくることで自身の作品の強度を増そうという意図の方が大きいわけである。
このとき、どうしてもこれらの引用は、著作権との兼ね合いを考えなくてはならない。著作権が継続されている作品を、著作者の許諾なく自由に引用として利用できるような場合は、一般に以下のように定められている。
引用(第32条)
[1]公正な慣行に合致すること,引用の目的上,正当な範囲内で行われることを条件とし,自分の著作物に他人の著作物を引用して利用することができる。同様の目的であれば,翻訳もできる。(注5)[2]国等が行政のPRのために発行した資料等は,説明の材料として新聞,雑誌等に転載することができる。ただし,転載を禁ずる旨の表示がされている場合はこの例外規定は適用されない。
(文化庁「著作物が自由に使える場合」[5])
上記における「公正な慣行に合致」「正当な範囲内」とは、過去の判例などから、以下のような条件を満たすことを指すとされることが多い。
・明瞭に区別されていること
・主従関係があること
・引用の必要性があること
・量・範囲が必要な範囲内であること
・引用方法が適切であること
・慣例に則るものであること
(参考:「他人の著作物を適法に「引用」する際のルール」[6])
こうした条件を眺めて心配に思うのは、果たして作品中への別のテクストの取り込みは、引用ないしその他の技法として適法と捉えられうるものなのかどうかということである。
引用の条件を上から見ていくと、これらはいずれもある引用の実施が、その引用元に対する何某かの効果を生み出すことによってこそ、引用であるとして捉えられている。たとえば、評論である記事の一部を引いて、その記事をほかのテクストとも付き合わせて論じる。あるいは、自由詩評で詩を引きながら、その詩や関連する事項を論じる。これらはつまり、ある引用をする目的がその引用元の何かに対して評価や批評による見え方の変化といった効果をもたらす、ということによってその引用性が担保されている。
それに対して、詩歌などの作品になんらかの形で別のテクストを引き込むというのはどうか? これは、先に引いた①の意味での引用であるとはいえないだろう。というのも、ある作品——論のように説明的な文章ではない、詩歌などの作品——がある引用を行うのは、その引用元に対する効果というよりも、その作品自体に対する引用元からの効果を期待するもののように思えるからだ。先に述べたとおり、この場合には②の意味合いでの引用と捉えられることになる。
先ほどまで引いた各詩作品(望月作品・大崎作品・野崎作品)を改めて見たとき、これらは完全にその自身への効果だけを狙った引用をしているわけではなく、その引用元への効果という逆照射もある程度効果として持っているように思う。しかし、あくまでも論としてではなく、詩として作品があるために、より意識されるのはやはり自身を補強する効果としての側面なのである。
そのように考えるなら、これらのような使用方法はどのくらい許容されているものなのだろう?
[質問] 立体作品の表面に、フォトコラージュをプリントしました。 コラージュ素材は、自分で撮影したものではなく、出版物等から収集したものですが、問題 ないでしょうか?
[解説] 条件が必要です。 素材の写真著作物の著作権が消滅していれば、原則としてその利用許諾の必要はありません。著作権が有効である場合で、その写真を複製、展示等する場合には、許諾が必要です。まずは、出版社に問い合わせてみましょう。出版社の同意が得られても、この質問の場合は素材の写真が変形されており、著作者が持つ著作者人格権にかかわるので、著作者に改変利用の許諾を受ける必要があります。他人の肖像写真を利用する場合には、写真に撮影されている本人の肖像権に配慮しておくことも重要です。この質問の場合での利用は、本人の肖像が変形されているためにその利用の態様によっては、本人が名誉を害すると感情的になることも懸念されるからです。
(「東京工芸大学芸術学部 作品制作と著作権Q&A集」[7])
他人が著作権を有する写真(元写真)を無断で用いて自分の作品を制作することは、写真(元写真)の著作権の侵害行為となる。パロディ等のフォトコラージュは、他人が著作権を有する写真(元写真)に改変(コラージュ)を加えるときに著作権侵害が発生する。特に、著作者に許諾を得ずに行ったパロディの制作(元写真の改変)は、著作権(著作者人格権、翻案権等)の侵害となる(上記事例参照)。
(……中略……)
翻案については「江差追分事件」(最判平成13年6月28日)において、翻案と判断するための基準が示されている[注25]。この基準に従って他人の写真著作物を利用したパロディ制作について検討すると、まず①他人の写真著作物と似た写真を撮影する行為は他人の写真著作物への「依拠」であり、②パロディはその性質上、元写真の「表現上の本質的な特徴を直接感得する」ものであるから、パロディは翻案権侵害となる。フォトコラージュに元写真の本質的特徴が感得できないときは、著作権侵害等を免れることができるが、それではパロディの意味が喪失する。また、一定の要件[注13]を満たすことで、引用として許容される可能性はあるが、判例上支持されていない。
(鈴木康平・松縄正登「フォトコラージュの諸問題—著作権、技術、社会倫理上の問題を中心として—」[8])
ここでは主としてフォトコラージュ、写真におけるパロディについての指摘であるが、これらの問題は、こうした画像に限った話とはいえまい。
実態として他者の著作物の改変を含むような、コラージュと見受けられる詩作品や表現については、完全に禁忌とまでは言えないものの、場合によっては著作権違反を侵すリスクがある。批評のための引用という形は認められている一方で、作品それ自体を作るあるいは強化する目的での引用・コラージュ・パロディと言った手法は、場合によっては他者の著作物を侵しているものと捉えられる場合があるわけである。
表現と法の二者の間で、いかに適切なふるまいを自身で選び取れるか。引用を自作品に取り入れる時、作者としてその法制度上の難しさに直面せざるを得ないことを、私たちは認識していなくてはならない。
*
ハイパーリンクを行き来する生活のさなかで、次から次へと異なる他者のテクストを飛び回っていると、いつのまにかそれぞれのテクストが溶けあって、一体のものに思えてくる瞬間がある。
詩歌に現れる引用も、現れ方としては唐突・異質ながら、実態はその異質さを自作品に取り込んで一体の美的感覚を創出しようという試みのひとつであって、それは行き着くところまでいけば一体の融合物になるのかもしれない。
唐突・異質を取り込もうと欲する交差のさなか、作る側としても、読む側としても、私たちは自身の作品に対する見方や寄り添い方が果たして適切なものであるのか、試され続けているのである。
【註】
[1]「現代詩手帖」2020年2月号(思潮社) pp. 14-17
[2]前掲書[1] pp. 25-27
[3]前掲書[1] pp. 74-76
[4]https://kotobank.jp/word/%E5%BC%95%E7%94%A8-11444
[5]https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
[6]https://ec-houmu.com/right/chosakuken_quotation.html
[7]https://www.t-kougei.ac.jp/static/file/qa201405.pdf
[8]「日本感性工学会論文誌」Vol. 12 No. 1 (Special Issue) pp. 123-133 (2013)(https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjske/12/1/12_123/_pdf)
*上記註のうち、Webサイトについてはいずれも2020年4月15日閲覧。











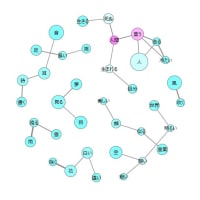


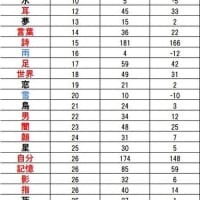
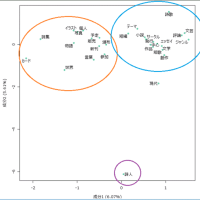
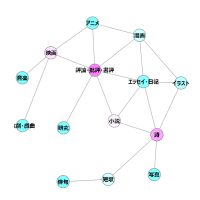
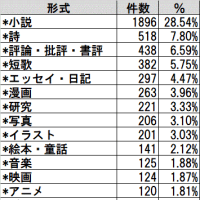
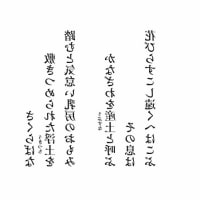
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます