26文字詰め、タイトル頁は14行、テキスト頁は16行、見開き30行。たっぷりの余白を額縁として、美しい矩形に収められた散文詩が22篇配されている。薄手なのに圧巻の読み応えである。装画は滲みの積層を活かした水彩画。有機的な幾何学模様が不思議な浮遊感と生命力を発揮している。海東の手造りの個人誌「ピエ」で静かな存在感を発揮していた本田征爾の作品だが、微妙な色彩の諧調の再現(そのための用紙の選択と色校正)、さらには微かな型押しを施して、本田のモティーフが有する形の境域、とでもいうべきもの――垂らし込みの技と礬水の溶け具合の調整によって地色との間に生じる、シャボン玉の膜のような繊細な境界線――の再現に挑戦した装幀に目を瞠る。
読み始めると、ぎっしり文字が“詰まって”いるのに、風が渡り、光が通う、不思議な空間が広がっている。流れるように続く言葉は時に思弁的で充実した重さを持つのに、軽やかな読後感が余韻として残る。
初めて海東の詩を読む人の脳裏には、どのような声音で再生されるのだろう。クリアで澄んだ、やわらかなソプラノではないだろうか。私は実際に会い、彼女の朗読を聞いたことがあるので特にそう思うのかもしれないが、肉声を知る詩人の作品であっても異なる声質や声音で脳内再生される詩集もあるので、この詩集の言葉そのものの持つ響き――です、ますという丁寧な言い切りの形、息の長いフレーズを言い継いでいくときの呼吸や、読点が打たれた時の残響、“て”止めなどの終止が喚起する響き――そのものが、しなやかに張りのある、やわらかいソプラノなのだと思う。
主題は〈家〉。家にカッコを付けたのは、家という単語に付随する重たい圧や目に視えぬ感情的なしがらみのようなマイナスのイメージも、あるいは磨き上げたり内装を整えたりしていく時間が付与するプラスのイメージも拭い去られ、居住空間という明朗なテーマとそこに動く〈ひと〉の気配が鮮やかに浮かび上がる作品群だからである。テーマは住居である、と呼ぶ方がふさわしいかもしれない。建築空間についての細やかな観察と感受、語り手の思弁が綴られていく作品には、しばしば注が施される。それは住宅や建材についての事典や、哲学や美学の観点から見た評論、随想などから引かれている。
語り手はどこにいるのだろうか。この住居の中で動き回っている〈ひと〉のようであるが、この〈ひと〉は、“暮らしている”というような生活臭を感じさせない。書名のドールハウスは文字通り訳せば人形の家だが、語り手を人形として押し込める抑圧の装置としては機能しない。三方の壁に囲まれた“人形”の家、縮小された家の模型のように、一面を透過して全体を見渡すことのできる空間が文字の向こうに広がっている。その中をこの〈ひと〉は自在に動き、自身の住む〈家〉とその中で起居する〈家族〉のことにも触れてはいるものの……“生活”に伴う様々な感情を沈殿させ、その上澄みの澄んだ部分で思索している。その〈ひと〉の五感を自らのものとして体感し、素通しの“ドールハウス”の前面を透過して〈ひと〉の動きを観察している見えない存在が、この作品の全体を統一している語り手である、といってもいいかもしれない。ソプラノの声音を持つのはこの見えざる語り手であり、中で動いている〈ひと〉は無言だ。ドールハウスの中に配置した人形や動物たちを自在に動かして夢想空間に遊ぶ少女、その心のうちでは人形や動物たちが自立して生きて動いている、そんな二重の空間が、そこに出現しているようにみえる。
この〈ひと〉は〈家〉から外に出て庭の手入れをしたり(「プリズム」「庭」など)、裏山に出かけて行ってキノコ狩りをしたり、近傍の街並みを歩いたりもするが(「動線」「仮寓」など)、作品の多くはこの〈ひと〉の居住する空間を構成する様々なパーツ……階段や窓、壁といった構成要素や、クッションフロア、砂壁、タイルといった建材、廊下や部屋といった居住空間の具体的な描写から始まり、いつしか○○とは何か、という本質への問いや機能の果たす役割、性質の吟味や思弁的考察へと飛躍していく。しかもその飛躍が、論理によるというよりは、言葉の響きやイメージの連想、体感が引き寄せる感覚による飛躍といった次元で起きているのだ。こうした具象/抽象という、いわば縦方向のレヴェルの重層と共に、肉体のある居住空間と、その肉体の内で感受し思索し、言葉を紡いでいる精神の働く空間という横方向のレヴェルの重層(多層)も描き出される。縦と横の安定した広がりがあり、斜め方向へのスピーディーな上昇や下降、螺旋を描くようなうねりやエネルギーの奔出といった不安定な動きはほとんど見られない。こうした特質が、明晰で静かな空間を生み出している。
この〈家〉は、言葉を生み出す人の住まう〈家〉でもあり、その〈家〉そのものが語り手を介して思弁し、語り出している、とも読める。居住空間が詩空間の暗喩となっていることは説明を要しないが、具体的に詩や言葉に言及している部分もある。
だんだんと上ってゆく階段の裏側が階段下の小部屋にあらわになり、剥きだしになったその部分は、ふいに現れて消える鳥の後ろ姿に似て、支えられてあるのか吊られてあるのか、解けない謎があるとしたら階段の自立についてですけれど、どことなくリズムのようであり詩のようであり、こうして2階の精神性は日ごと夜ごと漂いつつ形成される一方で、階段下の余白はすぐ動線や陽当たりの事情をまぬがれ得ぬものとなり、お風呂場の湿気が流れこめば陰気さをおび、ひとが増えると使いにくさがつのり、見えて隠れる、階段のその部位に頭をぶつけてしまうとき、余剰のうれしさより削られた空間への無念がもたげることこそが、潜在する階段の犠牲性といえますが……「とりいそぎ」や「ねんのため」が重ね置かれぶら下げられ、白いトランクだって待ち焦がれていますから、余白だった場所が部屋のすべてにおよぶ、これら渾沌は住まうひとらの表象とおぼえるべきで、余剰の生かし方は殺し方であることを、埋もれても埋もれずに中空をよぎる階段は示唆するのかもしれず、そうこうするうちに2階に育まれたひとが、蟻の巣観察キットで飼育をはじめたのも階段下のできごとでしたが、道すじを作ってせっせと運んでいた主体ごと、みんなどこかに死蔵されています。
「デッドスペース」から引いた。(文字詰めには従っていない。)息の長い長文が続く海東の作品群の中でも、すべてを一文で構成した一作。読点が生む中断や途切れを、継続する文章で塗り込めようとしているかのようだ。階段は、〈歩いて他のレベルに行くことを可能とさせる水平の段のつらなりからなる構成的要素〉だと事典には定義されているという。巻頭に置かれた「下廻り階段」に付された注で知ったことだが、〈水平の段のつらなり〉は改行によって他の行へ移行する文章の連なりでもあり、文章の連なりが具体的事物からなる世界から精神や意識、イメージの息づく場所への移行を可能とするものでもあることに気づかされる時、居住空間についての記述は詩空間、文章空間についての記述へと、いつのまにか移行している。
デッドスペースは、階段の裏側に出現する空間である。文章で言えば行の裏側、行間と呼ばれる場所、ということになろうか、しばしば壁面で覆われ、隠される場所でもある。空間のまま残されれば“有効活用”されていないことになるのか。デッド、つまり死んだ場所は、収納場所として用いられることで生きた場所になるのか……。〈余剰のうれしさ〉が文学や魂の豊かさへのレベルへの移行、〈削られた空間への無念〉が実生活のレベルへの回帰、その間を繋ぐ階段と、その階段の裏側に出現する空間、と読んでみる。階段下で、この〈家〉で育った子どもが蟻の飼育をはじめた、というのも面白い。実生活における“事実”の記載であるのかもしれないが、地面の下、という見えない場所に蟻/在りが巣という空間を作り上げていく、それを観察して豊かな気づきを得ていく〈ひと〉がいる。一般的には、収納場所として “有効活用”されていない場所は“死んだ”空間とみなされ、有用性を持たない。昨今の有用性の議論にも通じていくが、文字として表に現れ、読める部分だけが有用と考えるのか、そうした有用性の議論から見た時に〈デッド〉と名づけられる場所こそが、見えないものの動きや成長、存在を大切に守っている場所であるのかもしれない……そんなことを考えさせてくれる。
もうひとつ、言葉の出てくる作品を引こう。
朝のひかりが射しこむのは窓があるためだけど、べつだんひかりを求めるわけでもないと斜に構えていることこそすでに奔放に伸びた自我の茎のせりふだし、外に向かって伸びるべきものが内に向いたり折れ曲がったり、あのときことばがあってよかったのは曲がったさきにないものを見破ってくれるためで、何ごとかを書きつけるうちについ窓枠を踏み越えて、と千鳥はいうのです。
春のあの日、わたしは立たなければならず、そう決めてことばをつむいだのだから、ノートに書き留めるのはあなたがみちてゆく時間のことですし、わたしが発することばは窓を超えて羽ばたいてかまわず、窓辺て受けた佳いものを渡そうとすればおびただしく舞い降りてきますが、許したくないことには毅然と鎖して面会謝絶するだけの、窓辺にはこんな力もあるのよと、みちるはいいます。
「窓辺だけの部屋」から引いた。ひらがなの多用もあいまって、明るい陽射しを感じさせる空間で行われる〈千鳥〉と〈みちる〉、この二人の会話は、チルチルとミチルの二人が追い求める青い鳥を呼び寄せる。千鳥格子のカーテンが、この〈家〉には実際にあるのかもしれない(「ドールハウス」)。みちる、は、光が満ちる、〈佳いもの〉が満ちる、を含意しているだろう。具体的な事物が言葉を呼び寄せ、その言葉がまた、過去の物語やイメージを呼び、そのレベルへの移行を促す。そのレベルに素直に移行した語り手は、導き手となった言葉に〈家〉に住まう〈ひと〉としての肉体――イメージ界における具現化、であるが――を与え、語らせる。
窓は閉じたままであっても硝子によって光を透過させる。〈佳いもの〉を取り入れる開口部であると共に、満たされた部屋の豊かさを逃さないように防御するものでもあり、また、外部から入りこもうとする〈許したくないこと〉を遮断する機能を持つ。開けば風が通い、外部へと〈羽ばたいて〉いくことも自由。「窓辺だけの部屋」には、”Hope” is the thing with feathers というエミリー・ディキンソンの詩の1節がエピグラフとして置かれている。希望は羽ばたいていくものなのか。
「窓辺だけの部屋」には春の気配が満ち満ちているが、「換気」は真冬を描いている。
窓はあいていたのです。吹雪のきれぎれを燦めかせながら青い鳥は飛びこんできて、猛スピードのまま壁に衝突しては方向を変え、またぶつかることをくりかえすので、逃がしてやりたい一心で布を手に窓へ追い立て、けれども雪空へふたたび逃がすことが、よその家のかごを誤って飛びだしてきたであろうナイーブな鳥の死を意味することもわかっています。気がつくと床の上に落ちています。(中略)本の小口に付けられた色が、読んでいる最中はうしなわれるように、あざやかな青は目の前を消えています。あのあと鳥をどうしたか。雪の庭に埋めたか、蘇生させたのか、雪のふりしきる朝にどうして窓はあいていて、青はどこへ行ったのか。(中略)個室に備えられているのは一酸化炭素を発するポータブルストーブ。空気は入れ換えねばなりません。部屋ごとの換気は気分にゆだねられ(中略)ふりかえる性質のひとはしきりと窓をあけたがります。(中略)やがて住まいの気密性が向上すると、計画的な機械換気が不可欠になりますが古い家では計測も計算もなりたたず(中略)あの日は海側の部屋にいて、坂を上ってくるいとこたちを待ちあぐねているはずですが、記憶を飛びまわるのは山に面したもうひとりの部屋。ふたつの部屋は繋がっていたとでもいうのでしょうか。気がつくと鳥は床の上に落ちています。
青い鳥は、海側から(海外から)やってくるのだろうか。誰かの〈家〉で(精神世界で)、大切に飼われていた(養われていた)鳥が(ことばが)わたしの〈家〉に飛び込んで来る。居間には暖かいストーブがあり、この〈家〉の〈ひと〉たちが集っているが、個室には有毒なガスを発するポータブルストーブしかない。個室に閉じこもっていれば中毒を起こして死に至るので換気が必然となるわけだが、それは他者の生きた言葉を取り入れなければ自家中毒を起こす、という詩論でもある。〈家〉の外は、命を奪う吹雪の吹き荒れる世界。そんなときに(そんな時だからこそ?)窓を開けている部屋に果敢に飛び込んで来る青い鳥、しかしその鳥を、自分の〈家〉の壁が死なせてしまう哀しさ。壁のない(限界のない)家に住んでいればよかったのか。真冬である。命を奪う雪の中に住むのは不可能、床に落ちた色あせた鳥を、語り手は黙って見おろしている・・・。
この家、そのものが不動のものでも固定したものでもない、そのことも面白いと思う。
家は思想のやどりであって、たてましのたびにかたちをうしなってゆくばあい、すでに流浪の旅にあるとみてとれます。たとえ別れを惜しんで、柱をいだき壁をなでさすりしても、一見して合理的な思考回路によって三角の屋根でさまよいをはじめ、矩形や台形のすがたを増やし、分裂したり融合したり、そのころには住み手を離れ、アンバランスな両翼ではばたいています。(中略)住人のなかには、空想の渡り廊下を通って鍵のない自室にこもる者も出てきます。不在のときでも出入り自由ですが領域は保たれ(中略)複雑な形状の家ほど、雨漏りすが漏りひび割れのリスクが高く、繋いだ部分のすきまがひろがったり縮んだりすることこそ点検すべき点です。風のことは風にきくようにしなさい。縁の下から声がしても、屋根裏に届く前に次のたてましは決まってしまい、まるでたてましを追いかけて今をたてましているみたいな自転車操業に、きりきりまいの日々。(中略)そんなときです、妹というものになってみたいと思うのは。渡り廊下で夢想するのはどこか万能な妹で、兄のせなかに隠れているようで原初的な問いの手綱を握り、危険なことには目端が利くので要所で的確な判断をくだし、なおかつ理屈にならない駄々をこねられる、そんな妹が欲しいのではなく、そんな妹で自分があれば家の失踪を杞憂することもないのにと(中略)それもまたたてましの欲求のひとつかもしれず、かたちをうしなうとみせかけて、よりいっそう執拗に、実はかたちに執着する家の尖端が、こうしてまたたてまされてゆきます。
「たてまし」は、〈家〉そのものが羽ばたいて“ここ”から居なくなることをも想起させる。複雑になり過ぎれば破綻する、そのことを分かっていてもこの〈家〉の住人達は次々と部屋を建て増しし、渡り廊下を渡って離れにこもったりまた居間に戻ったり、どこかへ出かけて行ったりと自在に暮らしているようであり、この家そのものもハウルの動く城ではないが、自らどこかへ、流浪の旅や増築した〈翼〉でどこかへ羽ばたこうとしてもいるようにみえる。語り手の中の複数のペルソナが、みずからの欲求のままに建て増しを繰り返した家(構造体)は、語り手を乗せていったいどこへ行こうとしているのか……
目に見える構造を目に視えない構造で支える、階段とデッドスペースの関係を考える。それは、兄の背中に隠れているようでいて、実際は〈原初的な問いの手綱を握り(中略)的確な判断をくだし(中略)なおかつ駄々をこねられる〉妹の存在の重要性と重なる。ひとつのレベルから別のレベルへと移行するという目的を果たすための、目に見える構造(文章、行)が兄ならば、目に視えないところで、自由に空想を羽ばたかせ、なおかつ兄の背中に隠れて逸脱しない、常に問いを持ち理屈に合わないわがままも許される、そんな行間、文字の向こう側の領域が妹。兄がいなくては詩作品は成り立たないが、実際に詩を生きた空間にしているのは妹であるのかもしれない……そんなわがままな読み方も許してくれるのに、歪さや軋み、不必要なでっぱりや移動に不都合な空間の屈折などは排除された、快適で暮らしやすい居住空間。海東の美しく正確な文章、豊かな多層化と整然とした移行を可能とする構造、光や風、花やきのこといった外界の豊かさを自在に取り込み、〈家〉に暮らす〈ひと〉もまた、自在に出入りする〈家〉とその近郊も含めた居住空間。そこに海東の詩は“住んで”いる。この家の招きに預かりたい者は、黙って詩集の扉を開けばよい。鍵は、かけられていないのだから。
読み始めると、ぎっしり文字が“詰まって”いるのに、風が渡り、光が通う、不思議な空間が広がっている。流れるように続く言葉は時に思弁的で充実した重さを持つのに、軽やかな読後感が余韻として残る。
初めて海東の詩を読む人の脳裏には、どのような声音で再生されるのだろう。クリアで澄んだ、やわらかなソプラノではないだろうか。私は実際に会い、彼女の朗読を聞いたことがあるので特にそう思うのかもしれないが、肉声を知る詩人の作品であっても異なる声質や声音で脳内再生される詩集もあるので、この詩集の言葉そのものの持つ響き――です、ますという丁寧な言い切りの形、息の長いフレーズを言い継いでいくときの呼吸や、読点が打たれた時の残響、“て”止めなどの終止が喚起する響き――そのものが、しなやかに張りのある、やわらかいソプラノなのだと思う。
主題は〈家〉。家にカッコを付けたのは、家という単語に付随する重たい圧や目に視えぬ感情的なしがらみのようなマイナスのイメージも、あるいは磨き上げたり内装を整えたりしていく時間が付与するプラスのイメージも拭い去られ、居住空間という明朗なテーマとそこに動く〈ひと〉の気配が鮮やかに浮かび上がる作品群だからである。テーマは住居である、と呼ぶ方がふさわしいかもしれない。建築空間についての細やかな観察と感受、語り手の思弁が綴られていく作品には、しばしば注が施される。それは住宅や建材についての事典や、哲学や美学の観点から見た評論、随想などから引かれている。
語り手はどこにいるのだろうか。この住居の中で動き回っている〈ひと〉のようであるが、この〈ひと〉は、“暮らしている”というような生活臭を感じさせない。書名のドールハウスは文字通り訳せば人形の家だが、語り手を人形として押し込める抑圧の装置としては機能しない。三方の壁に囲まれた“人形”の家、縮小された家の模型のように、一面を透過して全体を見渡すことのできる空間が文字の向こうに広がっている。その中をこの〈ひと〉は自在に動き、自身の住む〈家〉とその中で起居する〈家族〉のことにも触れてはいるものの……“生活”に伴う様々な感情を沈殿させ、その上澄みの澄んだ部分で思索している。その〈ひと〉の五感を自らのものとして体感し、素通しの“ドールハウス”の前面を透過して〈ひと〉の動きを観察している見えない存在が、この作品の全体を統一している語り手である、といってもいいかもしれない。ソプラノの声音を持つのはこの見えざる語り手であり、中で動いている〈ひと〉は無言だ。ドールハウスの中に配置した人形や動物たちを自在に動かして夢想空間に遊ぶ少女、その心のうちでは人形や動物たちが自立して生きて動いている、そんな二重の空間が、そこに出現しているようにみえる。
この〈ひと〉は〈家〉から外に出て庭の手入れをしたり(「プリズム」「庭」など)、裏山に出かけて行ってキノコ狩りをしたり、近傍の街並みを歩いたりもするが(「動線」「仮寓」など)、作品の多くはこの〈ひと〉の居住する空間を構成する様々なパーツ……階段や窓、壁といった構成要素や、クッションフロア、砂壁、タイルといった建材、廊下や部屋といった居住空間の具体的な描写から始まり、いつしか○○とは何か、という本質への問いや機能の果たす役割、性質の吟味や思弁的考察へと飛躍していく。しかもその飛躍が、論理によるというよりは、言葉の響きやイメージの連想、体感が引き寄せる感覚による飛躍といった次元で起きているのだ。こうした具象/抽象という、いわば縦方向のレヴェルの重層と共に、肉体のある居住空間と、その肉体の内で感受し思索し、言葉を紡いでいる精神の働く空間という横方向のレヴェルの重層(多層)も描き出される。縦と横の安定した広がりがあり、斜め方向へのスピーディーな上昇や下降、螺旋を描くようなうねりやエネルギーの奔出といった不安定な動きはほとんど見られない。こうした特質が、明晰で静かな空間を生み出している。
この〈家〉は、言葉を生み出す人の住まう〈家〉でもあり、その〈家〉そのものが語り手を介して思弁し、語り出している、とも読める。居住空間が詩空間の暗喩となっていることは説明を要しないが、具体的に詩や言葉に言及している部分もある。
だんだんと上ってゆく階段の裏側が階段下の小部屋にあらわになり、剥きだしになったその部分は、ふいに現れて消える鳥の後ろ姿に似て、支えられてあるのか吊られてあるのか、解けない謎があるとしたら階段の自立についてですけれど、どことなくリズムのようであり詩のようであり、こうして2階の精神性は日ごと夜ごと漂いつつ形成される一方で、階段下の余白はすぐ動線や陽当たりの事情をまぬがれ得ぬものとなり、お風呂場の湿気が流れこめば陰気さをおび、ひとが増えると使いにくさがつのり、見えて隠れる、階段のその部位に頭をぶつけてしまうとき、余剰のうれしさより削られた空間への無念がもたげることこそが、潜在する階段の犠牲性といえますが……「とりいそぎ」や「ねんのため」が重ね置かれぶら下げられ、白いトランクだって待ち焦がれていますから、余白だった場所が部屋のすべてにおよぶ、これら渾沌は住まうひとらの表象とおぼえるべきで、余剰の生かし方は殺し方であることを、埋もれても埋もれずに中空をよぎる階段は示唆するのかもしれず、そうこうするうちに2階に育まれたひとが、蟻の巣観察キットで飼育をはじめたのも階段下のできごとでしたが、道すじを作ってせっせと運んでいた主体ごと、みんなどこかに死蔵されています。
「デッドスペース」から引いた。(文字詰めには従っていない。)息の長い長文が続く海東の作品群の中でも、すべてを一文で構成した一作。読点が生む中断や途切れを、継続する文章で塗り込めようとしているかのようだ。階段は、〈歩いて他のレベルに行くことを可能とさせる水平の段のつらなりからなる構成的要素〉だと事典には定義されているという。巻頭に置かれた「下廻り階段」に付された注で知ったことだが、〈水平の段のつらなり〉は改行によって他の行へ移行する文章の連なりでもあり、文章の連なりが具体的事物からなる世界から精神や意識、イメージの息づく場所への移行を可能とするものでもあることに気づかされる時、居住空間についての記述は詩空間、文章空間についての記述へと、いつのまにか移行している。
デッドスペースは、階段の裏側に出現する空間である。文章で言えば行の裏側、行間と呼ばれる場所、ということになろうか、しばしば壁面で覆われ、隠される場所でもある。空間のまま残されれば“有効活用”されていないことになるのか。デッド、つまり死んだ場所は、収納場所として用いられることで生きた場所になるのか……。〈余剰のうれしさ〉が文学や魂の豊かさへのレベルへの移行、〈削られた空間への無念〉が実生活のレベルへの回帰、その間を繋ぐ階段と、その階段の裏側に出現する空間、と読んでみる。階段下で、この〈家〉で育った子どもが蟻の飼育をはじめた、というのも面白い。実生活における“事実”の記載であるのかもしれないが、地面の下、という見えない場所に蟻/在りが巣という空間を作り上げていく、それを観察して豊かな気づきを得ていく〈ひと〉がいる。一般的には、収納場所として “有効活用”されていない場所は“死んだ”空間とみなされ、有用性を持たない。昨今の有用性の議論にも通じていくが、文字として表に現れ、読める部分だけが有用と考えるのか、そうした有用性の議論から見た時に〈デッド〉と名づけられる場所こそが、見えないものの動きや成長、存在を大切に守っている場所であるのかもしれない……そんなことを考えさせてくれる。
もうひとつ、言葉の出てくる作品を引こう。
朝のひかりが射しこむのは窓があるためだけど、べつだんひかりを求めるわけでもないと斜に構えていることこそすでに奔放に伸びた自我の茎のせりふだし、外に向かって伸びるべきものが内に向いたり折れ曲がったり、あのときことばがあってよかったのは曲がったさきにないものを見破ってくれるためで、何ごとかを書きつけるうちについ窓枠を踏み越えて、と千鳥はいうのです。
春のあの日、わたしは立たなければならず、そう決めてことばをつむいだのだから、ノートに書き留めるのはあなたがみちてゆく時間のことですし、わたしが発することばは窓を超えて羽ばたいてかまわず、窓辺て受けた佳いものを渡そうとすればおびただしく舞い降りてきますが、許したくないことには毅然と鎖して面会謝絶するだけの、窓辺にはこんな力もあるのよと、みちるはいいます。
「窓辺だけの部屋」から引いた。ひらがなの多用もあいまって、明るい陽射しを感じさせる空間で行われる〈千鳥〉と〈みちる〉、この二人の会話は、チルチルとミチルの二人が追い求める青い鳥を呼び寄せる。千鳥格子のカーテンが、この〈家〉には実際にあるのかもしれない(「ドールハウス」)。みちる、は、光が満ちる、〈佳いもの〉が満ちる、を含意しているだろう。具体的な事物が言葉を呼び寄せ、その言葉がまた、過去の物語やイメージを呼び、そのレベルへの移行を促す。そのレベルに素直に移行した語り手は、導き手となった言葉に〈家〉に住まう〈ひと〉としての肉体――イメージ界における具現化、であるが――を与え、語らせる。
窓は閉じたままであっても硝子によって光を透過させる。〈佳いもの〉を取り入れる開口部であると共に、満たされた部屋の豊かさを逃さないように防御するものでもあり、また、外部から入りこもうとする〈許したくないこと〉を遮断する機能を持つ。開けば風が通い、外部へと〈羽ばたいて〉いくことも自由。「窓辺だけの部屋」には、”Hope” is the thing with feathers というエミリー・ディキンソンの詩の1節がエピグラフとして置かれている。希望は羽ばたいていくものなのか。
「窓辺だけの部屋」には春の気配が満ち満ちているが、「換気」は真冬を描いている。
窓はあいていたのです。吹雪のきれぎれを燦めかせながら青い鳥は飛びこんできて、猛スピードのまま壁に衝突しては方向を変え、またぶつかることをくりかえすので、逃がしてやりたい一心で布を手に窓へ追い立て、けれども雪空へふたたび逃がすことが、よその家のかごを誤って飛びだしてきたであろうナイーブな鳥の死を意味することもわかっています。気がつくと床の上に落ちています。(中略)本の小口に付けられた色が、読んでいる最中はうしなわれるように、あざやかな青は目の前を消えています。あのあと鳥をどうしたか。雪の庭に埋めたか、蘇生させたのか、雪のふりしきる朝にどうして窓はあいていて、青はどこへ行ったのか。(中略)個室に備えられているのは一酸化炭素を発するポータブルストーブ。空気は入れ換えねばなりません。部屋ごとの換気は気分にゆだねられ(中略)ふりかえる性質のひとはしきりと窓をあけたがります。(中略)やがて住まいの気密性が向上すると、計画的な機械換気が不可欠になりますが古い家では計測も計算もなりたたず(中略)あの日は海側の部屋にいて、坂を上ってくるいとこたちを待ちあぐねているはずですが、記憶を飛びまわるのは山に面したもうひとりの部屋。ふたつの部屋は繋がっていたとでもいうのでしょうか。気がつくと鳥は床の上に落ちています。
青い鳥は、海側から(海外から)やってくるのだろうか。誰かの〈家〉で(精神世界で)、大切に飼われていた(養われていた)鳥が(ことばが)わたしの〈家〉に飛び込んで来る。居間には暖かいストーブがあり、この〈家〉の〈ひと〉たちが集っているが、個室には有毒なガスを発するポータブルストーブしかない。個室に閉じこもっていれば中毒を起こして死に至るので換気が必然となるわけだが、それは他者の生きた言葉を取り入れなければ自家中毒を起こす、という詩論でもある。〈家〉の外は、命を奪う吹雪の吹き荒れる世界。そんなときに(そんな時だからこそ?)窓を開けている部屋に果敢に飛び込んで来る青い鳥、しかしその鳥を、自分の〈家〉の壁が死なせてしまう哀しさ。壁のない(限界のない)家に住んでいればよかったのか。真冬である。命を奪う雪の中に住むのは不可能、床に落ちた色あせた鳥を、語り手は黙って見おろしている・・・。
この家、そのものが不動のものでも固定したものでもない、そのことも面白いと思う。
家は思想のやどりであって、たてましのたびにかたちをうしなってゆくばあい、すでに流浪の旅にあるとみてとれます。たとえ別れを惜しんで、柱をいだき壁をなでさすりしても、一見して合理的な思考回路によって三角の屋根でさまよいをはじめ、矩形や台形のすがたを増やし、分裂したり融合したり、そのころには住み手を離れ、アンバランスな両翼ではばたいています。(中略)住人のなかには、空想の渡り廊下を通って鍵のない自室にこもる者も出てきます。不在のときでも出入り自由ですが領域は保たれ(中略)複雑な形状の家ほど、雨漏りすが漏りひび割れのリスクが高く、繋いだ部分のすきまがひろがったり縮んだりすることこそ点検すべき点です。風のことは風にきくようにしなさい。縁の下から声がしても、屋根裏に届く前に次のたてましは決まってしまい、まるでたてましを追いかけて今をたてましているみたいな自転車操業に、きりきりまいの日々。(中略)そんなときです、妹というものになってみたいと思うのは。渡り廊下で夢想するのはどこか万能な妹で、兄のせなかに隠れているようで原初的な問いの手綱を握り、危険なことには目端が利くので要所で的確な判断をくだし、なおかつ理屈にならない駄々をこねられる、そんな妹が欲しいのではなく、そんな妹で自分があれば家の失踪を杞憂することもないのにと(中略)それもまたたてましの欲求のひとつかもしれず、かたちをうしなうとみせかけて、よりいっそう執拗に、実はかたちに執着する家の尖端が、こうしてまたたてまされてゆきます。
「たてまし」は、〈家〉そのものが羽ばたいて“ここ”から居なくなることをも想起させる。複雑になり過ぎれば破綻する、そのことを分かっていてもこの〈家〉の住人達は次々と部屋を建て増しし、渡り廊下を渡って離れにこもったりまた居間に戻ったり、どこかへ出かけて行ったりと自在に暮らしているようであり、この家そのものもハウルの動く城ではないが、自らどこかへ、流浪の旅や増築した〈翼〉でどこかへ羽ばたこうとしてもいるようにみえる。語り手の中の複数のペルソナが、みずからの欲求のままに建て増しを繰り返した家(構造体)は、語り手を乗せていったいどこへ行こうとしているのか……
目に見える構造を目に視えない構造で支える、階段とデッドスペースの関係を考える。それは、兄の背中に隠れているようでいて、実際は〈原初的な問いの手綱を握り(中略)的確な判断をくだし(中略)なおかつ駄々をこねられる〉妹の存在の重要性と重なる。ひとつのレベルから別のレベルへと移行するという目的を果たすための、目に見える構造(文章、行)が兄ならば、目に視えないところで、自由に空想を羽ばたかせ、なおかつ兄の背中に隠れて逸脱しない、常に問いを持ち理屈に合わないわがままも許される、そんな行間、文字の向こう側の領域が妹。兄がいなくては詩作品は成り立たないが、実際に詩を生きた空間にしているのは妹であるのかもしれない……そんなわがままな読み方も許してくれるのに、歪さや軋み、不必要なでっぱりや移動に不都合な空間の屈折などは排除された、快適で暮らしやすい居住空間。海東の美しく正確な文章、豊かな多層化と整然とした移行を可能とする構造、光や風、花やきのこといった外界の豊かさを自在に取り込み、〈家〉に暮らす〈ひと〉もまた、自在に出入りする〈家〉とその近郊も含めた居住空間。そこに海東の詩は“住んで”いる。この家の招きに預かりたい者は、黙って詩集の扉を開けばよい。鍵は、かけられていないのだから。











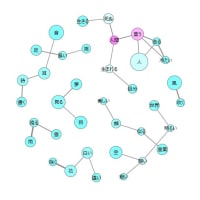


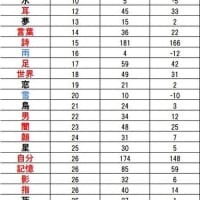
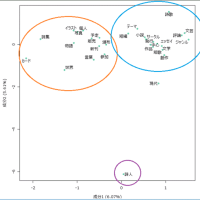
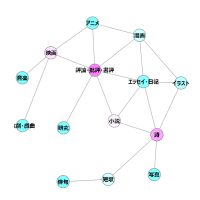
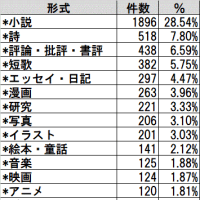
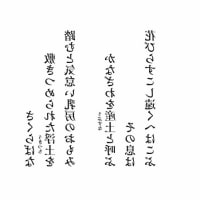
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます