「俳句は上から下へ言葉に添ってゾロゾロと読み下すものではなく、一句の上下同時に眼にはめ込まれるようにうけとられるものである。俳句一行のこの棒は、私には眼玉の直径となり得るギリギリの長さのように思われてならない。眼玉の直径は、一つの世界の直径であり、直径はその世界を決めるものである。一つの世界の重圧のかかる一行は当然、強固な、いつまでも終らない能力をもった言葉であらねばならない」(「言葉の現れるとき」)と、先達、飯島晴子は述べた。このたびいろいろな詩を読みながら私は気がつくとこの言葉を思い出していた。詩は、言葉の配置や余白で緻密に構成されているから、全体で捉えるのが本意なのだろうが、俳人である私はつい部分に目が行ってしまう。そして、部分あるいは行が統合して発生する吸引力の有無によって一篇の詩を好ましいか好ましくないか振り分けてしまう。相も変わらず、詩の良し悪しを判断する力はない。ただ、詩にかける作者の想いは迫力となってドスンと私を揺さぶる。私はその「詩的体験」を求めているのだ。
私は句会などで度々「俳句は意味じゃない」と言う。逆に「意味がわからない」といって退けることもある。相矛盾した自分の物言いに立ち止まってみると、それはゴダールの言葉を借りれば「努めて物事を見ること。努めて物事を想像すること。前者は“目を開けて見よ”、後者は“目を閉じよ”ということ」だろう。詩を読むときも、自分で自分の作り出した世界に酔っているような、意味で終わっている詩にはあまり魅力を感じない。詩は「意味として捉えること以上の」ものであり、むしろそこにこそ詩の本質があるとも思うからだ。言葉から意味を剥がすことは困難だが、詩も俳句も、意味の後ろ側にあるもの、見えているものの後ろ側に確かに存在している何かを表そうとする試みにおいて、短歌よりもより近いと言えなくはないか。
たくさん
さんらん
している
光もないのに勝手な手口で影と化した者たちが、口をあけて笑っている。あり
ふれた光景だ。影はいつからか、当たり前に射し込んで、照らすように匿す。
転倒するときにそこへ至る足どりを思う、そしてなにかへの途上で、立ち上が
り過つ。また過つ。遂に喪われるなにかから、影が射し込んで染め上げる。ヒ
トガタのそれは、次つぎと現れてはたくさんでかたまって、哄笑する磁場とな
る。都市の熱っぽいコンクリートの重なり合うそこに、否そこここに、何故か
「おまえ」を卑屈にさせるような笑い声が満ちているのを、うまくやり過ごし、
しかし白昼、「おまえ」の背中はもろくも影と崩れる。
「おまえ」が私のことだと悟った刹那、影に、照らすように匿された私は、都市の熱っぽいコンクリートの重なり合うそこ(不特定のどこにでもある日常行き来する場)、また途上(人生の)で哄笑する影たちをうまくやり過ごし、逃れたはずの白昼に崩れる。私はバラバラになり欠片になる。しかし見上げれば、崩れずに依然ヒトガタである私が直立している。脆くも崩れる私は何者なのか。たくさんさんらんしているのは影か私の欠片か。ピーラーで皮を剥かれた馬鈴薯のような寒さだ。ああ、この感覚は痛いほどだ。
いざ消滅へと抹消へと向かうひとりきりの行進に、最早凶器すらその必然性を
欠き、血しぶきすら意味なく、行為の為の行為すら為されず、希望も絶望も
追いつかない。
死者ははじめ数字として並べられ、改めて明示され、名指され、焼尽の果てに、
また数字へと戻る。
血は理由にはならなかった、目的にもなり損なった。そのことを悟って自ら縊死
する路を選ぶとき、圧倒的な空白が、その肉体を抱きとめるだろう。血まなこ
で這いずりまわったその肉体は
「きわめて健全であり健康である」。
この部分を読みながら、最近観たゴダール監督の映画『アワーミュージック』を思い出していた。映画の主人公オルガはロシア出身ユダヤ系フランス人女性で、平和のための自死を考え続けている女子学生である。そのオルガが「イスラエルの人が平和のために一緒に死んでくれればうれしい」と、たてこもった映画館で、バッグから本を取り出そうとしたときにテロリストと間違えられて射殺される。死の前に語った「生にも死にも無関心でこそ、完全な自由になれる。それが目標よ」という言葉。オルガにとって血は理由にはならず、目的にもなり損なって、結局自死ではなく他者によって死に至った。そして天国に赴くとき、まさに「圧倒的な空白」に「抱き留められ」、「きわめて健全であり健康」な姿を見せるのだ。
現代を生きる行為は看破された。もう少しワタクシに引きつけるならば、表現者であることの「ひとりきりの行進」も、希望も絶望も追いつかないままの不確実さを常に曳きずりながら、書き続け、表現しつづける行為だ。たとえ「数字」で置き換えられてしまう終焉に向かうのが必然だとしても、小林は「きわめて健全で健康」なのだと大肯定で受けとめる。
未明、
無数の暮らしが、
影とかたまるその時間に、
ハッハッハッ
散歩する者ども、
暗いほうを暗いほうを
目指して。
喜びも憤りも不安も、日常に均されていく。「その時間」、普段の暮らしを送るノーバディな私は、TVのバラエティ番組を見ては爆笑し、遠い土地での戦争のニュースを歎き、ゲーム農園の麦を刈り取りながら鉢植えの植物を枯らす。警鐘は鳴り続けているのだ。ハッハッハッ、このままでいくはずかない。動き出せ。
ところでこの詩のモチーフは次の詩に通じるものがある。黒田喜夫の「爬行のとき」の断片を拾う。
十月は生まれて死につつある
おれは死から生まれつつある
このときおれは自由になる
あまりにも言葉も絶望も息絶え
さけびが残る
おれは夢のなにものも生まず
さけびは街と群集を生む
朝の底しれない口から吐き出された人たちが
背姿から背姿へかさなってゆくと
おれは押さえがたい嘔吐の躰をまげ
人たちの足もとにながいさけびを生む
硬変した日常と武器と
肝臓をともに
底知れない口から吐き出された人たちは、生者か死者か。小林の詩において勝手な手口で影と化した者のようでもであり、同時に影に匿される者でもある。自由とさけびと嘔吐の循環の中に「おれ」は在りつづける。「おれ」は群集を生み、その姿を見て嘔吐の躰を曲げ叫ぶ。自己は他己に、他己は自己となりうることの戦慄。
小林と黒田。生きている、生きてきた時代もまったく違うこの二人に通底しているものは何だろう。
次の黒田の言葉が端的に示していよう。
<ひとつの心が世界、周囲、自然と親和した心境をなし、その心境をもとに、世界、周囲、自然との間の感情のやりとりを生花やボンサイを作るように詩の形にして満足するというようなことは、そこではもうできないのである>
<詩をかく自分に、その時の自分の全状況の全衝迫を、全部ぶちこまなければおさまらない>
<「私」も「意味」も、詩に駆られ生きられている動機にとっては、最低でも再帰的であり形成的であり、それが生きつつ生きられるところに現出されるものだろう。逐語の意味は全体の生きられる文脈とリズムの中の機能を通って極限化、超意味化、あるいは反立化される。その行為作用の言葉を生きること。近代以降の個人が述べがたいことを述べようとして、個の証明を(言葉の窮極性を)背理的にも共世界的・共人間的な振幅において求めようとせざるを得ない詩という行為の、それは内実の一片であると思う>
生花や盆栽を軽んじている物言いは少々乱暴だが、物書きとしての宿命を受け入れた詩人の矜持と迫力が伝わってくる。俳人の中で俳句を書きつづけるという宿命を引き受ける覚悟を持った者はどれだけいるだろう。あまり多くないのではないだろうか。まあそれはさておき、詩という器は、黒田の言う「全状況の全衝迫を全部ぶちこむ」 だけの度量があると思う。 自由だ。自由だからこそ作者の意図を読み切ることも難しい。普段、極小の詩型の中で格闘している私が詩を読むとき、その自由さに絡めとられて、まるで迷宮に迷い込んでしまったように足が竦み、すごすごと引き返してしまうのはそのせいだろう。
さて、俳句を書く私と、こうして詩を読む私と、働く私と、日常些事に振り回される私は、時代の危うさに少なからず怯えながら、崩れてバラバラになる寸前で自分をかろうじて保っている。私だけではない、きっとそういう人は今の社会には少なくないはずだ。
正気ではないぼくたちの未来なら明日燃えていく人たちの言の葉もれて
失うは安らぎでありいくつもの足に踏まれバラバラの破片になって
バラバラの眼が見つづけるバラバラの掌つかむバラバラの語りかけても
バラバラを許しはしない正しいといういつわりにせめてもの否を記せよと
死んでいく人であるなら爪立てる道のはざまに正気ではないぼくたちの
冷えていく体の内に傷付いたままにとどまりまだ沁みる過度の汚染が
眩むまま迷宮になりバラバラの足首いたみバラバラの水の反射に
バラバラの土地を辿ればバラバラの沈黙の果てバラバラに眼が溢れだし
沈みいく片側からへ棒状になる背中へと誰ひとり結べはしない
言葉すら踏みにじられる正気ではないぼくたちの日日の手が忘却されて
ざらついた舌の面に切り結ぶ間合をとれば一面は荒れ果てていく
バラバラのぱらのいあにもバラバラの天国かさねバラバラの腹が痛んで
バラバラの念仏のあとバラバラへ水が満ちいく常ならぬ唾を吐きつけ
いつまでも呟いている心臓が破裂していく磨滅する足裏のために
正気ではないぼくたちのおとがいの崩れるままにただよいは漠とはじまり
見えぬうち熱狂は去る遠景に侵食するバラバラの巻頭言が
バラバラの末端としてバラバラの胴であるならバラバラの夕暮れになる
バラバラを天国に置く問い詰める喉元までも虚になる終の棲家の
ひきつれた笑いにも似る死にかけの腕を伸ばせば正気ではないぼくたちの
土すらも失われいく明暗のしずくに濡れていつまでも叫びは止まず
くぐつにもなる昼下がりバラバラの殺意にまでもバラバラの靴音までも
バラバラの隔絶までもバラバラの予感にまでもバラバラに末端となる
引き続く空蝉としてまだ消えぬ月影を追いいつまでも諍いつづき
人たちの怒りは止まず正気ではないぼくたちの体温は安定せずに
冷えていく掌こすりひび割れた空見あげれば突然の遠雷ひびき
バラバラの声が落下しバラバラの火が燃え上がりバラバラの流血つづき
バラバラの地軸が揺らぐバラバラへ靴音しるし片言のことばつぶやく
吹きすぎる風に切られて空気すら波紋になるひと粒の毒が目に落ち
正気ではないぼくたちのまだ見ない地形をたどる手に掴まれる
身体中の穴という穴から一気に噴き出したような言葉、言葉。森川は夕暮れも殺意も予感も地軸も、私たちに関わる全てがバラバラだと言う。主語である「バラバラ」と状態を表す「バラバラ」、「正気ではないぼくたち」の連続によって、どこで切れても、逆にどこまで続けて読んでも意味を崩さず、かえってその重複が、反復運動が、リズムとスピードを増しながら、いくつものシーンが私を連射する。一行ごとに短い息をつく他は、意味に立ち止まることも許されない。連射された私は正気を剥ぎ取られ、そして未だ見ぬ地形をたどる手に掴まれるのだ。そうだ元々私はバラバラだったじゃないか。バラバラな世界にバラバラを保って生きているじゃないか。これがいつわりのない時代の姿だ。
この詩、自由律短歌と詩を圧縮して詩化した新しい試みとして、地に限りなく近い言葉の曠野となった。私はこの詩篇の傍らで、静かな一つの石でいるしかない。しかしこの眩暈のような脈略は、全体の空間を感じさせることなしに否応なく読み手を突き動かしてゆく。まるで、かたまって降る音階のように。
「笑」「吐」「崩」「影」「血」「水」
最後にもう一度黒田の詩を引く。
濁った河を見ていた
荒々しい水音を聴いていた
金色の
腐った嘔吐のあとが洗われた
またとない岸だ
泥酔の無慈悲な純粋さだ
丸太のように飛びこめば
よいのだと思った
さて今回は三人の詩人の作品を見てきた。黒田喜夫については図書館に所蔵されているが、小林坩堝と森川雅美については、詩人の知人がいないため詩集を読む手だてがないまま今日に至っている。あいかわらず短詩型同士の壁それは厚く、風通しが悪い(同じ詩型内でも風通しがいいとは言えないが)。しかしそれぞれが全く別物で、それぞれに盛り込める内容が異なり、それぞれに魅力があることは疑う余地はない。私は前回より少しでも詩に近づけただろうか。近づけたとしたらとてもいい気分だ。
私はバラバラじゃない。やるべきことをやっている。
私は句会などで度々「俳句は意味じゃない」と言う。逆に「意味がわからない」といって退けることもある。相矛盾した自分の物言いに立ち止まってみると、それはゴダールの言葉を借りれば「努めて物事を見ること。努めて物事を想像すること。前者は“目を開けて見よ”、後者は“目を閉じよ”ということ」だろう。詩を読むときも、自分で自分の作り出した世界に酔っているような、意味で終わっている詩にはあまり魅力を感じない。詩は「意味として捉えること以上の」ものであり、むしろそこにこそ詩の本質があるとも思うからだ。言葉から意味を剥がすことは困難だが、詩も俳句も、意味の後ろ側にあるもの、見えているものの後ろ側に確かに存在している何かを表そうとする試みにおいて、短歌よりもより近いと言えなくはないか。
たくさん
さんらん
している
光もないのに勝手な手口で影と化した者たちが、口をあけて笑っている。あり
ふれた光景だ。影はいつからか、当たり前に射し込んで、照らすように匿す。
転倒するときにそこへ至る足どりを思う、そしてなにかへの途上で、立ち上が
り過つ。また過つ。遂に喪われるなにかから、影が射し込んで染め上げる。ヒ
トガタのそれは、次つぎと現れてはたくさんでかたまって、哄笑する磁場とな
る。都市の熱っぽいコンクリートの重なり合うそこに、否そこここに、何故か
「おまえ」を卑屈にさせるような笑い声が満ちているのを、うまくやり過ごし、
しかし白昼、「おまえ」の背中はもろくも影と崩れる。
小林坩堝「或る空白」より
「おまえ」が私のことだと悟った刹那、影に、照らすように匿された私は、都市の熱っぽいコンクリートの重なり合うそこ(不特定のどこにでもある日常行き来する場)、また途上(人生の)で哄笑する影たちをうまくやり過ごし、逃れたはずの白昼に崩れる。私はバラバラになり欠片になる。しかし見上げれば、崩れずに依然ヒトガタである私が直立している。脆くも崩れる私は何者なのか。たくさんさんらんしているのは影か私の欠片か。ピーラーで皮を剥かれた馬鈴薯のような寒さだ。ああ、この感覚は痛いほどだ。
いざ消滅へと抹消へと向かうひとりきりの行進に、最早凶器すらその必然性を
欠き、血しぶきすら意味なく、行為の為の行為すら為されず、希望も絶望も
追いつかない。
死者ははじめ数字として並べられ、改めて明示され、名指され、焼尽の果てに、
また数字へと戻る。
血は理由にはならなかった、目的にもなり損なった。そのことを悟って自ら縊死
する路を選ぶとき、圧倒的な空白が、その肉体を抱きとめるだろう。血まなこ
で這いずりまわったその肉体は
「きわめて健全であり健康である」。
同上
この部分を読みながら、最近観たゴダール監督の映画『アワーミュージック』を思い出していた。映画の主人公オルガはロシア出身ユダヤ系フランス人女性で、平和のための自死を考え続けている女子学生である。そのオルガが「イスラエルの人が平和のために一緒に死んでくれればうれしい」と、たてこもった映画館で、バッグから本を取り出そうとしたときにテロリストと間違えられて射殺される。死の前に語った「生にも死にも無関心でこそ、完全な自由になれる。それが目標よ」という言葉。オルガにとって血は理由にはならず、目的にもなり損なって、結局自死ではなく他者によって死に至った。そして天国に赴くとき、まさに「圧倒的な空白」に「抱き留められ」、「きわめて健全であり健康」な姿を見せるのだ。
現代を生きる行為は看破された。もう少しワタクシに引きつけるならば、表現者であることの「ひとりきりの行進」も、希望も絶望も追いつかないままの不確実さを常に曳きずりながら、書き続け、表現しつづける行為だ。たとえ「数字」で置き換えられてしまう終焉に向かうのが必然だとしても、小林は「きわめて健全で健康」なのだと大肯定で受けとめる。
未明、
無数の暮らしが、
影とかたまるその時間に、
ハッハッハッ
散歩する者ども、
暗いほうを暗いほうを
目指して。
同上
喜びも憤りも不安も、日常に均されていく。「その時間」、普段の暮らしを送るノーバディな私は、TVのバラエティ番組を見ては爆笑し、遠い土地での戦争のニュースを歎き、ゲーム農園の麦を刈り取りながら鉢植えの植物を枯らす。警鐘は鳴り続けているのだ。ハッハッハッ、このままでいくはずかない。動き出せ。
ところでこの詩のモチーフは次の詩に通じるものがある。黒田喜夫の「爬行のとき」の断片を拾う。
十月は生まれて死につつある
おれは死から生まれつつある
このときおれは自由になる
あまりにも言葉も絶望も息絶え
さけびが残る
おれは夢のなにものも生まず
さけびは街と群集を生む
朝の底しれない口から吐き出された人たちが
背姿から背姿へかさなってゆくと
おれは押さえがたい嘔吐の躰をまげ
人たちの足もとにながいさけびを生む
硬変した日常と武器と
肝臓をともに
黒田喜夫「爬行のとき」より
底知れない口から吐き出された人たちは、生者か死者か。小林の詩において勝手な手口で影と化した者のようでもであり、同時に影に匿される者でもある。自由とさけびと嘔吐の循環の中に「おれ」は在りつづける。「おれ」は群集を生み、その姿を見て嘔吐の躰を曲げ叫ぶ。自己は他己に、他己は自己となりうることの戦慄。
小林と黒田。生きている、生きてきた時代もまったく違うこの二人に通底しているものは何だろう。
次の黒田の言葉が端的に示していよう。
<ひとつの心が世界、周囲、自然と親和した心境をなし、その心境をもとに、世界、周囲、自然との間の感情のやりとりを生花やボンサイを作るように詩の形にして満足するというようなことは、そこではもうできないのである>
<詩をかく自分に、その時の自分の全状況の全衝迫を、全部ぶちこまなければおさまらない>
<「私」も「意味」も、詩に駆られ生きられている動機にとっては、最低でも再帰的であり形成的であり、それが生きつつ生きられるところに現出されるものだろう。逐語の意味は全体の生きられる文脈とリズムの中の機能を通って極限化、超意味化、あるいは反立化される。その行為作用の言葉を生きること。近代以降の個人が述べがたいことを述べようとして、個の証明を(言葉の窮極性を)背理的にも共世界的・共人間的な振幅において求めようとせざるを得ない詩という行為の、それは内実の一片であると思う>
黒田喜夫『人はなぜ詩に囚われるか』
生花や盆栽を軽んじている物言いは少々乱暴だが、物書きとしての宿命を受け入れた詩人の矜持と迫力が伝わってくる。俳人の中で俳句を書きつづけるという宿命を引き受ける覚悟を持った者はどれだけいるだろう。あまり多くないのではないだろうか。まあそれはさておき、詩という器は、黒田の言う「全状況の全衝迫を全部ぶちこむ」 だけの度量があると思う。 自由だ。自由だからこそ作者の意図を読み切ることも難しい。普段、極小の詩型の中で格闘している私が詩を読むとき、その自由さに絡めとられて、まるで迷宮に迷い込んでしまったように足が竦み、すごすごと引き返してしまうのはそのせいだろう。
さて、俳句を書く私と、こうして詩を読む私と、働く私と、日常些事に振り回される私は、時代の危うさに少なからず怯えながら、崩れてバラバラになる寸前で自分をかろうじて保っている。私だけではない、きっとそういう人は今の社会には少なくないはずだ。
正気ではないぼくたちの未来なら明日燃えていく人たちの言の葉もれて
失うは安らぎでありいくつもの足に踏まれバラバラの破片になって
バラバラの眼が見つづけるバラバラの掌つかむバラバラの語りかけても
バラバラを許しはしない正しいといういつわりにせめてもの否を記せよと
死んでいく人であるなら爪立てる道のはざまに正気ではないぼくたちの
冷えていく体の内に傷付いたままにとどまりまだ沁みる過度の汚染が
眩むまま迷宮になりバラバラの足首いたみバラバラの水の反射に
バラバラの土地を辿ればバラバラの沈黙の果てバラバラに眼が溢れだし
沈みいく片側からへ棒状になる背中へと誰ひとり結べはしない
言葉すら踏みにじられる正気ではないぼくたちの日日の手が忘却されて
ざらついた舌の面に切り結ぶ間合をとれば一面は荒れ果てていく
バラバラのぱらのいあにもバラバラの天国かさねバラバラの腹が痛んで
バラバラの念仏のあとバラバラへ水が満ちいく常ならぬ唾を吐きつけ
いつまでも呟いている心臓が破裂していく磨滅する足裏のために
正気ではないぼくたちのおとがいの崩れるままにただよいは漠とはじまり
見えぬうち熱狂は去る遠景に侵食するバラバラの巻頭言が
バラバラの末端としてバラバラの胴であるならバラバラの夕暮れになる
バラバラを天国に置く問い詰める喉元までも虚になる終の棲家の
ひきつれた笑いにも似る死にかけの腕を伸ばせば正気ではないぼくたちの
土すらも失われいく明暗のしずくに濡れていつまでも叫びは止まず
くぐつにもなる昼下がりバラバラの殺意にまでもバラバラの靴音までも
バラバラの隔絶までもバラバラの予感にまでもバラバラに末端となる
引き続く空蝉としてまだ消えぬ月影を追いいつまでも諍いつづき
人たちの怒りは止まず正気ではないぼくたちの体温は安定せずに
冷えていく掌こすりひび割れた空見あげれば突然の遠雷ひびき
バラバラの声が落下しバラバラの火が燃え上がりバラバラの流血つづき
バラバラの地軸が揺らぐバラバラへ靴音しるし片言のことばつぶやく
吹きすぎる風に切られて空気すら波紋になるひと粒の毒が目に落ち
正気ではないぼくたちのまだ見ない地形をたどる手に掴まれる
森川雅美「日録」(三詩型融合作品)
身体中の穴という穴から一気に噴き出したような言葉、言葉。森川は夕暮れも殺意も予感も地軸も、私たちに関わる全てがバラバラだと言う。主語である「バラバラ」と状態を表す「バラバラ」、「正気ではないぼくたち」の連続によって、どこで切れても、逆にどこまで続けて読んでも意味を崩さず、かえってその重複が、反復運動が、リズムとスピードを増しながら、いくつものシーンが私を連射する。一行ごとに短い息をつく他は、意味に立ち止まることも許されない。連射された私は正気を剥ぎ取られ、そして未だ見ぬ地形をたどる手に掴まれるのだ。そうだ元々私はバラバラだったじゃないか。バラバラな世界にバラバラを保って生きているじゃないか。これがいつわりのない時代の姿だ。
この詩、自由律短歌と詩を圧縮して詩化した新しい試みとして、地に限りなく近い言葉の曠野となった。私はこの詩篇の傍らで、静かな一つの石でいるしかない。しかしこの眩暈のような脈略は、全体の空間を感じさせることなしに否応なく読み手を突き動かしてゆく。まるで、かたまって降る音階のように。
「笑」「吐」「崩」「影」「血」「水」
最後にもう一度黒田の詩を引く。
濁った河を見ていた
荒々しい水音を聴いていた
金色の
腐った嘔吐のあとが洗われた
またとない岸だ
泥酔の無慈悲な純粋さだ
丸太のように飛びこめば
よいのだと思った
黒田喜夫「河」
さて今回は三人の詩人の作品を見てきた。黒田喜夫については図書館に所蔵されているが、小林坩堝と森川雅美については、詩人の知人がいないため詩集を読む手だてがないまま今日に至っている。あいかわらず短詩型同士の壁それは厚く、風通しが悪い(同じ詩型内でも風通しがいいとは言えないが)。しかしそれぞれが全く別物で、それぞれに盛り込める内容が異なり、それぞれに魅力があることは疑う余地はない。私は前回より少しでも詩に近づけただろうか。近づけたとしたらとてもいい気分だ。
私はバラバラじゃない。やるべきことをやっている。
映画 <巨匠ニコラス・レイ教授の「映画の授業」>より











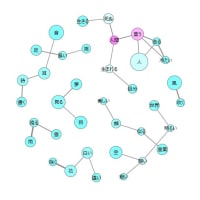


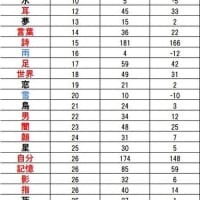
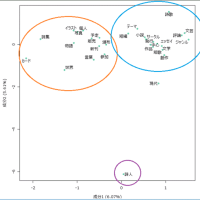
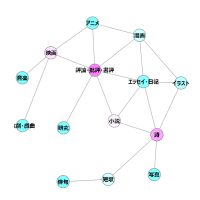
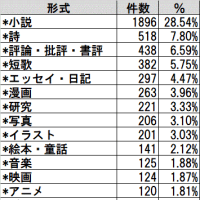
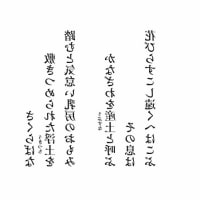
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます