【ベンチャー魂の系譜 1.命懸け、古代の東西交流(張騫、班超、クセノポン、アレクサンドロス)】
この授業『ベンチャー魂の系譜』は、どのような環境下においても挑戦する心、チャレンジ精神が必要だということを学生に理解してもらうために行っている。チャレンジ精神とニュアンスには、がむしゃらに挑戦する、というような無謀な意味も含まれているようにも解釈される。従って、チャレンジ精神のポジティブな面を捉え、かつそれにしたたかさやしなやかさを加えたのが、ここでいう『ベンチャー魂』と私は定義している。
授業では、次の14個のテーマから成り立つ。前半の7つ(1.~7.)は、冒険や知的分野で新たな分野へ挑戦した人たちを取り上げている。後半の7つ(8.~14.)は、文字通りベンチャー魂に溢れた起業家・事業家を取り上げている。私は起業することだけにしかベンチャー魂が存在するとは考えていない。困難な状況を克服して事業を継続・発展させて行く人の中にも確実にベンチャー魂を感じさせてくれる人がいる。
テーマ
1.命懸け、古代の東西交流(張騫、班超、クセノポン、アレクサンドロス)
2.世界中、至らざる所なしの探検家(アムンゼン、クック)
3.自由、それはベンチャー魂の源泉(Livius、ローマ建国史、ヨセフス)
4.死と隣り合わせの求道(法顕、玄奘、空海、河口慧海)
5.鎖国時代、開かれた世界への情熱(前野良沢、杉田玄白、平賀源内)
6.限りなき知の探検(Plinius、南方熊楠)
7.言語に魅せられた辞書作り(James Murray、諸橋轍次、大槻文彦)
8.江戸のベンチャー(住友、三井)
9.明治のベンチャー(三菱、安田、大倉、渋沢)
10.昭和のベンチャー(小林一三、和田一夫、盛田昭夫)
11.伝説をつくったベンチャー(電子立国日本の自叙伝、孫正義)
12.アメリカ活力の源泉、ベンチャー魂(カーネギー、ビル・ゲイツ)
13.急成長する中国・インドのベンチャー(ハイアール、アリババ、インフォシス、ウィプロ)
14.ベンチャー陰の立役者・ベンチャーキャピタリストと起業家
**************************************
モデレーター:セネカ3世(SA)
パネリスト
(H)(総人・1)
(B)(総人・1)
A:聴衆
【根岸先生の「若者よ、海外から日本を見よ」の文】
日本は非常にcomfortableな居心地のいい国である。ある一定期間、旅行者としてではなく、海外に出て、外から日本を見ることが重要。
(SA):パデュー大学に根岸先生は在籍していて、昔はパデュー大学にも日本人がたくさんい
た。しかし、このごろは、非常に減った。私も、ピッツバーグのカーネギーメロン大学に
留学した。昔は企業から、たくさん留学生が派遣されていた。このごろは企業もお金がな
くなってきたので、派遣しない。それ以上に問題なのは、皆さんのような二十歳代の人の
海外への志向が落ちている。根岸先生は、海外志向が落ちていることを言っている。根岸
先生が言うには、旅行ではなく、海外に住むということ。なぜ旅行ではダメなのか。
A:旅行したときには、想像したものと見ているけど、住むと本物が見えてくる。毎日、
用事を済まさないといけないときに感じる。
(SA):旅行者は問題を起こすことはない。しかし、住むとなると、住民登録をするなり、泥
棒が入ってきたら、警察に届けるなど、ちょっとしたことで、ネゴシエーション、つまり
話をして、解決しなければならない。旅行者ならば、そのようなことは、勝手にほってお
いて、次のところに行けるが、定住しているとそれができない。その意味では、定住する
意味は非常に高い。
A:例えば、携帯電話を買うには、(日本人の)皆さんは10分で買えるけど、(外国人)
の私は、1週間かかった。
(SA):その国の人たちのメンタリティを知ることができる。
【パネリストがこの話題を選んだ理由】
(H)タイトルを見て、世界史でやったことがあるので、ある程度知識がありそうだと思った。
最初の回は、点数がもらえるから。
(B)ほくと君(H)に誘われた。将来、起業する可能性もあるから。
(SA):この授業は、ベンチャーを興すのもいいし、自分でチャレンジすることが大事。
日本が疲弊しているのは、チャレンジ精神の欠乏。
(SA):ほくと君は、誰を調べたか。
(H)クセノホン以外の4人を調べた。
(SA):クセノホンは、なぜダメだったのか。
(H)クセノホンは、世界史で勉強したときに、作家か何かだと思ったけど、用語集に載っ
てなかったので、マイナーだと思ったから。
(SA):クセノホンという名前を知っていた人は?
A:世界史で名前だけ知っていた。たぶん政治家だと思う。
A:ギリシャの哲学者。
(SA):古典ギリシャ語を学ぶ人は、クセノホンのアナバーシスを、日本の高校生がちょうど徒然草を読むよ
うに、まずこの本を読む。一番オーソドックスな本。敵陣の中、1万6千キロを1万人を率いて
移動し、ほとんど無傷で生還した。
(SA):ばたオ君は、誰を選んだか。
(B)アレキサンドロスと張騫を選んだ。
(SA):なぜその二人を選んだのか。
(B)世界史のなかで、印象が強かった。

(SA):イヴンバトゥータはどういう人だったか。
(H)イヴンバトゥータは旅人。モロッコ出身。主にイスラム地域、フビライのときも元に
行ったことがある、世界を旅しているような人。大旅行記を書いた。
(SA):最近、「大旅行記」(平凡社)が出た。この本は、非常にいい。なぜかというと、我々
は、イスラムというと9・11以降、概して否定的なイメージを持っている人が多い。しかし、こ
れを読むとイスラムへの考えが変わる。まず第一に、14世紀にイスラムの人たちはどうして
世界をまたにかけて旅行ができたのか?現在のように、お金を払って切符を手配できるわけでもない。どうやって旅行できるのか。
(H)たぶん、仲間は何人かいて、砂漠とかは、地元で手伝ってくれる人を探して、案内し
てもらったりした。
(SA):無料でやってくれるのか?
(H)お金を払って旅行した。
(SA):いくらお金を払うのか。
(H)具体的な数字は、わからない。
(SA);しかし、何年彼は旅行したのか。
(H)20年間くらい。
(SA):20年間の中で、一日最低でもどれくらいお金がかかるか。現代価格で。
(H)最低で計算すると一日、1000円くらい。
(B)ムスリムには、助け合いの概念がある。
(SA):ムスリムだけが、互いに助け合うのか。
(SA):お金を払わなくてもやってくれるのか。
(B)金を払わなくてもやってくれる。
(SA):お金をもらわないと損しないか?ひとり、一日食べさせていくとしたら、いくらぐらいかかるか。
(B)現在価格で、少なくとも1500円、2000円はかかる。
(SA):それで、一か月だといくらかかるか。
(B)4万円。
(SA):それで、一年間だと。
(B)50万円かかる。
(SA):それは、単に食べるだけだ。旅行したり、どこかにお土産をあげたりすると、
100万円かかる。20年間くらいしたら、いくらぐらいかかるのか。
(B)2000万円くらいかかる。
(SA):それでは当時、2000万円くらいのお金をどうやって、運んだのか。彼は、その2000万円の
お金を持って旅行したのか?当時の状況を想定してほしい。例えば、
馬一頭買うと、600万円くらいかかる。それは、誰が出してくれたのか?そういうことを考え
てほしい。実際に自分がその場にいると考えて、歴史というものを考えてころ、初めて歴史的
事実が分かってくる。そして、その土地の人の考えがわかる。
次に同じことが果たして昔の日本では、可能であったかどうか?と考えて欲しい。
(SA):それでは、なぜムスリム同士では只でくれるのか?助けるのは、自分の知って
いる人だけか、それとも知らない人までも含むのか?
(H)それは、知らない人も含まれる。
(SA):なぜ、知らない人も助けるのか?助けることがどんなメリットがあるのか?日本の場合だと、乞食
みたいな人がやってきた場合、只で泊める人はいるか?なぜ旅人だけがそうなるのか?どういう背
景があるのか?それは、イスラムだけか?キリスト教徒はどうか?
(H)キリスト教徒も慈愛の精神がある。
(SA):ムスリムはキリスト教徒も泊めるのか?キリスト教徒同士は泊めるのか?
(H)ムスリムとキリスト教徒が、仲がよかったとは思えない。
(SA):そうしたら、殺すのか?殺して物を奪うのか?
(H)そういう事例もある。
(SA):キリスト教徒は殺すのに、ムスリム同士はなぜ助け合うのか?
(H)同じ宗教だという仲間意識がある。
(SA):イスラムというのは、いくつの宗教でできているのか。
(B)アラビア半島にあったものを集約して、イスラム教ができた。
(SA):イスラムというのは、ひとつの宗教か。
A:簡単に言うと、宗派がたくさんある。カトリックや、プロテスタント、日本の仏教が
様々な宗派があるように、イスラム教も様々な宗派がある。
(SA):イスラムは大きく分けていくつあるか。
A:3つか4つはある。絶対それ以上ある。
(H)大きく分けるとスンニ派とシーア派。その他のも細かい宗派がある。それぞれの派閥
同士は、仲が悪い。
(SA):ざっくり言って、イランだけがシーア派で、それ以外はスンニ派。もとの話に戻って、なぜ見も知らな
いような人を助けるのか。
(B)情報提供。知らない情報を教える代わりに、寝食をつくろってもらった。
(SA):では、情報提供してくれない人は、どうするか?
(B)泊めないのではないか。
(SA):「ペルシャ放浪記」(東洋文庫)を読むことを勧める。筆者は、もともとマジャール
人で、ハンガリー出身。子供のころから、いろんな言語を勉強して、トルコに旅行をする。
非常にいろんな人に助けられる。イスラムというのは、もともと遊牧民の宗教で、
お互い助け合うためにやっている。情報交換などではなく、単に旅行者をもてなすという、
熱い心があるらしい。同じ派の人しか助けないのかという問題があるが、それについてど
う考えるか?再度問うが、イスラムは、キリスト教徒を助けるのか?
A:はっきりとはわからないが、本当は、イスラム教徒は全人類を平等に扱って、す
べての人たちを、旅人としてきたらもてなす文化だと思う。コーランの教えに従って生き
ている人であれば、旅人であったら、誰でも引き受けると考えられる。
A:イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒、全て啓典の民で、もとは同じ民
族であったということがコーランに書かれている。その人たちを、助けてあげないといけ
ないとコーランに書かれていると思うので、その人たちを助けると思う。
==>(SA意見):コーランにこういうことが書かれている、というより、これら3派は皆
旧約聖書を共通の経典としている、と言う言い方の方が正しいと思われる。
(SA):啓典の民以外の人は、助けないのか。
A:中近東の砂漠に住んでいる人たちは、概して啓典の民であった。
A:イスラムは、六信五行(6つの信仰箇条と、5つの信仰行為)があって、その中で、喜捨と
いう行動規範があり、困っている人を助けることで、自分が救われる。
(SA):日本人の考えでは、旅人を助けるというのは、見返りがないので自分の金を損する、
と考える。日本で生まれ育った我々の感覚では、それは当り前。しかし、彼らの
考えは違う。自分が、困っている人に、お金をあげれば、自分が今度救われる。自分が低
い所ら、上に行く。人にお金お与えることによって、自分が高くなる。だから、人にお金
を恵む。しかし、そういう論理は、我々にはなかなか分からない。イスラムの世界の考
えに則って生きている人が、どのように考えているかを日常の一コマを使って、ひとつひ
とつ理解していくのには、イブンバトゥータなどを読むといい。
(SA)これまでは、イスラムのいい面の話をしたが、アフガンなどでは、人を殺すこと
が、ゲームのように考えている節がある。本を読むとゲームのような感覚で、人を殺している
場面に出くわすことがある。数日かけて砂漠を500キロも横断して襲撃する。プラス面も、
マイナス面も、両方見るべし。「ペルシャ放浪記」の筆者の、ヨーロッパ人の観点から、ア
ジア人は、非常に親切と書いてある。正しいかどうかは、現地に行って、確認してみるべし。
以上で、イヴンバトゥータ、イスラム(ムスリム)の部分は終了。
(続く。。。)
この授業『ベンチャー魂の系譜』は、どのような環境下においても挑戦する心、チャレンジ精神が必要だということを学生に理解してもらうために行っている。チャレンジ精神とニュアンスには、がむしゃらに挑戦する、というような無謀な意味も含まれているようにも解釈される。従って、チャレンジ精神のポジティブな面を捉え、かつそれにしたたかさやしなやかさを加えたのが、ここでいう『ベンチャー魂』と私は定義している。
授業では、次の14個のテーマから成り立つ。前半の7つ(1.~7.)は、冒険や知的分野で新たな分野へ挑戦した人たちを取り上げている。後半の7つ(8.~14.)は、文字通りベンチャー魂に溢れた起業家・事業家を取り上げている。私は起業することだけにしかベンチャー魂が存在するとは考えていない。困難な状況を克服して事業を継続・発展させて行く人の中にも確実にベンチャー魂を感じさせてくれる人がいる。
テーマ
1.命懸け、古代の東西交流(張騫、班超、クセノポン、アレクサンドロス)
2.世界中、至らざる所なしの探検家(アムンゼン、クック)
3.自由、それはベンチャー魂の源泉(Livius、ローマ建国史、ヨセフス)
4.死と隣り合わせの求道(法顕、玄奘、空海、河口慧海)
5.鎖国時代、開かれた世界への情熱(前野良沢、杉田玄白、平賀源内)
6.限りなき知の探検(Plinius、南方熊楠)
7.言語に魅せられた辞書作り(James Murray、諸橋轍次、大槻文彦)
8.江戸のベンチャー(住友、三井)
9.明治のベンチャー(三菱、安田、大倉、渋沢)
10.昭和のベンチャー(小林一三、和田一夫、盛田昭夫)
11.伝説をつくったベンチャー(電子立国日本の自叙伝、孫正義)
12.アメリカ活力の源泉、ベンチャー魂(カーネギー、ビル・ゲイツ)
13.急成長する中国・インドのベンチャー(ハイアール、アリババ、インフォシス、ウィプロ)
14.ベンチャー陰の立役者・ベンチャーキャピタリストと起業家
**************************************
モデレーター:セネカ3世(SA)
パネリスト
(H)(総人・1)
(B)(総人・1)
A:聴衆
【根岸先生の「若者よ、海外から日本を見よ」の文】
日本は非常にcomfortableな居心地のいい国である。ある一定期間、旅行者としてではなく、海外に出て、外から日本を見ることが重要。
(SA):パデュー大学に根岸先生は在籍していて、昔はパデュー大学にも日本人がたくさんい
た。しかし、このごろは、非常に減った。私も、ピッツバーグのカーネギーメロン大学に
留学した。昔は企業から、たくさん留学生が派遣されていた。このごろは企業もお金がな
くなってきたので、派遣しない。それ以上に問題なのは、皆さんのような二十歳代の人の
海外への志向が落ちている。根岸先生は、海外志向が落ちていることを言っている。根岸
先生が言うには、旅行ではなく、海外に住むということ。なぜ旅行ではダメなのか。
A:旅行したときには、想像したものと見ているけど、住むと本物が見えてくる。毎日、
用事を済まさないといけないときに感じる。
(SA):旅行者は問題を起こすことはない。しかし、住むとなると、住民登録をするなり、泥
棒が入ってきたら、警察に届けるなど、ちょっとしたことで、ネゴシエーション、つまり
話をして、解決しなければならない。旅行者ならば、そのようなことは、勝手にほってお
いて、次のところに行けるが、定住しているとそれができない。その意味では、定住する
意味は非常に高い。
A:例えば、携帯電話を買うには、(日本人の)皆さんは10分で買えるけど、(外国人)
の私は、1週間かかった。
(SA):その国の人たちのメンタリティを知ることができる。
【パネリストがこの話題を選んだ理由】
(H)タイトルを見て、世界史でやったことがあるので、ある程度知識がありそうだと思った。
最初の回は、点数がもらえるから。
(B)ほくと君(H)に誘われた。将来、起業する可能性もあるから。
(SA):この授業は、ベンチャーを興すのもいいし、自分でチャレンジすることが大事。
日本が疲弊しているのは、チャレンジ精神の欠乏。
(SA):ほくと君は、誰を調べたか。
(H)クセノホン以外の4人を調べた。
(SA):クセノホンは、なぜダメだったのか。
(H)クセノホンは、世界史で勉強したときに、作家か何かだと思ったけど、用語集に載っ
てなかったので、マイナーだと思ったから。
(SA):クセノホンという名前を知っていた人は?
A:世界史で名前だけ知っていた。たぶん政治家だと思う。
A:ギリシャの哲学者。
(SA):古典ギリシャ語を学ぶ人は、クセノホンのアナバーシスを、日本の高校生がちょうど徒然草を読むよ
うに、まずこの本を読む。一番オーソドックスな本。敵陣の中、1万6千キロを1万人を率いて
移動し、ほとんど無傷で生還した。
(SA):ばたオ君は、誰を選んだか。
(B)アレキサンドロスと張騫を選んだ。
(SA):なぜその二人を選んだのか。
(B)世界史のなかで、印象が強かった。

(SA):イヴンバトゥータはどういう人だったか。
(H)イヴンバトゥータは旅人。モロッコ出身。主にイスラム地域、フビライのときも元に
行ったことがある、世界を旅しているような人。大旅行記を書いた。
(SA):最近、「大旅行記」(平凡社)が出た。この本は、非常にいい。なぜかというと、我々
は、イスラムというと9・11以降、概して否定的なイメージを持っている人が多い。しかし、こ
れを読むとイスラムへの考えが変わる。まず第一に、14世紀にイスラムの人たちはどうして
世界をまたにかけて旅行ができたのか?現在のように、お金を払って切符を手配できるわけでもない。どうやって旅行できるのか。
(H)たぶん、仲間は何人かいて、砂漠とかは、地元で手伝ってくれる人を探して、案内し
てもらったりした。
(SA):無料でやってくれるのか?
(H)お金を払って旅行した。
(SA):いくらお金を払うのか。
(H)具体的な数字は、わからない。
(SA);しかし、何年彼は旅行したのか。
(H)20年間くらい。
(SA):20年間の中で、一日最低でもどれくらいお金がかかるか。現代価格で。
(H)最低で計算すると一日、1000円くらい。
(B)ムスリムには、助け合いの概念がある。
(SA):ムスリムだけが、互いに助け合うのか。
(SA):お金を払わなくてもやってくれるのか。
(B)金を払わなくてもやってくれる。
(SA):お金をもらわないと損しないか?ひとり、一日食べさせていくとしたら、いくらぐらいかかるか。
(B)現在価格で、少なくとも1500円、2000円はかかる。
(SA):それで、一か月だといくらかかるか。
(B)4万円。
(SA):それで、一年間だと。
(B)50万円かかる。
(SA):それは、単に食べるだけだ。旅行したり、どこかにお土産をあげたりすると、
100万円かかる。20年間くらいしたら、いくらぐらいかかるのか。
(B)2000万円くらいかかる。
(SA):それでは当時、2000万円くらいのお金をどうやって、運んだのか。彼は、その2000万円の
お金を持って旅行したのか?当時の状況を想定してほしい。例えば、
馬一頭買うと、600万円くらいかかる。それは、誰が出してくれたのか?そういうことを考え
てほしい。実際に自分がその場にいると考えて、歴史というものを考えてころ、初めて歴史的
事実が分かってくる。そして、その土地の人の考えがわかる。
次に同じことが果たして昔の日本では、可能であったかどうか?と考えて欲しい。
(SA):それでは、なぜムスリム同士では只でくれるのか?助けるのは、自分の知って
いる人だけか、それとも知らない人までも含むのか?
(H)それは、知らない人も含まれる。
(SA):なぜ、知らない人も助けるのか?助けることがどんなメリットがあるのか?日本の場合だと、乞食
みたいな人がやってきた場合、只で泊める人はいるか?なぜ旅人だけがそうなるのか?どういう背
景があるのか?それは、イスラムだけか?キリスト教徒はどうか?
(H)キリスト教徒も慈愛の精神がある。
(SA):ムスリムはキリスト教徒も泊めるのか?キリスト教徒同士は泊めるのか?
(H)ムスリムとキリスト教徒が、仲がよかったとは思えない。
(SA):そうしたら、殺すのか?殺して物を奪うのか?
(H)そういう事例もある。
(SA):キリスト教徒は殺すのに、ムスリム同士はなぜ助け合うのか?
(H)同じ宗教だという仲間意識がある。
(SA):イスラムというのは、いくつの宗教でできているのか。
(B)アラビア半島にあったものを集約して、イスラム教ができた。
(SA):イスラムというのは、ひとつの宗教か。
A:簡単に言うと、宗派がたくさんある。カトリックや、プロテスタント、日本の仏教が
様々な宗派があるように、イスラム教も様々な宗派がある。
(SA):イスラムは大きく分けていくつあるか。
A:3つか4つはある。絶対それ以上ある。
(H)大きく分けるとスンニ派とシーア派。その他のも細かい宗派がある。それぞれの派閥
同士は、仲が悪い。
(SA):ざっくり言って、イランだけがシーア派で、それ以外はスンニ派。もとの話に戻って、なぜ見も知らな
いような人を助けるのか。
(B)情報提供。知らない情報を教える代わりに、寝食をつくろってもらった。
(SA):では、情報提供してくれない人は、どうするか?
(B)泊めないのではないか。
(SA):「ペルシャ放浪記」(東洋文庫)を読むことを勧める。筆者は、もともとマジャール
人で、ハンガリー出身。子供のころから、いろんな言語を勉強して、トルコに旅行をする。
非常にいろんな人に助けられる。イスラムというのは、もともと遊牧民の宗教で、
お互い助け合うためにやっている。情報交換などではなく、単に旅行者をもてなすという、
熱い心があるらしい。同じ派の人しか助けないのかという問題があるが、それについてど
う考えるか?再度問うが、イスラムは、キリスト教徒を助けるのか?
A:はっきりとはわからないが、本当は、イスラム教徒は全人類を平等に扱って、す
べての人たちを、旅人としてきたらもてなす文化だと思う。コーランの教えに従って生き
ている人であれば、旅人であったら、誰でも引き受けると考えられる。
A:イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒、全て啓典の民で、もとは同じ民
族であったということがコーランに書かれている。その人たちを、助けてあげないといけ
ないとコーランに書かれていると思うので、その人たちを助けると思う。
==>(SA意見):コーランにこういうことが書かれている、というより、これら3派は皆
旧約聖書を共通の経典としている、と言う言い方の方が正しいと思われる。
(SA):啓典の民以外の人は、助けないのか。
A:中近東の砂漠に住んでいる人たちは、概して啓典の民であった。
A:イスラムは、六信五行(6つの信仰箇条と、5つの信仰行為)があって、その中で、喜捨と
いう行動規範があり、困っている人を助けることで、自分が救われる。
(SA):日本人の考えでは、旅人を助けるというのは、見返りがないので自分の金を損する、
と考える。日本で生まれ育った我々の感覚では、それは当り前。しかし、彼らの
考えは違う。自分が、困っている人に、お金をあげれば、自分が今度救われる。自分が低
い所ら、上に行く。人にお金お与えることによって、自分が高くなる。だから、人にお金
を恵む。しかし、そういう論理は、我々にはなかなか分からない。イスラムの世界の考
えに則って生きている人が、どのように考えているかを日常の一コマを使って、ひとつひ
とつ理解していくのには、イブンバトゥータなどを読むといい。
(SA)これまでは、イスラムのいい面の話をしたが、アフガンなどでは、人を殺すこと
が、ゲームのように考えている節がある。本を読むとゲームのような感覚で、人を殺している
場面に出くわすことがある。数日かけて砂漠を500キロも横断して襲撃する。プラス面も、
マイナス面も、両方見るべし。「ペルシャ放浪記」の筆者の、ヨーロッパ人の観点から、ア
ジア人は、非常に親切と書いてある。正しいかどうかは、現地に行って、確認してみるべし。
以上で、イヴンバトゥータ、イスラム(ムスリム)の部分は終了。
(続く。。。)


















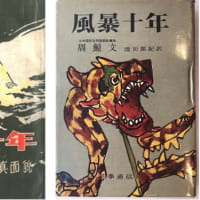








丸チンさんのいうように、自分も強大に着てからであった外国の方が、携帯電話の契約に二週間ほどかかっていたことを思い出した。
自分がオーストラリアにいたとき、日本に向けて手紙を書き、郵便局に言った経験によってもそのことはよくわかる。
どうせ海外に行くなら、すまないともったいないようなそんな感覚にさえなってしまった。