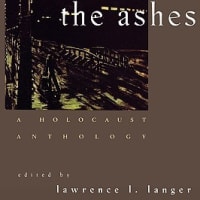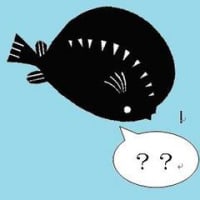「お尻のエスプリ」
J=R・エニッグ著 江下雅之・山本淑子訳
リブロス刊 2200円
無類のお尻好きが書いた、あふれるようなお尻賛歌である。フランス語版『ローリングストーン』誌編集長だった著者は、人間がいかに尻を愛してきたか、実に楽しげに古今東西に資料収集し編集してくれた。
日本では、俗なるものを極める人々を「おたく」と呼ぶ。しかし本書には、おたくのタコ壺的閉鎖感がない。尻という俗なるものを深く極め、他者に語ろうとする精神が熱く感じられる。
私は女性の尻は大好きだが、尻の起源など考えたこともなかった。著者は冒頭でわれらが進化における重大な事実を見逃さない。即ち人類は直立によって尻の筋肉がいちじるしく発達し、「現存する霊長類193種類のなかで、人類だけが常時突き出た半球状の尻をもっている」。直立歩行は同時に大脳の発達を促した。「ヒトの尻は、いわば大脳の急激な進化による結果なのではないか」。
この性急な仮説によって、「ケツ」とおとしめられてきたものが、ガゼン重大な文化的な問いかけに変貌し、読者を一気にめくるめくお尻ワールドに引き込むのである。
お尻とは突き出た肉塊である。これがなぜ官能、陶酔、誘惑、優美、快楽、恍惚……へと人を誘うのか?
このフシギを解くために、ギリシャ彫刻やルネサンス絵画、モンローやバルドーの尻が総動員され、はたまた「上品な丸み、優雅なうねり」の尻にまつわる詩や散文がふんだんに引用される。
究極の愛情表現として女性の尻のソテーを食った日本人、佐川一政のことばも忘れずに記している。「……尻を切ればすぐに肉が露出すると思ったのだが、脂身ばかりだったのに驚いた。……尻は女体の中で一番そそられる部分だった」。
私にとってあこがれてやまない西欧とは「金髪」ではない、尻だった。食ってしまうにはあまりにもったいなく、映画館の暗がりで見た女優たちの尻、進駐軍の将校夫人の尻、触れることの許されないわが青春の尻を思い出しながら本書を読んだ。
たかが尻が、ここまで知的に面白く語れるのか。言葉をつくして語る値打ちがあるものだったのか、という新鮮な驚き。これは、知られざる尻の幾山河を踏破してやまないチャレンジの書である。尻の量感では永遠に勝てない日本人は、せめてこのまっしぐらに好きなものに向かう知的姿勢は模倣したいものだ。
「動物学者デズモンド・モリスによれば、愛の普遍的な象徴であるハートは、尻、それも後ろから見た女の尻に由来する」というくだりに、尻の秘めた精神性に打たれる。
かと思うとドルマンセはこう叫ぶ。「畜生!何というデブ、何というさわやかさ、何という炸裂、何という優雅さ!……」。男なら誰でも思い当たる尻に焦がれる切ない思いがちりばめられた本である。
「現代」1998年4月号掲載
J=R・エニッグ著 江下雅之・山本淑子訳
リブロス刊 2200円
無類のお尻好きが書いた、あふれるようなお尻賛歌である。フランス語版『ローリングストーン』誌編集長だった著者は、人間がいかに尻を愛してきたか、実に楽しげに古今東西に資料収集し編集してくれた。
日本では、俗なるものを極める人々を「おたく」と呼ぶ。しかし本書には、おたくのタコ壺的閉鎖感がない。尻という俗なるものを深く極め、他者に語ろうとする精神が熱く感じられる。
私は女性の尻は大好きだが、尻の起源など考えたこともなかった。著者は冒頭でわれらが進化における重大な事実を見逃さない。即ち人類は直立によって尻の筋肉がいちじるしく発達し、「現存する霊長類193種類のなかで、人類だけが常時突き出た半球状の尻をもっている」。直立歩行は同時に大脳の発達を促した。「ヒトの尻は、いわば大脳の急激な進化による結果なのではないか」。
この性急な仮説によって、「ケツ」とおとしめられてきたものが、ガゼン重大な文化的な問いかけに変貌し、読者を一気にめくるめくお尻ワールドに引き込むのである。
お尻とは突き出た肉塊である。これがなぜ官能、陶酔、誘惑、優美、快楽、恍惚……へと人を誘うのか?
このフシギを解くために、ギリシャ彫刻やルネサンス絵画、モンローやバルドーの尻が総動員され、はたまた「上品な丸み、優雅なうねり」の尻にまつわる詩や散文がふんだんに引用される。
究極の愛情表現として女性の尻のソテーを食った日本人、佐川一政のことばも忘れずに記している。「……尻を切ればすぐに肉が露出すると思ったのだが、脂身ばかりだったのに驚いた。……尻は女体の中で一番そそられる部分だった」。
私にとってあこがれてやまない西欧とは「金髪」ではない、尻だった。食ってしまうにはあまりにもったいなく、映画館の暗がりで見た女優たちの尻、進駐軍の将校夫人の尻、触れることの許されないわが青春の尻を思い出しながら本書を読んだ。
たかが尻が、ここまで知的に面白く語れるのか。言葉をつくして語る値打ちがあるものだったのか、という新鮮な驚き。これは、知られざる尻の幾山河を踏破してやまないチャレンジの書である。尻の量感では永遠に勝てない日本人は、せめてこのまっしぐらに好きなものに向かう知的姿勢は模倣したいものだ。
「動物学者デズモンド・モリスによれば、愛の普遍的な象徴であるハートは、尻、それも後ろから見た女の尻に由来する」というくだりに、尻の秘めた精神性に打たれる。
かと思うとドルマンセはこう叫ぶ。「畜生!何というデブ、何というさわやかさ、何という炸裂、何という優雅さ!……」。男なら誰でも思い当たる尻に焦がれる切ない思いがちりばめられた本である。
「現代」1998年4月号掲載