今年の3月1日から一カ月間、私達テレビ取材班は中央アフリカのザイールを訪問した。東部の火山帯とそのすそ野に広がるサバンナの悪路に悩まされながら、移動とキャンプと水の出ないホテルで夜を過ごすことをくり返しながらの一カ月だった。
3月30日、国境のゴマの町を発ち、ルワンダの首都キガリに7時間のドライブの末到着。そこで二泊ののち飛行機でベルギーの首都ブリュッセルに飛び、そこで乗り換えて日本へ帰ってきた。
遠い、はるかな道のりだったが私たちは旅の無事をよろこびあった。機内で、レポーター―のC.W.ニコル氏は上機嫌で私の席にやってきた。食後の習慣に飲むコニャックで顔を赤らめながら彼は言った。
「シンペイ、すばらしい旅だったよ。ホントにいい取材ができたね。来年ボクは十六年ぶりにエチオピアを訪ねるけど、また、きっとタキオンで番組を作ってくれるね」
私に異存があるはずがない。さらに彼は、広島に投下された原爆が実はカナダの美しい湖に近いところで発掘されたウランで作られた事実を基にしてドキュメンタリーを私と一緒にぜひ作りたいとも言った。
私はこの瞬間の幸福を忘れることができない。自分が日頃敬愛する作家をレポーターにして長い旅が無事に終り、それをきっかけに新しい仕事が又約束されたのだ。私はこの時ほど、自分の今の職業を誇らしく思ったことはない。
長い旅の間に、東京では一人の女の子が誕生していた。ビデオエンジニアのT氏は、初の出産を間近に控えた若い妻のもとに残るか、長いアフリカ行きを選ぶか悩んだ末、結局後者を選んだ。プロ意識がそうさせた以上に、二年前に別の番組取材で行ったアフリカの魅力が俺をそうさせた、と彼は述懐していた。その言葉はニコル氏を感動させた。だれよりもアフリカを愛すると自負するニコル氏は、また、昨年秋に女の子をさずかった父親である。旅のあいだ中、東京の妻を思いやるT氏に、ニコル氏は温かい激励の言葉をかけてくれた。テレックスも電話もない地方での旅先で、それがどんなに心強かったか想像に難くない。
成田到着が迫り、ニコル氏の発案でT氏の子供の誕生を祝ってスタッフ六名のカンパが集められた。ニコル氏とスタッフ一同の心が一つになった瞬間であった。
それから約半年後、ニコル氏は一文を雑誌に寄稿した。私達テレビスタッフを「連中」と呼びすてにして、番組を「四流番組」となじり、「今後、彼らのうちの誰ひとりとも一緒に仕事をすることは二度とあるまい」と結んでいる。この予告なき突然の仕打ちは、私を戸惑わせるに充分だった。
ニコル氏の文章の波紋
その雑誌は文芸春秋社刊『ナンバー』9月20日号である。「テレビで見たから、真実なのか?!」のタイトルで発表されたこの文章の中で、ニコル氏はテレビスタッフが取材中にいかに無礼でウソツキであったか、そして放送された番組がいかにウソとヤラセに満ちているかと弾劾している。その怒りはとどまるところを知らず、日本のテレビ局全体を敵に廻した攻撃の砲火で紙面も燃え上がらんばかりであった。(しかし周到にも「NHKは別だ。私が攻撃しているのは民放各局である」と注をふっている。)
この記事はノンフィクション作家本田靖春氏によって雑誌「ダカーポ」に引用され、その結果他の雑誌に次々と飛び火した。私は、これらの取材に応じることが、日課にさえなってしまった。ふだんの仕事に集中できないこのような事態を一体どのように受けとめればよいのだろう。あの日、飛行機の中で感じた幸福感は幻想だったのだろうか。
活字によって撹乱される日々を過ごしながら、かつて自分が十三年間、出版編集者だった事実に思いをはせた。テレビ制作者に転じて七年が過ぎようとしている。そうして二十年が過ぎたのだ。昔はものをおもはざりき。書かれて初めて知る活字の怖さだ。人の書いた文章をまとめて本を作った十三年ではわからなかったものを、この一ヶ月間で体験した思いがする。
つづく
1986年12月号「創」寄稿
3月30日、国境のゴマの町を発ち、ルワンダの首都キガリに7時間のドライブの末到着。そこで二泊ののち飛行機でベルギーの首都ブリュッセルに飛び、そこで乗り換えて日本へ帰ってきた。
遠い、はるかな道のりだったが私たちは旅の無事をよろこびあった。機内で、レポーター―のC.W.ニコル氏は上機嫌で私の席にやってきた。食後の習慣に飲むコニャックで顔を赤らめながら彼は言った。
「シンペイ、すばらしい旅だったよ。ホントにいい取材ができたね。来年ボクは十六年ぶりにエチオピアを訪ねるけど、また、きっとタキオンで番組を作ってくれるね」
私に異存があるはずがない。さらに彼は、広島に投下された原爆が実はカナダの美しい湖に近いところで発掘されたウランで作られた事実を基にしてドキュメンタリーを私と一緒にぜひ作りたいとも言った。
私はこの瞬間の幸福を忘れることができない。自分が日頃敬愛する作家をレポーターにして長い旅が無事に終り、それをきっかけに新しい仕事が又約束されたのだ。私はこの時ほど、自分の今の職業を誇らしく思ったことはない。
長い旅の間に、東京では一人の女の子が誕生していた。ビデオエンジニアのT氏は、初の出産を間近に控えた若い妻のもとに残るか、長いアフリカ行きを選ぶか悩んだ末、結局後者を選んだ。プロ意識がそうさせた以上に、二年前に別の番組取材で行ったアフリカの魅力が俺をそうさせた、と彼は述懐していた。その言葉はニコル氏を感動させた。だれよりもアフリカを愛すると自負するニコル氏は、また、昨年秋に女の子をさずかった父親である。旅のあいだ中、東京の妻を思いやるT氏に、ニコル氏は温かい激励の言葉をかけてくれた。テレックスも電話もない地方での旅先で、それがどんなに心強かったか想像に難くない。
成田到着が迫り、ニコル氏の発案でT氏の子供の誕生を祝ってスタッフ六名のカンパが集められた。ニコル氏とスタッフ一同の心が一つになった瞬間であった。
それから約半年後、ニコル氏は一文を雑誌に寄稿した。私達テレビスタッフを「連中」と呼びすてにして、番組を「四流番組」となじり、「今後、彼らのうちの誰ひとりとも一緒に仕事をすることは二度とあるまい」と結んでいる。この予告なき突然の仕打ちは、私を戸惑わせるに充分だった。
ニコル氏の文章の波紋
その雑誌は文芸春秋社刊『ナンバー』9月20日号である。「テレビで見たから、真実なのか?!」のタイトルで発表されたこの文章の中で、ニコル氏はテレビスタッフが取材中にいかに無礼でウソツキであったか、そして放送された番組がいかにウソとヤラセに満ちているかと弾劾している。その怒りはとどまるところを知らず、日本のテレビ局全体を敵に廻した攻撃の砲火で紙面も燃え上がらんばかりであった。(しかし周到にも「NHKは別だ。私が攻撃しているのは民放各局である」と注をふっている。)
この記事はノンフィクション作家本田靖春氏によって雑誌「ダカーポ」に引用され、その結果他の雑誌に次々と飛び火した。私は、これらの取材に応じることが、日課にさえなってしまった。ふだんの仕事に集中できないこのような事態を一体どのように受けとめればよいのだろう。あの日、飛行機の中で感じた幸福感は幻想だったのだろうか。
活字によって撹乱される日々を過ごしながら、かつて自分が十三年間、出版編集者だった事実に思いをはせた。テレビ制作者に転じて七年が過ぎようとしている。そうして二十年が過ぎたのだ。昔はものをおもはざりき。書かれて初めて知る活字の怖さだ。人の書いた文章をまとめて本を作った十三年ではわからなかったものを、この一ヶ月間で体験した思いがする。
つづく
1986年12月号「創」寄稿










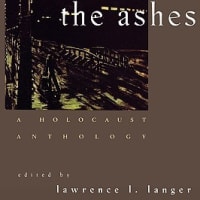




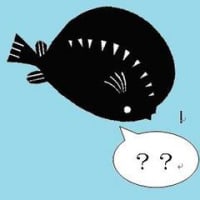




早いものですね。引き続きこのブログを楽しみにしてます。
CWニコルについては今も近所関係が良くないとかむつかしい人みたいですね。と今は何をしているのでしょうか。処女作の本は好きでしたが。畑正憲のフェードアウトしましたね。最初のころの本は面白かったですけど。
そうです、ようやく1年経ちました。CWニコルさんのこの件は、たまたま書類を整理していた際に見つけた手書きの原稿でした。少しだけこの話を聞いたことがありましたがこんな内容だったとはつゆ知らず。
信平さんの心外な思いと怒りがよく理解できました。どこまでもまっすぐな信平さんらしい文章だと思います。これから最後が面白くなります。引き続きお楽しみください。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
忘れずにいらしていただける信平さんは幸せですね。