
小笠原明峰
小笠原明峰(めいほう 1900~1947)という度外れの愛活家(あいかつか)のことを書いておきたい。
昔は映画とは言わずに活動写真、略して活動(カツドウ)と呼んでいた。愛活家とは、活動写真を愛好し一家言ある人のことである。今の言葉でいうと、映画ファンというより映画マニアの方が近いようだ。最近の私のように、大正の終わりから昭和十年代までの映画のことばかり調べている者も、一種の、遅れてきた愛活家と言えるかもしれない。(と、ちょっと誇らしげに言っちゃったりして)
昔、カツドウ全盛期には、熱心な愛活家が都会のあちこちにたむろしてはカツドウ談義に花を咲かせていたようだ。貧しい下宿部屋、街のカフェ、あるいはお屋敷の洋間などで、である。
小笠原明峰の家はお屋敷であった。場所は、東京の郊外、新宿から甲州街道を一里ほど行った幡ヶ谷村笹塚にあった。この呼称は正確ではない。1889年に代々木村と幡ヶ谷村が合併し代々幡村となり、1915年に代々幡町となったので、大正10年代は正確に言うと東京府豊多摩郡郡代々幡町である。なぜ私がこんなことにこだわるかと言うと、今その近くに住んでいて、この原稿もそこで書いているからだ。京王線の幡ヶ谷の次が笹塚で、私は次の代田橋と明大前の間にある住宅街の二世帯住宅の一階にいるのだ。笹塚というのは甲州街道を新宿からちょうど一里行った道端に一里塚が立っていて、それが笹の茂みにあったからだそうだ。町名で言うと、私は笹塚というこの呼び名が好きだ。昔、笹塚には、月形龍之介や古今亭志ん生が住んでいて、戦後は内田吐夢の家があったそうな。
全然話が進まないが、小笠原明峰というのは大変な青年だった。華族の子弟(つまりブルジョア階級のお坊ちゃま達)で愛活家仲間のボスとでもいおうか、梁山泊の主人とでもいおうか、リーダー的存在だった。
東坊城家のように当主が亡くなって家が傾いた華族ではなく、同じ子爵でも当主の親父はバリバリの海軍中将、それも東郷平八郎元帥の側近だったというから凄い。父の名は、小笠原長生(ながなり)。大正半ばに引退して宮中顧問官を務めていたが、文才もあり、「海戦日録」(明治28年)「東郷元帥詳伝」(大正10年刊)「撃滅 日本海海戦秘史」(昭和5年)といった書物まで著している。息子が親父の映画を作ると言ったら、原作権を与え、協力を惜しまない。道楽息子に厳しいのか甘いのか、分らないほど。この親父の父つまり祖父は、小笠原長行(ながみち)といい、幕末期に江戸幕府の老中だった人物。また、母親というのも名高い家の出身で、元前橋藩主、松平直方伯爵の長女である。
1900年(明治33年)6月、そんな家系の両親の間に長男(子爵の跡継ぎ)として生まれたのが小笠原明峰だった。血統書付きである。本名は長隆(ながたか)で、明峰は号というか芸名である。明峰には、二歳年下の弟がいて、長英(ながひで)というが、兄の影響を受けて彼も愛活家になり、映画監督から俳優になって活躍する。後の楠英二郎、改名して小笠原章二郎である。(内田吐夢監督、中村錦之助主演の『宮本武蔵』で寺の和尚さんなんかをやっています。)
明峰は、学習院高等部から明治大学へ進学するが、その頃からカツドウに狂い、説明者(弁士)に憧れ、学業そっちのけで新宿の武蔵野館などに出入りしていた。友人には古川緑波(ロッパ)や説明者の山野一郎がいた。そして、友人・知人を屋敷に連れ込んではパーティなどを催した。果ては、庭にスクリーンを張り、客を招いて、チャールズ・レイの『平和の谷』を上映し、山野一郎と分担して説明したほどで、明峰の活弁は旦那芸以上だという評判だった。ここまでなら良かったのだが、さらに進んで、映画製作にまで乗り出すのだから、見上げたものである。
人脈と親の財産をあてにして、プロダクションを作る。1923年春のことで、明峰は弱冠22歳。本社と撮影所は、東京府豊多摩郡代々幡町の自宅である。最初は、小笠原映画研究所という地味な名称で、今で言う自主製作の独立プロのような形態だった。
この小笠原プロが、日本映画史にとって人材派遣所のような重要な役割を果すのである。(続く)










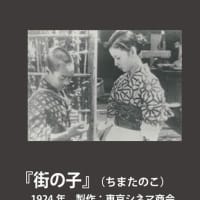



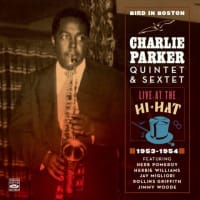
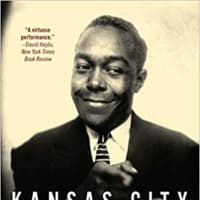

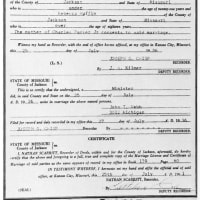


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます