
森田芳光の初長編映画『の・ようなもの』(1981年)を初めて観た。もう32年前の作品で、彼が映画監督として世間に注目されたデビュー作と言ってもよい映画である。田舎(栃木県?)から上京したと思われるまだ修業中の若手落語家を主人公(伊藤克信)に、その日常生活を描いたちょっぴりペーソスが漂うコメディであった。やりたいことや描きたいことをできる限り表現しようとした森田芳光の実験性と奔放さと斬新さはさすがであり、今観ても大変面白い映画だと思った。デビュー作には、良くも悪くも、映画作家の個性というものが表れるが、森田監督の特長は、観客を意識したエンターテイメント性であり、映像表現の意外性もセリフの面白さも、良い意味での「受け狙い」だと言えるだろう。深刻なことを真面目に描くのは苦手と言うか、多分照れ臭いのだろう。70年安保の世代(団塊の世代)より少し下の彼は、思想とかイデオロギーは胡散臭く、そんなものには不信感を抱いていたのかもしれない。彼の本領は、面白いことへの飽くなき追求であり、深刻な事柄でもドライでユーモラスに表現することであった。
『の・ようなもの』の出演者も、普通の俳優を使わず、ユニークな顔ぶれだった。この頃すでに人気女優だった秋吉久美子が大胆にもトルコ嬢(ソープ嬢と改称する前だから古い)を演じ、兄弟子役の尾藤イサオは歌手から俳優に転身した頃だったのか。ほかにも懐かしいタレントが揃っていた。漫才の内海好江、将棋指しの芹沢博文、落語家の春風亭柳朝は、故人である。内海桂子、入船亭扇橋はまだ元気なようだ。ほかにも、でんでん、鷲尾真知子、ラビット関根(関根勤)、小堺一機、室井滋、三遊亭楽太郎などが出演していたが、私のように二、三十年ほど時間が止まっている者にとっては違和感がないが、今の彼らの顔をよく知っている人が見たら、昔日の感があるだろう。
森田芳光が大学(明治大学)の落研にいたことは有名だが、この映画には、落語のネタがいくつか使われ、また落語通ならあの噺のパロディだと分かるような場面もあった。例えば、主人公の志ん魚(とと)が高校生の彼女の家(堀切駅)から夜中に歩いて浅草まで帰るくだりは、「黄金餅」のパクリであろう。タイトルの『の・ようなもの』は、三遊亭金馬の十八番「居酒屋」の中で小僧が酔客に酒の肴を言うセリフ「できますものは、つゆはしらたらこぶあんこうのようなもの」から採ったという。
なにしろこの映画は、アイディアのてんこ盛りのような作品で、受けようが受けまいが、次から次へとアイディアを繰り出してくるので、終始、目が離せない作品であった。主人公の志ん魚の落語がまったく笑えないところが逆におかしく、秋吉久美子がボディー洗いしたり、兄弟子のでんでんが夜中に迫ってきたり、エロチックな見せ場もあり、人名の固有名詞(例えば、ジャンゴ・ラインハルトの名前が突然出て来た時は驚いた)を使ったセリフも効果的であった。主役の伊藤克信は、言われてみれば確かにアル・パチーノに目と鼻のあたりが似ているのだ。















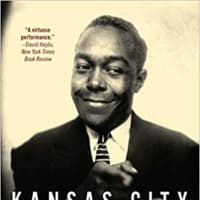

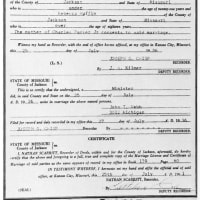


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます