
立原正秋の小説は映画化されることがまれだった。在日朝鮮人でありながら、立原ほど一途に古き日本人の情念や美意識を描いた作家はいなかったのに、他の作家に比べ映画化された作品が少なかった。それはなぜだか分からない。立原自身が作品の映画化を拒んだのか、それとも彼の退廃的な滅びの美学は映画化するのが困難だったのだろうか。立原正秋は昭和55年、多くの熱烈な愛読者に惜しまれ、54歳の若さで死んだ。
「春の鐘」は、立原正秋の死後、彼の長編小説を、久しぶりに映画化した作品だった。監督は蔵原惟繕(これよし)。「南極物語」の大ヒットで一躍有名になった映画監督だが、もともと日活黄金時代に石原裕次郎や浅丘ルリ子の映画を手がけ、男女の情愛を描くことにかけては鬼才と呼ばれた監督である。「春の鐘」は、蔵原が「南極物語」の酷寒のロケから帰還後、動物と自然といったテーマから一転し、彼の本領ともいえる人間の男女の愛欲の世界を描いた秀作だった。私はこの映画を十年ほど前ビデオで見て、いたく感動した覚えがある。また見たいと思っているが、ビデオをどこで借りたかも忘れてしまい、見られない状態が続いている。まだDVDにもなっていないようだ。
「春の鐘」は、古都奈良を舞台に、美術館の館長(北大路欣也)と陶芸家の出戻り娘(古手川裕子)のひた向きな恋愛を描いた映画である。この中年男の館長は、東京に妻子を残し、単身赴任で奈良に来ている。が、妻(三田佳子)との関係は冷え切っていた。妻は得られない愛の渇きから、つい医者と不倫をしてしまう。中年男はそれに気づいてはいるが、離婚は考えず、美術館の仕事に一層専念した。そんなある日、旧知の陶芸家(岡田英次)の仕事場を訪ね、彼の娘と運命的な再会をする。幼い時分に見たことがある女の子が、驚くばかりの美しい女になっていたのだ。離婚したばかりで実家に出戻ってきたのだという。知り合いの娘の不幸に同情して、というのは表向きの理由で、実はこの娘に心惹かれて、中年男は彼女を自分の美術館に勤めさせる……。
うろ覚えのあらすじを書くことはやめよう。安直なメロドラマみたいに思われてしまうからだ。この映画は、男女の移ろいやすい愛とその宿命を、滅びゆく日本の美しい情景のなかで描き切った類まれな作品だといえる。中年男の燃えくすぶっていた恋情のとめどない発露、妻の夫に対する未練と別れ際の修羅場のすさまじさ、否応なく女と別れた男の愚かなまでの執着など、男と女のどろどろした愛欲の世界を、無常観漂う古都の美しく静かな営みの中で、いわば俯瞰的に描いていた。そこが素晴らしく、感動せずにはいられなかったのだろう。
蔵原惟繕は、映画人生最後の執念を賭けて「春の鐘」を作った。その蔵原も今はない。彼の死が報道されたのは、平成15年の正月のことだった。百八つの煩悩の鐘が鳴る、あの年の暮れを迎えることもなく、この世からひっそり去っていた。
<立原正秋「春の鐘」>

「春の鐘」は、立原正秋の死後、彼の長編小説を、久しぶりに映画化した作品だった。監督は蔵原惟繕(これよし)。「南極物語」の大ヒットで一躍有名になった映画監督だが、もともと日活黄金時代に石原裕次郎や浅丘ルリ子の映画を手がけ、男女の情愛を描くことにかけては鬼才と呼ばれた監督である。「春の鐘」は、蔵原が「南極物語」の酷寒のロケから帰還後、動物と自然といったテーマから一転し、彼の本領ともいえる人間の男女の愛欲の世界を描いた秀作だった。私はこの映画を十年ほど前ビデオで見て、いたく感動した覚えがある。また見たいと思っているが、ビデオをどこで借りたかも忘れてしまい、見られない状態が続いている。まだDVDにもなっていないようだ。
「春の鐘」は、古都奈良を舞台に、美術館の館長(北大路欣也)と陶芸家の出戻り娘(古手川裕子)のひた向きな恋愛を描いた映画である。この中年男の館長は、東京に妻子を残し、単身赴任で奈良に来ている。が、妻(三田佳子)との関係は冷え切っていた。妻は得られない愛の渇きから、つい医者と不倫をしてしまう。中年男はそれに気づいてはいるが、離婚は考えず、美術館の仕事に一層専念した。そんなある日、旧知の陶芸家(岡田英次)の仕事場を訪ね、彼の娘と運命的な再会をする。幼い時分に見たことがある女の子が、驚くばかりの美しい女になっていたのだ。離婚したばかりで実家に出戻ってきたのだという。知り合いの娘の不幸に同情して、というのは表向きの理由で、実はこの娘に心惹かれて、中年男は彼女を自分の美術館に勤めさせる……。
うろ覚えのあらすじを書くことはやめよう。安直なメロドラマみたいに思われてしまうからだ。この映画は、男女の移ろいやすい愛とその宿命を、滅びゆく日本の美しい情景のなかで描き切った類まれな作品だといえる。中年男の燃えくすぶっていた恋情のとめどない発露、妻の夫に対する未練と別れ際の修羅場のすさまじさ、否応なく女と別れた男の愚かなまでの執着など、男と女のどろどろした愛欲の世界を、無常観漂う古都の美しく静かな営みの中で、いわば俯瞰的に描いていた。そこが素晴らしく、感動せずにはいられなかったのだろう。
蔵原惟繕は、映画人生最後の執念を賭けて「春の鐘」を作った。その蔵原も今はない。彼の死が報道されたのは、平成15年の正月のことだった。百八つの煩悩の鐘が鳴る、あの年の暮れを迎えることもなく、この世からひっそり去っていた。
<立原正秋「春の鐘」>












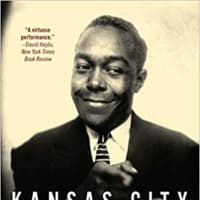

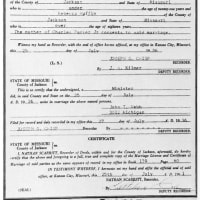







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます