これ、まだ感想書いてない『染模様恩愛御書』より後に観たけんだけど、まあいいや(……いや、よくないって。26日の楽までに書けるんだろか )
)
操り三番叟(あやつりさんばそう)長唄囃子連中 三番叟物の一種
<配役>
三番叟:中村翫雀/後見:中村亀鶴/千歳:坂東亀三郎/翁:市川左團次
亀三郎さんの千歳がとっても凛々しく綺麗でうっとり眺めつつも、脳内では愛之助さんにやってほしいなあと思ってました(亀三郎さんすんません)が、後で番附観たら7年前にやってたわ …………ファン失格、とはいえ愛之助さんを認識したのはもう少し後だから仕方ないか。
…………ファン失格、とはいえ愛之助さんを認識したのはもう少し後だから仕方ないか。
後見役の亀鶴さんが初役ながら頑張ってたと思います。切れた操り糸を繋いで唾で湿らせて扱くとこは、本当にそこに糸があるように見えました。
翫雀さんの操り人形はさすがに上手い。ただ、ピンと糸を張った状態の動きをもっと感じたかったんだけど、弛んだ状態のほうが目立ってて踊りが柔らかすぎて酔っ払いみたい
絡まった操り糸が戻る時に人形がくるくるくるくる高速回転。後見の慌てっぷりが面白く、必死な様子がよく伝わってきました。
口上
上手から
尾上菊五郎 片岡秀太郎 坂東三津五郎 市川左團次 中村雀右衛門 中村鴈治郎改め坂田藤十郎
中村翫雀 中村扇雀 中村時蔵 片岡我當
勘三郎さんのように亡くなられた先代の名の襲名ではなく、231年前の大名跡復活襲名だから、なんとなく華やいだお祭り気分の口上でした。
雀右衛門さんの挨拶から始まったんですが、御年86歳とは思えない実に滑らかな立て板に水状態の挨拶。
いつまでも元気でいていただきたいですね。
以下、藤十郎さんへの言葉で笑いを取ってた部分。
左團次さん
「藤十郎さんは、19歳以上の女性は恋愛対象ではないとおっしゃられてますが、それでは世の女性が悲しむので、もう少し対象年齢を上げていただかないと……」
秀太郎さん
「昔から色々教えていただきましたが、十代の頃からお茶屋遊びを教えていただきました」
秀太郎さんが一番長い挨拶だったと思うんだけど、もっと話したそうでした(笑)
菊五郎さん
「2人には共通点がございまして、それは妻が恐いことです」
扇雀さん
「紋も屋号も親子で違うものになりましたが、決して親子の縁を切ったわけではありません」
枕獅子(まくらじし)長唄囃子連中 鏡獅子の元になったもの
<配役>
傾城弥生:坂田藤十郎/新造若菜:中村翫雀/新造梅ヶ枝:中村扇雀
鏡獅子や枕獅子と同じ石橋物は、亀治郎さんの天下る傾城の印象が強く残っていて、今回の枕獅子はちょっと物足りなかったかな。
振付けが全然違うんで比べちゃいけないんだけど、スピード感溢れる亀治郎さんの傾城とは対照的に、藤十郎さんの弥生はあくまでも典雅で鷹揚で優雅。あのテンポで50分は長すぎかも(亀治郎さんの45分は長いと感じませんでした)
胡蝶になってからの新造2人の踊りが揃ってないのが気になりました。演出?……じゃないよねえ。
梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう) 髪結新三 あらすじはコチラ
<主な配役>
髪結新三:尾上菊五郎/白子屋娘お熊:片岡孝太郎/車力善八:坂東秀調/白子屋後家お常:坂東竹三郎
加賀屋藤兵衛:市川團蔵/白子屋手代忠七:中村時蔵/弥太五郎源七:坂東三津五郎
下剃勝奴:尾上松緑/家主長兵衛:市川左團次
新三は菊五郎さんが菊五郎劇団で何度も演じてるようなので、台詞や仕種のひとつひとつが実に手馴れた感じで、非常な安定感を感じました。
ただ、菊五郎さんが新三というチンピラをやるには、ちょっと貫禄ありすぎかも。とは言っても、髪結稼業の人当たりの良さと本来の小悪党な部分のギャップや、源七をやり込める時の痛快さは、貫禄なんぞ気にならないほどよかったんですけど
小判を投げて勝奴にあげているところの表情が実に楽しげで、素敵でした。
孝太郎さんは、武家の奥方とか年かさの女性の時はいいんだけど、娘役の時は声を張りすぎて甲高くなってヒステリック気味に聞こえるのが残念。
お熊が母親に「婚礼って誰の?」と聞くとこは可愛らしかったです。
“初鰹”で盛り上る長屋の面々の遣り取りが面白かったですね。
あの作り物の“鰹”はよく出来てます。身の剥がれっぷりが見事(笑)
長兵衛の左團次さんは、新三との15両・30両云々の台詞が大変そうでした。長い上に似たような遣り取りの繰り返しで、“目の子勘定”の回数忘れてもおかしくないかも。
三津五郎さんの弥太五郎源七は、存在感や貫禄はもちろん、白子屋への想い、新三に対する焦りや怒り、どれも素晴らしい表現力でしたね。
この役って、たぶん新三役より年上の役者が演じるものだと思うんだけど、菊五郎さんより若い三津五郎さんが演じたことによって、源七という人物像が丁寧に深く掘り下げられてたのでは?
江戸時代の下町の風俗がたっぷり味わえる面白い舞台でした。
ただ、135分ぶっ通しは長い!
途中に暗転が3度(うろ覚え)ほどあったけど、15分休憩を1回でいいから入れて欲しかった。
 )
)操り三番叟(あやつりさんばそう)長唄囃子連中 三番叟物の一種
<配役>
三番叟:中村翫雀/後見:中村亀鶴/千歳:坂東亀三郎/翁:市川左團次
亀三郎さんの千歳がとっても凛々しく綺麗でうっとり眺めつつも、脳内では愛之助さんにやってほしいなあと思ってました(亀三郎さんすんません)が、後で番附観たら7年前にやってたわ
 …………ファン失格、とはいえ愛之助さんを認識したのはもう少し後だから仕方ないか。
…………ファン失格、とはいえ愛之助さんを認識したのはもう少し後だから仕方ないか。後見役の亀鶴さんが初役ながら頑張ってたと思います。切れた操り糸を繋いで唾で湿らせて扱くとこは、本当にそこに糸があるように見えました。
翫雀さんの操り人形はさすがに上手い。ただ、ピンと糸を張った状態の動きをもっと感じたかったんだけど、弛んだ状態のほうが目立ってて踊りが柔らかすぎて酔っ払いみたい

絡まった操り糸が戻る時に人形がくるくるくるくる高速回転。後見の慌てっぷりが面白く、必死な様子がよく伝わってきました。
口上
上手から
尾上菊五郎 片岡秀太郎 坂東三津五郎 市川左團次 中村雀右衛門 中村鴈治郎改め坂田藤十郎
中村翫雀 中村扇雀 中村時蔵 片岡我當
勘三郎さんのように亡くなられた先代の名の襲名ではなく、231年前の大名跡復活襲名だから、なんとなく華やいだお祭り気分の口上でした。
雀右衛門さんの挨拶から始まったんですが、御年86歳とは思えない実に滑らかな立て板に水状態の挨拶。
いつまでも元気でいていただきたいですね。
以下、藤十郎さんへの言葉で笑いを取ってた部分。
左團次さん
「藤十郎さんは、19歳以上の女性は恋愛対象ではないとおっしゃられてますが、それでは世の女性が悲しむので、もう少し対象年齢を上げていただかないと……」
秀太郎さん
「昔から色々教えていただきましたが、十代の頃からお茶屋遊びを教えていただきました」
秀太郎さんが一番長い挨拶だったと思うんだけど、もっと話したそうでした(笑)
菊五郎さん
「2人には共通点がございまして、それは妻が恐いことです」
扇雀さん
「紋も屋号も親子で違うものになりましたが、決して親子の縁を切ったわけではありません」
枕獅子(まくらじし)長唄囃子連中 鏡獅子の元になったもの
<配役>
傾城弥生:坂田藤十郎/新造若菜:中村翫雀/新造梅ヶ枝:中村扇雀
鏡獅子や枕獅子と同じ石橋物は、亀治郎さんの天下る傾城の印象が強く残っていて、今回の枕獅子はちょっと物足りなかったかな。
振付けが全然違うんで比べちゃいけないんだけど、スピード感溢れる亀治郎さんの傾城とは対照的に、藤十郎さんの弥生はあくまでも典雅で鷹揚で優雅。あのテンポで50分は長すぎかも(亀治郎さんの45分は長いと感じませんでした)
胡蝶になってからの新造2人の踊りが揃ってないのが気になりました。演出?……じゃないよねえ。
梅雨小袖昔八丈(つゆこそでむかしはちじょう) 髪結新三 あらすじはコチラ
<主な配役>
髪結新三:尾上菊五郎/白子屋娘お熊:片岡孝太郎/車力善八:坂東秀調/白子屋後家お常:坂東竹三郎
加賀屋藤兵衛:市川團蔵/白子屋手代忠七:中村時蔵/弥太五郎源七:坂東三津五郎
下剃勝奴:尾上松緑/家主長兵衛:市川左團次
新三は菊五郎さんが菊五郎劇団で何度も演じてるようなので、台詞や仕種のひとつひとつが実に手馴れた感じで、非常な安定感を感じました。
ただ、菊五郎さんが新三というチンピラをやるには、ちょっと貫禄ありすぎかも。とは言っても、髪結稼業の人当たりの良さと本来の小悪党な部分のギャップや、源七をやり込める時の痛快さは、貫禄なんぞ気にならないほどよかったんですけど

小判を投げて勝奴にあげているところの表情が実に楽しげで、素敵でした。
孝太郎さんは、武家の奥方とか年かさの女性の時はいいんだけど、娘役の時は声を張りすぎて甲高くなってヒステリック気味に聞こえるのが残念。
お熊が母親に「婚礼って誰の?」と聞くとこは可愛らしかったです。
“初鰹”で盛り上る長屋の面々の遣り取りが面白かったですね。
あの作り物の“鰹”はよく出来てます。身の剥がれっぷりが見事(笑)
長兵衛の左團次さんは、新三との15両・30両云々の台詞が大変そうでした。長い上に似たような遣り取りの繰り返しで、“目の子勘定”の回数忘れてもおかしくないかも。
三津五郎さんの弥太五郎源七は、存在感や貫禄はもちろん、白子屋への想い、新三に対する焦りや怒り、どれも素晴らしい表現力でしたね。
この役って、たぶん新三役より年上の役者が演じるものだと思うんだけど、菊五郎さんより若い三津五郎さんが演じたことによって、源七という人物像が丁寧に深く掘り下げられてたのでは?
江戸時代の下町の風俗がたっぷり味わえる面白い舞台でした。
ただ、135分ぶっ通しは長い!
途中に暗転が3度(うろ覚え)ほどあったけど、15分休憩を1回でいいから入れて欲しかった。


















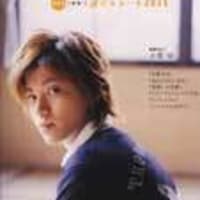








今まで幾度かは寄せて頂いていましたが、今回初めてのコメントです…(汗)
簡潔なレポート、参考になります。要点をバシッと押さえておられますね…♪
私が観たときの口上で…菊五郎さんは、
『お兄さんには一つ趣味が御座いまして…その趣味とは…参議院議長に御座いますm(__)m』
と言った、バージョンでした…(苦笑)
宜しくお願い致します~♪
コメント&TBありがとうございます!
rikaさん宅でお見かけするので、お名前は存じておりました。
>簡潔なレポート、参考になります
とんでもないです。ありがとうございます。
口上も小ネタが日替わりで、考えるのも結構大変そうですね。
しかし「趣味が参議院議長」って(笑)
こちらこそよろしくお願いしますね~~~。