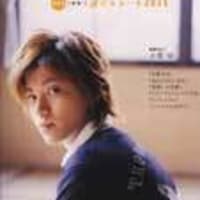三谷幸喜、、香川照之、内野聖陽、坂元健児……『第五回亀治郎の会』筋書(A5版全128P)にコメントを寄せている面々。こんなとこで坂健さんの名前を目にするとは(笑)
三谷さんは『決闘!高田馬場』、香川照之はいとこ、うっちーは来年の大河で共演、ていうつながりがあるけど、坂健さんは…………何を思ったか(失礼)亀治郎さんが去年、坂健さんの舞台を観に行きそれ以来の仲だそうです。亀健ユニット誕生かも(マジな話らしい)
この筋書1冊で記事書けそう。
奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)
環宮明御殿(たまきのみやあきごてん)の場
『瓜生山歌舞伎』の『袖萩祭文』と同じです。以上。
というのは冗談で、内容は同じなんですが、瓜生山では無かったものが………。
筋書に、腰元と郎党の名前が載ってました。何故、瓜生山の筋書に載ってなかったんだろ?
腰元は松ヶ枝、竹野、紅梅、小冬、こずえ。郎党は、秩父十郎竹綱、伴次郎助兼、和田左衛門為宗、大宅四郎惟弘。この中で名前呼ばれたひとっていたかなー 腰元の誰かが呼ばれてたような気もするんだけど……(既に記憶なし
腰元の誰かが呼ばれてたような気もするんだけど……(既に記憶なし )
)
ま、後は同じです(笑)
さすがに2回目なのでストーリーはすっかり頭の中に入ってて、役者さんの演技を堪能することができました。
今回、花道外側・前から4列目の席で、袖萩&お君ちゃんがいる位置に近いのはいいんだけど、花道が高くって、舞台下手~中央にいる役者さんの足元が見えず 日本女性の平均身長より10cm大きい私でこうなので、普通サイズの女性はかなり観辛かったと思われます。
日本女性の平均身長より10cm大きい私でこうなので、普通サイズの女性はかなり観辛かったと思われます。
いつもながら下手前方の席に座ると、正面からは見えない色々なものが見えますね(笑)
後見さんのお仕事まで堪能してしまいました
ハプニングがひとつ。
宗任が矢の根で白旗に和歌を書き付けた後、白いままの旗を旗竿から引き落として、一瞬で後ろにあった和歌が書かれた白旗に変わるはずが、2つとも旗竿から落ちちゃったーーっっ


後見さんが、必死で絡まった旗を外して旗竿に掛けようとする中、お芝居はどんどん進んでいきます(亀治郎さんはなるべく間を取るようにしてたと思う)
結局、亀治郎さんが御殿の縁から手を伸ばして後見さんから和歌が書かれた旗を受け取って、観客に見えるように広げて(といっても旗は長くて和歌は全部見えず )なんとかお芝居続行
)なんとかお芝居続行
あーびっくりした
竹三郎さん@浜夕は瓜生山より熱演度UP。袖萩&お君ちゃんとの絡みが多い浜夕なので下手を向いてのお芝居が多く、表情がよく見えました。
最後の方は、今にも涙こぼれそうなくらい、目の中がうるうるしててもらい泣き
今回の『奥州安達原』は亀鶴さんが出色でしたねー、私としては。
愛之助さんは動きが少なく台詞も安定感がなければいけない役で、面白みという点では物足りなかったです。ただ、あの役は私は“観賞用の時々喋る武者人形”だと思ってて、動かないなら見目よろしくないとほんっとにつまんないので、美形がやらないとダメなんじゃないかと………見方間違ってたらすいません
天下る傾城(あまくだるけいせい) 長唄囃子連中
<主な配役>
傾城後に獅子の精:市川亀治郎
禿:中村扇之丞、中村京紫/力者:市川茂之助、市川段一郎
<解説>(『第五回亀治郎の会』筋書より)
文化12年(1815年)3月、江戸の中村座で初演された九変化舞踊『素九絵彩四季桜』のうちの『江口の君』『牡丹の石橋』がひとつになった曲で、♪天下る~♪の歌詞で始まるところから『天下る傾城』の題で呼ばれるようになった。関西では『江口の石橋』または『九変化の石橋』の名称で伝わっている。初世杵屋勝五郎作曲、三代目中村歌右衛門による初演。
昭和38年のラジオ放送の際、この曲の伝承者である故・今藤長十郎師により、伝承の明確でない部分が整理されたという経緯がある。
今回は振付けの藤間勘吉郎師による発案によって、稀音家祐介氏、田中傳左衛門氏の協力の下、江戸の初演以来途絶えていた舞踊が復活する。
45分と長い踊りだし、愛之助さんがいないので寝るかと思ったんですが(大大大暴言)なんのなんの、素晴らしかったです。『松廼羽衣』は踊りも衣裳も清楚で可憐でしたが、こちらは傾城→獅子だけあって、全てが豪華で華やかでしたね。
最初は花魁姿で手には扇子。内掛けは黒地に金糸銀糸色とりどりの松と竹と鶴。あれ?梅は?と思ったら下の着物が赤地に梅でした。帯は紫。禿の衣裳は赤地に花模様(色忘れました )
)
扇子を上に投げて取ったり、後ろ向きに投げて禿がそれを取ったり、結構楽しい(笑)
持ち物が次々変わります。
銀色と紺色の扇子→オレンジの紐がついた銀色の団扇→桜の花笠→扇子の獅子頭。
この獅子頭、天の部分に金色の鈴がついた扇子(やっぱり金色)を2枚骨のところで合わせてあって、上側の扇子にはミニ連獅子みたいな赤い毛と赤い牡丹が付いてるという構造です。これを2枚ぱくぱくさせると獅子が口を開け閉めする感じになってました。このときもちろん鈴が鳴るんだけど、主に花道での所作だったので鈴の音がよく聞こえて心地良かったです。
獅子の精に変わってからは一段とテンポUP&ヒートUPで圧巻


衣裳は花魁の赤い着物の上に白の袍のようなものを着て、連獅子でおなじみの手には紅白の牡丹、頭には赤い毛を被ってます。
毛振りがお見事~~~。“連獅子”ではないから1人での毛振りでちょっと寂しいかもと思ってたけど、そんなのは杞憂で、2人分振ってたんじゃないかってくらい(笑)
去年御園座で観た勘太郎君の連獅子が観客からどよめきがおこるくらいすごい迫力で、それに匹敵するくらいの毛振りでした。
最後は舞台中央の石橋で力者と共にポーズを決めて、会場割れんばかりの大拍手







この時力者が石橋から前宙で床に落ちます。石橋が結構高い位置にあって落ちた時すんごい音がして痛そ~ (「痛い」って顔はしてませんが/当たり前
(「痛い」って顔はしてませんが/当たり前 )
)
受身を取ってるから、こっちが思うほど痛みはないんでしょうけど……。
瓜生山に引き続き、とてもいいものを見せていただきました。
九月の歌舞伎座を最後に、来年の『第六回亀治郎の会』まで舞台はお預けですね(パリ公演はあるけど観に行けるわけもなく……)
こうしていい舞台を観ると、しばらく観れないからってことでやっぱり九月も観たいんですけど、金ないんですけど、日程的にもきついんですけど、吉右衛門さん&幸四郎さんなんですけど、雀右衛門さんの小町が観たいんですけど、きーーーーーーーー(壊れかけ)
平成十九年『第六回亀治郎の会』は国立大劇場です。千秋楽に行くぞー
ついでに(ついでかよ)歌舞伎座も行こ。
三谷さんは『決闘!高田馬場』、香川照之はいとこ、うっちーは来年の大河で共演、ていうつながりがあるけど、坂健さんは…………何を思ったか(失礼)亀治郎さんが去年、坂健さんの舞台を観に行きそれ以来の仲だそうです。亀健ユニット誕生かも(マジな話らしい)

この筋書1冊で記事書けそう。
奥州安達原(おうしゅうあだちがはら)
環宮明御殿(たまきのみやあきごてん)の場
『瓜生山歌舞伎』の『袖萩祭文』と同じです。以上。
というのは冗談で、内容は同じなんですが、瓜生山では無かったものが………。
筋書に、腰元と郎党の名前が載ってました。何故、瓜生山の筋書に載ってなかったんだろ?
腰元は松ヶ枝、竹野、紅梅、小冬、こずえ。郎党は、秩父十郎竹綱、伴次郎助兼、和田左衛門為宗、大宅四郎惟弘。この中で名前呼ばれたひとっていたかなー
 腰元の誰かが呼ばれてたような気もするんだけど……(既に記憶なし
腰元の誰かが呼ばれてたような気もするんだけど……(既に記憶なし )
)ま、後は同じです(笑)
さすがに2回目なのでストーリーはすっかり頭の中に入ってて、役者さんの演技を堪能することができました。
今回、花道外側・前から4列目の席で、袖萩&お君ちゃんがいる位置に近いのはいいんだけど、花道が高くって、舞台下手~中央にいる役者さんの足元が見えず
 日本女性の平均身長より10cm大きい私でこうなので、普通サイズの女性はかなり観辛かったと思われます。
日本女性の平均身長より10cm大きい私でこうなので、普通サイズの女性はかなり観辛かったと思われます。いつもながら下手前方の席に座ると、正面からは見えない色々なものが見えますね(笑)
後見さんのお仕事まで堪能してしまいました

ハプニングがひとつ。
宗任が矢の根で白旗に和歌を書き付けた後、白いままの旗を旗竿から引き落として、一瞬で後ろにあった和歌が書かれた白旗に変わるはずが、2つとも旗竿から落ちちゃったーーっっ



後見さんが、必死で絡まった旗を外して旗竿に掛けようとする中、お芝居はどんどん進んでいきます(亀治郎さんはなるべく間を取るようにしてたと思う)
結局、亀治郎さんが御殿の縁から手を伸ばして後見さんから和歌が書かれた旗を受け取って、観客に見えるように広げて(といっても旗は長くて和歌は全部見えず
 )なんとかお芝居続行
)なんとかお芝居続行
あーびっくりした

竹三郎さん@浜夕は瓜生山より熱演度UP。袖萩&お君ちゃんとの絡みが多い浜夕なので下手を向いてのお芝居が多く、表情がよく見えました。
最後の方は、今にも涙こぼれそうなくらい、目の中がうるうるしててもらい泣き

今回の『奥州安達原』は亀鶴さんが出色でしたねー、私としては。
愛之助さんは動きが少なく台詞も安定感がなければいけない役で、面白みという点では物足りなかったです。ただ、あの役は私は“観賞用の時々喋る武者人形”だと思ってて、動かないなら見目よろしくないとほんっとにつまんないので、美形がやらないとダメなんじゃないかと………見方間違ってたらすいません

天下る傾城(あまくだるけいせい) 長唄囃子連中
<主な配役>
傾城後に獅子の精:市川亀治郎
禿:中村扇之丞、中村京紫/力者:市川茂之助、市川段一郎
<解説>(『第五回亀治郎の会』筋書より)
文化12年(1815年)3月、江戸の中村座で初演された九変化舞踊『素九絵彩四季桜』のうちの『江口の君』『牡丹の石橋』がひとつになった曲で、♪天下る~♪の歌詞で始まるところから『天下る傾城』の題で呼ばれるようになった。関西では『江口の石橋』または『九変化の石橋』の名称で伝わっている。初世杵屋勝五郎作曲、三代目中村歌右衛門による初演。
昭和38年のラジオ放送の際、この曲の伝承者である故・今藤長十郎師により、伝承の明確でない部分が整理されたという経緯がある。
今回は振付けの藤間勘吉郎師による発案によって、稀音家祐介氏、田中傳左衛門氏の協力の下、江戸の初演以来途絶えていた舞踊が復活する。
45分と長い踊りだし、愛之助さんがいないので寝るかと思ったんですが(大大大暴言)なんのなんの、素晴らしかったです。『松廼羽衣』は踊りも衣裳も清楚で可憐でしたが、こちらは傾城→獅子だけあって、全てが豪華で華やかでしたね。
最初は花魁姿で手には扇子。内掛けは黒地に金糸銀糸色とりどりの松と竹と鶴。あれ?梅は?と思ったら下の着物が赤地に梅でした。帯は紫。禿の衣裳は赤地に花模様(色忘れました
 )
)扇子を上に投げて取ったり、後ろ向きに投げて禿がそれを取ったり、結構楽しい(笑)
持ち物が次々変わります。
銀色と紺色の扇子→オレンジの紐がついた銀色の団扇→桜の花笠→扇子の獅子頭。
この獅子頭、天の部分に金色の鈴がついた扇子(やっぱり金色)を2枚骨のところで合わせてあって、上側の扇子にはミニ連獅子みたいな赤い毛と赤い牡丹が付いてるという構造です。これを2枚ぱくぱくさせると獅子が口を開け閉めする感じになってました。このときもちろん鈴が鳴るんだけど、主に花道での所作だったので鈴の音がよく聞こえて心地良かったです。
獅子の精に変わってからは一段とテンポUP&ヒートUPで圧巻



衣裳は花魁の赤い着物の上に白の袍のようなものを着て、連獅子でおなじみの手には紅白の牡丹、頭には赤い毛を被ってます。
毛振りがお見事~~~。“連獅子”ではないから1人での毛振りでちょっと寂しいかもと思ってたけど、そんなのは杞憂で、2人分振ってたんじゃないかってくらい(笑)
去年御園座で観た勘太郎君の連獅子が観客からどよめきがおこるくらいすごい迫力で、それに匹敵するくらいの毛振りでした。
最後は舞台中央の石橋で力者と共にポーズを決めて、会場割れんばかりの大拍手








この時力者が石橋から前宙で床に落ちます。石橋が結構高い位置にあって落ちた時すんごい音がして痛そ~
 (「痛い」って顔はしてませんが/当たり前
(「痛い」って顔はしてませんが/当たり前 )
)受身を取ってるから、こっちが思うほど痛みはないんでしょうけど……。
瓜生山に引き続き、とてもいいものを見せていただきました。
九月の歌舞伎座を最後に、来年の『第六回亀治郎の会』まで舞台はお預けですね(パリ公演はあるけど観に行けるわけもなく……)
こうしていい舞台を観ると、しばらく観れないからってことでやっぱり九月も観たいんですけど、金ないんですけど、日程的にもきついんですけど、吉右衛門さん&幸四郎さんなんですけど、雀右衛門さんの小町が観たいんですけど、きーーーーーーーー(壊れかけ)
平成十九年『第六回亀治郎の会』は国立大劇場です。千秋楽に行くぞー

ついでに(ついでかよ)歌舞伎座も行こ。











 願ったり叶ったり
願ったり叶ったり