@decostatw 「論理」や「合理」も「人生哲学」の一部をなすものってことなんでしょうかね。演繹はそれだけじゃないぞと。まあでもチャレンジングなネーミングですよね……。
[MM登録] 人生哲学感情心理学(REBT)基本用語集 bit.ly/1a8eSkc 日本人生哲学感情心理学会基本用語編集委員会 (著), 菅沼憲治 吉田悟 (編集)
抑制のきかない豚には自由意志がない - noscience! d.hatena.ne.jp/noscience/2013… "抑制の障害を示すひとびと―たとえば,子供,高齢者,一部の患者―には痛烈である.こうしたひとびとは自由意志の障害に苦しんでいることになる"
「抑制のきかない豚には自由意志がない」と言われてドッと冷や汗が噴き出した僕こと豚ですけど,それはさておき,すごく面白かったです! d.hatena.ne.jp/noscience/2013…
@kosukesa @psypub 60ページのHebbの引用もぐっときた。さっそく「行動の機構」を机の端に積んでみました。あと,「連合学習理論はよい説明か」の部分で,何度も連合学習への期待と肩すかし感を経験してからの,表現論って流れが面白かったです。
ランバートの円グラフ(Asay and Lambert, 1999)が推定であることは、クーパー『エビデンスにもとづくカウンセリング効果の研究』(岩崎学術出版社, 2012)のp.70に載っている。 当該章は psycnet.apa.org/index.cfm?fa=b…で購入可能。
確かに僕には答える資格がありませんが、日本でも外国でも僕の好きなCBTセラピストは関係性を大切にしています。ただ考え方としてCBTは「良い関係の中で治療する」、ヒューマニスティックな心理療法は「関係が治す」と考え、力動学派は「関係を使って治す」という感じでしょうか。
【拡散希望】論文が公開されてたー!#PLOSONE: Role-Play Experience Facilitates Reading the Mind of Individuals with Different Perception dx.plos.org/10.1371/journa…
【PLOS ONE論文概要】 40名の正常色覚の大学生を対象に、相手の意図を読み取ることが必要なコミュニケーション課題を行ったところ 事前に自分が制限された色覚の世界をバーチャルに知覚し、通常色覚の相手とコミュニケーションを行って失敗が起こるという(続く)
(続き)ロールプレイを経験した参加者は、 相手が自己と異なる色覚であっても同じ色覚であっても誤答率に差はなかった。 そのようなロールプレイを他者が行っているのを見ていただけの参加者は相手が自己と異なる色覚である場合、相手が自己と同じ色覚である場合よりも有意に誤答率が高かった。
「……人は豚であり,豚は人である。ここにわれわれは擬豚主義に別れを告げ,唯豚論的世界へと漕ぎ出そう!」(「豚よ豚よに豚見ごろ」より抜粋)










 *サイパブ @psypub
*サイパブ @psypub am_i_jiik? @shokou5
am_i_jiik? @shokou5 yknst @akabuchiyk
yknst @akabuchiyk HORIO, Naomi @hn_Focusing
HORIO, Naomi @hn_Focusing 福島哲夫 @ftetsuo1
福島哲夫 @ftetsuo1 ぶんいち @FurumiF
ぶんいち @FurumiF

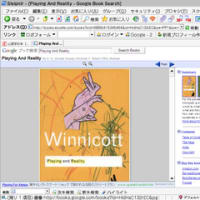


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます