日本経済新聞 電子版がレポートしていた。ホンダ車がコネクテッド・カーでアリババ・ネットワークを使うということになれば、急速に日本でもアリババ決済が採用される。
ホンダは中国の電子商取引大手アリババ集団と「コネクテッドカー(つながる車)」を開発する。アリババのインフラを活用し、スマートフォン(スマホ)のように車そのものに決済などの機能を持たせる。世界最大の自動車市場である中国では政府主導で次世代車の技術開発が進んでおり、ホンダは日本勢で先行して現地のネット大手と組み成長市場を開拓する。
コネクテッドカーは通信を介してネットなどに接続できる機能を備えた車で、乗ったままで決済をしたり駐車場の予約をしたりできる。コネクテッドと「オートノマス(自動運転)」「シェアリング(共同所有)」「エレクトリシティー(電動化)」の英語の頭文字「CASE(ケース)」は、自動車業界の勝ち残りを握る次世代技術とされている。
アリババ集団傘下の地図情報大手、高徳軟件(オートナビ)とコネクテッドカーのサービスを開発する。ホンダと高徳は2015年から多機能型カーナビゲーションシステムで協業。目的地までの正確な到着時間などを提供してきた。
コネクテッドカーは通信回線の高速化で従来より大容量データのやりとりができるようになる。ホンダは高徳の地図情報を基に、アリババが中国で展開するネット決済機能を備えた車を開発するとみられる。
アリババグループのネット決済サービス「支付宝(アリペイ)」は登録者数が5億人を超え、中国の生活インフラとして定着している。車載端末にアリペイの決済機能を付ければ、スマホを操作するように車の端末から駐車場やガソリンスタンドの支払いができるようになる。ホンダが中国で計画するカーシェア事業でも決済サービスなどで応用する可能性がある。
中国は世界の中でも電気自動車(EV)やシェアリングといった技術・サービスが先行して普及する。世界最大の自動車市場でもあり、中国で競合他社よりコスト面などで優れたサービスを確立できれば、最先端のコネクテッドカーを日本などの消費者も将来、利用できそうだ。
中国では自動運転などでもネット大手が台頭し、自動車大手との連携も相次ぐ。
検索最大手の百度(バイドゥ)は17年7月に自動運転技術開発プロジェクト「アポロ計画」を始動させた。中国政府と一体となって開発を進める人工知能(AI)を活用し、独ダイムラーや米フォード・モーター、米インテルなど国内外の1700社と開発を進める。
時価総額が50兆円を超える騰訊控股(テンセント)は米テスラに2000億円出資するほか、中国のEVスタートアップ企業などにも出資。馬化騰最高経営責任者(CEO)は「将来の自動車はコネクテッドカーの進化であり、我々のクラウド技術などと統合していく」と自動車事業の拡大に意欲を示す。
ネット販売で圧倒的な存在となったアリババも中国自動車大手にカーナビなど車載端末を音声で操作するシステムを提供する。米フォード・モーターにも同様の仕組みの提供を発表するなど、自動車各社との協業を広げている。
コネクテッドカーではAIや決済などでスマホと重複分野が増える。現地で圧倒的な事業基盤を持つネット大手と連携しなければ、中国の自動車市場で優位に立つことは難しい。日本車メーカーにとってもより深い関係の構築が課題になりそうだ。
しかしながらアリババ決済がホンダの採用で急速に普及することになり、日本の決済システムは厳しくなる。結局、日本、ITでアメリカ、中国に後れを取り始めたということ。自民党政府が長期政権に安座していたため、世界の動きから取り残されてしまった。
ここからリンク→ビッグバンの防犯カメラにリンク←ここまでリンク














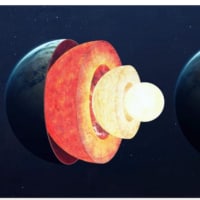

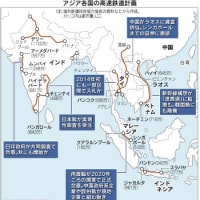
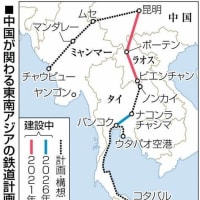

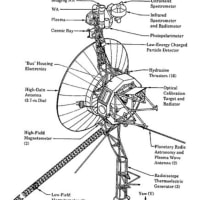
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます