日本経済新聞が表題の記事をだしていた。日本車が中国で販売するには、中国企業と合弁で製造した車であること、部品も中国で製造したものを使わなければならないなど、強い規制がかかっている。GDPが世界一になってもこの規制は存在するだろう。そして、GDPトップ3国に成長するインドも同様の規制を敷き始めている。アメリカもトランプ政権がセーフガード、輸入時の関税を導入しようとしていて、世界経済のあり方が変わるであろう。
また、自動車の種類も、従来のセダン中心からSUV中心に変化しているという。
以下、日経が報じている内容である。日本車各社が中国で一斉に電気自動車(EV)を投入する。マツダは19年をメドに中国大手と共同開発したEVを販売する。ホンダやトヨタ自動車、日産自動車も多目的スポーツ車(SUV)のEVを出す。中国で19年から始まる環境規制ではメーカーに一定数のEVなどの製造・販売を義務付ける。日本車各社は合弁相手との連携で規制に対応しながら、世界最大の中国のEV市場の攻略を急ぐ。
19年からの新エネルギー車(NEV、新エネ車)の環境規制では部品の現地調達の条件は示されていないが、中国製電池の採用を求められる可能性が高い。寧徳時代新能源科技(CATL)など高いシェアを持つ中国勢から調達しなければ競争力を維持できない状況だ。
中国の17年の新車販売台数は2887万台で前年比3%増にとどまったが、NEVは53%増の77万台と大きく伸びた。ナンバープレートの発給制限や購入補助金など、政府は需要と供給の両面でEVシフトを進める。
ホンダは合計で中国販売の2割を超える小型SUV「ヴェゼル」とその兄弟車をベースにしたEVを18年に発売する。広汽本田汽車(広東省)と東風本田汽車(湖北省)の両合弁会社が設計や生産のノウハウを持ち寄る。
トヨタは20年に自社開発のEVを販売する方針。広汽トヨタ(広東省)で生産予定の小型SUV「C―HR」と天津一汽トヨタ(天津市)で生産を予定する兄弟車をベースに開発する方向で検討している。日産は合弁を組む東風汽車集団や資本提携する仏ルノー、三菱自動車と連携し既存の小型SUVの車台を活用したEVを開発している。
中国の17年のSUVの販売台数は前年比13%増。日本車各社は得意の小型SUVをベースにしたEVで存在感を高めるという。















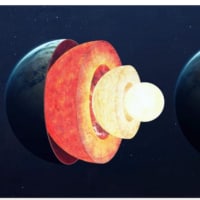

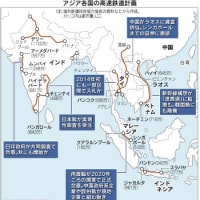
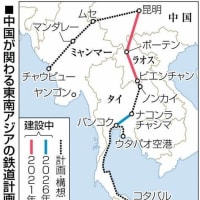

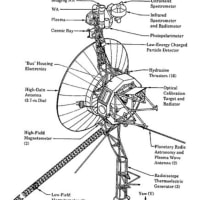
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます