ご訪問ありがとうございます→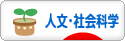 ←ポチっと押してください
←ポチっと押してください
その昔、報光寺最請遠寺で二代の相州に仕えて、引付(鎌倉・室町時代の裁判所)の役人を務める、青砥左衛門という者がいた。
ある時、夜になってから出仕した際、いつも火打袋に入れて持ち歩いていた銭から、十文を取り出したところ、取り出し損なって、滑川へ落としてしまった。青砥左衛門は非常に慌てて、人を走らせ、五十文で松明を十把買い求め、これを灯して、ついに十文の銭を探し出した。
後日、この話を聞いた人が、
「十文の銭を探すために、五十文で松明を買ったのでは、結局、大損ではないか」
と笑えば、青砥左衛門は眉をひそめて、
「そんなふうに、私の事を愚か者のように言うのは、世の中の経済が分かっておらず、民を潤そうという気持ちのない人が言うことだ。もし、落とした十文の銭を探そうとしなかったら、銭は滑川の底に沈んだまま、永久に出てこなかった。一方、私が松明を買わせた五十文の銭は、商人の利益になった。そう考えると、私も商人も何ら損をしていない上に、かれこれ六十文の銭が一文も失われることはなかったのだから、これが天下の利益にならない筈がない」
と言った。
その昔、報光寺最請遠寺で二代の相州に仕えて、引付(鎌倉・室町時代の裁判所)の役人を務める、青砥左衛門という者がいた。
ある時、夜になってから出仕した際、いつも火打袋に入れて持ち歩いていた銭から、十文を取り出したところ、取り出し損なって、滑川へ落としてしまった。青砥左衛門は非常に慌てて、人を走らせ、五十文で松明を十把買い求め、これを灯して、ついに十文の銭を探し出した。
後日、この話を聞いた人が、
「十文の銭を探すために、五十文で松明を買ったのでは、結局、大損ではないか」
と笑えば、青砥左衛門は眉をひそめて、
「そんなふうに、私の事を愚か者のように言うのは、世の中の経済が分かっておらず、民を潤そうという気持ちのない人が言うことだ。もし、落とした十文の銭を探そうとしなかったら、銭は滑川の底に沈んだまま、永久に出てこなかった。一方、私が松明を買わせた五十文の銭は、商人の利益になった。そう考えると、私も商人も何ら損をしていない上に、かれこれ六十文の銭が一文も失われることはなかったのだから、これが天下の利益にならない筈がない」
と言った。










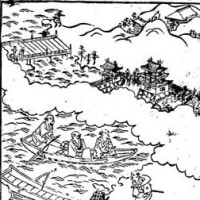
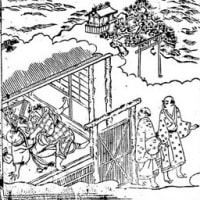
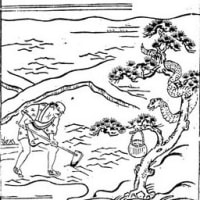

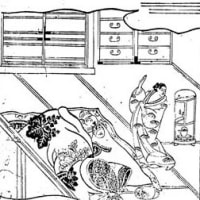


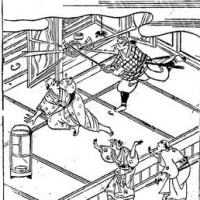
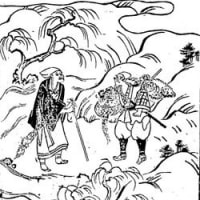
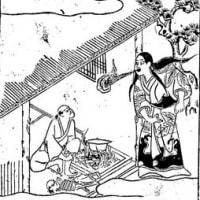
このコメントを、江戸時代の苗村丈伯に届けられないのが残念ですが。
たしかに、松明と労力を損しているという見方もありますね。
でも、松明には代金が支払われ、家来には給料が支払われているわけですから、損でも得でもありません。
また、(ちょっと大雑把に言うと)そもそも消費することによって経済は回ります。
だから、「損をしている」と見るか、「経済が回った」と見るかは、同じものを違う方向から見ているに過ぎないと思います。