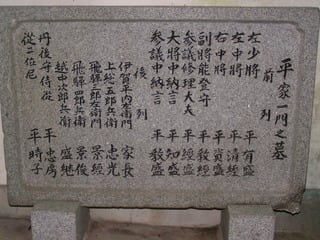ご訪問ありがとうございます→

←ポチっと押してください
これもまた、私が長い間疑問に思っていたことです。
まずは鉄砲の三段撃ちについて、「常識」となっている事実をおさらいしてみましょう。
『火縄銃は、一発発射してから次を発射するまで時間がかかり、その間に騎馬や歩兵が襲来したり、敵が矢の射程距離内まで攻め入って来たりするので、必ずしも効果的な兵器ではなかった。明智光秀はこの点を改良すべく、鉄砲隊を三列に配置し、先頭が撃ったら後ろに下がり、二列目・三列目が続いて射撃を行い、その間に最初の射手は次の発射準備をしてまた撃つ、ということの繰り返しで、間断なく射撃を行うよう工夫し、実際に長篠の戦において、武田軍を壊滅させた。この画期的な戦法は、戦国時代の戦闘を一変させた』
見事な戦法で、確かに火縄銃の弱点を克服しており、なるほど武田騎馬隊が大敗を喫したのも頷けます。
この戦術は映画やドラマでたびたび再現されていて、号令に従って、足軽が一糸乱れず射撃・交替を行っているのは、まるで一幅の絵画を観るようです。
ところが絵画といっても、有名な
「長篠合戦図屏風」(江戸時代)では、まさに私の疑問どおり鉄砲隊が三列になっていません。(一部、前後して並んでいる者もいますが、三列ではないし、全体の状況からして、たまたま重なったと見るべきでしょう)
が、これほど衝撃的な戦法を絵師が失念するはずはなく、少なくともこの屏風絵が描かれた当時には、三段撃ち戦法が「常識」ではなかったことを示しています。
・・・これだけでも、鉄砲の三段撃ちが否定される有力な証拠ですが。
では、私たちの「常識」となっている三段撃ちの要点をまとめてみましょう。
1.三千丁の鉄砲隊が三列になり、一列ずつ、号令に従って一糸乱れぬ一斉射撃を行った
2.三千名の足軽が次々と交替で、みな、射撃をした
3.飛び道具は、弓矢から鉄砲へと、その後の戦術が一変した
次に、私の疑問点です。
1.号令による一斉射撃
三千丁は誇張でしょうが、鉄砲の数を少なく見積もっても、一列につき数百名が並んでいたとすれば、1m間隔でも、端から端まで数百mもの長さになるわけで、ただでさえ鬨の声が響き渡る戦場で、指揮者の号令が末端まで届くとは思えません。たぶん、指揮者の近くにいて、号令の聞こえた者が撃ったのを合図に、聞こえなかった者も射撃を開始したと思われ、少なくとも、一糸乱れず、とはいかなかったでしょう。
また、受けて立つ武田軍にしても、最初の一発は不意打ちでどうしようもなかったでしょうし、織田軍が武田軍を十分引き付けていれば、武田軍はなす術なく犠牲者の山を築いたでしょうが、その後は、武田軍とて撃たれっぱなしのはずがなく、織田軍が種子島(鉄砲)を使用していると判ったところで、一斉突撃は断念して新手を講じるはずで、織田軍が斉射を続け、無謀にも突撃する武田軍がばたばたと倒れるという、映画さながらの図式は成立しないと思われます。
したがって、整然と射撃したのは最初の一発だけで、その後は3人一組が各自の判断で射撃したとみるのが妥当ですが、まあ、この方法でも、結果的に間断なく射撃を行って弾幕が張られ、武田軍は前進できなかったでしょう。
ただ、武田軍の敗戦は必然としても、なぜ武田軍が、壊滅的なまでの打撃を被ったのかという、別な疑問が残ります。
2.3人が交代して射撃を行った
最大見積もって三千人全員が同じ腕前なら、この方法でもいいでしょう。しかし射撃そのものの腕前とともに、迅速に次の射撃準備をする腕前も含めて、皆が同じ技量であったとは到底考えられず、足並みは乱れることになります。
また、仮に3人が交代で射撃するとなれば、撃ち終わった者は大急ぎで最前列から最後列へ移動し、弾込め作業をしつつ中間列へ、さらに再び最前列へ戻って撃ち、また・・・という繰り返しで、甲冑を身に着け鉄砲を抱えた重装備でこれをやっていたのでは、屈強な男でもへとへとになるでしょうし、そんな状態で射撃という精密作業を行うのは不可能です。
おまけに、三千人がひしめき合ってそうこうしているうちに、転倒したり、手元を誤ったりで、火薬に引火し自爆してしまう危険性だってあります。
こうした問題点は、事前に鉄砲隊が稽古を行えば、すぐ明らかになるはずです。
安全で効率的で疲労も少ないのは、3人の配置を固定しておき、3人の中で最も射撃に秀でた者が最前線で撃ち方だけに専念し、あとの2人には弾込めを担当してもらう方法です。
・・・と、私でも考えつく程度の戦法を、光秀ほどの智将が思い至らなかったとは、これまた考えられないことです。
3.戦術が一変した
これは考えられません。なぜなら、その後の局地戦は言うに及ばず、天下を決する25年後の関ヶ原においてでさえ、
「関ヶ原合戦図屏風」に見られるとおり、主力は歩兵と弓矢でした。もちろん、鉄砲や大砲も使用され(屏風絵の中には、勇猛果敢で知られる薩摩鉄砲隊が描かれており、これはさもありなん図です)、それなりの効果を挙げましたが、戦闘の主役ではなく、ましてや趨勢を決めるには至っていません。
・・・家康が、小早川秀秋の本陣へ向かって脅しのために撃ち込んだ鉄砲が、秀秋に出陣を決意させ、東軍を勝利へ導いた、と言う意味では、鉄砲は、紛れもなく趨勢を決めた主役ですが。
もし、以降「戦術が一変した」のであれば、関ヶ原は歩兵の乱戦ではなく、銃撃戦となっていたはずですが、規模が違うので単純比較はできないものの、「関ヶ原合戦図屏風」の中で鉄砲を構えている兵は、「長篠合戦図屏風」のそれよりも明らかに少なく、「関ヶ原」は「長篠」よりも戦術的に退行していることとなり、通説と「長篠合戦図屏風」および「関ヶ原合戦図屏風」の間には、埋めがたい矛盾が生じてしまいます。
さて、最近の研究では、私が「あり得ないだろう」と思っていた疑問に対し、まさに「あり得ない」という結論を下していますので、以下にはそれを要約しましょう。
まず三段撃ち戦法について、それが否定される根拠として、文献上、三段撃ちの記述が、ただ一点(およびそれから派生した各資料)を除いて存在しないこと、私が何となく合理的でないと思った戦法の細かい点が、現地踏査や鉄砲の射程距離・射撃間隔、人馬の進撃速度、鉄砲隊の配置などの科学的合理的な計算、さらには実演によって、困難ないし不可能と判明したものです。
ただ、ひとつ不可解だった武田軍壊滅の理由は、弾丸が機関銃のように連続して降り注いだからでも、武田軍が無謀に突撃したからでもなく、武田軍が、鉄砲の煙幕で戦場が覆い隠されるという、それまで経験したことのない状況に置かれ、味方の劣勢に気づかず、戦況判断を誤って、のこのこと織田鉄砲隊の眼前に兵を進めたからでした。
また、「長篠合戦図屏風」から「関ヶ原合戦図屏風」に至るまでの絵図および諸資料に見られるとおり、戦術や築城の様式が一変したという事実は、どこにも見当たりません。長篠の戦のあとでも、鉄砲の役割は決定的というほどではなく、刀と弓矢を戦の中心に据えるという戦法に基本的な変化はなかったことを、「関ヶ原合戦図屏風」は忠実に描いています。
以上まとめれば、三段撃ち戦法は存在せず、鉄砲が、戦術はもとより築城形式まで変えてしまった事実はない、という結論です。
よって、鉄砲伝来の年号「以後、予算(1543)は鉄砲に」という語呂合わせも、予算みなを鉄砲につぎ込むというほどでもなかったというわけです。
そうすると、なぜ根拠薄弱な三段撃ちが、かくも広まったのか、という疑問だけが残ります。
これは調べていくうちに、またもやそうか、という事実に行き当たります。
長篠の戦を記録した、最も信頼できる資料としては、17世紀に、信長の家臣であり、実際に長篠の戦にも参加したであろう太田牛一が著した、「信長公記」という書物があるのですが、もちろんこの中に、三段撃ちの記述は全くありません。
ところがそのあとに、同じく信長の家臣である小瀬甫庵という人が、「信長公記」を参考にして「信長記」(注:混同を防ぐため、こちらは「甫庵信長記」と呼ばれる)を著しているのですが、この中に「だけ」三段撃ちが登場します。
そして、前者「信長公記」が事実の記録に徹した軍記物であり、非常に信憑性の高い第一級の資料であるのに対して、後者「甫庵信長記」は脚色を多く加えたり、甫庵自身の思想を散りばめたり、ひとつの合戦をまるまる創作するなど、記録というより文学作品として、娯楽性の高い物語になっています。
しかし、正確な資料と、読んで面白い物語では、どちらが人口に膾炙するかというと、まあ、残念ながら後者であり、ちょうど史実の赤穂浪士ではなく歌舞伎の忠臣蔵が人々の固定観念となってしまったように、長篠の戦における三段撃ちが定説として伝えられたのは、止めようがなかったのかもしれません。
それでも、現在私たちが、忠臣蔵はお芝居であり、史実は少し違うのだということを知識として持っているように、長篠の戦も、物語は物語として無邪気に楽しむ傍ら、史実はこうであるという、正しい見解を世に知らしめる機会はいくらでもあったはずですが、現在に至るまで、大衆はともかく、研究者から文部科学省までもが三段撃ちを支持してきたのには、「またもやそうか」という経緯があります。
明治時代、日本が軍備の近代化を進めていた頃、軍は、日本の合戦史をまとめ、士官の教育に利用していました。それ自体、別に悪くも不思議でもないのですが、その中で長篠の戦に関する部分では、こともあろうに正確な資料である「信長公記」を無視し、物語の「甫庵信長記」にある三段撃ちを史実として採用しており、この点は悪いし不思議です。
資料をきちんと調べれば、三段撃ちが史実ではないことぐらい明白なのですが、それでも三段撃ちを史実として採用したのには、そうするべき理由があったからに違いありません。
その理由は推測するしかありませんが、おそらく軍としては、三段撃ちという、それまでの常識を覆すような発想で敵に勝利した勇ましい話は、士官の士気を鼓舞するのにうってつけだったのでしょうし、また、西洋の軍備を取り入れて近代化を進めていた時代に、やはり西洋の兵器を効果的に使って戦術を一変させた三段撃ちは、時代に迎合し、富国強兵政策を強力に援護するものだったのでしょう。
そして、その「間違い」は訂正されることなく、現在も教科書に堂々と記載されています。もうそろそろ訂正されてもいい頃なのに、未だになされていないのは、文部科学省の怠慢・・・旧弊に固執する体質・・・に他なりません。
歴史的事実が、政治によって歪曲された例は、古今東西、枚挙に暇がありません。
歪曲するには、歪曲しなければならない理由があるからですが、その理由は少なくとも、歴史を学び、これから社会へ羽ばたく学生にとって有益な理由ではありえません。
もっとも、受験のためだけに歴史を学ぶ学生にとっては、三段撃ちが史実であろうとなかろうと、どちらでもいいことで、入試を実施する側も、それが事実であろうとなかろうと、教えたことをどれだけ忠実に覚えているかだけが重要ですが、それは、受験勉強が全く意味のない知識の詰め込み(しかも間違った知識)であることを、逆説的に証明してしまい、歴史「を」学ぶのではなく、歴史「に」学ぶという態度を、全く育まなくなってしまいます。
歴史に学ばなかった者がどういう失敗をしてきたかは、言うまでもありません。
・・・ということさえも学ばないとすれば、もはや言うべき言葉もありませんが。