▲赤くライトアップされた善光寺本堂正面
オリンピックの「平和を願う精神」を後世に遺してゆくため、長野オリンピック開催5周年をきっかけに誕生した長野灯明まつり、今年は第12回を迎えて新たなステージへ。
今回のテーマは「共創」。世界の平和をみんなで考え創っていくというもの。
2月7日(土)~15日(日)開催中。
お出かけになっては如何ですか。
▼5色のライトアップで幻想的な雰囲気に











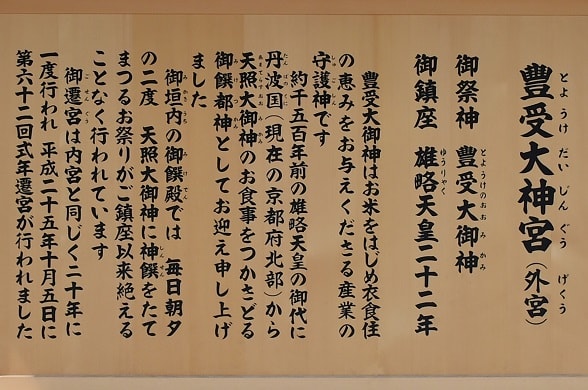




















▲正に豪華絢爛な雛段
2月4日長野市内での私的な会合の後、須坂市の須坂アートパーク内『世界の民族人形博物館』で開催されている『三十段飾り千体の雛祭り』を見に足を延ばした。
中央の大きなホールいっぱいに造られた高さ6m、30段の棚、そこに飾られた千体もの雛人形は、正に絢爛豪華、その迫力に圧倒される。
写真撮影OKということで、来場者はみんな雛段をバックに記念写真を撮っている。雛段だけを撮ろうとしても中々シャッターチャンスが来ないほどだ。
博物館を出ると、隣の版画美術館と歴史的建物園でも雛が飾られている。全会場で、6,000体の雛人形が飾られているとのこと。実に驚きの雛祭りを見た。
▼高さ6m、30段に飾られた千体の雛人形とハート形に配置されたぼんぼり

▼歴史的建物園の民家に飾られた雛人形

▲大きな山が割れていくような大沢崩れ
12月16日富士宮市から朝霧高原を通り中央自動車道に入った。
今の時期には珍しく、好天に恵まれ車窓からは美しい富士山を眺めることができたのだが、大沢崩れが不気味なほど大きくハッキリと見えた。
毎日、数百トンもの土石が崩れ落ち、大きな割目を更に少しづつ大きくしているとのこと・・・。このまま浸食が進むと、冨士山は二つに割れて中から噴火の溶岩が噴出するのではないかと心配になる。
砂防事業が継続されているとのことですが、“日本一の富士山”をいつまでも美しく残るよう頑張ってもらいたいものです。
▼富士山はどこから見ても美しい“日本一の山” (朝霧高原から)

▲羽田発ANA885が富山空港に到着着陸
時速数百kmで正面を横切る飛行機を、時速100kmを超す車から撮る、しかも高速道路上の特定の場所を通過する一瞬となると、そのシャッターチャンスはめったには無い。
先日、富山から北陸道を上越に向っていた際、富山インター手前の神通川を渡るあたりで正面左から富山空港の降りるボーイング76Pの機影をバッチリと撮ることができた。しかも、『航空機通過 わき見注意』の看板も収まった。立山連邦も背景となっている。11月18日13時54分05秒、我ながら“驚き!”のシャッターチャンスとなった。
▲いにしえ人の憧れの月「姨捨山にかかる月」
『更級や姨捨山の高嶺より嵐をわけていずる月影』正三位家隆卿
平安の時代から名月の里と知られた信州麻績の地、姨捨山から上る月はこの地からのみ見ることができる。
姨捨山や月と共に歌われる『更級』の枕詞(まくらことば)は、ここ麻績の地で生まれたとも云われている。
いにしえの都人たちが憧れた「姨捨山にかかる美しい月」、今宵はしっかりと見ることができた。
▲荻町城址展望台から集落を望む
10月7日、岐阜県大野郡白川村荻町集落を訪れました。
ここは白山連峰に囲まれた南北に細長い集落で、合掌造りの建物が約60棟建っており、1995年12月9日にユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録されています。
北側にある荻町城址展望台からは集落が一望でき、全ての合掌造り家屋が強風や冬場の融雪を考えて南北に並んで建てられている光景が見えます。
紅葉は未だでしたが、多くの観光客で賑わっていました。世界遺産ということなのか外国からの観光客が多い多いのにも驚きました。
▼改修中の家屋(荻町集落内) 一旦曳いて、基礎工事をしている

▼縁側でそばを食べる家族(野外博物館「合掌造り民家園」)

▼美しい切妻屋根(野外博物館「合掌造り民家園」)

▼火の見やぐら(野外博物館「合掌造り民家園」)

▲重文指定の大日如来座像
9月23日、お隣筑北村坂北の岩殿寺塔頭(たっちゅう)「大日堂」の秋祭りが行われました。
このお堂に安置されている本尊大日如来座像は国の重要文化財に指定されており、お大日様と呼ばれ親しまれています。普段は本尊の拝観はできませんが、この秋まつりには優しく微笑む“お大日様”が開帳され、大勢の人々が参拝をします。
大日如来は亡き父の干支守護神だったことから、この大日堂のお祭りには父とよくお参りをしました。
山間に迫力ある音を響かせる呼び物の奉納花火を観ながら、父のことを思い出したお祭りとなりました。
▼呼び物の打上げ花火、山間に迫力ある音を響かせていました

▲ 広い砂浜を借り切っての地引網漁
夏は山? 海? 海の無い信州人にとっては、やはり海が魅力的だ。
7月6日、地域ぐるみで村おこし活動をしている村内の団体「大峠を世に出す会」の研修会にお誘を受け新潟県の柿崎海岸を訪れ、地引き網漁を体験させて頂いた。
夏の海水浴シーズンにはまだ早いこともあり、砂浜には我々一行だけ。広い砂浜を借り切ったような贅沢気分で地引き網漁へ。
400mほどの沖から引くのだが、網が砂浜に引き寄せられるまではエンジンがロープを巻き取ってくれる。網が砂浜に現れてから、全員が二手に分かれて網を引く。
引き寄せられると魚影が見えてくる。『いた! いた! 大きな鯛だ!』歓声が上がる。
鯛、ホウボウ、イサキ、イワシ、ふぐ、など大漁とは言えないが、地引き網を楽しませて頂いた。
▼3kgを超す大きな鯛 
▼ホウボウ 海底を方々(ほうぼう)歩き回ることから、この名がついたとか。

▼新鮮なお刺身 信州人にとっては最高のご馳走だ

▲修理を終えてお帰りになった仁王様
4月6日、福満寺の金剛力士像(阿吽二体の仁王像;村指定有形文化財)が、解体修復作業を終えて1年ぶりにお帰りになりました。
修復には千曲市の長谷川玄隆仏師(智照院住職)と長男の高隆仏師(同寺副住職)が当たられ、力強く躍動感のある仁王像のお姿になりました。
解体修復作業では、中にあった木片から過去の修復経過や、室町時代の作と言われていた2体が各所の特徴から室町時代の作の可能性が強いとのことなどが判明しました。
5月3日には、春の例祭と併せて開眼法要が予定されています。
▼修復前の仁王様とはすっかり変った阿吽二体の仁王像
仁王門の右に立つ阿形像

仁王門の左に立つ吽形像

▲乙女滝、ここはマイナスイオン値(1cc中の数)が20000とのこと
2月20日、奥蓼科温泉郷にある横谷渓谷を訪ねた。
まだ多くの雪が残り、風は冷たい。含鉄泉の横谷温泉でしっかりと温まり、その勢いで雪の渓谷歩道を歩いた。
横谷渓谷は長野県を代表するパワースポットの一つで、冬でも県内外から多くの人が訪れるとのこと、細い雪道で何人にも行きあう。
人気の乙女滝は見事な氷と水しぶきで美しい姿を見せている。川まで下りると岩肌を覆う大きな氷柱が屏風のように広がる。流れる水も迫力があり、吸い込まれるような気持ちになる。
ゆったりと露天風呂に入り、美しい横谷渓谷を歩く、改めて訪れたい思いがした。
▼岩肌を覆う氷柱

▼吸い込まれるような川の流れ













 お帰りにはこちらも
お帰りにはこちらも


 お帰りにはこちらも
お帰りにはこちらも