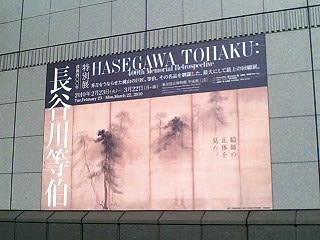三の丸尚蔵館で開催中の
「大正・昭和初期の美術工芸 花ひらく個性、作家の時代」を拝見した。
平成5年11月に開館した三の丸尚蔵館。
若冲公開時は本当に日参してお世話になったが(笑)本展で50回目を迎えたそうだ。
今回の展覧会は3期に分かれているが、
その中でも、昭和の大礼に岩崎家が献上した5双の屏風のうちの3双が展示される。
一期は橋本関雪作「進馬図」。
白・黒・赤の妙
馬の鬣や筋肉の描写
静と動
本当に素晴らしかった!
「腕が邪魔する」と豪語していたそうで「さすが!」でした。
「大正・昭和初期の美術工芸 花ひらく個性、作家の時代」を拝見した。
平成5年11月に開館した三の丸尚蔵館。
若冲公開時は本当に日参してお世話になったが(笑)本展で50回目を迎えたそうだ。
今回の展覧会は3期に分かれているが、
その中でも、昭和の大礼に岩崎家が献上した5双の屏風のうちの3双が展示される。
一期は橋本関雪作「進馬図」。
白・黒・赤の妙
馬の鬣や筋肉の描写
静と動
本当に素晴らしかった!
「腕が邪魔する」と豪語していたそうで「さすが!」でした。