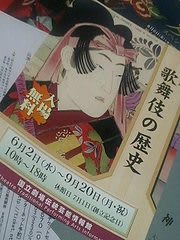屏風という漢字は「風をさえぎる」という意味があるそうで、
中国で風よけとして使われていた屏風は、日本に7~8世紀頃伝わったらしい。
その屏風の変遷をたどる展覧会が出光美術館で開催中である。
紙製の蝶番が考案され、連続する画面として日本独特の様式になったのは室町の頃。
それまでは、扇(せん)という一画面ずつが布で縁取られて革紐などでつなげられていたみたい。
屏風のしくみがわかる模型なども展示されていて、
より大画面で装飾性の高い表現ができる創意工夫をした日本人ってやはり凄いと思った。
以前にも心奪われた能阿弥の「四季花鳥図屏風」でまた動けなくなった。
狩野元信の「西湖図屏風」も好き!
岩佐又兵衛の三十六歌仙等も面白かったが、
今回特に拝見したかったのが、桃山時代の「祇園祭礼図屏風」だ。
ちょうど、「京都祇園祭の染織美術」という本を読んでいて
その中に、風俗画の中に観る山鉾の変遷みたいな話がのっていたので
私も屏風の中の山鉾の懸装品をチェックしたり楽しませてもらった。
風俗画の屏風は当時の人々の暮らしぶりや流行り物などが
詳細に描かれていてとても興味深い。
「阿国歌舞伎図屏風」もあったが、
特に惹かれたのは、小ぶりの「歌舞伎・花鳥図屏風」。
「遊女歌舞伎」と「若衆歌舞伎」の様子が描かれていて、
コンパクトな屏風からも遊女や若衆の色香が漂ってくるようであった。
後期の大雅や蕪村も拝見したいが、ちょっと日程的に無理そう…
中国で風よけとして使われていた屏風は、日本に7~8世紀頃伝わったらしい。
その屏風の変遷をたどる展覧会が出光美術館で開催中である。
紙製の蝶番が考案され、連続する画面として日本独特の様式になったのは室町の頃。
それまでは、扇(せん)という一画面ずつが布で縁取られて革紐などでつなげられていたみたい。
屏風のしくみがわかる模型なども展示されていて、
より大画面で装飾性の高い表現ができる創意工夫をした日本人ってやはり凄いと思った。
以前にも心奪われた能阿弥の「四季花鳥図屏風」でまた動けなくなった。
狩野元信の「西湖図屏風」も好き!
岩佐又兵衛の三十六歌仙等も面白かったが、
今回特に拝見したかったのが、桃山時代の「祇園祭礼図屏風」だ。
ちょうど、「京都祇園祭の染織美術」という本を読んでいて
その中に、風俗画の中に観る山鉾の変遷みたいな話がのっていたので
私も屏風の中の山鉾の懸装品をチェックしたり楽しませてもらった。
風俗画の屏風は当時の人々の暮らしぶりや流行り物などが
詳細に描かれていてとても興味深い。
「阿国歌舞伎図屏風」もあったが、
特に惹かれたのは、小ぶりの「歌舞伎・花鳥図屏風」。
「遊女歌舞伎」と「若衆歌舞伎」の様子が描かれていて、
コンパクトな屏風からも遊女や若衆の色香が漂ってくるようであった。
後期の大雅や蕪村も拝見したいが、ちょっと日程的に無理そう…