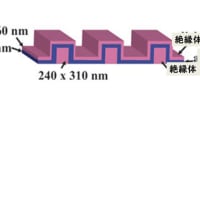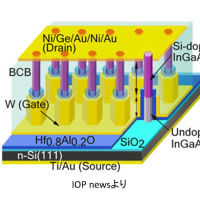建築作業もナノテクノロジーに対する期待は大きい。第一に新しい材料の開発である。強靭性、耐久性がナノテクノロジーによって改善される可能性がある。第二にコーティングによって新しい機能を持たせることが出来る。水を弾くコーティング材料で汚染を防止することが出来ることについて説明した(3/3参照)。赤外線や熱線を反射するコーティングも模索されている。
セメントなど多くの建築材料は通常微結晶の集まりである。微結晶間の結合があまり強くない。また、結晶には転位と呼ばれる欠陥が含まれていて、これらが強度を下げる原因となっている。原子間の結合が強いカーボンナノチューブ(9/8,10/31参照)を混入して強化することが試みられている。カーボンナノチューブが微結晶と結合し互いに動きにくくする可能性がある。これまで多くの研究がなされているが、カーボンナノチューブは水にとってにくく、セメントの強化にはあまり適しているとはいえない。最近スペインの研究グループは"セメントナノチューブが存在するだろうか"という論文を発表した。彼らは、水酸化カルシウムとケイ酸カルシウム水和物をベースとするナノチューブの作成に成功し、これを用いて強化セメントの作成を試みた。現在のところ、カーボンナノチューブ強化セメントと同程度の結果しか得られていないが、新しいブレークスルーが見つけ出されさらなる発展が期待出来る。
www.nanowerk.com/spotlight/spotid=17138.php
ナノ粒子が建築材料に用いられ始めると、ナノ粒子が起こすかもしれない公害に懸念が生じる。ライス大学の研究グループが"建築産業におけるナノ材料"と題する総括的な論文を発表しているが、その中に示されている下図に、人間がナノ粒子の影響を受けるすべての可能性が示されている。技術者には公害を発しない製品を提供する義務がある。
http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=17138.php