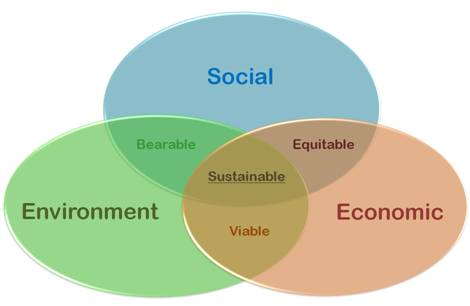持続可能な発展になくてはならないものがクリーンウォーターである。地球上に住む人々の25%が良質の水を十分得ることができないと言われている。さらに人工の増加に伴いクリーンウォーターに対する要望が急激に増加するものと見なされている。地球上の98%の水が塩分を含むことから、海水の淡水化(desalination)技術の開発が期待されている。
水中の不純物を取り除くのに通常用いられるのは、逆浸透膜法(reverse osmosis)である。不純物の濃度が異なる2種類の水を浸透膜で隔てると、水は濃度の高い方から低い方へ移動し、全体として不純物濃度が一定となる。これに対して、一方に圧力を加えると水が不純物濃度の低い方から高い方へ流れる。これによって海水をより純粋にすることが出来る。
逆浸透膜法による海水の淡水化のプラントは、スペインやイスラエルなど水が不足しがちな多くの国々にすでに設置されている。圧力を加えるのにエネルギーを必要とする。必要とするエネルギーは浸透膜の透過度によって異なるが、現在のところ理論値、1立方メーカーあたり1.8kWh)の3または4倍程度(我々が払っている立方メートル当たりの水道代金とほぼ同じ)に達している。しかしながら、浸透膜を準備することおよびその汚れを取り除くのに必要なコストがエネルギーコストよりはるかに大きいのが現状である。
浸透膜には高分子材料で作成したものが用いられている。これに対してナノ材料を用いたより高性能の浸透膜の開発が試みられている。例えば浸透膜に下図のようにカーボンナノチューブ(HP2.2A2)を並べたものを用いることが提案され、多くの実験やコンピュータシミュレーションがなされている。孔の直径が一定であること、透過度が高分子材料で作成した浸透膜の約1000倍に達するなど、優れた性質を持っている。透過度が大きいのはカーボンナノチューブの疎水性(ブログ12/17/2011)による。ナトリウムイオンには数個の水分子が付着している(水和現象と呼ばれている)ので、1 nm以下のカーボンナノチューブを用いた浸透膜では、ナトリウムイオンなどが真水の方に漏れることが防げるものと期待されている。最近、韓国の研究グループなどは(例えばY. Baek et al 2014 J Membrane Sci 460, 171) 、カーボンナノチューブと高分子を組み合わせて汚れがつかない浸透膜の作成に成功している。現在のところこのような浸透膜は高価で面積が大きいものを得ることが困難であるが、今後の技術開発に期待するところが大きい。
参考文献
M. Elimelech and W. P. Phillip 2011 Science 333, 712
T. Humplik et al 2011 Nanotechnology 22, 292001