「岩泉尋常高等小學校」(旧下閉伊郡岩泉村)
(現 岩泉町立岩泉小学校)

岩泉尋常高等小学校の創立は明治8年(1877年)8月で、雲泉寺の一室を校舎として始まりました。その後明治42年(1909年)に校舎を現在地に新築移転しました。
この写真は新築されたばかりの校舎の冬景色で、正面玄関に国旗が飾っていますので、祝日の撮影かと思われます。宇霊羅山の山裾に石垣を組んで整えた日当たりと見晴らしの良い校地に、平屋の建物ですが、両翼に講堂らしき大きな建物を備えた高い屋根の大変立派な校舎です。
「岩泉尋常高等小學校」(旧下閉伊郡岩泉村)
(現 岩泉町立岩泉小学校)

岩泉尋常高等小学校の創立は明治8年(1877年)8月で、雲泉寺の一室を校舎として始まりました。その後明治42年(1909年)に校舎を現在地に新築移転しました。
この写真は新築されたばかりの校舎の冬景色で、正面玄関に国旗が飾っていますので、祝日の撮影かと思われます。宇霊羅山の山裾に石垣を組んで整えた日当たりと見晴らしの良い校地に、平屋の建物ですが、両翼に講堂らしき大きな建物を備えた高い屋根の大変立派な校舎です。
「豊間根尋常高等小學校」(下閉伊郡豊間根村)
(現 山田町立豊間根小学校)

豊間根尋常高等小学校の創立は明治8年(1877年)6月で、同地区にある宝珠院の一室を校舎として始まりました。その後明治10年(1879年)に豊間根村新田(現山田町豊間根)に校舎新築移転し、さらに明治44年に高等科移設に伴い現在地に校舎を移転新築しています。
この写真はその落成記念に撮影されたものと思われます。平屋の建物ですが、とても高い屋根と広い校庭を持つ立派な校舎です。当時豊間根村だけでなく地方の町村が学校教育に力を注いでいたことが伺い知れます。また写真に写る児童の数は現在よりも多いようです。
「山田尋常高等小學校」 (下閉伊郡山田町)
(現 山田町立山田南小学校・同山田北小学校の前身)

山田尋常高等小学校とネット検索すれば、岩手県山田町だけでなく、全国各地の山田小学校が続々と出てきます。もしかすると日本で一番多い小学校名かもしれません。しかし残念ながら肝心の三陸の山田尋常高等小学校の沿革その他詳しいことは、山田尋常高等小学校が戦後山田小学校となり、その後山田南小学校と山田北小学校に分かれたこともあり、また現在山田南小学校のホームページが更新中ということで詳しいことを調べることがませんでしたが、資料が集まり次第補足追加します。
左側の2階建ての立派な校舎、右の講堂と思われる大屋根の建物の前に大勢の児童職員が整列しています。岩手県立山田高校の沿革などを見ると、昔は現在山田町役場が立っている地にこの山田尋常高等小学校の校舎があったようで、この写真は同地で撮影されたものと思われます。
「江繋尋常小學校」(下閉伊郡小国村)
(現 宮古市立江繋小学校)

江繋尋常小学校の沿革その他詳しいことは、残念ながら調べがつきませんでしたが、資料が集まり次第補足追加します。
なお同校の事を調べていたら、女啄木とも呼ばれた岩手の女流歌人西塔幸子が教師として同校に在職していたことが分かりました。だが残念のことに同女史は同校在任中の昭和11年(1936年)に病を得て急逝されています。女史は、明治33年に現在の岩手県矢巾町に生まれ、長じて小学校教員となり北三陸の各地に足跡を残しながら歌を詠んでいます。最後の赴任地となった江繋には記念館が建てられています。
「刈屋尋常高等小學校」(下閉伊郡刈屋村)
(現 宮古市立刈屋小学校)

刈屋尋常高等小学校の創立は明治8年(1877年)6月1日で、旧新里村管内では最初に、現宮古市内でも6番目と比較的早くに開校しています。最初は他校と同じく民家かお寺の仮住まいだったでしょうが、明治40年代までには写真のとおり立派な校舎となっていたようです。その他詳しいことは分かりませんが、資料が集まり次第補足追加します。
校庭に植えられている樹木は、桐です。校舎建築を記念して植えられたものですが、桐は成長が早く家具材として人気が高い高級木材なので、ゆくゆくは学校の資産となるように選ばれたようです。もともと南部桐の名のとおり岩手県内各地には多く見られ、女の子が生まれると桐を植え、結婚する際にはその桐で箪笥を作り嫁入り道具にするという風習もあったように聞いています。今でも刈屋地区の屋敷周りによく植えられており、初夏に薄紫色の花を咲かせています。(実は写真帳のこの写真のタイトルは「刈屋尋常高等小学校及建築記念植立の桐」と桐がもう一つの主役となっています)
なお写真撮影と同時期にこの校舎で学んでいた生徒に大正・昭和に「籠の鳥」を始めとする数々の楽曲を作曲し、街頭演歌師としても活躍した「鳥取春陽」がいます。鳥取春陽は明治33年(1900年)刈屋に生まれ、7才で刈屋尋常小学校に入学し、13才で高等小学校に進んでいますので、この写真撮影のときちょうど校舎の中で授業中だったかもしれません。
「津軽石尋常高等小學校」(下閉伊郡津軽石村)
(現 宮古市立津軽石小学校)

津軽石尋常高等小学校は、明治9年(1876年)6月19日に新町の民家を改装して開校し、明治11年(1878年)に校舎を新築移転しています。写真撮影日は不明ですが、本写真帳刊行前の明治44年前後と思われます。また場所についても定かではありませんが、写真を見るに現在地と思われます。
さて写真には石垣を組んで土盛りした校地に立派な校舎が立ち、その周りを木柵が囲み、その前の校庭に児童職員が整列しています。児童は何人いるのでしょうか?100人近い子供達が写っています。現在は少子高齢化の進行で生徒数が激減していますが、当時は各町村とも学校教育に力を入れて立派な校舎を造り、学校は大勢の子供達の元気な声があふれていました。
「千徳尋常高等小學校」(下閉伊郡千徳村)
(現 宮古市立千徳小学校)

千徳尋常高等小学校は、明治6年(1873年)11月に、民家を改装して開校し、明治15年(1882年)に校舎を新築移転しました。場所は定かではありませんが、写真を見るに昭和59年(1984年)に近内小学校と統合移転前に位置した現在千徳地区体育館他がある場所と思われます。
さて写真はいつ頃撮影されたものでしょうか?正面玄関に国旗を飾り、全校生徒と思われる児童と先生達が整列しています。新築落成時では古過ぎるので、私は写真集掲載用として、他の学校と同様に明治45年(1912年)頃に撮影したものと推測します。写真中央を横切る線は、ルーペで拡大して見ると傷ではなく、電線と思われます。なお先のVOL3.7に記述したとおり、宮古に初めて電燈が灯ったのがこの写真集が刊行された明治45年のことです。
なお千徳村は、明治22年(1889年)の町村制の実施によりに、旧千徳村・花原市村・根市村の3カ村が合併して新制の千徳村(219戸、1,342人)として発足しました。その後昭和16年(1941年)に宮古町と近隣の3村(千徳村、山口村、磯鶏村)との合併により宮古市となり現在に至っています。
「鍬ケ崎尋常高等小學校」(下閉伊郡鍬ケ崎町)
(現 宮古市立鍬ケ崎小学校)

鍬ケ崎町は、明治22年(1889年)の町村制の実施によりに浦鍬ヶ崎村が単独で町制(3635人)を敷き、その後大正13年(1924年)に宮古町と合併して新制の宮古町(旧宮古町9193人、旧鍬ケ崎町8387人)となり、その後昭和16年(1941年)に宮古町(16,023人)は、近隣の3村(山口村2,432人、千徳村1,646人、磯鶏村2,704人)との合併により宮古市となり現在に至っています。
鍬ケ崎小学校は明治8年(年)に当時鍬ケ崎3丁目にあった東屋長屋を校舎として開校し、折しも町制を施行した明治22年に現在の校地に移転新築しています。(本写真は、この写真帖掲載の為に撮影したものではなく、正面校舎棟上に祭壇が設けてあることからこの校舎落成式の際の撮影? あるいは先に右の校舎を建てその後の生徒増により増築?と推測)
さて鍬ケ崎小学校と本写真帖作成の緒となった「明治の三陸大津波」とは因縁浅からぬものがあります。明治の三陸大津波は、明治29年6月15日の夜8時7分に鍬ケ崎の町を襲い、鍬ケ崎町だけで死者137名、家屋流失倒壊547棟と甚大な被害を与えました。この時の津波は今回の津波とは異なり、震度2と揺れは小さく、誰もが大津波の襲来を予期しないものでした。しかしながら此の日は旧の端午の節句の日に当たり、偶々同時刻に鍬ケ崎小学校で「幻燈会」が開催(正面校舎右側に片屋根が見えるのが会場の講堂か?)されて、大勢の児童と家族が参集していて、為に幸い大津波(鍬ケ崎で最大波高8.5m)から難を逃れることができたということです。(此の事を伝える碑が学校近くの蛸の浜町の心公院境内に建立されています)
「宮古尋常高等小學校」(下閉伊郡宮古町)
(現宮古市立宮古小学校)

私自身が40数年前に卒業した小学校ですが、この写真を最初に見たときはどこかわかりませんでした。写真は現在のつちや本舗さんあたりから東に向いて撮影されています。(VOL7掲載の下写真の逆方向、校舎は右手山際に隠れた処)
宮古小学校の校地は、現在も写真当時と同じ場所に在りますが、狭かった敷地は大きく拡がり手前の田圃は校庭となっています。勿論校舎も下記のとおり何度も建て替えられて、
明治6年(1873年)に写真左奥の山手にある常安寺一室を仮教室として創立し(生徒数20名)、翌明治7年に現校地に移転しています。写真の校舎は明治28年(1895年)に落成(14教室、建坪409坪)したものです。その後生徒の増加に伴い、講堂兼雨天体操場新築(150坪、大正6年)、校地の拡張と校舎の増設(大正11年)、同新校舎火災消失・再築(昭和24~26年)、旧体育館竣工(482坪、昭和35年)、現東校舎新築(昭和41年)、現西校舎新築(昭和53年)、現体育館竣工(平成15年)と続いて現在に至っています。
写真の明治の校舎は昭和24年の火災で焼け残り、私はこの校舎で学んでいます。薄暗くて長い廊下、踏板がすり減った階段、黒光りする手摺等がおぼろげに思い出されます。下の写真は私の在校当時ものです。中央の玄関は余り記憶にないのですが、明治の本写真と同じ形状なことがわかります。実は講堂も入学時は残っていて、その後旧体育館ができ、次にプールと新校舎建設のためにこの校舎が取り壊しになり、一時体育館を薄いベニヤ板で間仕切りして授業をしていました。

現在宮古小学校の児童数は260名前後ですが、校歌に謳われているように20名から始まり、明治16年には464名、写真の当時は既に高等科を併設(明治35年)していますので1000名前後、昭和10年には一時愛宕小の併置もあり2344名、戦後になると昭和22年は1863名、昭和33年には2027名が在校しています。私の時はベビーブームが過ぎた後でしたが、それでも1学級50名前後で1学年6学級で全校で入学時で1800名、卒業時でも1500名以上はいた記憶があります。それが今では1学年分もいないのですから……。
なお宮古小学校のことについては、「まぼろし小学校~1960年代の宮古小学校~」というHPを見つけました。
http://www.geocities.jp/jinysd02/syougakkou.html
どうやら私の2.3学年下のようですが、当時のエピソードが事細かく楽しく綴られています。
「岩手県立水産學校」(下閉伊郡宮古町)

当時の三陸沿岸地域には、小学校を卒業した後の上級学校といえば、本稿の「岩手県立水産学校」(現在の岩手県立宮古水産高校)と、次稿の「遠野中学校(現在の岩手県立遠野高校)の2校しかなかったので、漁業関係の子弟にかぎらず地域の秀才が競って入学し、鈴木善幸元首相・熊谷義雄元衆議院議員(普代村出身)などの人材を輩出しています。(私の祖父は8期生でした)
因みに内陸には盛岡中学校(同盛岡一高)や一関中学校(同一関一高)、福岡中学校(福岡高校)などの中学校があり、宮古から盛岡中学校へ入る生徒も大勢いたようです。
さて岩手県立水産学校ですが、明治28年(1895年)に水産補習学校として設立、その後下閉伊郡立水産学校を経て明治34年(1901年)に県立移管されています。校舎は現在宮古市磯鶏地区にありますが、写真の当時は藤原地区(現在の藤原小学校)にあり白い外壁が一際目立つ存在でした(当時の上級学校は、盛岡中学や遠野中学もなぜか校舎は白く塗られています)。《VOL6.明治の宮古の街並み其の1 参照》
明治末期の三陸沿岸地域においては学校の重要度は現代の比ではありませんでした。この写真が本写真帖には各郡役所の次の頁に掲載されていることからも推し量れます。

明治の鍬ケ崎湊(現宮古市鍬ケ崎町)其の3
写真は、鍬ケ崎の裏山から湊を見下ろしたものです。鍬ケ崎湊は、北に突き出して大きく宮古湾を囲う重茂半島と、小さく南に出ている竜神崎に囲まれた波静かな天然の良港であり、江戸の昔から東日本太平洋沿岸有数の港であった訳が分かります。
さてご覧のとおり停泊している3隻の船は帆柱の残る2本マストの機帆船です。小さな船は艀や漁船でしょうか。前回掲載した三陸汽船の東北丸やこの後に紹介する釜石港に停泊する汽船と較べると些か旧式の船ばかりで、いかにも明治の湊らしい風情があります。当たり前ですが重茂半島や竜神崎の自然の姿は今と変わりません。
余聞(4)「鍬ケ崎に寄港した文人たち」
この鍬ケ崎の港には、江戸時代から多くの文人墨客が訪ねていますが、明治末期から昭和初期に来訪した岩手を代表する3人の文人の足跡を紹介します。
1人目は石川啄木。明治41年(1908年)23歳の時に北海道から再起を期して上京する旅の途中に立ち寄っています。この時の日記を刻んだ「啄木寄港の地」の碑が、鍬ケ崎港を見下ろすVOL5で紹介した旧宮古測候所後の宮古漁協ビルの敷地にあり、「…午後2時10分宮古港に入る。すぐ上陸して入浴、梅の蕾を見て驚く。四方の山に松や杉、これは北海道では見られぬ景色だ。…街は古風な、沈んだ、黴の生えた様な空気に充ちて、料理屋と遊女屋が軒を並べて居る。…」と刻まれています。
次は宮沢賢二。大正6年(1917年)の盛岡高等農林3年生の時に、釜石から三陸汽船で来港しました。その時当地随一の景勝地であった浄土ヶ浜を訪ねて詠んだ「うるはしの 海のビロード昆布らは 寂光のはまに敷かれひかりぬ」歌碑が浜の一隅に建てられています。
最後は東京出身ですが高村光太郎。戦中から戦後の昭和27年まで花巻で独居生活を送るなど岩手とゆかりの深い(因みに最初に疎開したのは宮沢賢二の実家、戦後戦争協力への自責の念から7年の独居生活を粗末な小屋で過ごす)詩人ですが、昭和6年に三陸汽船で石巻から三陸沿岸を北上して宮古に立ち寄っています。その時書いた随想には鍬ケ崎の街を「…鍬ヶ崎は両側に大きな妓楼が建ち並び、門口には妓夫や女が立っている。…人力車の車夫が奨めるので、此所から拾余町ある宮古にむかう。車上から物珍しげに左右を見まわす。一人の女性が『何見ておれんす』と、私をはやす。皆がどっと笑う。ひどくなごやかな所へ来た気がする。車は暗い切り通しを越え、長い黒塀つづきの魚くさい河岸を走って宮古につく…」と書いています。
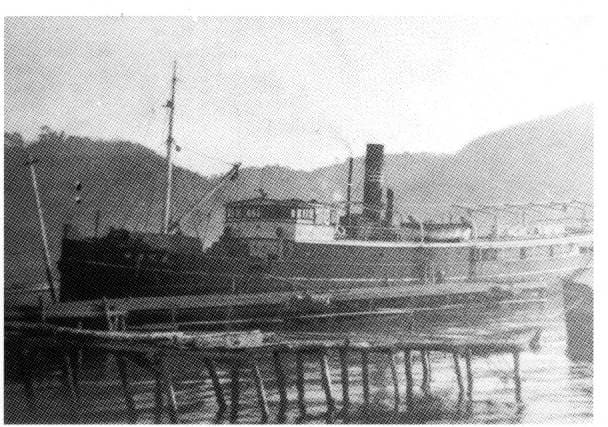
鍬ケ崎湊の風景(現宮古市)其の2
「三陸汽船」
この写真は明治41年に宮古・塩釜間の三陸航路に就航した三陸汽船の4隻の木造貨客船の一つ東北丸(145t)と思われます。(但しこの写真は本写真帖に掲載されていません。参考の為に用意しました)
平成の岩手県三陸沿岸の各都市は、「国道45号」と朝ドラ『あまちゃん』で有名となった「三陸鉄道」及び「JR各線」で結ばれています (但し東日本大震災の大津波により一部区間休止中)。
しかし明治後期まではVOL2で紹介した本写真帳附属の地図のとおり、鉄道はおろか道路も整備されておらず、大量輸送には江戸時代と変わらぬ海路に頼らざるをえませんでした。明治30年に東京湾汽船が東京から進出し塩釜を経由して宮古港に至る航路を開設しましたが、独占資本の法外な高額運賃設定で、これに反発した釜石鉱山田中製鉄所を始めとする地元資本家が共同出資で明治41年に立ち上げたのが三陸汽船株式会社です。
航路開設に当たって岩手県は補助金を出し、その代り岩手県内12港、宮城県内2港へ寄港することを義務付け、第1航路を塩釜・宮古間、第2航路を宮古・久慈間として就航しました。云わば今の「三陸鉄道」に当る三陸沿岸の待望久しい動脈です。その後東京航路や北海道航路も就航し、その拠点となった鍬ケ崎港は賑わいました。
当時の定期航路は次のとおりで、本社は釜石にありましたが、航路は宮古港を中心に組み立てられていました。これは本写真帖付属の明治43年における三陸沿岸各港の下記貨物取扱データ(後日詳細を本ブログに掲載します)を見ると、既に本格稼働していた釜石鉱山田中製鉄所を抱える釜石港が移出入とも全体の半分を占めていましたが、製鉄所関連の物資(鉄鋼材:移出、石炭:移入)を除くと、宮古港が全体の4割を占め拠点性が高かった故と思います。なお東京湾汽船は明治44年に撤退し、三陸汽船に凱歌が上がりましたが後日談があります(後記余聞参照)。
時代が進み、鉄路が三陸の地に達するようになると(宮古・盛岡間の山田線開通は昭和9年/1934年、大船渡・一関間の大船渡線は昭和10年/1935年、釜石・花巻間の釜石線は昭和25年/1950年)、人も貨物もあっという間に鉄道に奪われ経営は悪化し、戦時中の昭和18年(1943年)に会社は解散してしまいました。
所属船舶は、軍に徴用されて殆どが太平洋の藻屑と消えてしまいました。
三陸汽船の航路
≪宮古航路/毎日1便相互運行≫ 塩釜港~気仙沼港~脇ノ沢港(陸前高田)~細浦港~大船渡港(盛町)~越喜来港~小白浜港(唐丹)~釜石港~大槌港~山田港~宮古港(鍬ヶ崎)
≪久慈航路/明治44年就航≫ 宮古港~野田港~久慈港
≪気仙沼航路/≫ 塩釜港~石巻港~十五浜港(雄勝)~志津川港~気仙沼港
≪東京航路/月1便:明治45年就航≫ 宮古港~小名浜港~銚子港~東京港(築地)
≪北海道航路/月2便≫ 宮古港~八戸港~函館港~室蘭港
余聞(3)「三陸汽船の裏話」
三陸汽船の進出により、暴利を貪っていた先行の東京湾汽船との間で激しい競争が始まり、船賃は約1/3以下となり、上述のとおり明治44年(1911年)に東京湾汽船は所有船舶を三陸汽船に売却し、ついに三陸の海から撤退しました。
このことを関係県町村史で『東北の現地資本が巨大な中央資本に一矢を報いて打ち勝った』と賞賛している例があり、私も最初は明治の三陸商人なかなかやると思っていましたが、実際はそうではありませんでした。東京湾汽船は確かに船舶を三陸汽船に売却しましたが、と同時に三陸の地元商人らの株を買い取り三陸汽船の筆頭株主となり、そして設立時の取締役らは退任し、名を捨て実を取る戦略により三陸汽船は事実上東京湾汽船に乗っ取られたのが真相のようです。

鍬ケ崎湊の風景(現宮古市)其の1
この写真は、明治45年当時の鍬ケ崎町(今の宮古市鍬ケ崎上町)の風景です。現在はこの浜辺を数十m先まで埋め立てられて、砂浜は姿を消し、コンクリートの岸壁となっています。
鍬ケ崎の湊(現宮古港)は、リアス式海岸特有の奥まった波静かな天然の良港で、江戸初期より南部藩の海の玄関口として、また江戸と松前を結ぶ東廻り航路の寄港地として、回線問屋や海産物の仲買商家が建ち並び栄えてきました。この写真ではわかりませんが、俗謡で「江戸で吉原、南部で宮古、宮古まさりの鍬ケ崎」と唄われたように港に立ち寄る人々を相手とした遊郭や料理屋が軒を連ね、三陸随一の歓楽街としても賑わっていました。
本ブログのVOL 8に記しましたが、宮古港の起こりは、400年前の慶長の大津波(慶長16年/1611年)により壊滅した宮古(鍬ケ崎含む)の再興の際に、南部藩初代藩主南部利直候が宮古港を同藩の外港と定めたことに因ります。
さて写真を見ると、三陸一の港と云いながら粗末な木造の桟橋しか見当たりません。宮古港が現在のように埋め立てられて岸壁が出現するのは大正6年のことで、当時は写真のように小型の船は桟橋を使い、より大きな船の場合は沖合に停泊して艀で荷卸しをしていました。

市日の風景(今の宮古市中央通)
写真は当時片桁(カタゲダ)と呼ばれていた今の宮古市中央通りで、毎月2と9の付く日に開かれていたという市日の一コマです。川岸に露店が立ち並び、写真手前ではカゴやザルなどの竹製品、その先は野菜でしょうか、自ら作り育てたものを所狭しと並べています。買い物する人には背負い籠(しょいかご)姿が目に着きます。近郷近在から沢山の人が集まり、先は正に黒山の人だかりで活気が溢れ、街が賑わっている様が見てとれて、今の商店街の姿と比較すると羨ましくなってしまいます。
写真奥の川の曲がり具合や途中に右方(北)から入る大きめの道路が見当たらないことから、この写真の撮影場所は現在の高橋交差点より西寄りかと思えます。撮影年は電信柱が見えることから、宮古に初めて電燈が点いた写真帳の発行年である明治45年、時季は通行人が綿入れの厚い着物を着て、また川の向こう岸や遠くの山に残雪が見えること、川面に薄氷が張っていることから寒い2月頃でしょうか。高い位置から撮られています。当時も今もこの撮影地点には建物がない筈なので高い脚立の上からでも俯瞰したのかも、それとも川岸に大きな木があってそこに登ったのかも知れません。
さて山口川に蓋をかける工事が始まったのが昭和29年、蓋をかけ終わり全面舗装工事が終了したのが昭和34年のことです。この写真撮影当時は南北の本町通りや新町通りが賑わっていましたが、山口川が暗渠となり道路が広くなると、宮古駅から末広町そしてここ中央通を経て宮古市役所へ向かう一本道が、宮古のメイン通りとなりました。
ところで私はこの写真を本写真帖以外でも、様々な資料集で何度も目にしています。どれが本元か分からりませんが、前述のとおり電信柱が写っていることなどから推察すると、この写真帳が元となり広がったのかも知れません。ともかく宮古の往時の賑わいが窺い知れるとても良い写真であることは間違いありません。
実は、この市日の風景が、私が勝手に選んだ 「もし今でも宮古に残っていたらと思う7つの風景」 の 其の5 です。市は、昨今の商店街になくなったの風情があり、人の交流と賑わいがあります。今で云う農工商連携の元となるものです。スローシティーという言葉が気になり始めたこの頃です。
(余話)
最近気象庁の過去データを調べたら明治45年(1912)の宮古の月毎の最低気温下表データを見つけ、その結果本写真の撮影日をある程度まで推測できましたので加筆します。
本写真の撮影日は、①写真帖の出版は明治45年4月であり、宮古に電気が通じたのが同45年なので明治45年に確定。②川面には薄氷が、遠景の山には雪が見え、気象庁データでは宮古の最低気温は同年1月/-5.1℃、2月/-3.2℃(氷点下3度程度では川の流れがあるので薄氷が張るまでには至りません)、3月/-1.2℃なので1月、③市が立っているので1月9.12.19.22.29日までと推定しました。

(2013.9.6に投稿したものを、2017.2.11に一部修正)
今回は、写真帳から外れて、前々回の最後に書いた続きをします。
400年前の宮古の町割りと
慶長の大津波の関係とは
町割りとは、今でいう都市計画のことです。
宮古にはVOL3でも書いたように何度も大津波が押し寄せていますが、特に400年前の慶長の津波(慶長16年/1611年)では、当時八幡山と舘合の合間にあった常安寺を押し流し、宮古村は山麓の数戸を僅かに残すのみで壊滅的な被害を蒙ったと記録にあります。(先の東日本大震災の大津波は、埋め立て等により海岸線が沖に延び、また防潮堤等の効果があったのか、江戸初期に常安寺あった付近よりずっと手前で波は止まっていますので、もしかすると宮古に関しては慶長の大津波は今回より大規模だったのかも知れません)

その当時宮古を治めていたのが南部藩初代藩主南部利直候で、4年後の元和元年(1615年)に宮古を訪れて、20日間滞在し復興の陣頭指揮をとったと云われています。宮古代官所に残された記録には5月5日藩主が小本代官を伴って眺望のよい横町の小山に登り、松のそばの大石に上がって宮古一帯を見渡し、町割りを定めたとあります。そして最初に決めた町が今の本町です。それからこの大石を「町割り石」と呼ぶようになり今に伝えられています。
その18年後に小本代官が本町から横に伸びる横町、本町の隣り通りに新町、山口川を渡った向いに田町と海沿いに南部藩の水夫が住む御水主町(後の向町)の4町が新たに決められました。
開町と云う言葉があるならば、元和元年(1615年)こそが宮古開町元年に当り、正にこの大石は、宮古の原点であり宮古市の記念すべき大切な史跡です。すると再来年の平成27年(2015年)は、宮古市開町400周年の区切りの年となります。しかし今宮古市は、なぜかこの史実を顧みず、この町割りと同時期の宮古港を南部藩の外港としたことにのみ目を向け、宮古港開港400周年記念として様々なイベントを企画していると聞きます。なぜ港のみなのか分かりません。街か港かで綱引きをするつもりは毛頭なく、今は「宮古開町&開港400周年」として全市を挙げて東日本大震災からの復興に当るべきではないでしょうか。
また元を辿ればその4年前に遭った慶長の大津波(慶長16年/1611年)から立ち興ったのが宮古の街です。
この史実を宮古の皆がしっかり捉えていたら、2年前の平成23年(2011年)は、慶長16年の大津波からちょうど400年に当たっていたので、何かしらの警鐘を鳴らしその心構えを説くことができて、もしかすると東日本大震災の犠牲が多少とも軽減できたかも知れないと思うと残念でなりません。そしてこの写真帳はそれから300年後に作られたことを思うと何かしらの縁を感じます。
しかし残念なことに町割り石の存在は今ではすっかり忘れ去られ、案内板一つなく、利直候が登った沢田から道は石垣で閉ざされ、常安寺の墓地の間を縫って西の外れに残る山道を藪をかき分けながら辿りついても、周りに木が生い茂り残念ながら眺望がよくありません。
下の図面1は、安政4年(1857)に作成されたものです。翌年が井伊直弼の安政の大獄があった年ですから、幕末の大変動が正に起きなんとなるときで、宮古開町から240年余り経った頃です。既に街並みは整い、代官所前には下町ができ、移転した常安寺も境内も整っています。

下図2は元禄5年(1692年)に描かれた当時の宮古村の建物の間口を1戸毎に表記した図面の復元図です。本写真帳にはありませんが、私のデータにあったので参考までに転記します。

余聞(1)
私がこの町割り石を初めて見に行ったのは約50年前のことです。当時健在であった明治27年(1894年)生まれの祖父に連れられて寺に墓参りに行った時に、「町割り石」とその傍にある「唐かさ松」を知っているかと尋ねられ、知らないと答えると、ではと連れて行かれ、南部の殿様の話を教えて貰いました。祖父が云うには、祖父が幼少の頃は町割り石の周りはきれいに草木が刈り取られた広場となっており、子供達はよく相撲などをして遊んだそうです。
また私は12.3年前に小学生だった息子の自由研究の題材に町割り石を取り上げて、無理やり連れて登ったこともありました。その時町割り石の由来を伝えた筈ですが、先日聞いたらすっかり忘れていました。小さい子には無理だったかもしれませんが、大切な試みと今でも思っています。
私達は400年前の慶長の大津波の教訓を生かすことはできませんでしたが、今回の東日本大震災の記憶は、祖父から孫へ、孫から子へと、長く伝え残して行かねばなりません。