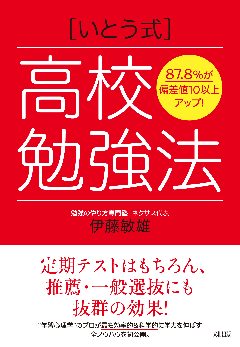ある中学校の「自由進度学習」というものが何なのか
実際に、塾生からどんなようすなのか教えてもらいました。
・基本的には全教科、自由進度学習(一部の教科は例外)
・授業の最初に、各自その日にやる内容(目標)を決める
(グーグルクロームに書きこむ)
・自分で動画や教科書を見て理解する
・わからないことがあっても教師に質問せず、自分で調べる
・授業の最後に、その時間の「ふり返り」を書く(3~5分)
率直な感想を述べると、これは自由進度学習ではなく「ただの自習」です。
これ、教師(教員免許持っている専門家)要りますか?
まず、各自その日にやる内容(目標)を決めるというのを
学校では目標設定と呼んでいるようですが、
ただの記録ですよね?
目標設定って
・~できるようにする
とか到達度目標を決めることです。
例えば、1年生なら
・5W1Hの疑問詞を使った疑問文と応答文をつくって口頭で言えるようにする
・ 〃 書けるようにする
といったものです。
ただ、残念ながら
このような目標設定レベルまでできている子は少ないでしょう。
グーグルクロームで“目標を設定”しても、
その目標が適切かどうか、教師からのフィードバックはないそうです。
あれれ?
だから、大半の生徒は目標といっても
「教科書○ページから○ページまでをやる」
というものしか立てられません。
もう一度言いますが、
これただの記録ですよね?
そして、自由進度学習中に、
わからないことがあった場合、
教師に聞いても教えてくれないそうです。
「わからないことは自分で解決しましょう」
あれれれ?
ますます教師要らないですよね?
数学だったら、
途中の計算式をこのように書いた方が計算ミスが減る
国語だったら、
発着という熟語の成り立ちは、出発する到着する→対になる漢字の組合せとわかる
など、学び方を教えて初めて「教師」って呼べると思うんですが、
私の勘違いでしょうか?
あくまでも、
自分でわかりやすい動画などを探して、
それで理解する
の一点張りだそうです。
何て効率の悪い、、、
そもそも、
学校の勉強をそこまでして理解したいと思う子の方がむしろ少数派ですよね。
そんなめんどくさいんだったらもういいやって諦める子も出てくるでしょう。
さらに、授業の最後の数分を使って、
その授業での
「ふり返り」
・
・・
・・・
という名の感想を書く時間があるのですが、
無駄ですよね?
どんな感想を書いているか
「今日は○○を学びました。難しかったので次回はできるようにがんばりたいです」
(゚Д゚)ハァ?
文字通り、感想ですよね。
毎回、授業の貴重な時間を使ってこんなこと書いても、
学習効果はゼロですよ。
仮に、せっかく、
「負の数のひき算を正の数のたし算にして計算する問題がよくわからなかった。次回は、できるようにがんばりたい」
といった、精緻化されたふり返りができていたとして、
教師からのフィードバック(コメント返し)はないそうです。
あれれれ?
ますます、これ自習とどこがちがうんですか??
折角のふり返りも、
教師からのフィードバックがなければ、修正ができません。
一部の、ものわかりのよい子、かしこい子は別として、
多くの子が間違って理解したまま先へ進んでしまう恐れがあります。
そこをふり返らないといけないのに、
ふり返りへのフィードバックもなしです。
本当に自由進度「学習」であるならば、
このフィードバックこそが重要です。
個人的にはふり返りは意味がないと思っていますが、
仮にも、毎回生徒にふり返りを書かせているのであれば、
教師は、それをチェックして、適切なフィードバックをすべきでしょう。
それが「学習」です。
ところが、ひとクラス30名いて、
1日4クラス授業を受け持ったとしたら、
30×4≒100名以上の生徒のふり返りに目を通し、
フィードバックをしないといけないはずです。
一人1分かかったとしても、2時間はかかる計算です。
昨今の、働き方改革が叫ばれている中、そんな時間ないはずです。
っで、実際、そのようなきめ細かい指導はできていないでしょう。
従来ならば一斉形式で、
期間巡視しながらの個別形式で
フィードバックするからこそ教師の存在意義があるので、
自由進度学習という名の自習に成り下がっている。
実際、生徒からは
「教師が楽をしている」
という不満が出てきています。
これでも、教師(教員免許持っている専門家)要りますか?
■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓
勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)
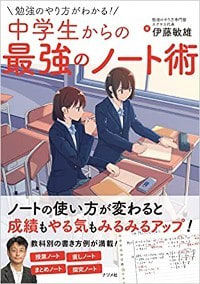
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます
実際に、塾生からどんなようすなのか教えてもらいました。
・基本的には全教科、自由進度学習(一部の教科は例外)
・授業の最初に、各自その日にやる内容(目標)を決める
(グーグルクロームに書きこむ)
・自分で動画や教科書を見て理解する
・わからないことがあっても教師に質問せず、自分で調べる
・授業の最後に、その時間の「ふり返り」を書く(3~5分)
率直な感想を述べると、これは自由進度学習ではなく「ただの自習」です。
これ、教師(教員免許持っている専門家)要りますか?
まず、各自その日にやる内容(目標)を決めるというのを
学校では目標設定と呼んでいるようですが、
ただの記録ですよね?
目標設定って
・~できるようにする
とか到達度目標を決めることです。
例えば、1年生なら
・5W1Hの疑問詞を使った疑問文と応答文をつくって口頭で言えるようにする
・ 〃 書けるようにする
といったものです。
ただ、残念ながら
このような目標設定レベルまでできている子は少ないでしょう。
グーグルクロームで“目標を設定”しても、
その目標が適切かどうか、教師からのフィードバックはないそうです。
あれれ?
だから、大半の生徒は目標といっても
「教科書○ページから○ページまでをやる」
というものしか立てられません。
もう一度言いますが、
これただの記録ですよね?
そして、自由進度学習中に、
わからないことがあった場合、
教師に聞いても教えてくれないそうです。
「わからないことは自分で解決しましょう」
あれれれ?
ますます教師要らないですよね?
数学だったら、
途中の計算式をこのように書いた方が計算ミスが減る
国語だったら、
発着という熟語の成り立ちは、出発する到着する→対になる漢字の組合せとわかる
など、学び方を教えて初めて「教師」って呼べると思うんですが、
私の勘違いでしょうか?
あくまでも、
自分でわかりやすい動画などを探して、
それで理解する
の一点張りだそうです。
何て効率の悪い、、、
そもそも、
学校の勉強をそこまでして理解したいと思う子の方がむしろ少数派ですよね。
そんなめんどくさいんだったらもういいやって諦める子も出てくるでしょう。
さらに、授業の最後の数分を使って、
その授業での
「ふり返り」
・
・・
・・・
という名の感想を書く時間があるのですが、
無駄ですよね?
どんな感想を書いているか
「今日は○○を学びました。難しかったので次回はできるようにがんばりたいです」
(゚Д゚)ハァ?
文字通り、感想ですよね。
毎回、授業の貴重な時間を使ってこんなこと書いても、
学習効果はゼロですよ。
仮に、せっかく、
「負の数のひき算を正の数のたし算にして計算する問題がよくわからなかった。次回は、できるようにがんばりたい」
といった、精緻化されたふり返りができていたとして、
教師からのフィードバック(コメント返し)はないそうです。
あれれれ?
ますます、これ自習とどこがちがうんですか??
折角のふり返りも、
教師からのフィードバックがなければ、修正ができません。
一部の、ものわかりのよい子、かしこい子は別として、
多くの子が間違って理解したまま先へ進んでしまう恐れがあります。
そこをふり返らないといけないのに、
ふり返りへのフィードバックもなしです。
本当に自由進度「学習」であるならば、
このフィードバックこそが重要です。
個人的にはふり返りは意味がないと思っていますが、
仮にも、毎回生徒にふり返りを書かせているのであれば、
教師は、それをチェックして、適切なフィードバックをすべきでしょう。
それが「学習」です。
ところが、ひとクラス30名いて、
1日4クラス授業を受け持ったとしたら、
30×4≒100名以上の生徒のふり返りに目を通し、
フィードバックをしないといけないはずです。
一人1分かかったとしても、2時間はかかる計算です。
昨今の、働き方改革が叫ばれている中、そんな時間ないはずです。
っで、実際、そのようなきめ細かい指導はできていないでしょう。
従来ならば一斉形式で、
期間巡視しながらの個別形式で
フィードバックするからこそ教師の存在意義があるので、
自由進度学習という名の自習に成り下がっている。
実際、生徒からは
「教師が楽をしている」
という不満が出てきています。
これでも、教師(教員免許持っている専門家)要りますか?
■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓
勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)
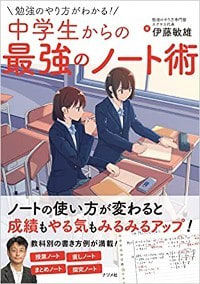
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます