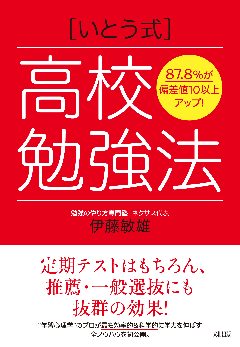まあ、学校の先生も思うところはあるんでしょう。
最近では、不登校の子も激増していますから、
・学校の勉強に馴染めない
・教科の勉強にコミットできない
そういう子への配慮なんでしょう。
でも、
「今年から、甲子園で勝ち負けを争いません!出場校全部が優勝です!」
とか言われたらどう思います???
一宮高校では
「一宮市以外出身の中学生が苦戦している」
という話を聞いたことがあります。
確かにそういう面はあるかもしれません。
一宮市の中学校の中には、
定期テストも含めると1年間に10回ほどテストがある中学もあります。
宿題の量も質もハイレベルです。
そういうのが当たり前で一宮高校に入ってくる子と
「定期テストで順位出ません」
って中学校では、だいぶん温度差があるでしょう。
また、一宮高校とは無縁の子でも、
例えば、中学で全然勉強してないのに
中途半端な新が高校へ行けば
そこはそこで徹底的な詰めこみ教育が行われています。
そもそも「賛否両論」があるかもしれませんが、
古知野中から通っているのが比較的多い
KやIやB高校では
エグイほどの詰めこみ教育が行われています。
そういう中学と高校のギャップについていない子も少なからずいます。
確かにこれからAI時代を迎えるにあたって
ペーパーテストがなんぼのもんじゃい?
偏差値教育古くいね?
って思う人は増えてくるかもしれません。
でも、義務教育の勉強まで否定すべきでしょうか。
(高校の勉強はやりすぎな感はありますが)
中学や高校の勉強をガチでやりたい子も中にはいるわけです。
そういう子たちのことは考えているでしょうか?
順位を出さない教育
いくら、いち中学が崇高な理念を掲げても、
高校受験はなくならないし、
大学受験もなくならない。
世の中には、
教員や公務員の採用試験もあれば、
看護師や理学療法士などの国家試験もあります。
学校の勉強が
好きな子/嫌いな子
できる子/できない子
いろんな子がいるのが学校です。
でも、
順位
という臭いものに蓋をしたところで、
根本的な解決にはならないでしょう。
「あちらを立てればこちらが立たず」
なのはよくわかりますが、
義務教育が、
できない子に迎合して、
むしろ、できる子を見捨てるようなことをして
保護者からの信頼を失わないかが心配です。
「やっぱり勉強させるなら学校より○○だよね」
みたいなことになるとしたら、、、
■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓
勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)
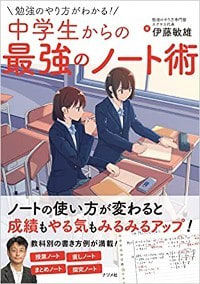
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます
最近では、不登校の子も激増していますから、
・学校の勉強に馴染めない
・教科の勉強にコミットできない
そういう子への配慮なんでしょう。
でも、
「今年から、甲子園で勝ち負けを争いません!出場校全部が優勝です!」
とか言われたらどう思います???
一宮高校では
「一宮市以外出身の中学生が苦戦している」
という話を聞いたことがあります。
確かにそういう面はあるかもしれません。
一宮市の中学校の中には、
定期テストも含めると1年間に10回ほどテストがある中学もあります。
宿題の量も質もハイレベルです。
そういうのが当たり前で一宮高校に入ってくる子と
「定期テストで順位出ません」
って中学校では、だいぶん温度差があるでしょう。
また、一宮高校とは無縁の子でも、
例えば、中学で全然勉強してないのに
中途半端な新が高校へ行けば
そこはそこで徹底的な詰めこみ教育が行われています。
そもそも「賛否両論」があるかもしれませんが、
古知野中から通っているのが比較的多い
KやIやB高校では
エグイほどの詰めこみ教育が行われています。
そういう中学と高校のギャップについていない子も少なからずいます。
確かにこれからAI時代を迎えるにあたって
ペーパーテストがなんぼのもんじゃい?
偏差値教育古くいね?
って思う人は増えてくるかもしれません。
でも、義務教育の勉強まで否定すべきでしょうか。
(高校の勉強はやりすぎな感はありますが)
中学や高校の勉強をガチでやりたい子も中にはいるわけです。
そういう子たちのことは考えているでしょうか?
順位を出さない教育
いくら、いち中学が崇高な理念を掲げても、
高校受験はなくならないし、
大学受験もなくならない。
世の中には、
教員や公務員の採用試験もあれば、
看護師や理学療法士などの国家試験もあります。
学校の勉強が
好きな子/嫌いな子
できる子/できない子
いろんな子がいるのが学校です。
でも、
順位
という臭いものに蓋をしたところで、
根本的な解決にはならないでしょう。
「あちらを立てればこちらが立たず」
なのはよくわかりますが、
義務教育が、
できない子に迎合して、
むしろ、できる子を見捨てるようなことをして
保護者からの信頼を失わないかが心配です。
「やっぱり勉強させるなら学校より○○だよね」
みたいなことになるとしたら、、、
■↓中学生の勉強の仕方(ノート術)は↓
勉強のやり方がわかる!中学生からの最強のノート術(ナツメ出版)
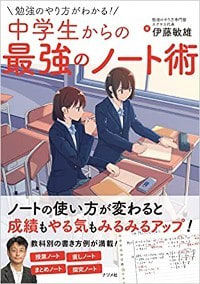
■LINEでお問い合わせ

■空席状況をチェック
・学年ごとの曜日・空席状況がチェックできます