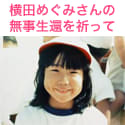今日は4月の<庫裏のコース>を開催いたしました。
このコースは、伝統の食文化を子どもたちに残して行くために始めました。
昔から台所仕事は、女の生き方が反映して、
その家、その家のしきたりや我が家の味が生まれてきます。
おばあちゃんからお母さんに、お母さんから娘(嫁)に代々伝わる女の仕事は
一家を繁栄させるか衰退させるかを二分するほどの力があるものなのです。
スーパーでお漬物を買うという女性は、添加物で家族のカラダをむしばみ、無駄遣いで家計をむしばみ、日本の伝統を途絶えさせ文化を衰退させます。
「あげまん」「さげまん」と言う言葉がありますが
「まん」は「間」と言う字が由来で、運気・潮目・出会い・巡り合わせの意味。
女性の社会進出は大賛成ですが、社会にでたからできないなんて情けないことを言わず、
しっかり台所を女の城として守って運気をあげていってほしいものです。
さて、タイトルとはずいぶん違う内容になりましたが、
今日は、ふんわり「桜の花の塩漬け」と「糠床」を作りました。



今年の八重桜は、綺麗な濃いピンクのものが手に入りました。
無農薬のものです。

塩水で洗って、小さな尺取り虫などを除きます。
その後、梅酢に漬けて、干して塩漬けにします。
春の名残りを、お茶にしたり、お菓子のかざりにしたり、時折楽しみたいと思います。





糠床は、無農薬の糠と塩天華(えんてんか)という塩を使いました。
昆布、唐辛子、リンゴなどを混ぜます。
私は、生姜やニンニクなどもいれたりします。
酸っぱくなったら、辛子や卵の殻などを入れて調整をします。
下漬けに2週間、美味しく発酵するまでには2ヶ月くらいかかります。
ちょうど夏に間に合いますね。
毎日、混ぜて
我が家自慢の糠床に育ててくださいね。
教室の後、石巻に持っていく食糧の準備をいたしました。




「みそだま」はお昼用です。
泥出しをする現場で熱いお味噌汁を飲んでいただけるように、
1杯分づつに小分けにいたしました。
みなさん、お手伝いいただいてありがとうございました。
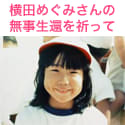
このコースは、伝統の食文化を子どもたちに残して行くために始めました。
昔から台所仕事は、女の生き方が反映して、
その家、その家のしきたりや我が家の味が生まれてきます。
おばあちゃんからお母さんに、お母さんから娘(嫁)に代々伝わる女の仕事は
一家を繁栄させるか衰退させるかを二分するほどの力があるものなのです。
スーパーでお漬物を買うという女性は、添加物で家族のカラダをむしばみ、無駄遣いで家計をむしばみ、日本の伝統を途絶えさせ文化を衰退させます。
「あげまん」「さげまん」と言う言葉がありますが
「まん」は「間」と言う字が由来で、運気・潮目・出会い・巡り合わせの意味。
女性の社会進出は大賛成ですが、社会にでたからできないなんて情けないことを言わず、
しっかり台所を女の城として守って運気をあげていってほしいものです。
さて、タイトルとはずいぶん違う内容になりましたが、
今日は、ふんわり「桜の花の塩漬け」と「糠床」を作りました。



今年の八重桜は、綺麗な濃いピンクのものが手に入りました。
無農薬のものです。

塩水で洗って、小さな尺取り虫などを除きます。
その後、梅酢に漬けて、干して塩漬けにします。
春の名残りを、お茶にしたり、お菓子のかざりにしたり、時折楽しみたいと思います。





糠床は、無農薬の糠と塩天華(えんてんか)という塩を使いました。
昆布、唐辛子、リンゴなどを混ぜます。
私は、生姜やニンニクなどもいれたりします。
酸っぱくなったら、辛子や卵の殻などを入れて調整をします。
下漬けに2週間、美味しく発酵するまでには2ヶ月くらいかかります。
ちょうど夏に間に合いますね。
毎日、混ぜて
我が家自慢の糠床に育ててくださいね。
教室の後、石巻に持っていく食糧の準備をいたしました。




「みそだま」はお昼用です。
泥出しをする現場で熱いお味噌汁を飲んでいただけるように、
1杯分づつに小分けにいたしました。
みなさん、お手伝いいただいてありがとうございました。