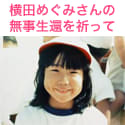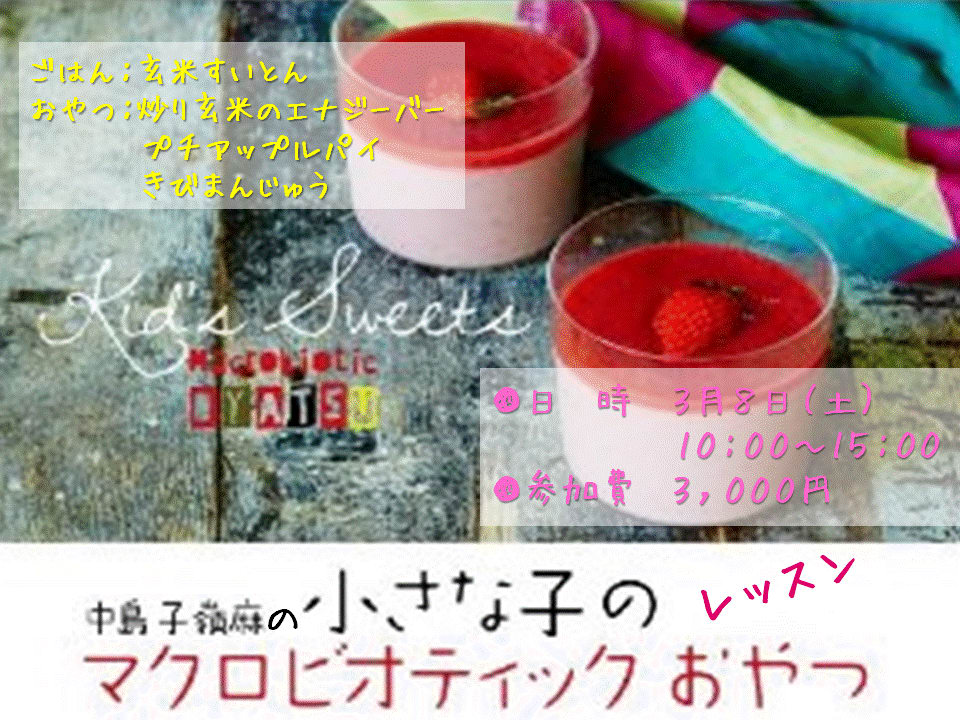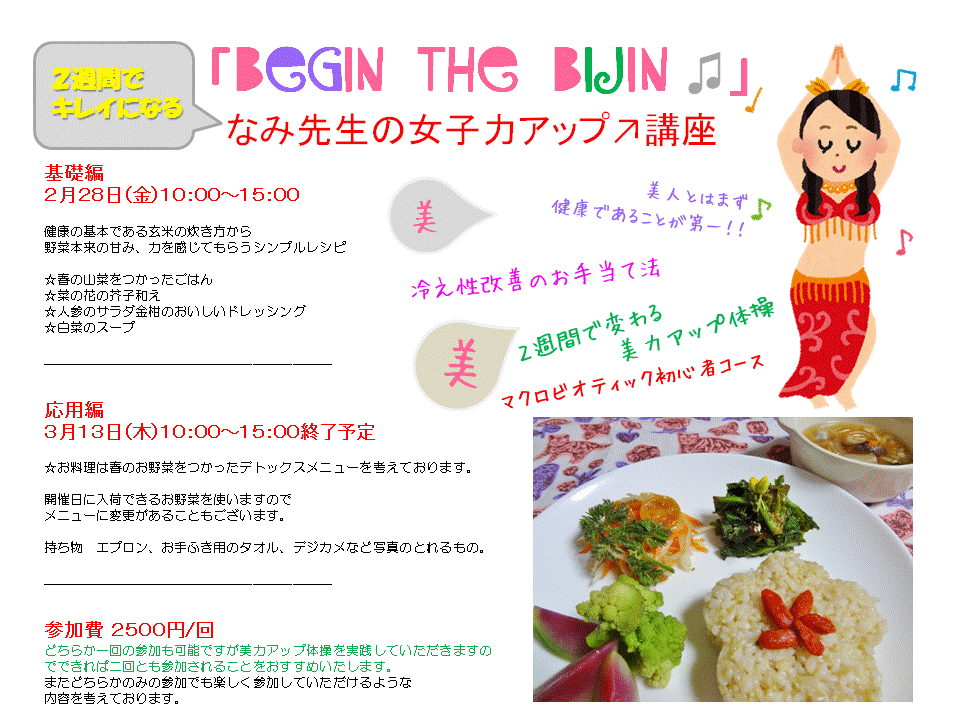昨日、一昨日と酷い大気の状態で、香川県でもPM2.5の注意喚起がようやく出ましたね。
放射能汚染についても、しっかりと対応してくれないとこまっちゃう。
さて、こんな環境の中ですから、待ってましたとばかりに普段の不節制を棚に上げて、体の不調をすべてPM2.5や放射能のせいにして、どこかPM2.5アリガトウ!な方いませんか?
我が家にも、一匹。
「目の充血はPM2.5に違いない」とか「風邪っぽい症状は間違いなくPM2.5やな」とか。挙句の果てには「ワシの痛風はやっぱりPM2.5からきたストレスが原因や」などと云いそうな不養生な輩がおりますが(笑)、いえいえ、あなたの不調の数々は「アルコール」が原因です!アルコールによる肝機能の低下がストレスをも招きやすくしてるだけです!
と、つっこんでやってください!
という小ネタでしたが、ここからはちょっとまじめに。
昨日ニュースに出た「子宮頚癌ワクチン」についての厚生労働省の見解についてですが、以下、ニュースから転載します。
テレビ朝日系(ANN) 2月26日(水)22時38分配信
副作用が問題となっている子宮頸(けい)がんワクチン。厚生労働省の有識者会議は、副作用は接種時の痛みやストレスが引き起こしたと結論付け、接種の呼び掛けを再開するかどうか最終的な検討に入る。26日の会議では、「小児精神」に関わる専門家を呼んで議論し、接種する際、事前に「効果」とともに「痛みが出る」ことを伝えることで副作用を減らせるなどとした。また、会議では、海外の臨床医らが訴えた「ワクチンの成分が脳に炎症を起こす危険性」などが紹介された。しかし、有識者は「科学的根拠が乏しい」と否定し、その見解については検討しないという。再開するかどうか近く判断を下す有識者会議。メンバー10人のうち、少なくとも2人はワクチン製造会社から規定以上の寄付金をもらっているため、それ以外のメンバーで結論を出すという。
副作用による重篤な心身の問題を起こしているワクチンの(他のワクチンも同様だよね)保障問題が絡むだけに、国は「ストレス」などとどうとでも取れるあいまいな原因を前面に出して、海外の医師から寄せられた「ワクチンの成分アルミニウムによって脳や体に炎症が起きた疑いがある」などとする意見も「科学的根拠が乏しい」として否定したそうですが、いやいや、「ストレス説」も大概科学的根拠がないやないの!と突っ込み満載な発表ですね。世界保健機関(WHO)も「安全性を再確認した」とする報告をまとめるなど、WHOのやっぱり!な対応には、もう信頼ゼロですね~。
だいたい、何故ここ数年で子宮頚癌が取りざたされたのかも大きな「疑問(?_?)」
今現在、ヤフーの検索で子宮頚癌についてとか原因とか治療法などのキーワードを入れても全く情報入手出来なくなっているのもおかしな話です。なにかわからない力がかかっているのかも?
ま、それはさておき、このような健康被害を受けた時に、ちゃんとその原因特定をするのは至難の業です。放射能問題においても、同様。癌になるような生活を棚に上げて、原因が放射能にあるとしても、国は、癌になるのは放射能だけが原因ではないと必ず言うのではないでしょうか?
環境が悪くても、同じ環境下で不調になる方と、不調にならずに普通に生活されている方とありますよね。
もちろん、感受性の問題や意識の問題などあると思いますし、PM2.5も放射能も、そして、各種ワクチンも絶対にカラダに良くないと確信しておりますが、それでも、松見歯科の臨床の中で、体調不良を訴え、いくつかの病気を併せ持ってきた人を観ると、「アララララ~」さもあらん(^_^;)と、ため息が出るようなライフスタイルを垣間見ることがよくあります。不調な方とお元気な方では、その暮らしぶりは全く違うんです。
不調を訴える方は、毎日甘いお菓子や果物を複数回食べて、主食はパンや麺類、あるいはおかず中心。ほとんどお米のごはんを食べていません。おかずも添加物だらけで加工食品を並べただけだとか、インスタントに仕上がる調味料やレトルトなどの多用。
そして外食によるジャンクフードの多食。
また、健康補助食品やサプリメント、常に医者通い、薬漬け、夜深し、運動不足などなど、目に見えて不自然な暮らし方をされている方が多いのです。
それらを反省して、食や環境などの暮らし方を改善された方は、みなさん、今までの不調はなんだったんだろうっておっしゃいます。
こうして快調になられた方は、毎年、誰よりも先に風邪を引いていたのが引かなくなり、冷え症が改善され、アレルギー疾患が目に見えて良くなり、慢性病や難病までも医者いらずになります。生活習慣病の最たる癌でさえ消えてなくなることもよくあることです。
国や医療機関は、放射能や、PM2.5が原因だと断定しにくいなどとよくいわれますが、確かに、上記のような暮らし方では放射能を浴びなくてもPM2.5を吸い込まなくても癌になるわけですから、保障問題がからむようなことですから、断定するには二の足を踏むというのも納得はできます。まぁ、国の思うツボとなってしまうのです。
だからこそ、日々の暮らしの秩序を最低限でも正して、病気にならないような備えが必要だと思います。
お塩を自然塩にしませんか?調味料から化学添加物を取り除きませんか?砂糖などの糖類の摂取の仕方を考え直してみませんか?糖質は基本、主にはご飯から(できれば未精製)摂るようにすることが主食の意味です。パンや麺類が多くなっていませんか?毎日果物を食べていませんか?
改善する糸口はいくらでもあります。
出来るところから取り組んで見られると、きっと心身がその答えを出してくれますよ。(←糖尿病患者さんの before and after です)
それからそれから、放射能もしかり、PM2.5もしかり、花粉症もしかり。
予防が大切。それは食改善はもちろんのことだけど、マスクをするとか、鼻を洗うとか、出来ることはいろいろあるから、まずはやってみてね。

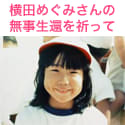
放射能汚染についても、しっかりと対応してくれないとこまっちゃう。
さて、こんな環境の中ですから、待ってましたとばかりに普段の不節制を棚に上げて、体の不調をすべてPM2.5や放射能のせいにして、どこかPM2.5アリガトウ!な方いませんか?
我が家にも、一匹。
「目の充血はPM2.5に違いない」とか「風邪っぽい症状は間違いなくPM2.5やな」とか。挙句の果てには「ワシの痛風はやっぱりPM2.5からきたストレスが原因や」などと云いそうな不養生な輩がおりますが(笑)、いえいえ、あなたの不調の数々は「アルコール」が原因です!アルコールによる肝機能の低下がストレスをも招きやすくしてるだけです!
と、つっこんでやってください!
という小ネタでしたが、ここからはちょっとまじめに。
昨日ニュースに出た「子宮頚癌ワクチン」についての厚生労働省の見解についてですが、以下、ニュースから転載します。
テレビ朝日系(ANN) 2月26日(水)22時38分配信
副作用が問題となっている子宮頸(けい)がんワクチン。厚生労働省の有識者会議は、副作用は接種時の痛みやストレスが引き起こしたと結論付け、接種の呼び掛けを再開するかどうか最終的な検討に入る。26日の会議では、「小児精神」に関わる専門家を呼んで議論し、接種する際、事前に「効果」とともに「痛みが出る」ことを伝えることで副作用を減らせるなどとした。また、会議では、海外の臨床医らが訴えた「ワクチンの成分が脳に炎症を起こす危険性」などが紹介された。しかし、有識者は「科学的根拠が乏しい」と否定し、その見解については検討しないという。再開するかどうか近く判断を下す有識者会議。メンバー10人のうち、少なくとも2人はワクチン製造会社から規定以上の寄付金をもらっているため、それ以外のメンバーで結論を出すという。
副作用による重篤な心身の問題を起こしているワクチンの(他のワクチンも同様だよね)保障問題が絡むだけに、国は「ストレス」などとどうとでも取れるあいまいな原因を前面に出して、海外の医師から寄せられた「ワクチンの成分アルミニウムによって脳や体に炎症が起きた疑いがある」などとする意見も「科学的根拠が乏しい」として否定したそうですが、いやいや、「ストレス説」も大概科学的根拠がないやないの!と突っ込み満載な発表ですね。世界保健機関(WHO)も「安全性を再確認した」とする報告をまとめるなど、WHOのやっぱり!な対応には、もう信頼ゼロですね~。
だいたい、何故ここ数年で子宮頚癌が取りざたされたのかも大きな「疑問(?_?)」
今現在、ヤフーの検索で子宮頚癌についてとか原因とか治療法などのキーワードを入れても全く情報入手出来なくなっているのもおかしな話です。なにかわからない力がかかっているのかも?
ま、それはさておき、このような健康被害を受けた時に、ちゃんとその原因特定をするのは至難の業です。放射能問題においても、同様。癌になるような生活を棚に上げて、原因が放射能にあるとしても、国は、癌になるのは放射能だけが原因ではないと必ず言うのではないでしょうか?
環境が悪くても、同じ環境下で不調になる方と、不調にならずに普通に生活されている方とありますよね。
もちろん、感受性の問題や意識の問題などあると思いますし、PM2.5も放射能も、そして、各種ワクチンも絶対にカラダに良くないと確信しておりますが、それでも、松見歯科の臨床の中で、体調不良を訴え、いくつかの病気を併せ持ってきた人を観ると、「アララララ~」さもあらん(^_^;)と、ため息が出るようなライフスタイルを垣間見ることがよくあります。不調な方とお元気な方では、その暮らしぶりは全く違うんです。
不調を訴える方は、毎日甘いお菓子や果物を複数回食べて、主食はパンや麺類、あるいはおかず中心。ほとんどお米のごはんを食べていません。おかずも添加物だらけで加工食品を並べただけだとか、インスタントに仕上がる調味料やレトルトなどの多用。
そして外食によるジャンクフードの多食。
また、健康補助食品やサプリメント、常に医者通い、薬漬け、夜深し、運動不足などなど、目に見えて不自然な暮らし方をされている方が多いのです。
それらを反省して、食や環境などの暮らし方を改善された方は、みなさん、今までの不調はなんだったんだろうっておっしゃいます。
こうして快調になられた方は、毎年、誰よりも先に風邪を引いていたのが引かなくなり、冷え症が改善され、アレルギー疾患が目に見えて良くなり、慢性病や難病までも医者いらずになります。生活習慣病の最たる癌でさえ消えてなくなることもよくあることです。
国や医療機関は、放射能や、PM2.5が原因だと断定しにくいなどとよくいわれますが、確かに、上記のような暮らし方では放射能を浴びなくてもPM2.5を吸い込まなくても癌になるわけですから、保障問題がからむようなことですから、断定するには二の足を踏むというのも納得はできます。まぁ、国の思うツボとなってしまうのです。
だからこそ、日々の暮らしの秩序を最低限でも正して、病気にならないような備えが必要だと思います。
お塩を自然塩にしませんか?調味料から化学添加物を取り除きませんか?砂糖などの糖類の摂取の仕方を考え直してみませんか?糖質は基本、主にはご飯から(できれば未精製)摂るようにすることが主食の意味です。パンや麺類が多くなっていませんか?毎日果物を食べていませんか?
改善する糸口はいくらでもあります。
出来るところから取り組んで見られると、きっと心身がその答えを出してくれますよ。(←糖尿病患者さんの before and after です)
それからそれから、放射能もしかり、PM2.5もしかり、花粉症もしかり。
予防が大切。それは食改善はもちろんのことだけど、マスクをするとか、鼻を洗うとか、出来ることはいろいろあるから、まずはやってみてね。