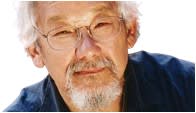久しぶりにグラントの話しをします。ここでは医学、理工学系の場合に話しを限定します。以前にも言いましたが、グラントには様々な種類があります。大きく分けると、
オペレーティング・グラント(以下OPと略す)
プログラム・グラント(同PR)
エクイプメント・グラント(同EQ)
メインテナンス・グラント(同MT)
パーソナルアワード(同PA)
といったところでしょうか。もちろんこの他にも特別な目的に標的を絞ったグラントがNIH(米国)やCIHR(カナダ)などから出ていますが、ここでは触れません。
OPとPRは、消耗品や人件費を主体としたグラントで通常3年から5年の期間に年間500万円から3000万円ぐらいまでの予算が計上できます。OPは主に一人の研究者が中心になって行う研究ですが、PRは複数の研究者が同一の研究目的に向けて共同研究を行うことで何らかの相乗効果が生まれることが期待される場合に適しています。PRは複数の研究者によるOPをまとめたものと見ることができます。研究者同士が互いに相補的に働いて、それぞれ一人で行うよりもより生産性が高くなるのであればいいのですが、往々にしてグループの中の一人が論文発表が好ましい結果でなく、他の人の足を引っ張りかねない状況が生まれますので、注意が必要です。逆にジュニアな研究者にとっては、経験がありすでにプロダクティブなグループに加わることで、グラント獲得のチャンスが増すというケースも当然生じますので、グループに入ることはプラスに考えたほうが懸命でしょう。予算の額に開きがあるのは、やはり人件費に対する考慮があるからです。すなわち、ジュニアな研究者は、新人のテクニシャンやポスドクを取るわけでしょうから、人件費は最小限に抑えられます。逆に、20年、30年継続してグラントを獲得している研究者には、長い間プロジェクトに貢献してきたテクニシャンがいるでしょうから、そう言う場合には人件費は必要なだけ支給される可能性が高くなるわけです。まあ他にも様々なファクターが関与してきますから、一概には言えませんが、予算の勾配はグラント獲得年数に比例してくるという法則はある程度あります。すなわち、ジュニアな方は最初から高額を要求しても、削られるか、悪くすると採点時にマイナスに働く可能性がありますから、予算の妥当性を十分に考慮することを薦めます。
EQは文字通り、装置の購入のみに当てられるグラントで、通常複数の研究者(多いほうが説得力がある)が利用することを前提にしています。ですから、「自分の研究に必要だから購入したい」という趣旨の申請書では、他の申請書と較べられたとき、それがどんなに重要な目的であっても、説得力に差が出ます。高額な装置が、学部全体、大学全体でどのように利用されるか、さらには学外の利用者も考慮されているか、などの項目がチェックされるでしょう。もちろん、これはケース・バイ・ケースで、きわめて特殊な装置は専門家のみで利用するとしても、科学的妥当性がしかっりしていて、その研究者の生産性が高ければ、通る可能性は十分あります。
MTは、既存の装置の保守・運転目的に必要は経費を計上できるグラントです。大型装置の保守契約などが該当します。この場合も、上記のEQの場合と同じで、できるだけ多くの研究者が、時間ロスのない運転を必要としていることを明白にし、そのためにMTが必要であることを説くことが、カギになります。
最後のPAは、科学者の給与に当てられるもので、5年間が普通です。勤務期間によって、何段階かのアワードがあるのが普通ですが、いづれの場合も直接研究者自身に入ってくるのではなく、グラントは大学や研究所に帰属されます。そして、給与の全額もしくは一部がこの予算を用いて支払われることになるので、得をするのは研究機関のほうである、という見方もできます。アメリカの場合、自分の給料はグラントから80%-100%支払うのが一般化してきていますが、こういうアワードがつけば、自分のOPへの負担も減るので研究室にとってもプラスになります。カナダの場合は、PAを取っていると、研究に専念するという大儀名文のため、ティーチングの責任を減らしてもらえたり、獲得金額に対して何割かを学内グラントとして支給する機関もあるようです。もちろん、こういうアワードは研究者自身のCVには大きなプラスになります。
以上グラントの話しでした。参考になれば幸いです。質問や意見はコメントでどうぞ。すべてにお答えできるかどうかは分かりませんが、できるだけお答えします。
オペレーティング・グラント(以下OPと略す)
プログラム・グラント(同PR)
エクイプメント・グラント(同EQ)
メインテナンス・グラント(同MT)
パーソナルアワード(同PA)
といったところでしょうか。もちろんこの他にも特別な目的に標的を絞ったグラントがNIH(米国)やCIHR(カナダ)などから出ていますが、ここでは触れません。
OPとPRは、消耗品や人件費を主体としたグラントで通常3年から5年の期間に年間500万円から3000万円ぐらいまでの予算が計上できます。OPは主に一人の研究者が中心になって行う研究ですが、PRは複数の研究者が同一の研究目的に向けて共同研究を行うことで何らかの相乗効果が生まれることが期待される場合に適しています。PRは複数の研究者によるOPをまとめたものと見ることができます。研究者同士が互いに相補的に働いて、それぞれ一人で行うよりもより生産性が高くなるのであればいいのですが、往々にしてグループの中の一人が論文発表が好ましい結果でなく、他の人の足を引っ張りかねない状況が生まれますので、注意が必要です。逆にジュニアな研究者にとっては、経験がありすでにプロダクティブなグループに加わることで、グラント獲得のチャンスが増すというケースも当然生じますので、グループに入ることはプラスに考えたほうが懸命でしょう。予算の額に開きがあるのは、やはり人件費に対する考慮があるからです。すなわち、ジュニアな研究者は、新人のテクニシャンやポスドクを取るわけでしょうから、人件費は最小限に抑えられます。逆に、20年、30年継続してグラントを獲得している研究者には、長い間プロジェクトに貢献してきたテクニシャンがいるでしょうから、そう言う場合には人件費は必要なだけ支給される可能性が高くなるわけです。まあ他にも様々なファクターが関与してきますから、一概には言えませんが、予算の勾配はグラント獲得年数に比例してくるという法則はある程度あります。すなわち、ジュニアな方は最初から高額を要求しても、削られるか、悪くすると採点時にマイナスに働く可能性がありますから、予算の妥当性を十分に考慮することを薦めます。
EQは文字通り、装置の購入のみに当てられるグラントで、通常複数の研究者(多いほうが説得力がある)が利用することを前提にしています。ですから、「自分の研究に必要だから購入したい」という趣旨の申請書では、他の申請書と較べられたとき、それがどんなに重要な目的であっても、説得力に差が出ます。高額な装置が、学部全体、大学全体でどのように利用されるか、さらには学外の利用者も考慮されているか、などの項目がチェックされるでしょう。もちろん、これはケース・バイ・ケースで、きわめて特殊な装置は専門家のみで利用するとしても、科学的妥当性がしかっりしていて、その研究者の生産性が高ければ、通る可能性は十分あります。
MTは、既存の装置の保守・運転目的に必要は経費を計上できるグラントです。大型装置の保守契約などが該当します。この場合も、上記のEQの場合と同じで、できるだけ多くの研究者が、時間ロスのない運転を必要としていることを明白にし、そのためにMTが必要であることを説くことが、カギになります。
最後のPAは、科学者の給与に当てられるもので、5年間が普通です。勤務期間によって、何段階かのアワードがあるのが普通ですが、いづれの場合も直接研究者自身に入ってくるのではなく、グラントは大学や研究所に帰属されます。そして、給与の全額もしくは一部がこの予算を用いて支払われることになるので、得をするのは研究機関のほうである、という見方もできます。アメリカの場合、自分の給料はグラントから80%-100%支払うのが一般化してきていますが、こういうアワードがつけば、自分のOPへの負担も減るので研究室にとってもプラスになります。カナダの場合は、PAを取っていると、研究に専念するという大儀名文のため、ティーチングの責任を減らしてもらえたり、獲得金額に対して何割かを学内グラントとして支給する機関もあるようです。もちろん、こういうアワードは研究者自身のCVには大きなプラスになります。
以上グラントの話しでした。参考になれば幸いです。質問や意見はコメントでどうぞ。すべてにお答えできるかどうかは分かりませんが、できるだけお答えします。