この人の声を聴いたのは、このアルパム以来。
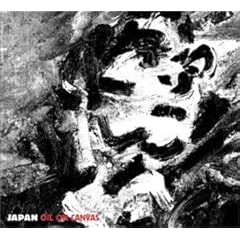
ゴーストでは、ここまで音を削るか、と思うほどのバックで歌うD.シルヴィアンの声の魅力には驚きました。
Japanを聴いてから、もう20年近く経つと思います。
その間、坂本龍一との共演や、R.フリップとの共演など、惹かれたものもありましたが、なんとなく聴かずじまいで今に至っています。
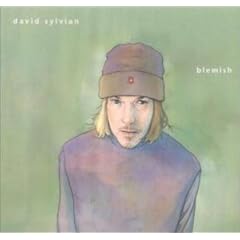
[Blemish]
1. Blemish
2. The Good Son
3. The Only Daughter
4. The Heart Knows Better
5. She Is Not
6. Late Night Shopping
7. How Little We Need to Be Happy
8. A Fire in the Forest
このアルバムに興味を持ったのは、実はディレク・ベリイの追悼盤をHMVで見つけたため。
これも随分前の事になりますが、この遺作、D.シルヴィアンとの共演のアウトテイクとのこと。「へー、ディレク・ベリイとねも共演していたんだ」ということで、興味がムクムク湧いてきて、行き当たったのがBlemish。以前、ジャケットを見て気になっていたアルバムが、そのアルバムでした。
D.ベリイとの共演は、3曲しか入っていませんでした。ベリイのギターをバックに、ボソボソとD.シルビアンのボーカルが乗っかってきます。解説によると、即興のギターに、即興で詩を付けて録音したとか。
もし、それが本当なら、とても幸運に恵まれたのでしょう。
D.ベリイのギターとD.シルヴィアンのボーカルがとても良くあっています。
D.ベリイとの共演の他の作品も、不要な音は削り取り、最小の音だけを残した音作り。
改めて、声に力のある人だなと感じました。
ただ、やはり、どこか物悲しいものを感じてしまいます。
ジャケットを開くと、スーパーマーケットからの帰りでしょうか。雪道をカートを押しながら歩くD.シルヴィアンの後ろ姿が、ジャケットと同じトーンのイラストで描かれています。
マーケットでの買い物というのが、とても家庭的な雰囲気を持っているのですが、寒そうな雪道を一人歩き去って行くその姿は、物悲しいものを感じてしまいます。
アルバム全体が、そんなトーンで仕上がっているような気がします。
声のイメージが強いだけに、全部を一人で引き受けてしまう、ある種の「厳しさ」が目立ちます。孤高のボーカリスト、ちょっとばかりそんな印象を受けてしまいます。
アメリカのニューイングランドに、家族と暮らし、新しいスタジオ/レーベルを興しての第一段という事で、最小の構成からスタートしたのでしょうか。
それならばいいのですが・・・
同時に聴いたNine Horsesのミニアルバム。
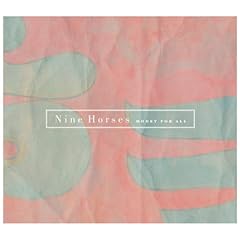
Wonderful WorldやBirds Sing for Their Livesなど、こちらでは、D.シルヴィアンの歌声が日だまりのような心地よさに充ちています。
バートン・フリードマン、スティーブ・ジャンセンと組んだユニット。
ソロにはない、心地よさを感じたのでしょうか。
今後、Blemishをきっかけに、Nine Horsesとしての活動に移って行くのでしょうか。
魅力的な声の持ち主なので、今後どんどん活躍してもらいたいものです。
その活動をサポートする、良き仲間が必要なのかもしれないですね、この人には。
----
にほんブログ村へ登録しました。
 ←この記事が気に入ったらクリックしてください
←この記事が気に入ったらクリックしてください
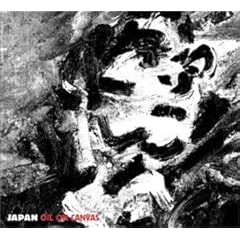
ゴーストでは、ここまで音を削るか、と思うほどのバックで歌うD.シルヴィアンの声の魅力には驚きました。
Japanを聴いてから、もう20年近く経つと思います。
その間、坂本龍一との共演や、R.フリップとの共演など、惹かれたものもありましたが、なんとなく聴かずじまいで今に至っています。
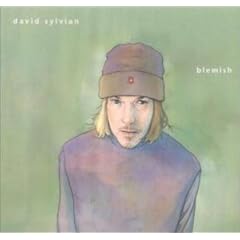
[Blemish]
1. Blemish
2. The Good Son
3. The Only Daughter
4. The Heart Knows Better
5. She Is Not
6. Late Night Shopping
7. How Little We Need to Be Happy
8. A Fire in the Forest
このアルバムに興味を持ったのは、実はディレク・ベリイの追悼盤をHMVで見つけたため。
これも随分前の事になりますが、この遺作、D.シルヴィアンとの共演のアウトテイクとのこと。「へー、ディレク・ベリイとねも共演していたんだ」ということで、興味がムクムク湧いてきて、行き当たったのがBlemish。以前、ジャケットを見て気になっていたアルバムが、そのアルバムでした。
D.ベリイとの共演は、3曲しか入っていませんでした。ベリイのギターをバックに、ボソボソとD.シルビアンのボーカルが乗っかってきます。解説によると、即興のギターに、即興で詩を付けて録音したとか。
もし、それが本当なら、とても幸運に恵まれたのでしょう。
D.ベリイのギターとD.シルヴィアンのボーカルがとても良くあっています。
D.ベリイとの共演の他の作品も、不要な音は削り取り、最小の音だけを残した音作り。
改めて、声に力のある人だなと感じました。
ただ、やはり、どこか物悲しいものを感じてしまいます。
ジャケットを開くと、スーパーマーケットからの帰りでしょうか。雪道をカートを押しながら歩くD.シルヴィアンの後ろ姿が、ジャケットと同じトーンのイラストで描かれています。
マーケットでの買い物というのが、とても家庭的な雰囲気を持っているのですが、寒そうな雪道を一人歩き去って行くその姿は、物悲しいものを感じてしまいます。
アルバム全体が、そんなトーンで仕上がっているような気がします。
声のイメージが強いだけに、全部を一人で引き受けてしまう、ある種の「厳しさ」が目立ちます。孤高のボーカリスト、ちょっとばかりそんな印象を受けてしまいます。
アメリカのニューイングランドに、家族と暮らし、新しいスタジオ/レーベルを興しての第一段という事で、最小の構成からスタートしたのでしょうか。
それならばいいのですが・・・
同時に聴いたNine Horsesのミニアルバム。
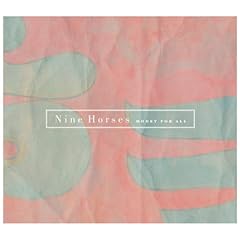
Wonderful WorldやBirds Sing for Their Livesなど、こちらでは、D.シルヴィアンの歌声が日だまりのような心地よさに充ちています。
バートン・フリードマン、スティーブ・ジャンセンと組んだユニット。
ソロにはない、心地よさを感じたのでしょうか。
今後、Blemishをきっかけに、Nine Horsesとしての活動に移って行くのでしょうか。
魅力的な声の持ち主なので、今後どんどん活躍してもらいたいものです。
その活動をサポートする、良き仲間が必要なのかもしれないですね、この人には。
----
にほんブログ村へ登録しました。






























