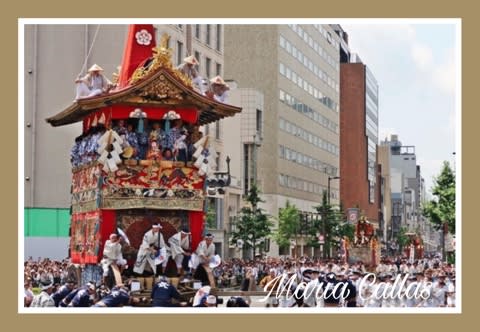全国的には8月15日が主流ですが、東京では7月15日がお盆になりますね😊
お盆は正式には「盂蘭盆会」と言う仏教行事の一つです。
もともとは盂蘭盆経の説話に由来するのですが、お釈迦様の弟子の弟子のひとり「目連尊者」が初めて神通力を得た際に、餓鬼道に落ち餓鬼に苦しめられる亡き母のためにご飯を差し出したところ、母の罪が重すぎて、ご飯🍚は口に入れる前に炭になって食べさせることが出来なかったそうです💦
それをお釈迦様に話すと、「旧暦7月15日に夏安居の修業を終えた修行僧達にごちそうをふるまい心から供養すれば、先祖は三途の苦しみから逃れ、解脱して衣食に困ることはないでしょう」と言われたとか😳
目連尊者がその通りにしたところ、母は餓鬼道から逃れ、無事往生できました❤️

目連尊者はこの慣わしを後々まで残したいとお釈迦様に伝えたところ、「旧暦の7月15日にお盆に食べ物や飲み物を盛り、仏や僧たちに供養すれば、その功徳でたくさんの先祖が苦しみから救われるでしょう」と言われて、これが盂蘭盆会のはじまりとなったようです。
この盂蘭盆会に日本に古来からあった先祖を祀る「御霊祭り」が融合して現在のお盆行事となっていきました🎵
江戸時代には庶民のあいだでもお盆行事が普及していきます。
江戸時代には10代前半頃から商家などに丁稚奉公に出る奉公人がたくさんいて、住み込みで働く彼らもお盆と正月だけは休みを取って実家に帰ることが許されていたのですが、この時期を「藪入り」と呼んでいました。
お盆の藪入りは盆の入りで忙しい7月15日を避けて、7月16日からだったとか。
藪入りには奉公先の主人から衣服や小遣いを与えられて実家に帰っていたそう。家から出て行った人たちが実家に帰ることのできる貴重な時期だったのですね💕
現在もお盆と正月には実家に帰る人がたくさんいますが、江戸時代の風習がまだ続いているのだなぁと思うと、なにやら感慨深いものです😊