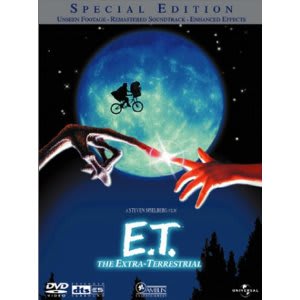
(今回もまた、画像と本文の間にはなんの関係もありません・笑)
ところで、小説本編とはあんまり関係ない話なのですが……天使の図書館と探偵Lの部屋のサイトって、忍者さんのお世話になってます(笑)
でもつい先週、アップロードの方法の仕方が変わってしまったことから、わたしこのやり方がよくわかんなくて、金曜と土曜は司書の部屋を更新できませんでした
ええと今、アルファポリスさんの青春小説大賞に登録してるので、このままサイトをどこも動かせないと、自分的にちょっとなんだかなあwwという気がするんですけど、そんな理由によって向こうは少しの間更新が滞るかもしれません。。。
それと、この天使の図書館、作る直前になるまで、「天使の図書館」というサイト名にするつもりはまったくありませんでした(笑)
単に自分の書いた小説を置いておくまとめ倉庫☆みたいなものだったので、極めてシンプルな素材によって、飾り気のないサイトを簡単に作れればいいな~と最初は思っていたのです。
でも素材の森さんに、「天使素材」っていうジャンル(?)があって、そこで見つけたのが「幻想素材サイト」様だったわけです♪(^^)
そこで、「うおおおッ!!なんてわたし好みッ 」(ジョ○゛ョ風に☆)とか思って作った結果、「全体としてなんか天使っぽい??」と思い、サイト名を天使の図書館にすることにしたという(笑)
」(ジョ○゛ョ風に☆)とか思って作った結果、「全体としてなんか天使っぽい??」と思い、サイト名を天使の図書館にすることにしたという(笑)
まあ、わたしブログの中で時々自分がクリスチャンだって書いてるので、そことの関連から「天使の図書館」なのかなって思われるかもしれないんですけど、宗教的な理由はほとんどないと思います(^^;)
第一、クリスチャンになるずっと前から、天使とか悪魔とか精霊とか、もうそういうのが大好き!! っていう強い傾向みたいのがわたしの中にはあって……たとえば、エヴァンゲリヲンとか青のエクソシストとか、宗教的なこととは分けて好きなので、「創作」と「宗教」っていうのはわたしの中ではイコールで結びついてないんですよ
っていう強い傾向みたいのがわたしの中にはあって……たとえば、エヴァンゲリヲンとか青のエクソシストとか、宗教的なこととは分けて好きなので、「創作」と「宗教」っていうのはわたしの中ではイコールで結びついてないんですよ
ただ、天使とか悪魔って、結局聖書にその起源があるらしいので……そういう意味で面白いなあ♪と思うことは、聖書を読んでいて結構あるかもしれません。
まあわたし、「キリスト教を科学する」であるとか、「科学の観点から見たキリスト教」といった視点も好きですし(ダ・ヴィンチコードも読みましたよ・笑)、キリスト教を批判・非難する報道とかも、かなり冷静に見るタイプの人間です(イスラム教徒から見たキリスト教とか、イスラム教国から見たキリスト教徒とか、そういうのもかなり興味あるので)。
これも結構前のことになるかなって思うんですけど、テレビで「ツールキット遺伝子」のことをやっていたことがありました。
ええと、正直難しすぎてうまく説明できないんですけど(すみません )、その遺伝子が何になるか決まってる遺伝子があって、たとえば進化のある段階で「それは腕になる」というようにその遺伝子が決まっていた場合、翼というものはそれ以外で生えてくることは絶対ないのだそうです。逆にいうと、元を辿ると「腕」にもなれる遺伝子が「翼」になると決定した場合、翼の他に腕というものは絶対生えてこない……つまり、遺伝子学的には「有翼人種」というのは絶対存在しえないということがわかった、ということでした。
)、その遺伝子が何になるか決まってる遺伝子があって、たとえば進化のある段階で「それは腕になる」というようにその遺伝子が決まっていた場合、翼というものはそれ以外で生えてくることは絶対ないのだそうです。逆にいうと、元を辿ると「腕」にもなれる遺伝子が「翼」になると決定した場合、翼の他に腕というものは絶対生えてこない……つまり、遺伝子学的には「有翼人種」というのは絶対存在しえないということがわかった、ということでした。
いやまあ、「ロマンがないなあ☆」って、わたしもその時思ったんですけど(笑)、にも関わらず、旧約聖書では割合早い段階でケルヴィム(天使)のことに触れてるんですよね。遺伝子学的には絶対存在しえない有翼人種……でも、神の前にはそういうものが天的存在としているんですよ、と聖書では語られてるのって、なんだかとても不思議な感じがします♪
↓の本編主人公は、自分の霊的ペット(?)に不遜にもケルビーとか名づけてるんですけど(笑)、ケルヴィムというのは複数形で、単数形はケルブ、だからケルビーという愛称で彼は呼んでいるのだと思われます(^^;)
なんにしても、「おかしな人生」というタイトルのおかしな小説ですが、あと1回で終わる予定なので、最後までおつきあいいただけると嬉しいです♪(^^)
それではまた~!!
おかしな人生~Part.3~
ところで、ケルビーの「食糧」の問題に話を戻したいと思う。
そう……霊的な存在の<彼>にも、「食糧」といったものは確かに存在した。
すなわち、霊的存在には、霊的な「食べもの」が必要だったのである……つまり、ケルビーは人間の負の感情や病いといったものを食べる心獣ともいうべき存在だった。
わたしの話を聞いて、とうとう気が狂ってきたなと思う人もいるに違いないが、これは天地神明に誓って本当のことなのだ。たとえば、ケルビーはわたしからそうした負の感情を日常的に吸いとっていた。そして彼と一緒に長く過ごすうちに――わたしにはだんだんわかってきたことがある。
何故といって、怪我をしてもすぐに治り、普通なら心理的にどう考えても落ちこむだろう場面で……わたしは常に笑い、喜んでいられるようにさえなったのだから!
そのことに気づいたのは最初、重いインフルエンザで寝込んだ時のことだった。前に似た症状に見舞われた時には、病院でもらった薬を飲み、さらに四日ほど臥せっていなくてはならなかったのだが、苦しく咳きこみ、ケルビーの姿さえぼやけるような高熱の中――翌日にはすっきりとわたしは目を覚ましていた。
そして、布団の隅に犬のように丸まっているケルビーのことを見て、わたしは初めて理解した。以前、転んで怪我をした時にすぐ傷がなくなったのも、おそらくはケルビーがしたことに違いない、と……。
わたしは、こんなに素晴らしいことを自分の内にだけ留めておくのはどうかという気がして、ケルビーを自分以外の人間にも「馴れさせる」ことは出来ないものかと考えはじめた。
それで派遣会社に派遣されて、色々な職場で働く傍ら、休日はもっぱら<病院巡り>をするようになったのである。
つまり、どういうことかというと――十階以上も病棟を抱えたような大病院では、それほど人の出入りをチェックされたりはしないものだ。とにかく、見舞いに来たような振りをしてエレベーターに乗り、適当に病棟を見てまわりつつ、ケルビーが自分の「食糧にしたい」と思えるような人間を探すのである。
わたしが思うにはどうも……ケルビーはこの種の嗜好にうるさく、人間的な言い方をすると、どうもグルメな質らしかった。その人間の「精神的苦悩」を吸いとって自分の食糧にしたいと思うこともあるし、またその人を苦しめている「肉体的病い」の苦痛を吸いとって、相手の人間を楽にしてあげることも出来るのだが――ケルビーはどうやら、選り好みが激しいらしい。
たとえばこの場合、ケルビーには人間的基準から見て、容姿の美しい者ばかりを癒そうとするであるとか、清らかさを内に秘めた人間ばかりを癒そうとするらしい……といったようなある種の選考基準といったものはまったくないと言っていい。
わたしが病棟内をなんとなく歩き回っていると、<彼>は本当に気まぐれにある病室へふらっと入っていき、そして戻ってくるのだ。ケルビーはその時、わたしに対してするように患者の顔や体をなめるということはせず、ただ黙ってその者の傍らに数秒佇み、何か「黒い塊」のようなものを口の中へ吸いとるのである。
もちろん、ケルビーの存在が相手に見えることはなく、「黒い塊」といったものもまた、彼の存在同様、わたしにしか見えないものなのだが……。
そうして、何かの不治の病いにかかった人たちを癒すため、わたしは休みの日には市内全域にある大きな病院を渡り歩くようになったというわけなのだ。
三十歳頃にわたしは、とある病院で夜の巡回警備をする仕事に就くようになったと先に書いたが、その理由もまあ、そうした事情が絡んでのことだったと言っていいだろう。
わたしがその病院でしていたのはおもに、電話番と見舞い客や業者の人間の出入りのチェック、それから夜の決まった時間に暗い病棟を見てまわるといったような仕事だったのだが――わたしが来る前まで、何故かその病院には警備員がなかなか居つかなかったという。
「なんかどうも、<あれ>が出るって噂なんだよね。精神病棟のほうで昔、首を吊って自殺した患者ってのがいたらしくて……まあ、ただの噂なんだけどね」
わたしが仕事をする宿直室の隣が、医療事務員たちの休む休憩室になっていて、病院に勤める事務員のひとりが、わたしにそんな話をしていたことがある。
「如月さんはさ、夜中になんか見たり、変な気配を感じたりしたこと、ない?」と、オカルト好きらしい彼に聞かれたこともあったが――わたしが首を横に振ると、その医療事務員の若い男は、がっかりと肩を落としていたっけ。
もっとも、その彼のすぐ隣にケルビーがいて、ケルビーはいつものように白い人差し指を口の中に入れ、首を傾げたりしていたのだけれど……。
このころになるとわたしはもう、「何故ケルビーはわたしにしか見えないのか」とか、「彼の存在理由は一体何か」とか、「いつか宇宙からお迎えが来たりしたら、わたしはどれほど寂しい思いをせねばならないか」といったようなことについては、ほとんど考えないようになっていた。
夕方、仕事帰りのサラリーマンやOL、学校帰りらしい学生たちで満杯の電車に揺られながら、わたしは職場へと急ぐ。だが、運よく座席に座れた時など――どんなに電車が混んでいようとも、わたしの隣に座ろうとする人間だけは絶対に現われない。
何故かというと、そこにはケルビーがどこかかしこまったようにちょこんと座っており、彼は時々、近くの座席に座る人間の物真似をして、わたしを笑わせようとすることさえあったからだ。
そうなのである。ケルビーはわたしが思っていた以上に実は知能が高く、顔の中に人間が考えるような形での<眼>こそないものの……彼はきちんと周囲のものが見え、さらにはわたしを笑わせるためのユーモアセンスまで、きちんと持っているのである。
もっともこれは、出会った最初の時からそうだったというわけではない。わたしが思うにはケルビーは、わたしがいつも部屋でつけっぱなしにしているテレビなどを見て、わたしの「趣味/嗜好」といったものを除々に学習していったのではないかと思われる節がある。
なんにしてもこんなふうにして、出会って数ヶ月が過ぎる頃には――わたしにとってケルビーはなくてはならない存在になっていたといっていい。
わたしの人生を知っている人はもしかしたら、友達やガールフレンドのひとりもいない、とても寂しい人生を送った人間だと、そんなふうに思ったかもしれないが……わたしの人生は本当に、ケルビーのお陰で充実した、楽しいものだったといっていいと思う。
実際のところ、わたしはその気にさえなれば、かなり愛想のよい質の人間だったし、そういう意味で友達は作る気にさえなれば、いつも何人か出来てはいたのだ。それにガールフレンドというか、恋人についても、持とうと思えば持てる機会は何度かあった。
だが、そのたびにケルビーが、わたしが<彼>以外の誰かと仲良くすることに対して、快く思っていないということが、わたしにははっきりわかっていたのである。友達についても、それが男ならさほどでもないにも関わらず、相手が女性ということになると――ケルビーは時々すねて、部屋の片隅にうずくまり、三日間そのままの姿勢で微動だにしないということさえあった。
「わかったよ。もうあの子とは二度と会わないし、電話もメールもしない。それでいいんだろ?」
わたしがそう言うが早いか、ケルビーは再びむくりと起き上がり、わたしに仲直りの不気味な頬ずりをしてきたものだった。
「でもなあ、そうなると俺、このまま一生結婚も出来ないってことだよな。あんまり考えたくないけど……」
そう言ってわたしはこの時、ケルビーの姿を頭の上から足の爪先まで、じっと見つめ直した。前にも一度述べたとおり、ケルビーの姿形からは、雌雄がわかるような特徴は一切見られない。それと、<彼>は人間から「黒い塊」を吸収してはいるが、それはいわゆる糞尿として排泄器官から出てくるということもないのだ。
「おまえさ、もしかしてメスだったりするのかな。俺はてっきりおまえが男だとばっかり思ってたんだけど。胸板なんか鉄板みたいだし、腕のあたりも結構筋肉がついてるもんな。しかも恐竜みたいな尾まであるし……」
わたしがそう言うと、ケルビーはまるでボディビルダーのようにポーズを決めはじめ、最後には1メートルほどもある尾を、左右に振り回すということまでした。
それから、「イヤン、ばかん☆」というように床の上に横になり、気味の悪いしなを作りはじめる。しかも、両方の手で大きなおっぱいを形作ると、片手でチュッとキスを風に飛ばすということまでしてきた。
「あ~もう、わかったよ!!とにかく、この件はいったん棚上げな。おまえは俺がおまえの他に強い関心を示す存在のことが気に入らないってことだろ?まあ、その点でいくとすれば、俺にとって一番大切なのはやっぱりケルビー、おまえなんだよ」
わたしがそう言うと、<彼>(もしかしたら彼女?)は、顔を輝かせて(いるようにわたしには見えた)、わたしの顔を真っ赤な舌でベロベロとなめた……そう、ケルビーが日常的にわたしの体の一部をなめることで、おそらくわたしの精神的内部には例の「黒い塊」が<溜まる>ということはほとんどなかったに違いない。
つまりそれは、極めて露骨な言い方をするとしたら、女性を犯したいといったような欲情さえも、ケルビーが日常的に吸いとっているので、そうした欲望が高まるあまり、どうしてもそうしなくてはならないといった衝動も、わたしの中では衰えていたということだった。
そのせいかどうか、わたしはケルビーさえいれば、そう無理して結婚など望まなくてもよいと考えるようになっていたし――そして事実、女性を口説こうとすることもなければ、いわゆる婚活をしようという考えも、のちにはまるで頭に浮かばないまでになっていた。
第一、なんとかケルビーを説き伏せて結婚したところで……わたしにしか見えないケルビーという存在を、相手の女性にどう納得させたらいいのか、わたしにはまるでわからなかった。それどころか、結婚して二、三年のうちはともかくとしても、そのあとはおそらく、わたしは妻という存在よりもケルビーのほうが大切になっているだろうと、はっきり予感されてもいたのだ。
それとも、子供が二人も出来るころには、いつの間にかわたしの目にもケルビーの存在が見えなくなる……そんなことさえ起きかねない可能性だってある。あるいは、彼がわたしに失望するあまり、わたしの元を去って別の惑星へいってしまうといったような可能性も。
そんなわけで結局、わたしは結婚ということについては、人生のある段階で完全に諦めることにした。
そしてケルビーとふたり、結婚などということはまるで問題にならない、より実り多い、魂の充実した人生を生きることを選択したのだ。
それともうひとつ、ケルビーについて書き記しておきたいことがある。
わたしが特定の女性と懇意にするといった態度をとり、ケルビーがへそを曲げるといったような日の夜には――わたしは必ず、信じられないくらいの美女が自分の横にいて、口も聞けなくなるといったタイプの夢を見た。
彼女は黒い髪に、長い睫毛に縁取られた大きな瞳をしており、その肌は輝くような真珠色だった。わたしはハリウッド女優のような女性が、何故自分のすぐ横で慕わしげな目で自分を見ているのかが理解できず……彼女が服を脱ぎはじめても、それを見てはいけないと思うところで、必ず目が醒めるのだった。
おそらく人間は、自分が体験したことのないことは、夢でも見ることが出来ないものなのだろう。わたしはその後も、ほんのたまに彼女のことを夢に見るたび――こう思ったものだった。夢の中で彼女と寝るためにだけ、現実の世界で女性と関係を持ってみてはどうだろうか、と。
つまり、<彼女>が服を脱ぐ次の段階へわたしが進むためには、それ以上のことを現実の世界でわたしが知っていなくてはならないと思ったからだ。そう……次こそは彼女がキスでもしてくれないかと願いつつ、(ここで目よ醒めるな、ここで目よ醒めるな)と呪文を唱え続けた結果として、わたしに見ることが許されたもの――それが<彼女>の上半身裸になった豊満な乳房だったかもしれない。
だが残念なことに、わたしが夢の中で彼女に触れるということはついぞなく、わたしは自分の人生を終えるということになってしまった。
>>続く……。
ところで、小説本編とはあんまり関係ない話なのですが……天使の図書館と探偵Lの部屋のサイトって、忍者さんのお世話になってます(笑)
でもつい先週、アップロードの方法の仕方が変わってしまったことから、わたしこのやり方がよくわかんなくて、金曜と土曜は司書の部屋を更新できませんでした

ええと今、アルファポリスさんの青春小説大賞に登録してるので、このままサイトをどこも動かせないと、自分的にちょっとなんだかなあwwという気がするんですけど、そんな理由によって向こうは少しの間更新が滞るかもしれません。。。
それと、この天使の図書館、作る直前になるまで、「天使の図書館」というサイト名にするつもりはまったくありませんでした(笑)
単に自分の書いた小説を置いておくまとめ倉庫☆みたいなものだったので、極めてシンプルな素材によって、飾り気のないサイトを簡単に作れればいいな~と最初は思っていたのです。
でも素材の森さんに、「天使素材」っていうジャンル(?)があって、そこで見つけたのが「幻想素材サイト」様だったわけです♪(^^)
そこで、「うおおおッ!!なんてわたし好みッ
 」(ジョ○゛ョ風に☆)とか思って作った結果、「全体としてなんか天使っぽい??」と思い、サイト名を天使の図書館にすることにしたという(笑)
」(ジョ○゛ョ風に☆)とか思って作った結果、「全体としてなんか天使っぽい??」と思い、サイト名を天使の図書館にすることにしたという(笑)まあ、わたしブログの中で時々自分がクリスチャンだって書いてるので、そことの関連から「天使の図書館」なのかなって思われるかもしれないんですけど、宗教的な理由はほとんどないと思います(^^;)
第一、クリスチャンになるずっと前から、天使とか悪魔とか精霊とか、もうそういうのが大好き!!
 っていう強い傾向みたいのがわたしの中にはあって……たとえば、エヴァンゲリヲンとか青のエクソシストとか、宗教的なこととは分けて好きなので、「創作」と「宗教」っていうのはわたしの中ではイコールで結びついてないんですよ
っていう強い傾向みたいのがわたしの中にはあって……たとえば、エヴァンゲリヲンとか青のエクソシストとか、宗教的なこととは分けて好きなので、「創作」と「宗教」っていうのはわたしの中ではイコールで結びついてないんですよ
ただ、天使とか悪魔って、結局聖書にその起源があるらしいので……そういう意味で面白いなあ♪と思うことは、聖書を読んでいて結構あるかもしれません。
まあわたし、「キリスト教を科学する」であるとか、「科学の観点から見たキリスト教」といった視点も好きですし(ダ・ヴィンチコードも読みましたよ・笑)、キリスト教を批判・非難する報道とかも、かなり冷静に見るタイプの人間です(イスラム教徒から見たキリスト教とか、イスラム教国から見たキリスト教徒とか、そういうのもかなり興味あるので)。
これも結構前のことになるかなって思うんですけど、テレビで「ツールキット遺伝子」のことをやっていたことがありました。
ええと、正直難しすぎてうまく説明できないんですけど(すみません
 )、その遺伝子が何になるか決まってる遺伝子があって、たとえば進化のある段階で「それは腕になる」というようにその遺伝子が決まっていた場合、翼というものはそれ以外で生えてくることは絶対ないのだそうです。逆にいうと、元を辿ると「腕」にもなれる遺伝子が「翼」になると決定した場合、翼の他に腕というものは絶対生えてこない……つまり、遺伝子学的には「有翼人種」というのは絶対存在しえないということがわかった、ということでした。
)、その遺伝子が何になるか決まってる遺伝子があって、たとえば進化のある段階で「それは腕になる」というようにその遺伝子が決まっていた場合、翼というものはそれ以外で生えてくることは絶対ないのだそうです。逆にいうと、元を辿ると「腕」にもなれる遺伝子が「翼」になると決定した場合、翼の他に腕というものは絶対生えてこない……つまり、遺伝子学的には「有翼人種」というのは絶対存在しえないということがわかった、ということでした。いやまあ、「ロマンがないなあ☆」って、わたしもその時思ったんですけど(笑)、にも関わらず、旧約聖書では割合早い段階でケルヴィム(天使)のことに触れてるんですよね。遺伝子学的には絶対存在しえない有翼人種……でも、神の前にはそういうものが天的存在としているんですよ、と聖書では語られてるのって、なんだかとても不思議な感じがします♪
↓の本編主人公は、自分の霊的ペット(?)に不遜にもケルビーとか名づけてるんですけど(笑)、ケルヴィムというのは複数形で、単数形はケルブ、だからケルビーという愛称で彼は呼んでいるのだと思われます(^^;)
なんにしても、「おかしな人生」というタイトルのおかしな小説ですが、あと1回で終わる予定なので、最後までおつきあいいただけると嬉しいです♪(^^)
それではまた~!!
おかしな人生~Part.3~
ところで、ケルビーの「食糧」の問題に話を戻したいと思う。
そう……霊的な存在の<彼>にも、「食糧」といったものは確かに存在した。
すなわち、霊的存在には、霊的な「食べもの」が必要だったのである……つまり、ケルビーは人間の負の感情や病いといったものを食べる心獣ともいうべき存在だった。
わたしの話を聞いて、とうとう気が狂ってきたなと思う人もいるに違いないが、これは天地神明に誓って本当のことなのだ。たとえば、ケルビーはわたしからそうした負の感情を日常的に吸いとっていた。そして彼と一緒に長く過ごすうちに――わたしにはだんだんわかってきたことがある。
何故といって、怪我をしてもすぐに治り、普通なら心理的にどう考えても落ちこむだろう場面で……わたしは常に笑い、喜んでいられるようにさえなったのだから!
そのことに気づいたのは最初、重いインフルエンザで寝込んだ時のことだった。前に似た症状に見舞われた時には、病院でもらった薬を飲み、さらに四日ほど臥せっていなくてはならなかったのだが、苦しく咳きこみ、ケルビーの姿さえぼやけるような高熱の中――翌日にはすっきりとわたしは目を覚ましていた。
そして、布団の隅に犬のように丸まっているケルビーのことを見て、わたしは初めて理解した。以前、転んで怪我をした時にすぐ傷がなくなったのも、おそらくはケルビーがしたことに違いない、と……。
わたしは、こんなに素晴らしいことを自分の内にだけ留めておくのはどうかという気がして、ケルビーを自分以外の人間にも「馴れさせる」ことは出来ないものかと考えはじめた。
それで派遣会社に派遣されて、色々な職場で働く傍ら、休日はもっぱら<病院巡り>をするようになったのである。
つまり、どういうことかというと――十階以上も病棟を抱えたような大病院では、それほど人の出入りをチェックされたりはしないものだ。とにかく、見舞いに来たような振りをしてエレベーターに乗り、適当に病棟を見てまわりつつ、ケルビーが自分の「食糧にしたい」と思えるような人間を探すのである。
わたしが思うにはどうも……ケルビーはこの種の嗜好にうるさく、人間的な言い方をすると、どうもグルメな質らしかった。その人間の「精神的苦悩」を吸いとって自分の食糧にしたいと思うこともあるし、またその人を苦しめている「肉体的病い」の苦痛を吸いとって、相手の人間を楽にしてあげることも出来るのだが――ケルビーはどうやら、選り好みが激しいらしい。
たとえばこの場合、ケルビーには人間的基準から見て、容姿の美しい者ばかりを癒そうとするであるとか、清らかさを内に秘めた人間ばかりを癒そうとするらしい……といったようなある種の選考基準といったものはまったくないと言っていい。
わたしが病棟内をなんとなく歩き回っていると、<彼>は本当に気まぐれにある病室へふらっと入っていき、そして戻ってくるのだ。ケルビーはその時、わたしに対してするように患者の顔や体をなめるということはせず、ただ黙ってその者の傍らに数秒佇み、何か「黒い塊」のようなものを口の中へ吸いとるのである。
もちろん、ケルビーの存在が相手に見えることはなく、「黒い塊」といったものもまた、彼の存在同様、わたしにしか見えないものなのだが……。
そうして、何かの不治の病いにかかった人たちを癒すため、わたしは休みの日には市内全域にある大きな病院を渡り歩くようになったというわけなのだ。
三十歳頃にわたしは、とある病院で夜の巡回警備をする仕事に就くようになったと先に書いたが、その理由もまあ、そうした事情が絡んでのことだったと言っていいだろう。
わたしがその病院でしていたのはおもに、電話番と見舞い客や業者の人間の出入りのチェック、それから夜の決まった時間に暗い病棟を見てまわるといったような仕事だったのだが――わたしが来る前まで、何故かその病院には警備員がなかなか居つかなかったという。
「なんかどうも、<あれ>が出るって噂なんだよね。精神病棟のほうで昔、首を吊って自殺した患者ってのがいたらしくて……まあ、ただの噂なんだけどね」
わたしが仕事をする宿直室の隣が、医療事務員たちの休む休憩室になっていて、病院に勤める事務員のひとりが、わたしにそんな話をしていたことがある。
「如月さんはさ、夜中になんか見たり、変な気配を感じたりしたこと、ない?」と、オカルト好きらしい彼に聞かれたこともあったが――わたしが首を横に振ると、その医療事務員の若い男は、がっかりと肩を落としていたっけ。
もっとも、その彼のすぐ隣にケルビーがいて、ケルビーはいつものように白い人差し指を口の中に入れ、首を傾げたりしていたのだけれど……。
このころになるとわたしはもう、「何故ケルビーはわたしにしか見えないのか」とか、「彼の存在理由は一体何か」とか、「いつか宇宙からお迎えが来たりしたら、わたしはどれほど寂しい思いをせねばならないか」といったようなことについては、ほとんど考えないようになっていた。
夕方、仕事帰りのサラリーマンやOL、学校帰りらしい学生たちで満杯の電車に揺られながら、わたしは職場へと急ぐ。だが、運よく座席に座れた時など――どんなに電車が混んでいようとも、わたしの隣に座ろうとする人間だけは絶対に現われない。
何故かというと、そこにはケルビーがどこかかしこまったようにちょこんと座っており、彼は時々、近くの座席に座る人間の物真似をして、わたしを笑わせようとすることさえあったからだ。
そうなのである。ケルビーはわたしが思っていた以上に実は知能が高く、顔の中に人間が考えるような形での<眼>こそないものの……彼はきちんと周囲のものが見え、さらにはわたしを笑わせるためのユーモアセンスまで、きちんと持っているのである。
もっともこれは、出会った最初の時からそうだったというわけではない。わたしが思うにはケルビーは、わたしがいつも部屋でつけっぱなしにしているテレビなどを見て、わたしの「趣味/嗜好」といったものを除々に学習していったのではないかと思われる節がある。
なんにしてもこんなふうにして、出会って数ヶ月が過ぎる頃には――わたしにとってケルビーはなくてはならない存在になっていたといっていい。
わたしの人生を知っている人はもしかしたら、友達やガールフレンドのひとりもいない、とても寂しい人生を送った人間だと、そんなふうに思ったかもしれないが……わたしの人生は本当に、ケルビーのお陰で充実した、楽しいものだったといっていいと思う。
実際のところ、わたしはその気にさえなれば、かなり愛想のよい質の人間だったし、そういう意味で友達は作る気にさえなれば、いつも何人か出来てはいたのだ。それにガールフレンドというか、恋人についても、持とうと思えば持てる機会は何度かあった。
だが、そのたびにケルビーが、わたしが<彼>以外の誰かと仲良くすることに対して、快く思っていないということが、わたしにははっきりわかっていたのである。友達についても、それが男ならさほどでもないにも関わらず、相手が女性ということになると――ケルビーは時々すねて、部屋の片隅にうずくまり、三日間そのままの姿勢で微動だにしないということさえあった。
「わかったよ。もうあの子とは二度と会わないし、電話もメールもしない。それでいいんだろ?」
わたしがそう言うが早いか、ケルビーは再びむくりと起き上がり、わたしに仲直りの不気味な頬ずりをしてきたものだった。
「でもなあ、そうなると俺、このまま一生結婚も出来ないってことだよな。あんまり考えたくないけど……」
そう言ってわたしはこの時、ケルビーの姿を頭の上から足の爪先まで、じっと見つめ直した。前にも一度述べたとおり、ケルビーの姿形からは、雌雄がわかるような特徴は一切見られない。それと、<彼>は人間から「黒い塊」を吸収してはいるが、それはいわゆる糞尿として排泄器官から出てくるということもないのだ。
「おまえさ、もしかしてメスだったりするのかな。俺はてっきりおまえが男だとばっかり思ってたんだけど。胸板なんか鉄板みたいだし、腕のあたりも結構筋肉がついてるもんな。しかも恐竜みたいな尾まであるし……」
わたしがそう言うと、ケルビーはまるでボディビルダーのようにポーズを決めはじめ、最後には1メートルほどもある尾を、左右に振り回すということまでした。
それから、「イヤン、ばかん☆」というように床の上に横になり、気味の悪いしなを作りはじめる。しかも、両方の手で大きなおっぱいを形作ると、片手でチュッとキスを風に飛ばすということまでしてきた。
「あ~もう、わかったよ!!とにかく、この件はいったん棚上げな。おまえは俺がおまえの他に強い関心を示す存在のことが気に入らないってことだろ?まあ、その点でいくとすれば、俺にとって一番大切なのはやっぱりケルビー、おまえなんだよ」
わたしがそう言うと、<彼>(もしかしたら彼女?)は、顔を輝かせて(いるようにわたしには見えた)、わたしの顔を真っ赤な舌でベロベロとなめた……そう、ケルビーが日常的にわたしの体の一部をなめることで、おそらくわたしの精神的内部には例の「黒い塊」が<溜まる>ということはほとんどなかったに違いない。
つまりそれは、極めて露骨な言い方をするとしたら、女性を犯したいといったような欲情さえも、ケルビーが日常的に吸いとっているので、そうした欲望が高まるあまり、どうしてもそうしなくてはならないといった衝動も、わたしの中では衰えていたということだった。
そのせいかどうか、わたしはケルビーさえいれば、そう無理して結婚など望まなくてもよいと考えるようになっていたし――そして事実、女性を口説こうとすることもなければ、いわゆる婚活をしようという考えも、のちにはまるで頭に浮かばないまでになっていた。
第一、なんとかケルビーを説き伏せて結婚したところで……わたしにしか見えないケルビーという存在を、相手の女性にどう納得させたらいいのか、わたしにはまるでわからなかった。それどころか、結婚して二、三年のうちはともかくとしても、そのあとはおそらく、わたしは妻という存在よりもケルビーのほうが大切になっているだろうと、はっきり予感されてもいたのだ。
それとも、子供が二人も出来るころには、いつの間にかわたしの目にもケルビーの存在が見えなくなる……そんなことさえ起きかねない可能性だってある。あるいは、彼がわたしに失望するあまり、わたしの元を去って別の惑星へいってしまうといったような可能性も。
そんなわけで結局、わたしは結婚ということについては、人生のある段階で完全に諦めることにした。
そしてケルビーとふたり、結婚などということはまるで問題にならない、より実り多い、魂の充実した人生を生きることを選択したのだ。
それともうひとつ、ケルビーについて書き記しておきたいことがある。
わたしが特定の女性と懇意にするといった態度をとり、ケルビーがへそを曲げるといったような日の夜には――わたしは必ず、信じられないくらいの美女が自分の横にいて、口も聞けなくなるといったタイプの夢を見た。
彼女は黒い髪に、長い睫毛に縁取られた大きな瞳をしており、その肌は輝くような真珠色だった。わたしはハリウッド女優のような女性が、何故自分のすぐ横で慕わしげな目で自分を見ているのかが理解できず……彼女が服を脱ぎはじめても、それを見てはいけないと思うところで、必ず目が醒めるのだった。
おそらく人間は、自分が体験したことのないことは、夢でも見ることが出来ないものなのだろう。わたしはその後も、ほんのたまに彼女のことを夢に見るたび――こう思ったものだった。夢の中で彼女と寝るためにだけ、現実の世界で女性と関係を持ってみてはどうだろうか、と。
つまり、<彼女>が服を脱ぐ次の段階へわたしが進むためには、それ以上のことを現実の世界でわたしが知っていなくてはならないと思ったからだ。そう……次こそは彼女がキスでもしてくれないかと願いつつ、(ここで目よ醒めるな、ここで目よ醒めるな)と呪文を唱え続けた結果として、わたしに見ることが許されたもの――それが<彼女>の上半身裸になった豊満な乳房だったかもしれない。
だが残念なことに、わたしが夢の中で彼女に触れるということはついぞなく、わたしは自分の人生を終えるということになってしまった。
>>続く……。




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます