昨日の新年会のあと一宮のKさん宅に泊めてもらいました。
昨日の酒が少々残っていましたが、今日も気持ちの良い天気です。愛知県も暖かいです。いつもなら寒くて仕方ないのですが厚着しないでいられました。
帰る途中にこの辺の寺社を来訪してから帰ろうと思います。
まずは一宮駅に送ってもらいましたので、「真清田神社」に寄って行きました。送っていただいたKさんも参拝におつきあいいただきました。
尾張国一宮として崇敬されています。一宮の地名の由来となっています。
まだ新年になって日が浅いので初詣参拝に来られる方も多く見受けられます。

一宮市のシンボルともいうべき存在ですね。

本殿拝殿です。由緒ある神社ですので多くの参拝客がいました。
一宮を後にして隣の稲沢市の国府宮を訪ねてみます。
ここは2月に行われる「はだか祭」で有名です。正式には「尾張大國霊神(おわりおおくにたまのかみ)」ですが一般的には国府宮神社または国府宮と呼ばれています。最寄駅の名鉄の駅名も国府宮になっています。コヤチンも正式な名称知りませんでした。

参道がまっすぐに伸びています。
この神社には2つの国指定重要文化財の建物があります。
ひとつは楼門です。足利初期の建立。正保3年(1646年)解体大修理の際上層を改造しております。

楼門です。歴史を感じます。
もうひとつは拝殿です。徳川初期の建立。特徴として切妻造で内側に柱が並立しております。

拝殿です。こちらも多くの参拝の方が訪れていました。
さて国府宮での参拝を終えて、ここから1キロ程歩いた所に「萬徳寺」というお寺に2つの国指定重要文化財建造物がある事を知りました。せっかくですのでこちらも訪ねてみたいと思います。
国府宮を東方向に歩いて行きます。路地に入った所にあります。

小さいお寺ですが奈良時代創建の真言宗の古刹です。


多宝塔と鎮守堂が重要文化財の指定を受けています。
多宝塔は建立時期が特定できないものの様式や技法から室町時代後期のものと推定されています。
鎮守堂は八幡社とも呼ばれています。 建物は、一間杜流造で屋根は檜皮葺、棟札から享禄3年(1530)の建立であることが知られ、小規模ながら、建立年代の明らかな建造物として貴重な遺構であるとされています。
かつてはかなりの敷地を持つ寺だったようです。でも貴重な文化遺産に出会えて良かった。
JR稲沢駅が近いのでここから帰途につく予定でしたが、名古屋に着いた時に気が変わって熱田神宮に行ってみる事にしました。
さすがに全国でも屈指の大神宮です。参拝される方はまだ多かったです。こちらに元日に来た事がありましたが本宮までかなりの時間を要した事を覚えています。
本宮まで歩いて行く途中に気が付いた所を2つ

西楽所。神楽殿の前にあり、桧皮葺(ひわだぶき)が美しい建物です。貞享3年、将軍綱吉の再建で神宮にあっては数少ない明治以前の建造物の一つです。

信長塀。永禄3年(1560)織田信長が桶狭間出陣の時、熱田神宮に必勝祈願をしてみごと大勝したので、そのお礼として奉納した築地塀(ついじべい)です。
土と石灰を油で練り固め瓦を厚く積み重ねたもので、兵庫西宮(にしのみや)神社の大練塀、京都三十三間堂の太閤塀とともに日本三大土塀の一つとして有名です。

本宮。明治26年までは尾張造りの社殿でしたが、三種の神器奉斎の社であることから伊勢の神宮とほぼ同様の社殿配置・規模の神明造りに改造されました。

名古屋コーチンもいます。
慌ただしく4寺社を廻ってきましたが、この時期はじっくり参拝するという事は難しいですね。
熱田神宮も何回か行っていますがまだ知らない所いっぱいあると思います。オフシーズンにゆっくり来たいと思います。
昨日の酒が少々残っていましたが、今日も気持ちの良い天気です。愛知県も暖かいです。いつもなら寒くて仕方ないのですが厚着しないでいられました。
帰る途中にこの辺の寺社を来訪してから帰ろうと思います。
まずは一宮駅に送ってもらいましたので、「真清田神社」に寄って行きました。送っていただいたKさんも参拝におつきあいいただきました。
尾張国一宮として崇敬されています。一宮の地名の由来となっています。
まだ新年になって日が浅いので初詣参拝に来られる方も多く見受けられます。

一宮市のシンボルともいうべき存在ですね。

本殿拝殿です。由緒ある神社ですので多くの参拝客がいました。
一宮を後にして隣の稲沢市の国府宮を訪ねてみます。
ここは2月に行われる「はだか祭」で有名です。正式には「尾張大國霊神(おわりおおくにたまのかみ)」ですが一般的には国府宮神社または国府宮と呼ばれています。最寄駅の名鉄の駅名も国府宮になっています。コヤチンも正式な名称知りませんでした。

参道がまっすぐに伸びています。
この神社には2つの国指定重要文化財の建物があります。
ひとつは楼門です。足利初期の建立。正保3年(1646年)解体大修理の際上層を改造しております。

楼門です。歴史を感じます。
もうひとつは拝殿です。徳川初期の建立。特徴として切妻造で内側に柱が並立しております。

拝殿です。こちらも多くの参拝の方が訪れていました。
さて国府宮での参拝を終えて、ここから1キロ程歩いた所に「萬徳寺」というお寺に2つの国指定重要文化財建造物がある事を知りました。せっかくですのでこちらも訪ねてみたいと思います。
国府宮を東方向に歩いて行きます。路地に入った所にあります。

小さいお寺ですが奈良時代創建の真言宗の古刹です。


多宝塔と鎮守堂が重要文化財の指定を受けています。
多宝塔は建立時期が特定できないものの様式や技法から室町時代後期のものと推定されています。
鎮守堂は八幡社とも呼ばれています。 建物は、一間杜流造で屋根は檜皮葺、棟札から享禄3年(1530)の建立であることが知られ、小規模ながら、建立年代の明らかな建造物として貴重な遺構であるとされています。
かつてはかなりの敷地を持つ寺だったようです。でも貴重な文化遺産に出会えて良かった。
JR稲沢駅が近いのでここから帰途につく予定でしたが、名古屋に着いた時に気が変わって熱田神宮に行ってみる事にしました。
さすがに全国でも屈指の大神宮です。参拝される方はまだ多かったです。こちらに元日に来た事がありましたが本宮までかなりの時間を要した事を覚えています。
本宮まで歩いて行く途中に気が付いた所を2つ

西楽所。神楽殿の前にあり、桧皮葺(ひわだぶき)が美しい建物です。貞享3年、将軍綱吉の再建で神宮にあっては数少ない明治以前の建造物の一つです。

信長塀。永禄3年(1560)織田信長が桶狭間出陣の時、熱田神宮に必勝祈願をしてみごと大勝したので、そのお礼として奉納した築地塀(ついじべい)です。
土と石灰を油で練り固め瓦を厚く積み重ねたもので、兵庫西宮(にしのみや)神社の大練塀、京都三十三間堂の太閤塀とともに日本三大土塀の一つとして有名です。

本宮。明治26年までは尾張造りの社殿でしたが、三種の神器奉斎の社であることから伊勢の神宮とほぼ同様の社殿配置・規模の神明造りに改造されました。

名古屋コーチンもいます。
慌ただしく4寺社を廻ってきましたが、この時期はじっくり参拝するという事は難しいですね。
熱田神宮も何回か行っていますがまだ知らない所いっぱいあると思います。オフシーズンにゆっくり来たいと思います。


















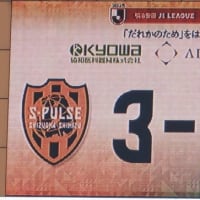

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます