今だからわかるカルト的思考回路
私の人生を振り返って考えると、高校時代(1960年代後半)はベトナム反戦、靖国問題で大学生のみならず高校生がデモに参加した時代であった。学校はミッションスクールで、ベトナム戦争、天皇制の批判と紀元節と建国記念日の問題が授業の合間に話された。
紀元節が建国記念日と制定され、2月11日は祝日となったが、私の通っていた学校は休校とはならず、抗議のための出校日となったのである。
当時、私自身は学校の影響で人間が作り出した社会の矛盾について考えることが多くなった。無力感に苛まれるときがあった。こうしている間にも、ベトナムでは多くの人が米軍の無差別爆撃で亡くなっているのに、何もできない自分がいると・・・・・。
当時、ボブデュランの「BLOWIN IN THE WIND」という反戦歌がラジオの深夜放送から流れていた。内容は、どれだけ多くの人が亡くなったら戦争は止むのだろうというもので、わかりやすい英語の歌で当時の若者のこころを引き付けた。
NHKの番組で「高校生時代」「われら高校生」というのがあり、高校生の自由討論の場があった。そこでも出場した高校生たちが反戦平和の問題を自主的に発言し始めた。その時だった。突然番組が「中学生群像」「中学生日記」と変えられていった。
学校の関係でプロテスタントの教会へも行った。教会には高校生会があり、そこでも先輩や同級生たちがいろいろと議論していた。議論の先頭に立っていた先輩たちは大学進学後、全共闘運動へとなだれ込んでいった。
私自身も大学進学後、バリケード封鎖に直面し自分がどういう道を選ぶべきか悩み続けた大学時代であった。私が選んだ道は、「大学解体」に象徴される全共闘の道ではなかった。
当時全共闘が配っていたガリ版刷りの「全共闘自己否定論」と題した論文がいまだに我が家の納戸の中に眠っている。
つい先日、全共闘と三島由紀夫が東大で論争しているフィルムを見た。論争している学生の顔には人間らしい生気がなく、排他的であると感じた。カルトの顔だ。
カルトは宗教だけの問題かと思っていたが、今振り返ると左翼カルトも存在していたと思った。
「全共闘自己否定論」を読んでみると、帝国主義的支配という人間社会の矛盾の中で、闘う自分の存在意義について、自分自身も完全ではないし、矛盾を受け入れざるを得ない生活をしている。帝国主義的支配に対して闘うためには、社会の全面否定と自己否定なしには、闘う自己は存在しない、というものである。そこから「大学解体」のスローガンが出てくるのであろう。
私は全共闘運動すべてを否定するつもりはない。当時の社会的問題を全面に押し出し、大衆的な支持をうけたのも事実だからだ。ただその排他的性格から、内紛、分裂をくりかえし、「大学解体」というスローガンで、最後は一般学生から支持を失って先鋭化していった。
彼らの自己否定に至る部分は、統一教会の原理講論の「総序」の部分によく似ている。
以下「原理講論 総序」よりコピー
とりわけ、このような本心の指向する欲望に従って、善を行おうと身もだえする努力の生活こそ、ほかならぬ修道者たちの生活である。しかしながら、有史以来、ひたすらにその本心のみに従って生きることのできた人間は一人もいなかった。それゆえ、聖書には「義人はいない、ひとりもいない。悟りのある人はいない、神を求める人はいない」(ロマ三・10、11)と記されているのである。また人間のこのような悲惨な姿に直面したパウロは「わたしは、内なる人としては神の律法を喜んでいるが、わたしの肢体には別の律法があって、わたしの心の法則に対して戦いをいどみ、そして、肢体に存在する罪の法則の中に、わたしをとりこにしているのを見る。わたしは、なんというみじめな人間なのだろう」(ロマ七・22~24)と慨嘆したのであった。ここにおいて、我々は、善の欲望を成就しようとする本心の指向性と、これに反する悪の欲望を達成させようとする邪心の指向性とが、同一の個体の中でそれぞれ相反する目的を指向して、互いに熾烈な闘争を展開するという、人間の矛盾性を発見するのである。存在するものが、いかなるものであっても、それ自体の内部に矛盾性をもつようになれば、破壊されざるを得ない。したがって、このような矛盾性をもつようになった人間は、正に破滅状態に陥っているということができる。ところで、このような人間の矛盾性は、人間が地上に初めて生を享けたときからあったものとは、到底考えられない。なぜかといえば、いかなる存在でも、矛盾性を内包したままでは、生成することさえも不可能だからである。もし人間が、地上に生を享ける以前から、既にこのような矛盾性を内包せざるを得ないような、運命的な存在であったとすれば、生まれるというそのこと自体不可能であったといえよう。したがって、人間がもっているこのような矛盾性は、後天的に生じたものだと見なければなるまい。人間のこのような破滅状態のことを、キリスト教では、堕落と呼ぶのである。
原理講論の堕落論の基本となる部分である。詳細な批判は機会を新たにしたいが、人間を「堕落」という言葉におきかえ、人間本来の理性的思考の埋没を意図して書かれていることに注目してほしい。
「堕落」を認めさせることにより「救い」が必要な世界に誘導し、そのためには違法勧誘、高額献金、霊感商法なんでもありの信者となっていく過程の「総序」の部分である。
全共闘は闘うために自己否定という観念的儀式が必要だった。自己否定するものとしない者との選別化がある。
矛盾した社会、矛盾した人間の姿を一面的に極大化し、自己否定すれば何でもできるような論理こそ、人間の本質的部分である理性の天秤を狂わせるものではないだろうか。
行くつく先は、全共闘にあっては、浅間山荘事件、よど号事件であった。
全共闘と統一教会の一致するところは、理性を失った「人間喪失」の世界。
違うところは、統一教会の場合は、頂点に「メシア」の仮面をかぶった詐欺師がいることだ。そして脱会すると、先祖の霊は未来永劫救われないし、自分や家族に不幸がおきるという呪縛の世界。
全共闘の脱会するということは、今まで散々他者に対して日和見主義批判をしていた自分に対して、日和見主義というレッテルを貼ることだが、これもまたマインドコントロールからの脱出であり大変な精神的苦渋をともなうはず。しかし40年前の時代の申し子的感慨から、「おれは昔全共闘だった」という輩がいることを思うと、なぜか滑稽に思われる。
なぜなら「私は昔統一教会だった」と感慨深げにいう人はいないからだ。
「総序」や「自己否定論」を読んで、同じような感情を持たれる人も少なくないと思う。まじめな人ほど、誘い込まれていく文章である。
多くのカルトは同じような手法で人間の欲、エゴを一面的に究極的なところまで追求することによって、人間の理性までも秤にかけて否定してしまう。
でも現代の人間社会をふりかえってよく見てほしい。人間社会にはいろいろな問題があるのは事実だが、宗教、非宗教にかかわらず、手を取り合い一生懸命生き、人々に勇気をあたえている人々がたくさんいることを忘れてはならない。
私の身近な問題でいえば、生まれつき多臓器障害の子供を救う住民運動が展開された。私もカンパを会社で集めさせてもらった。社会人、主婦、高校生といった見ず知らずの多くの人がボランティア、協力を申し出た。残念ながらそのお子さんは手術のかいもなく亡くなったが、そのお子さんが残したものは、計り知れないものがあると思う。
そこには「自己否定論」もないし、「堕落論」の入る余地などない。あるのは、人間同士の絆であり、助け合おうという理性的判断なのだ。
私のかかわっている労働運動、核兵器廃絶の運動も,然りである。また派遣村も然りである。
ただ以前のブログ記事で「なぜ堕落論は必要だったか」で紹介したH牧師が言われた言葉
「神は人間たちのおろかな思い上がりを咎め、深い愛情でその罪を許す」
これは人間が理性的であるための一つの真理のような気がする。なぜならばこの言葉に依拠するクリスチャンにとって、自分を堕落とみる必要もないし、自己否定も必要ない。なぜならば自分は神の深い愛情で許されているからだ。理性の天秤が狂うこともない。
高校生会のとき、確か宮古島台風の募金活動をするかしないかで混乱したことがあった。募金活動は偽善的行為か否かもめたのだが、今になってH牧師のこの言葉によって、私の頭の中で一件落着したような気がする。













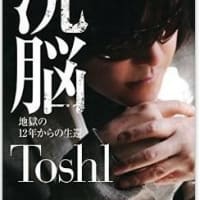

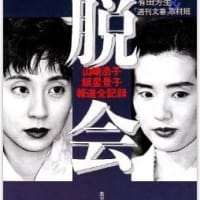




紀元節 〇
ご指摘ありがとうございます。訂正させていただきます。