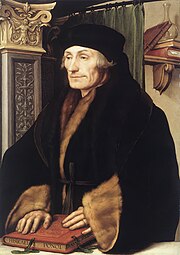土佐・長宗我部復権運動 竜馬伝から長宗我部元親伝へ
![]() ← 頑張ろう高知県 ポチっとよろしく 総合トップページへ
← 頑張ろう高知県 ポチっとよろしく 総合トップページへ
街づくりカフェ in ゆうあい工房 では、毎週金曜日に歴史談義を開いて、長宗我部元親の伝記(歴史小説)を書く準備をしています。このブログでも専用のウェブページで、歴史談義への参加・寄稿を呼び掛けています。
竜馬伝の人気で全国的高知人気が高まっていますが、その後は?
山内一豊伝の「功名が辻」、「竜馬伝」に続いて、NHK大河ドラマに期待されるのは、戦国ゲームで若者にも人気が高い「長宗我部元親伝」です。しかし、今のところ、元親を題材にした歴史小説は司馬遼太郎の「夏草の賦」しかなく、司馬氏は土佐武者を「田舎者」「野人的武士=野武士」として描いています。
土佐の侍は、「功名が辻」でも、荒くれで粗野で下品な姿で描かれていました。しかし、真の土佐の武士・民は、京・上方に引けを取らない知性と教養と力を兼ね備えた優れた集団でした。
武田の騎馬武者軍団と同様に、単に鉄砲(種子島)伝来以降の織田信長式の新式軍備に対応できなかっただけで、武田家軍学書の「甲陽軍鑑」には『名高キ武士』として、徳川家康 長宗我部元親 赤井直正 と並び称されています。つまり、鉄砲技術・装備を除けば全国ベスト3の武将だったのです。
![]() ← 頑張ろう高知県 ポチっとよろしく 総合トップページへ
← 頑張ろう高知県 ポチっとよろしく 総合トップページへ
SNS「コミュニティー高知」で、この「土佐・長宗我部復権運動 竜馬伝から長宗我部元親伝へ」の議論がスタートしたのですが、そちらである程度意見が出て、戦国武将の英知への探求心が見えてきました。まとまったものから順次公開します。
======
戦国武将らは、武勇と共に、宗教・祭祀・文学・医療・経済・土木・産業振興・貿易・航海技術など、あらゆる知識を追い求めていました。天下を治める者として、武芸以外の分野にも精通していなければ周囲から認められなかったのです。
キリスト教布教目的で日本を訪れた宣教師らを信長と元親が援助した背景には、「信仰」よりも、宣教師らがもたらす「西洋の知識・技術の吸収」があったのでしょう。まだ若く、純粋であった信親は、キリスト教に感化されて入信を考えていたようですが、元親は西海・南海の王となり、ライバル信長を打ち負かす力を養う術として、キリスト教の布教活動を利用し、西洋文化吸収に努めたものと思われます。
我々は、この信長と元親が追い求めた「西洋の知識・技術」が、それ以前には「神仏習合」でもたらされたことに着目すべきでしょう。当時の知識人は神仏習合下の僧や茶人で、神社仏閣は、我々現代人の想像を遥かに凌駕する英知を集めた施設であり、今の省庁に近い存在でした。
戦国時代、寺社は領地支配を天皇に許され自治権を主張して僧兵などを集めた「自治区」「城」でもあったのです。信長の比叡山焼き討ちは、独立・武装していた比叡山宗教者らからの自治権・統治権の剥奪並びに武装解除だったのです。また、この事件は「天皇の承認に基づく自治権」を否定する。という信長の決意を示したターニングポイントとなっています。
信長の横死については、こうした信長の宗教界への弾圧が主因だと巷で言われていますが、明智光秀・斉藤利三・長宗我部元親ラインの謀略(思惑)が複雑に絡まっています。
また、信長の死に因って、元親同様に戦火を免れた「毛利元就」の動向が気になります。彼らに仕えた滝本寺非有と安国寺恵瓊の「一対坊主」の策略があったと言うべきでしょう。
我々は、このもつれた思惑の糸を解きほぐすためにも、「信長と元親の認識の範囲」を見極めなければなりません。元親の参謀である「非有」、信長に仕えた「滝川一益」、元就には「恵瓊」。彼らの知識の根源がどこにあったのか?如何なる情報を得、与えたのか?探る必要があります。
元親が神社仏閣を訪ね歩いて参謀を探し出し、秀吉が千利休を重用し、家康が大樹寺の登誉上人に諭され自害を思いとどまったことなど、僧侶・茶人の戦乱への関与について具体的事例を掘り下げる必要もあるでしょう。
因みに、当時、茶の湯は、医療の一環であり、精神修養であり、現代で言うヒーリング・癒しの求道です。その作法を追求することは武士のたしなみと考えられていました。
「宝剣を天に投げ打つ」との辞世を遺した「千利休」ですが、これは韓国の詩を引用したもので、利休の草庵は朝鮮半島の民家を模しているとの指摘がみられる。その英知の源泉に朝鮮文化があることは、利休忌を営む薮内家の掛け軸に「立膝で座る利休」が描かれていることからも窺い知ることができる。(NHK放送資料より引用)
華々しく散ってゆく武将らの陰に隠れて、策略をめぐらしていたのは、宗教家・茶道家・商人らであることに疑いの余地はありませんが、彼らが日本と朝鮮・中国、西洋列強との取引に深く関与していたことも、また、見逃してはならないでしょう。
![]() ← 頑張ろう高知県 ポチっとよろしく 総合トップページへ
← 頑張ろう高知県 ポチっとよろしく 総合トップページへ