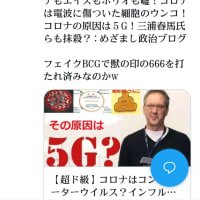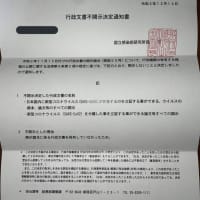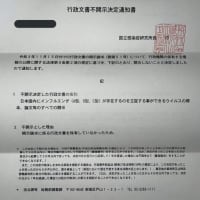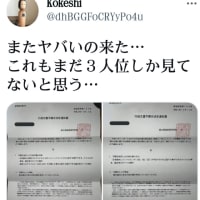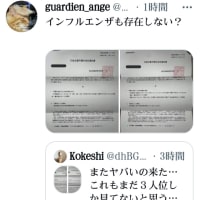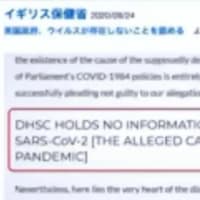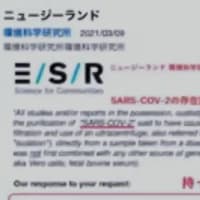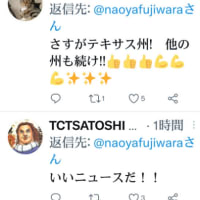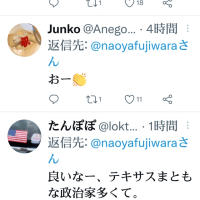秘密保護法という『実質改憲 』
国民主義より【国家権力主義】
世論が懸念を示し、内外メディアが
警鐘を鳴らしても、政府・与党は
特定秘密保護法案の成立に猛進している。
以下、「日々担々」資料ブログ様より
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10340.html
☆人びとの知る権利を弱める
☆政府はあらゆる不都合な情報を
☆秘密指定できるようになる
その底に流れているのは
「国家なくして国民なし」の論理だ。
自民党の「国民よりも国家(公益や公の秩序)優先」の
発想は、秘密保護法案の条文にも反映されている。


「日々担々」資料ブログ様より
……………………………………………
【秘密保護法という実質改憲】
(東京新聞「こちら特報部」11月21日)
世論が懸念を示し、内外メディアが警鐘を鳴らしても、政府・与党は特定秘密保護法案の成立に猛進している。
その底に流れているのは「国家なくして国民なし」の論理だ。
ここには主権在民の憲法の精神が抜け落ちている。同じ主張は、自民党の改憲草案にも貫かれている。「改憲が面倒なら、別の手で中身を取る」-。法案にはそうした政府・与党の野望が垣間見える。 (上田千秋、榊原崇仁)
「人びとの知る権利を弱める」「政府はあらゆる不都合な情報を秘密指定できるようになる」
米ニューヨーク・タイムズ紙(電子版)は先月二十九日付の社説で、安倍政権が進める法案にこう警鐘を鳴らした。
社説では、国家安全保障会議(日本版NSC)創設関連法案についても「東アジアにおいて日本への不信感を高める」と批判した。安倍政権が両法案の成立を急ぐ背景には、米国の意向があるとされてきた。だが、米国の反応は急速な右旋回に疑義を示している。
にもかかわらず、同政権が法案成立に突き進んでいる背景は何か。その「気分」を吐露した論考や発言がある。
「国そのものが揺らいだら、『知る権利』などと言っていられなくなるのだ。そういう意味で、『知らせない義務』は『知る権利』に優先するというのが、私の考えだ」
これは自民党の石破茂幹事長が野党時代、月刊誌「中央公論」昨年八月号に「国家機密の耐えられない軽さ」と題し、発表した論考の一部だ。
党の法案に関するプロジェクトチーム座長の町村信孝元官房長官も似た考えを表明している。
今月八日の衆院国家安全保障特別委員会で「国民の命が脅かされる、それを防止するためにこの法律をつくるんだということが、最も重要」と発言。
その上で「『知る権利は担保しました、しかし個人の生存が担保できませんとか、国家の存立が確保できません』というのは全く逆転した議論」「知る権利が国家や国民の安全に優先するという考え方は、基本的に間違い」と述べた。
こうした主権在民の憲法精神よりも国家が優先されるという考えは、自民党が昨年四月に公表した憲法改正草案にも随所ににじみ出ている。
草案では、現行憲法の「公共の福祉」が削除され、代わりに国家が判断の主体となる「公益及び公の秩序」という言葉がしばしば登場する。
例えば、国民の自由や権利に言及する一二条。現行憲法で「公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とあるのが、草案では「公益及び公の秩序に反してはならない」になっている。
幸福追求権に触れた一三条でも「公共の福祉に反しない限り」が「公益及び公の秩序に反しない限り」に代えられた。
二一条の「表現の自由」にもこの言葉が制約条件に追加され、二九条の「財産権」でも同様の言い換えがある。
秘密保護法案と、「公共の福祉」が「公の秩序」にすり替えられる改憲草案の絡み具合をさらに検証してみたい。
まず、現行憲法の「公共の福祉」と改憲草案の「公益」「公の秩序」はどう違うのだろうか。
東京大の高橋哲哉教授(哲学)は、「公共」は「国民一人一人に共通する」という意味で「公共の福祉」は国民それぞれの生命や人権、健康、財産などが大切にされている状態を指すと言う。
現行憲法にある「公共の福祉に反する」行為の制限は、国民一人一人の権利が損なわれないように、意見の対立がある時には調整することを意味する。つまり、あくまで国民本位の考えだ。
一方、「公益」「公の秩序」はどうか。高橋教授は、日本では歴史的に「公」は天皇や朝廷、ひいては国家権力を意味してきたと指摘する。
「自民党の憲法草案では、生まれながら国民一人一人が人権を持つ『天賦人権説』を取り入れていない点が現行憲法と大きく違う。自民党はそもそも国民以前に、天皇をいただく国家があり、固有の文化があるという考え方。国民の人権は国家がトップダウン的に認めると考えている。だから国民本位ではなく、国家ありきになっている」
少なくともこうした理解が、戦前まで支配的だった。結果的に国家に物言えない社会を生み、軍部の暴走を許した。
一八九三年制定の出版法や一九〇九年制定の新聞紙法では「安寧秩序を妨害する文書や図画を出版した時には内務大臣が発売、頒布を禁じる」などの規定があった。
関西大の高作正博教授(憲法)は「近代国家の理念は国民の自由や人権を守るために国家が存在するのであって、逆ではない。国民は国家が暴走せず、自分たちの要望に沿ってかじ取りしているか、チェックしなくてはならない。その判断材料を得るために『知る権利』は不可欠」と語る。

◆同様の成果 狙った動き
だが、自民党の「国民よりも国家(公益や公の秩序)優先」の発想は、秘密保護法案の条文にも反映されている。
例えば、同法の目的を定める一条で「我が国及び国民の安全の確保に資する」という記述があるが、高作教授は「言葉の順番として、国民より国家が先に来ている。どちらを優先したいかが表れている」とみる。
「自民党の改憲草案の前文でも最初に国の記述があり、次に国民が出てくる。法案でもその姿勢を踏襲した」
二一条では、知る権利を保障する報道の自由について「十分に配慮しなければならない」と定める一方、同条二項で「取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又(また)は著しく不当な方法によるものと認められない限り」と条件が付されている。
高作教授は「言い換えれば、国が自分たちに都合の悪い取材を『公益に反する』『著しく不当な方法』と判断すれば、報道を規制できるということ。国民の知る権利が容易に損なわれてしまう」と懸念を示す。
安倍政権は発足直後、改憲手続きを定めた九六条の緩和に挑んだ。しかし、米国も含めた内外の批判から、その手法は手控えた。ただ、その後の集団的自衛権行使の容認や秘密保護法成立へ向けた動きは、立法や解釈改憲の形で、改憲と同様の「成果」を得ようとしているように映る。
高橋教授は現状をこう危ぶんだ。「安倍政権が秘密保護法などを通じてしようとしていることは実質的な改憲。九六条改定はハードルが高く、改憲の動きは下火になったが、その火種は別の形で大きくなっている」
<デスクメモ> アーレントの映画が人気だが、彼女の師であるカール・ヤスパースはナチの権力掌握の過程で「われわれドイツ人は突然、監獄の中に閉ざされていることに気づいた」という言葉を残している。必ずしも歴史の境界線は越えた時点では意識できない。秘密保護法の恐ろしさに後日、気づいてももう遅い。 (牧)
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10340.html

国民主義より【国家権力主義】
世論が懸念を示し、内外メディアが
警鐘を鳴らしても、政府・与党は
特定秘密保護法案の成立に猛進している。
以下、「日々担々」資料ブログ様より
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10340.html
☆人びとの知る権利を弱める
☆政府はあらゆる不都合な情報を
☆秘密指定できるようになる
その底に流れているのは
「国家なくして国民なし」の論理だ。
自民党の「国民よりも国家(公益や公の秩序)優先」の
発想は、秘密保護法案の条文にも反映されている。

「日々担々」資料ブログ様より
……………………………………………
【秘密保護法という実質改憲】
(東京新聞「こちら特報部」11月21日)
世論が懸念を示し、内外メディアが警鐘を鳴らしても、政府・与党は特定秘密保護法案の成立に猛進している。
その底に流れているのは「国家なくして国民なし」の論理だ。
ここには主権在民の憲法の精神が抜け落ちている。同じ主張は、自民党の改憲草案にも貫かれている。「改憲が面倒なら、別の手で中身を取る」-。法案にはそうした政府・与党の野望が垣間見える。 (上田千秋、榊原崇仁)
「人びとの知る権利を弱める」「政府はあらゆる不都合な情報を秘密指定できるようになる」
米ニューヨーク・タイムズ紙(電子版)は先月二十九日付の社説で、安倍政権が進める法案にこう警鐘を鳴らした。
社説では、国家安全保障会議(日本版NSC)創設関連法案についても「東アジアにおいて日本への不信感を高める」と批判した。安倍政権が両法案の成立を急ぐ背景には、米国の意向があるとされてきた。だが、米国の反応は急速な右旋回に疑義を示している。
にもかかわらず、同政権が法案成立に突き進んでいる背景は何か。その「気分」を吐露した論考や発言がある。
「国そのものが揺らいだら、『知る権利』などと言っていられなくなるのだ。そういう意味で、『知らせない義務』は『知る権利』に優先するというのが、私の考えだ」
これは自民党の石破茂幹事長が野党時代、月刊誌「中央公論」昨年八月号に「国家機密の耐えられない軽さ」と題し、発表した論考の一部だ。
党の法案に関するプロジェクトチーム座長の町村信孝元官房長官も似た考えを表明している。
今月八日の衆院国家安全保障特別委員会で「国民の命が脅かされる、それを防止するためにこの法律をつくるんだということが、最も重要」と発言。
その上で「『知る権利は担保しました、しかし個人の生存が担保できませんとか、国家の存立が確保できません』というのは全く逆転した議論」「知る権利が国家や国民の安全に優先するという考え方は、基本的に間違い」と述べた。
こうした主権在民の憲法精神よりも国家が優先されるという考えは、自民党が昨年四月に公表した憲法改正草案にも随所ににじみ出ている。
草案では、現行憲法の「公共の福祉」が削除され、代わりに国家が判断の主体となる「公益及び公の秩序」という言葉がしばしば登場する。
例えば、国民の自由や権利に言及する一二条。現行憲法で「公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」とあるのが、草案では「公益及び公の秩序に反してはならない」になっている。
幸福追求権に触れた一三条でも「公共の福祉に反しない限り」が「公益及び公の秩序に反しない限り」に代えられた。
二一条の「表現の自由」にもこの言葉が制約条件に追加され、二九条の「財産権」でも同様の言い換えがある。
秘密保護法案と、「公共の福祉」が「公の秩序」にすり替えられる改憲草案の絡み具合をさらに検証してみたい。
まず、現行憲法の「公共の福祉」と改憲草案の「公益」「公の秩序」はどう違うのだろうか。
東京大の高橋哲哉教授(哲学)は、「公共」は「国民一人一人に共通する」という意味で「公共の福祉」は国民それぞれの生命や人権、健康、財産などが大切にされている状態を指すと言う。
現行憲法にある「公共の福祉に反する」行為の制限は、国民一人一人の権利が損なわれないように、意見の対立がある時には調整することを意味する。つまり、あくまで国民本位の考えだ。
一方、「公益」「公の秩序」はどうか。高橋教授は、日本では歴史的に「公」は天皇や朝廷、ひいては国家権力を意味してきたと指摘する。
「自民党の憲法草案では、生まれながら国民一人一人が人権を持つ『天賦人権説』を取り入れていない点が現行憲法と大きく違う。自民党はそもそも国民以前に、天皇をいただく国家があり、固有の文化があるという考え方。国民の人権は国家がトップダウン的に認めると考えている。だから国民本位ではなく、国家ありきになっている」
少なくともこうした理解が、戦前まで支配的だった。結果的に国家に物言えない社会を生み、軍部の暴走を許した。
一八九三年制定の出版法や一九〇九年制定の新聞紙法では「安寧秩序を妨害する文書や図画を出版した時には内務大臣が発売、頒布を禁じる」などの規定があった。
関西大の高作正博教授(憲法)は「近代国家の理念は国民の自由や人権を守るために国家が存在するのであって、逆ではない。国民は国家が暴走せず、自分たちの要望に沿ってかじ取りしているか、チェックしなくてはならない。その判断材料を得るために『知る権利』は不可欠」と語る。
◆同様の成果 狙った動き
だが、自民党の「国民よりも国家(公益や公の秩序)優先」の発想は、秘密保護法案の条文にも反映されている。
例えば、同法の目的を定める一条で「我が国及び国民の安全の確保に資する」という記述があるが、高作教授は「言葉の順番として、国民より国家が先に来ている。どちらを優先したいかが表れている」とみる。
「自民党の改憲草案の前文でも最初に国の記述があり、次に国民が出てくる。法案でもその姿勢を踏襲した」
二一条では、知る権利を保障する報道の自由について「十分に配慮しなければならない」と定める一方、同条二項で「取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又(また)は著しく不当な方法によるものと認められない限り」と条件が付されている。
高作教授は「言い換えれば、国が自分たちに都合の悪い取材を『公益に反する』『著しく不当な方法』と判断すれば、報道を規制できるということ。国民の知る権利が容易に損なわれてしまう」と懸念を示す。
安倍政権は発足直後、改憲手続きを定めた九六条の緩和に挑んだ。しかし、米国も含めた内外の批判から、その手法は手控えた。ただ、その後の集団的自衛権行使の容認や秘密保護法成立へ向けた動きは、立法や解釈改憲の形で、改憲と同様の「成果」を得ようとしているように映る。
高橋教授は現状をこう危ぶんだ。「安倍政権が秘密保護法などを通じてしようとしていることは実質的な改憲。九六条改定はハードルが高く、改憲の動きは下火になったが、その火種は別の形で大きくなっている」
<デスクメモ> アーレントの映画が人気だが、彼女の師であるカール・ヤスパースはナチの権力掌握の過程で「われわれドイツ人は突然、監獄の中に閉ざされていることに気づいた」という言葉を残している。必ずしも歴史の境界線は越えた時点では意識できない。秘密保護法の恐ろしさに後日、気づいてももう遅い。 (牧)
http://asumaken.blog41.fc2.com/blog-entry-10340.html