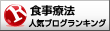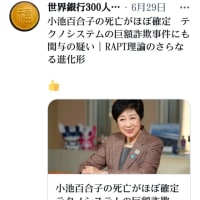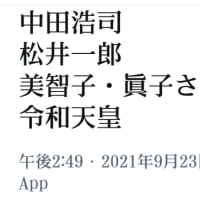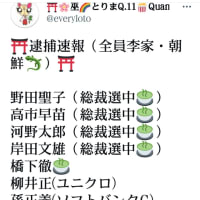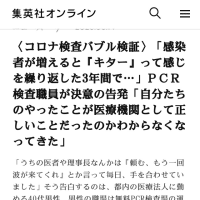アベノミクス円安効果に誤算
「相当ひどいことに」
輸出・物価への効果一過性の懸念!
政府、日銀。ロイターニュース。
消費増税後の内需落ち込み時期に、
このまま輸出が低迷すれば、
相当ひどいことになりかねない」と、
政府・日銀とも自らのシナリオに
危機感を抱きはじめている。

焦点:アベノミクス円安効果に誤算、輸出・物価への効果一過性の懸念
ロイターニュース
2014年 03月 3日 14:33 JST
[東京 3日 ロイター] -アベノミクスに大きな成果をもたらしたと内外の市場関係者から認識されたきた円安。だが、足元ではその効果に対し、疑問符が付くようなデータが連続的に出てきている。
期待されていた輸出数量の増加効果はいつまで待っても出て来ず、貿易赤字の膨張と経常黒字の縮小要因の1つに浮上。それが設備投資の伸び悩みにもつながってきた。
さらに2013年10─12月期になってもGDPデフレーターはマイナスのままで、輸入物価上昇によるコスト転嫁が十分に進んでいないことも示した。
今年の春闘における賃上げが一部の業績好調な大企業に限定されれば、円安の最大の効果である「期待」もしぼみかねず、円安効果の持続性に対しても懸念が高まっている。市場の一部には「円安は万能薬ではない」との声も出てきた。
<輸出数量、主要品目はむしろ減少傾向>
「消費増税後の内需落ち込み時期に、このまま輸出が低迷すれば、相当ひどいことになりかねない」と、政府・日銀とも自らのシナリオに危機感を抱きはじめている。
13年後半には輸出が高まるとの期待を持っていたが、7─9月、10─12月と外需はマイナスが継続。輸出が成長の足を引っ張る構図が出来あがってしまったからだ。
円安は輸出型産業を中心に円ベースでみた売上高に寄与、企業収益は増加したが、GDPベースの輸出は数量の概念だ。13年中、ドル/円レートは27%近く円安に振れたが、数量ベースでみた実質輸出の水準は年間を通じてほぼ変わらず、円安効果は輸出数量にはほとんど表れていないことを示している。
確かに新興国経済の停滞で、13年中は需要自体が伸びなかった面もある。海外経済が回復すれば、それに応じて輸出数量もある程度伸びることは期待できそうだ。しかし、輸出の伸び悩みはいつの間にか静かに進行してきた現象だ。
貿易統計をみると、日本経済のけん引役となってきた主要輸出品目の状況が、予想以上に悪化していることがわかる。自動車(普通・小型乗用車)の13年の輸出台数は、リーマンショック前の07年の7割弱。工作機械の外需受注額は、2011年をピークに年々減少し、今年1月のアジアからの受注は前年比半減、落ち込みは止まらない。半導体電子部品や半導体製造装置もすう勢的に減少し、それぞれ13年の輸出額は10年の85%、57%に過ぎない。
背景に海外への生産移転があることは、言うまでもない。国際協力銀行の調査では、13年度の海外生産比率は34%を超える見込みで、円安が進行する中でも、この1年でその比率は高まっている。その結果、国内設備投資は本格回復に至らず、10─12月期法人企業統計では足元で前期比2四半期連続で減少している。
海外需要の増加に伴って、従来通りのペースで輸出が回復する保証はなさそうだ。政策当局は、輸出数量の停滞が、外需自体によるものか、それとも構造的な要因なのか、慎重に見極め、要因に応じた対応を採ろうとしている。

<ホームメイドインフレに程遠く>
円安効果の当てが外れたのはそれだけでない。安倍晋三首相はじめ、黒田東彦日銀総裁も、円安による輸入原材料の価格転嫁だけでなく、幅広い物価上昇が起こっているとの認識を示しているが、そうとも言えないようだ。
というのも、消費者物価はプラス1%を超えているが、輸入物価上昇分を差し引いたGDPデフレータでみると、10─12月になっても前年比マイナス0.4%と、いまだプラス圏に浮上できていない。輸入物価上昇分さえ十分に価格転嫁しきれおらず、まして需給の引き締まりや賃金上昇など国内要因による物価上昇は起こっていないことを示している。
「日本ではまだ、ホームメイドインフレは起きていないということ」──。内閣府幹部はGDPデフレータが下落を続けている意味をこう解説する。
輸入品の価格上昇は、海外への所得流出にほかならない。みずほ銀行マーケット・エコノミスト・唐鎌大輔氏は「円安によるデフレ脱却シナリオは、CPIを引き上げることはできても、海外への所得流出という致命的欠陥を抱えるために、デフレの正体であるGDPデフレーターの下落を止めることは難しい」と指摘している。
<賃金への波及、企業の慎重姿勢根強くデフレ逆戻りリスク>
円安とともにデフレ脱却のカギを握る賃金動向だが、企業の腰は重そうだ。2月のロイター企業調査によると、今年の春闘で賃上げを実施すると回答した企業は全体の30%にとどまり、賃上げを実施しないと回答した37%を下回っている。
賃上げ実施方針の企業でも、ボーナスなど一時金での対応にとどまる企業が6割を超え、持続的な所得水準の底上げにはつながりにくい。「固定費の増加は何としても避けたい」との声が圧倒的に多いのが実情だ。一時金対応にとどまれば、持続的な所得底上げにはつながりにくい。
こうした状況のもとで、企業自身が再びデフレに舞い戻るリスクも想定しているようだ。ロイターが行った2月の企業調査では、増税を除いた1年後の物価見通しについて、足元より物価上昇が進むとの見方は相対的に少ない。デフレ基調に逆戻りするとの回答も全体の25%に達している。
2%程度の安定的物価上昇を目指す日銀自身、賃金の上昇に厳しい見方を指摘するリポートを公表(2月24日「賃金版ニューケイジアン・フィリップス曲線に関する実証分析」)。失業率が改善し、インフレ率も上昇しているとはいえ、近年はそうした状況が賃金上昇率に与える影響が低下していると分析、景気の改善下でもなかなか時間当たり賃金が上がりにくいことを示唆している。
「実質的に国民の懐が豊かになっているところまでまだ至っていない」--。麻生太郎財務相も今、起こっている物価上昇がまだ輸入インフレの段階にとどまっているのは、企業が賃金引き上げに慎重な姿勢をとっていることが背景だと見ている。
大幅な円安進行にもかかわらず、13年暦年の経済データからは、その効果が期待したほどではなかったことが浮かび上がる。企業が円安に伴う輸入コストをきちんと国内価格に転嫁することで、企業収益の改善を持続させ、それにより賃金上昇に積極的に取り組まない限り、安定的な景気回復は望めそうにない。
一方で、円安により海外への所得流出が続く中では、賃金上昇を実現することも難しい課題だ。「円安は万能薬ではない」と唐鎌氏は指摘している。
(中川泉 編集:石田仁志)
ロイターニュースより
http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?url=http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA2205620140303

アベノミクスは、すでに失敗している!?「金融緩和⇒円安⇒輸出増⇒給与アップ」のはずが…輸出減る!
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a1f6a0b029bbc9bbb2faafb7605c1ca8

アベノミクスに「大異変」!世界一の投資家ジョージ・ソロスが「日本株売り」これから何が起きるのか!
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/ce55101e60aa9997440d62a91ca04a51

福島原発事故直後、福島医大の医師たちはヨウ素剤を飲んでいた!「奴隷根性の日本」メディアも医師も‥
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a522367e24b05275eb9828acc35d1cc6

「相当ひどいことに」
輸出・物価への効果一過性の懸念!
政府、日銀。ロイターニュース。
消費増税後の内需落ち込み時期に、
このまま輸出が低迷すれば、
相当ひどいことになりかねない」と、
政府・日銀とも自らのシナリオに
危機感を抱きはじめている。
焦点:アベノミクス円安効果に誤算、輸出・物価への効果一過性の懸念
ロイターニュース
2014年 03月 3日 14:33 JST
[東京 3日 ロイター] -アベノミクスに大きな成果をもたらしたと内外の市場関係者から認識されたきた円安。だが、足元ではその効果に対し、疑問符が付くようなデータが連続的に出てきている。
期待されていた輸出数量の増加効果はいつまで待っても出て来ず、貿易赤字の膨張と経常黒字の縮小要因の1つに浮上。それが設備投資の伸び悩みにもつながってきた。
さらに2013年10─12月期になってもGDPデフレーターはマイナスのままで、輸入物価上昇によるコスト転嫁が十分に進んでいないことも示した。
今年の春闘における賃上げが一部の業績好調な大企業に限定されれば、円安の最大の効果である「期待」もしぼみかねず、円安効果の持続性に対しても懸念が高まっている。市場の一部には「円安は万能薬ではない」との声も出てきた。
<輸出数量、主要品目はむしろ減少傾向>
「消費増税後の内需落ち込み時期に、このまま輸出が低迷すれば、相当ひどいことになりかねない」と、政府・日銀とも自らのシナリオに危機感を抱きはじめている。
13年後半には輸出が高まるとの期待を持っていたが、7─9月、10─12月と外需はマイナスが継続。輸出が成長の足を引っ張る構図が出来あがってしまったからだ。
円安は輸出型産業を中心に円ベースでみた売上高に寄与、企業収益は増加したが、GDPベースの輸出は数量の概念だ。13年中、ドル/円レートは27%近く円安に振れたが、数量ベースでみた実質輸出の水準は年間を通じてほぼ変わらず、円安効果は輸出数量にはほとんど表れていないことを示している。
確かに新興国経済の停滞で、13年中は需要自体が伸びなかった面もある。海外経済が回復すれば、それに応じて輸出数量もある程度伸びることは期待できそうだ。しかし、輸出の伸び悩みはいつの間にか静かに進行してきた現象だ。
貿易統計をみると、日本経済のけん引役となってきた主要輸出品目の状況が、予想以上に悪化していることがわかる。自動車(普通・小型乗用車)の13年の輸出台数は、リーマンショック前の07年の7割弱。工作機械の外需受注額は、2011年をピークに年々減少し、今年1月のアジアからの受注は前年比半減、落ち込みは止まらない。半導体電子部品や半導体製造装置もすう勢的に減少し、それぞれ13年の輸出額は10年の85%、57%に過ぎない。
背景に海外への生産移転があることは、言うまでもない。国際協力銀行の調査では、13年度の海外生産比率は34%を超える見込みで、円安が進行する中でも、この1年でその比率は高まっている。その結果、国内設備投資は本格回復に至らず、10─12月期法人企業統計では足元で前期比2四半期連続で減少している。
海外需要の増加に伴って、従来通りのペースで輸出が回復する保証はなさそうだ。政策当局は、輸出数量の停滞が、外需自体によるものか、それとも構造的な要因なのか、慎重に見極め、要因に応じた対応を採ろうとしている。
<ホームメイドインフレに程遠く>
円安効果の当てが外れたのはそれだけでない。安倍晋三首相はじめ、黒田東彦日銀総裁も、円安による輸入原材料の価格転嫁だけでなく、幅広い物価上昇が起こっているとの認識を示しているが、そうとも言えないようだ。
というのも、消費者物価はプラス1%を超えているが、輸入物価上昇分を差し引いたGDPデフレータでみると、10─12月になっても前年比マイナス0.4%と、いまだプラス圏に浮上できていない。輸入物価上昇分さえ十分に価格転嫁しきれおらず、まして需給の引き締まりや賃金上昇など国内要因による物価上昇は起こっていないことを示している。
「日本ではまだ、ホームメイドインフレは起きていないということ」──。内閣府幹部はGDPデフレータが下落を続けている意味をこう解説する。
輸入品の価格上昇は、海外への所得流出にほかならない。みずほ銀行マーケット・エコノミスト・唐鎌大輔氏は「円安によるデフレ脱却シナリオは、CPIを引き上げることはできても、海外への所得流出という致命的欠陥を抱えるために、デフレの正体であるGDPデフレーターの下落を止めることは難しい」と指摘している。
<賃金への波及、企業の慎重姿勢根強くデフレ逆戻りリスク>
円安とともにデフレ脱却のカギを握る賃金動向だが、企業の腰は重そうだ。2月のロイター企業調査によると、今年の春闘で賃上げを実施すると回答した企業は全体の30%にとどまり、賃上げを実施しないと回答した37%を下回っている。
賃上げ実施方針の企業でも、ボーナスなど一時金での対応にとどまる企業が6割を超え、持続的な所得水準の底上げにはつながりにくい。「固定費の増加は何としても避けたい」との声が圧倒的に多いのが実情だ。一時金対応にとどまれば、持続的な所得底上げにはつながりにくい。
こうした状況のもとで、企業自身が再びデフレに舞い戻るリスクも想定しているようだ。ロイターが行った2月の企業調査では、増税を除いた1年後の物価見通しについて、足元より物価上昇が進むとの見方は相対的に少ない。デフレ基調に逆戻りするとの回答も全体の25%に達している。
2%程度の安定的物価上昇を目指す日銀自身、賃金の上昇に厳しい見方を指摘するリポートを公表(2月24日「賃金版ニューケイジアン・フィリップス曲線に関する実証分析」)。失業率が改善し、インフレ率も上昇しているとはいえ、近年はそうした状況が賃金上昇率に与える影響が低下していると分析、景気の改善下でもなかなか時間当たり賃金が上がりにくいことを示唆している。
「実質的に国民の懐が豊かになっているところまでまだ至っていない」--。麻生太郎財務相も今、起こっている物価上昇がまだ輸入インフレの段階にとどまっているのは、企業が賃金引き上げに慎重な姿勢をとっていることが背景だと見ている。
大幅な円安進行にもかかわらず、13年暦年の経済データからは、その効果が期待したほどではなかったことが浮かび上がる。企業が円安に伴う輸入コストをきちんと国内価格に転嫁することで、企業収益の改善を持続させ、それにより賃金上昇に積極的に取り組まない限り、安定的な景気回復は望めそうにない。
一方で、円安により海外への所得流出が続く中では、賃金上昇を実現することも難しい課題だ。「円安は万能薬ではない」と唐鎌氏は指摘している。
(中川泉 編集:石田仁志)
ロイターニュースより
http://sp.m.reuters.co.jp/news/newsBodyPI.php?url=http://jp.reuters.com/article/topNews/idJPTYEA2205620140303
アベノミクスは、すでに失敗している!?「金融緩和⇒円安⇒輸出増⇒給与アップ」のはずが…輸出減る!
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a1f6a0b029bbc9bbb2faafb7605c1ca8

アベノミクスに「大異変」!世界一の投資家ジョージ・ソロスが「日本株売り」これから何が起きるのか!
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/ce55101e60aa9997440d62a91ca04a51

福島原発事故直後、福島医大の医師たちはヨウ素剤を飲んでいた!「奴隷根性の日本」メディアも医師も‥
http://blog.goo.ne.jp/kimito39/e/a522367e24b05275eb9828acc35d1cc6