親方は昼前に帰ってきた。足場に上がってきた親方は、泥荒の仕事の進み具合に何も言
わなかったが、顔を不機嫌にしかめた。それを察して泥荒は、すいません、親方、今日は
体の調子が少し悪いもんでと謝った。
「おめぇ、おまんこの匂いがするぞ、昨日の夜、やったな」
親方はしょうがねぇな若いのはという表情で苦笑い顔で言った。泥荒はどきっとして一
瞬凍った。
昼時になって、濡縁で弁当を食っていると、神奈川リフォームの営業マンである、関塚
茂がアイスコヒー缶をふたつもってやってきた。塗り替え外装工事をしている渡辺寛之邸
は、訪問営業による関塚茂が契約したのだった。営業マンは工事管理もしていた。毎日現
場に顔を出し、施主にあいさつをする、施主とのコミュニケーションをうまくやらないと、
必ずクレームやトラブルが発生し、工事終了後に待っている工事代回収がうまくいかなか
った。
「親方、お世話になっています。次の現場、見てもらいましたか?」
「さっき、見てきたよ」親方が関塚に応じた。
「木部が多い現場ですが、よろしくお願いします。奥さん、いらしゃいますか?」
関塚が小指をたて、親方に聞いた。
「さっき、車で出かけたよ、なぁ」親方は泥荒にふった。
「はい」
泥荒は下を向いて弁当を食いながら答えた。親方である前田塗装店にペンキ工として職
を紹介してくれたのは、同じ矢板の出身である関塚茂だった。昼前の出来事が知れると、
大変な問題に発展してしまうと泥荒はびくびくしていた。
「おめぇ、今日、調子が悪そうだな、顔が青いぞ……」
関塚が泥荒に声をかけた。
「昨日、女とやったんだってよ、あんまり寝てねぇんじゃ、ねえか、あっははは」
親方が笑いながら言った。
「チッ、おめぇ、女もいいけどよ、仕事にさしつかえるまでやるなよ」
関塚も笑いながら泥荒に注意した。泥荒は苦笑いをしながら頭をペコペコした。
「それじゃ親方、よろしくお願いします」
関塚は親方に頭を下げると、カバンを持って訪問営業へと歩いていった。
翌日の朝、大雨が降っていた。有留めぐみが住むアパートは小田急線片瀬江ノ島駅から
鵠沼海岸駅方向に歩いていく裏道沿いにあった。それは江ノ島が見える大きな海岸通りの、
ひとつ裏の道だった。車は一車両しか通れなかった。海岸通りにある「すかいらーく」の
裏、住所は藤沢市片瀬海岸三丁目十三番地になる。有留めぐみはアパートのドアを開けた。
隣の部屋に住む関塚茂も丁度、雨の様子を見ようとドアを開けたとこだった。一階の一○
一号室にめぐみ、一○二号室に茂が住んでいた。アパートは二階建て四世帯のセキスイプ
レハブ住宅だった。ふたりは顔を見合わせた。おはようございますと茂が言った。その
声を聞いてからめぐみは、おはようございますと挨拶をした。めぐみはビニールゴミ袋、
ふたつを手に持ち、雨傘を開いた。
「田舎から、おじいちゃんが来ているので、ふたり分のゴミが出ちゃいました、エヘヘ」
可愛い笑顔でめぐみは茂に言った。そして近所のゴミ集積所まで歩いていった。
雨傘をさした群青のジーンズ、めぐみのうしろ姿を見ながら茂は、いいけつしているな
と欲情した。ああいう女学生と一発やれたら、最高だんべよ、バックでガンガン突きまく
るイメージに茂は朝から勃起した。あぁ、仕事なんぞせず、こういう雨の日は朝からおま
んこをやりたいもんだと茂は思った。泥荒もいいもんだな、寝ないで女とやれるなんてよ
と昨日の現場での会話を思い出した。
そうだ、おれもゴミを出さねば・・・だいぶたまってしまったからな、今日は燃えるゴ
ミの日か、茂は部屋に戻った。どうせ今日は一日中雨だから仕事にもならない、そう茂は
ずる休みをする決意をするのだが気持ちの奥底では迷った。雨の日に休むと根性無しと認
定されてしまうのが怖かった。雨の日はお客さんが玄関の外に出てこない。それで営業マ
ンは車の中や公共施設のなかで昼寝をしているのがおちであった。みんな朝に顔を出し、
大声で気合の合唱をしてら訪問営業に飛び出すのだが、雨の日は夕方まで時間をつぶすし
かなかった。
ゴミ袋を持って外に出ると、ちょうどめぐみが帰ってきたところだった。だいぶ、降っ
てきましたね、そう茂はめぐみに声をかけてみた。えぇ、雨の日は憂鬱だわ、そうめぐみ
は茂に笑顔で答えてみた。
「もしよかったら今度飲みに行きませんか? 鵠沼海岸駅通りに『ラ・メール』という面
白い店があるんですよ」
茂はそれとなく、めぐみを誘ってみた。
「あ! その店ならわたし一度、行ったことがあります。素敵な店ですね」
「飲みに来る店のお客さんが面白い人ばっかりなんですよ。今晩どうですか?」
茂は会話のかけひきに押してみた。
「そうですね、行きますか」
めぐみが承諾した。
「じゃあ、夜八時、鵠沼海岸駅での待ち合わせでどうですか?」
茂は約束を取り付けようとした。
「わかりました。行きます。じゃあ、そこで」
あっさりとめぐみが約束に乗ったので、茂は歓喜したが表情には出さなかった。めぐみ
は茂に頭をちょこんと下げ、自分の部屋の玄関に入り、そしてドアを閉めた。
めぐみの表情とからだには十九歳とは思えない色気と人をひきつけてやまないオーラー
があった。いいおんなだ、今日はいい日だと茂は雨のなかを濡れ踊るようにゴミ出しに歩
いていった。憂鬱なずる休みの誘惑などすでに消えていた。茂の体には今日も仕事でがん
ばるぞ、契約をとってみせるぞという気合が生まれていた。夜が楽しみだった。
「おじいちゃん、誘惑に成功したじゃけんね」
めぐみは部屋の中央に座っている有留源一郎に報告した。源一郎は満足そうにうなづい
た。有留一族の目的は「新昆類」のエサとなる男の精液エキスの収集だった。八十年代か
らの世代交配の反復により、二十一世紀には、新たなる新世代のゴキブリが誕生するはず
だった。「新昆類」昆虫情報体である。その開発とは広島がアメリカに原爆を落とされた
怨霊のなせる業でもあった。もうひとつの日本に有留一族は息を潜めて、ひたすら「新昆
類」昆虫情報体の新世代開発に勤しむ長期戦略があった。それはもうひとつの日本で潜水
している進行でもあった。出来事は二十一世紀ゼロ年代の中頃、日本列島各地にある在日
アメリカ軍に向けて、「新昆類」昆虫情報体が放されるはずである。原爆投下への復讐だ
った。秘密結社の棟梁、源一郎はめぐみの部屋で、タンスの上のガラス槽を見ながらゆっ
くりとパイプ煙草をふかしていた。そして彼はお茶をすすった。ガラス槽には、夜、活動
する茶色い昆虫が眠っている。彼にとってそれは沈黙の生物兵器だった。昭和五十七年、
夏の雨、広島原爆記念日はとうに過ぎ、晩夏の匂いがする朝だった。めぐみもアルバイト
に出かけひとり有留源一郎は、海岸通りにある「すかいらーく」裏のアパートで、二十一
世紀を夢想していた。
【第1回日本経済新聞小説大賞(2006年度)第1次予選落選】
わなかったが、顔を不機嫌にしかめた。それを察して泥荒は、すいません、親方、今日は
体の調子が少し悪いもんでと謝った。
「おめぇ、おまんこの匂いがするぞ、昨日の夜、やったな」
親方はしょうがねぇな若いのはという表情で苦笑い顔で言った。泥荒はどきっとして一
瞬凍った。
昼時になって、濡縁で弁当を食っていると、神奈川リフォームの営業マンである、関塚
茂がアイスコヒー缶をふたつもってやってきた。塗り替え外装工事をしている渡辺寛之邸
は、訪問営業による関塚茂が契約したのだった。営業マンは工事管理もしていた。毎日現
場に顔を出し、施主にあいさつをする、施主とのコミュニケーションをうまくやらないと、
必ずクレームやトラブルが発生し、工事終了後に待っている工事代回収がうまくいかなか
った。
「親方、お世話になっています。次の現場、見てもらいましたか?」
「さっき、見てきたよ」親方が関塚に応じた。
「木部が多い現場ですが、よろしくお願いします。奥さん、いらしゃいますか?」
関塚が小指をたて、親方に聞いた。
「さっき、車で出かけたよ、なぁ」親方は泥荒にふった。
「はい」
泥荒は下を向いて弁当を食いながら答えた。親方である前田塗装店にペンキ工として職
を紹介してくれたのは、同じ矢板の出身である関塚茂だった。昼前の出来事が知れると、
大変な問題に発展してしまうと泥荒はびくびくしていた。
「おめぇ、今日、調子が悪そうだな、顔が青いぞ……」
関塚が泥荒に声をかけた。
「昨日、女とやったんだってよ、あんまり寝てねぇんじゃ、ねえか、あっははは」
親方が笑いながら言った。
「チッ、おめぇ、女もいいけどよ、仕事にさしつかえるまでやるなよ」
関塚も笑いながら泥荒に注意した。泥荒は苦笑いをしながら頭をペコペコした。
「それじゃ親方、よろしくお願いします」
関塚は親方に頭を下げると、カバンを持って訪問営業へと歩いていった。
翌日の朝、大雨が降っていた。有留めぐみが住むアパートは小田急線片瀬江ノ島駅から
鵠沼海岸駅方向に歩いていく裏道沿いにあった。それは江ノ島が見える大きな海岸通りの、
ひとつ裏の道だった。車は一車両しか通れなかった。海岸通りにある「すかいらーく」の
裏、住所は藤沢市片瀬海岸三丁目十三番地になる。有留めぐみはアパートのドアを開けた。
隣の部屋に住む関塚茂も丁度、雨の様子を見ようとドアを開けたとこだった。一階の一○
一号室にめぐみ、一○二号室に茂が住んでいた。アパートは二階建て四世帯のセキスイプ
レハブ住宅だった。ふたりは顔を見合わせた。おはようございますと茂が言った。その
声を聞いてからめぐみは、おはようございますと挨拶をした。めぐみはビニールゴミ袋、
ふたつを手に持ち、雨傘を開いた。
「田舎から、おじいちゃんが来ているので、ふたり分のゴミが出ちゃいました、エヘヘ」
可愛い笑顔でめぐみは茂に言った。そして近所のゴミ集積所まで歩いていった。
雨傘をさした群青のジーンズ、めぐみのうしろ姿を見ながら茂は、いいけつしているな
と欲情した。ああいう女学生と一発やれたら、最高だんべよ、バックでガンガン突きまく
るイメージに茂は朝から勃起した。あぁ、仕事なんぞせず、こういう雨の日は朝からおま
んこをやりたいもんだと茂は思った。泥荒もいいもんだな、寝ないで女とやれるなんてよ
と昨日の現場での会話を思い出した。
そうだ、おれもゴミを出さねば・・・だいぶたまってしまったからな、今日は燃えるゴ
ミの日か、茂は部屋に戻った。どうせ今日は一日中雨だから仕事にもならない、そう茂は
ずる休みをする決意をするのだが気持ちの奥底では迷った。雨の日に休むと根性無しと認
定されてしまうのが怖かった。雨の日はお客さんが玄関の外に出てこない。それで営業マ
ンは車の中や公共施設のなかで昼寝をしているのがおちであった。みんな朝に顔を出し、
大声で気合の合唱をしてら訪問営業に飛び出すのだが、雨の日は夕方まで時間をつぶすし
かなかった。
ゴミ袋を持って外に出ると、ちょうどめぐみが帰ってきたところだった。だいぶ、降っ
てきましたね、そう茂はめぐみに声をかけてみた。えぇ、雨の日は憂鬱だわ、そうめぐみ
は茂に笑顔で答えてみた。
「もしよかったら今度飲みに行きませんか? 鵠沼海岸駅通りに『ラ・メール』という面
白い店があるんですよ」
茂はそれとなく、めぐみを誘ってみた。
「あ! その店ならわたし一度、行ったことがあります。素敵な店ですね」
「飲みに来る店のお客さんが面白い人ばっかりなんですよ。今晩どうですか?」
茂は会話のかけひきに押してみた。
「そうですね、行きますか」
めぐみが承諾した。
「じゃあ、夜八時、鵠沼海岸駅での待ち合わせでどうですか?」
茂は約束を取り付けようとした。
「わかりました。行きます。じゃあ、そこで」
あっさりとめぐみが約束に乗ったので、茂は歓喜したが表情には出さなかった。めぐみ
は茂に頭をちょこんと下げ、自分の部屋の玄関に入り、そしてドアを閉めた。
めぐみの表情とからだには十九歳とは思えない色気と人をひきつけてやまないオーラー
があった。いいおんなだ、今日はいい日だと茂は雨のなかを濡れ踊るようにゴミ出しに歩
いていった。憂鬱なずる休みの誘惑などすでに消えていた。茂の体には今日も仕事でがん
ばるぞ、契約をとってみせるぞという気合が生まれていた。夜が楽しみだった。
「おじいちゃん、誘惑に成功したじゃけんね」
めぐみは部屋の中央に座っている有留源一郎に報告した。源一郎は満足そうにうなづい
た。有留一族の目的は「新昆類」のエサとなる男の精液エキスの収集だった。八十年代か
らの世代交配の反復により、二十一世紀には、新たなる新世代のゴキブリが誕生するはず
だった。「新昆類」昆虫情報体である。その開発とは広島がアメリカに原爆を落とされた
怨霊のなせる業でもあった。もうひとつの日本に有留一族は息を潜めて、ひたすら「新昆
類」昆虫情報体の新世代開発に勤しむ長期戦略があった。それはもうひとつの日本で潜水
している進行でもあった。出来事は二十一世紀ゼロ年代の中頃、日本列島各地にある在日
アメリカ軍に向けて、「新昆類」昆虫情報体が放されるはずである。原爆投下への復讐だ
った。秘密結社の棟梁、源一郎はめぐみの部屋で、タンスの上のガラス槽を見ながらゆっ
くりとパイプ煙草をふかしていた。そして彼はお茶をすすった。ガラス槽には、夜、活動
する茶色い昆虫が眠っている。彼にとってそれは沈黙の生物兵器だった。昭和五十七年、
夏の雨、広島原爆記念日はとうに過ぎ、晩夏の匂いがする朝だった。めぐみもアルバイト
に出かけひとり有留源一郎は、海岸通りにある「すかいらーく」裏のアパートで、二十一
世紀を夢想していた。
【第1回日本経済新聞小説大賞(2006年度)第1次予選落選】














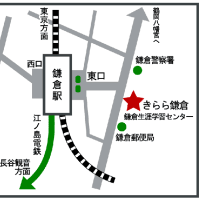



※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます