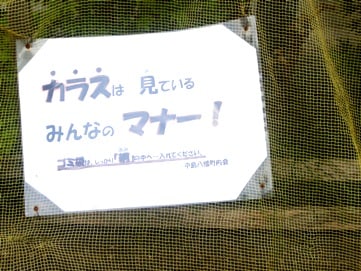みのるほど こうべをたれる いなほかな

人格者ほど謙虚であるという事をたとえた諺ではあるが、現実は中々稲穂のようにはいかないものである。ちょいとばかし実が入った(地位や金を手に入れた)人間ほど、頭を垂れるどころか逆に仰向いて、ふんぞり返ったりするものなんである。「オレは社長だぞっ!」な~んてね。
そんなことより実の入ってない人間は、元々垂れようもないんで、真っ直ぐ突っ立ってりゃいいのかな。

人格者ほど謙虚であるという事をたとえた諺ではあるが、現実は中々稲穂のようにはいかないものである。ちょいとばかし実が入った(地位や金を手に入れた)人間ほど、頭を垂れるどころか逆に仰向いて、ふんぞり返ったりするものなんである。「オレは社長だぞっ!」な~んてね。
そんなことより実の入ってない人間は、元々垂れようもないんで、真っ直ぐ突っ立ってりゃいいのかな。