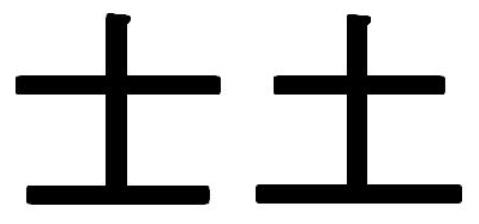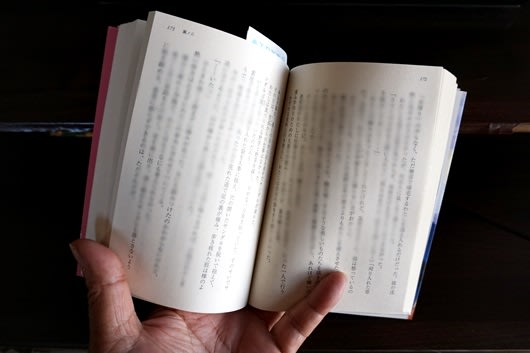
文庫本の文字サイズと言えば、凡そ8~9P(ポイント)前後。Q(級)で言えば12Q(3mm)前後だろうか。視力がどんどん低下している身としては、小さい、見づらい、ぼやける。はっきりと見えないと言ったことに対するストレスは、相当なものがある。
かと言って、文字が大きくなればそれでいいのかと言えば、必ずしもそうとは思わないこだわりがある。文字と言うものは、ただ読めればいいと言うものでもない。本や雑誌や新聞など、紙面に対するバランスを考慮して、マージンや文字サイズ、字送り、行送りなどが割付・レイアウトされるべきで、見た目の美しさも重要な要素なんである。
組版のバランスが悪い本なんて、見ただけで読もうという意欲が失せてしまうのだ。
幼児の絵本じゃあるまいし、文字サイズさえ大きくすれば済むと言う問題じゃないという処に、己のこだわりに対するジレンマがある。
文字が大きければ見やすくはなるだろうが、読みやすさとはまた別の次元の話である。ページ数だってどんどん増えていってしまうだろうしね。
[注]1P ≒ 0.35 mm
1Q = 0.25 mm