「捨てることで負う傷」酒井順子さん
中日新聞[読書欄]2014/3/9 Mon.
ここ数年、「捨てる」系の本が流行っています。物を捨てることによって人生も開けるのだ、だから躊躇なくどんどん捨てよう。・・・と、その手の本は語ります。
確かに、物を捨てるとスッキリし、「捨てハイ」とでも言うべき状態になるもの。①内澤旬子『捨てる女』(本の雑誌社・1680円)にも、そんな捨てる楽しさが描かれているのかと思いきや、読むうちに様子は異なってきます。
著者は人生のある時期に、大量にあった本等のコレクションを手放すのですが、その結果として襲われるのは、「捨てハイ」とは反対の気分。「人生を楽しむ気分」まで捨ててしまった、と著者は気づくのでした。「捨てる」とは、自分の中から何かをひきはがすことなのかもしれません。
「捨てる」と「捨てられる」は、実は表裏一体なのではないかと思わされるのは、②遠藤周作『新装版 わたしが・棄てた・女』。(略)
③深沢七郎『楢山節考』(新潮文庫・452円)は、子が親を捨てる物語です。

この物語においても、主体となるのは、捨てられる側。捨てる側、すなわち息子の心を慮り、自分でイニシアティブを持って捨てられようとする母・おりんの姿は、悲しいほどに強いのです。食い扶持を減らさなくてはならないほどの貧しい環境の中では、最後にとる行動によって、人の生き様は判断されるのでした。
捨てハイ状態になっているとき、捨てる側は「捨てられるもの」に対してそれまで抱いていた思いに、目をつぶろうとします。しかし、捨てるのが物でっても人であっても、捨てられるものには必ず、捨てる側の思いがこもるものであり、捨てる側の方が実は傷つくということを、これらの本は示します。
物もお金も人づきあいも、「もっともっと」の時代。「どう捨てるか」は、「どう生きるか」でもあるのでしょう。
◎上記事は[中日新聞]から転写しました。来栖
-------------------------------------
古典が伝える深い心の闇 大塚ひかり 著『本当はひどかった昔の日本』(新潮社・1365円)
評者:水原紫苑=歌人 中日新聞[読書欄]2014/3/9 Mon.
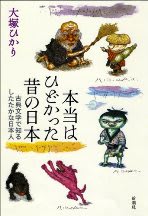
美しかった〈昔の日本〉など、存在しない。これは痛快な一冊である。
育児放棄や体罰などの児童虐待、老人を捨てる棄老、はたまた美醜による差別、と、今の世の問題は、ほとんどすべて〈昔〉からもっと大がかりにあったものだと、著者は語る。
美貌ゆえに望まれて次々と男と関係し、育児を放棄してしまった母の話は、まるで現代の週刊誌を写したようだが、よく考えてみれば逆に、児童虐待の歴史的な心性が今なお多くの人々の意識の底に沈んでいて、折々顔を出すのかも知れない。
とはいえ、尊属を絶対的優位とする儒教的道徳のために、自分たちを捨てた母のことさえ、「恨んでいる」とは言えない子供たちの哀れさは想像を絶している。
また、介護地獄も〈昔〉から存在した。今は超高齢化社会を迎えて、介護する側もされる側も追いつめられ、老いた親や病気の妻あるいは夫を殺してしまうような事件があとを絶たない。
親は絶対である〈昔〉は、むしろ、親の介護のために子を犠牲にした例を著者は挙げている。その一方で、もはや働けなくなった老人を山などに捨てる、棄老伝説もさまざまな形で残っている。
美醜の差別についても、〈昔〉は恐ろしいほどである。
『源氏物語』の末摘花の醜さの描写は、あまりの残酷さに驚くほどだが、著者は、醜女末摘花を、絶世の美男光源氏と結婚させた紫式部の独創を評価している。平安朝の貴族たちには考えられなかった結びつきであろう。 今でも、とりわけ女が、美醜によって差別されているのは変わらない。
〈昔の日本〉も今の日本も、人間の心は闇である。ただ、今はそれを隠そうとして、より深い闇の中で人々が倒れて行く。
古典を読むことは、私たちに、闇の中で決して倒れない歩き方を教えてくれるにちがいない。◇
◎上記事は[中日新聞]から転写しました。来栖
...................









