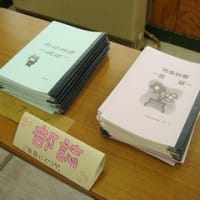2章:開拓の章
1、玉川上水開削
先ほどから繰り返し述べているように、小平はとにかく水に恵まれない所であった。そのため、小平は長い間一面に原っぱがあるだけの場所であった。
しかし、天正(てんしょう)十八年(一五九〇年)、豊臣秀吉の命によって徳川家康が江戸に天封となると、江戸は発展の一途をたどり、幕府の成立後は将軍のお膝元として人口は増え続けるばかりであった。しかし、これにともなって、大幅に増加した江戸の人々の飲料水の確保が問題となった。
その状況を改善するべくつくられたのが、承応(じょうおう)四年(一六五四年)に完成した玉川上水である。
小平市の中も通るこの玉川上水からは、数多くの分水が引かれ、小平の各地を通った。
明暦元年(一六五五年) 野火止用水開削
同二年(一六五六年) 小川用水開削
元禄九年(一六九六年) 田無用水開削 等
これが、小平の開拓に大きく寄与したのである。(つづく)(執筆;研究関連担当代表<前・会長全権代行>)
1、玉川上水開削
先ほどから繰り返し述べているように、小平はとにかく水に恵まれない所であった。そのため、小平は長い間一面に原っぱがあるだけの場所であった。
しかし、天正(てんしょう)十八年(一五九〇年)、豊臣秀吉の命によって徳川家康が江戸に天封となると、江戸は発展の一途をたどり、幕府の成立後は将軍のお膝元として人口は増え続けるばかりであった。しかし、これにともなって、大幅に増加した江戸の人々の飲料水の確保が問題となった。
その状況を改善するべくつくられたのが、承応(じょうおう)四年(一六五四年)に完成した玉川上水である。
小平市の中も通るこの玉川上水からは、数多くの分水が引かれ、小平の各地を通った。
明暦元年(一六五五年) 野火止用水開削
同二年(一六五六年) 小川用水開削
元禄九年(一六九六年) 田無用水開削 等
これが、小平の開拓に大きく寄与したのである。(つづく)(執筆;研究関連担当代表<前・会長全権代行>)