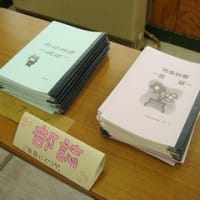2、中世の小平(1) ~まいまいず井戸~
一面の原っぱであった小平だが、中世になると鎌倉街道が通され、多くの人々が往来した。
「鎌倉街道」という名称は江戸時代につけられたようで、それ以前は「鎌倉道(みち)」とか「鎌倉往還(おうかん)」などと呼ばれていた。その鎌倉街道の中でも主要な道を「上(かみ)ノ道」「中(なか)ノ道」「下(しも)ノ道」と呼んだ。
その中で小平を通っていたのが、上ノ道である。鎌倉から上野国(群馬県)までを通っており、小平市内では上水本町(ほんちょう)から津田塾大学の東を通り、小川町二丁目辺りかで青梅街道を横切り、ブリジストン東京工場を越えて九道の辻(現・八坂交差点)に入り、東村山市の野口に抜けて行った。
この上ノ道、当時は上野・下野(栃木県)両国と鎌倉を結ぶ、唯一の道であり、たくさんの人々が行き来したようである。しかし、この頃の街道沿いは一面すすきに覆われた荒野で、人家が一軒もなかったため、旅人は飲み水が得られず相当の苦労があったようだ。
それを改善するべく、小平市内の街道沿いの二ヶ所には「まいまいず井戸(すり鉢井戸)」なるものがあったと言われ、一ヶ所はブリジストン東京工場内、もう一ヶ所は津田塾大学東側と伝えられている。
「まいまいず井戸」は武蔵野台地特有のもののようで、二十~三十メートルほどをうずまき状に地下水に至るまで掘り、そこを人がぐるぐる回りながら降りて、水を汲むと言う構造であったようだ。非常に大変な構造である。(つづく) (執筆:会長全権代行)
一面の原っぱであった小平だが、中世になると鎌倉街道が通され、多くの人々が往来した。
「鎌倉街道」という名称は江戸時代につけられたようで、それ以前は「鎌倉道(みち)」とか「鎌倉往還(おうかん)」などと呼ばれていた。その鎌倉街道の中でも主要な道を「上(かみ)ノ道」「中(なか)ノ道」「下(しも)ノ道」と呼んだ。
その中で小平を通っていたのが、上ノ道である。鎌倉から上野国(群馬県)までを通っており、小平市内では上水本町(ほんちょう)から津田塾大学の東を通り、小川町二丁目辺りかで青梅街道を横切り、ブリジストン東京工場を越えて九道の辻(現・八坂交差点)に入り、東村山市の野口に抜けて行った。
この上ノ道、当時は上野・下野(栃木県)両国と鎌倉を結ぶ、唯一の道であり、たくさんの人々が行き来したようである。しかし、この頃の街道沿いは一面すすきに覆われた荒野で、人家が一軒もなかったため、旅人は飲み水が得られず相当の苦労があったようだ。
それを改善するべく、小平市内の街道沿いの二ヶ所には「まいまいず井戸(すり鉢井戸)」なるものがあったと言われ、一ヶ所はブリジストン東京工場内、もう一ヶ所は津田塾大学東側と伝えられている。
「まいまいず井戸」は武蔵野台地特有のもののようで、二十~三十メートルほどをうずまき状に地下水に至るまで掘り、そこを人がぐるぐる回りながら降りて、水を汲むと言う構造であったようだ。非常に大変な構造である。(つづく) (執筆:会長全権代行)